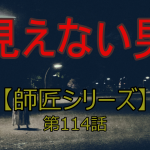馬霊刀 1/4
0 喫茶店
『服部調査事務所』と書かれたドアに背を向けて、狭い階段を下りていく。
目の前で師匠の頭が揺れている。少し猫背で、ポケットに手を入れ、愉快なことなどなにもない、という足取り。
1階まで降りて、雑居ビルの外に出ると、すぐそばに『ボストン』という名前の喫茶店の入り口がある。
「なんか食ってくか」
師匠がぼそりと言った。
「はい」
ドアを開けると、カラン、という控え目な音がした。喫茶店のなかは落ち着いた照明で、コンビニやファミレスに慣れてしまった目には薄暗く感じられた。
「いらっしゃい」
鼻の下にヒゲを蓄えたマスターが、カウンターから声をかける。
「あれ。久しぶりじゃない。あのー、アレを着てきた時以来だね」
マスターは蓑笠の紐を喉元で括るようなジェスチャーをして、笑っている。
師匠は頭をかいて、「うす」と言いながらカウンターの隅に座った。俺もマスターに「こんにちは」と頭を下げて、師匠の隣に座る。
師匠から聞かされた話に何度か出てきた喫茶店だ。俺が初めて訪れた時は、ここは京介さんのバイト先だった。その京介さんへの嫌がらせのために、わざわざ雨のなかを蓑笠を着てやってくる、というテロを敢行した師匠だったが、入店して早々にびしょぬれの蓑を掛けさせろと喚くはずが、妙に暗いテンションで黙って入り口に突っ立っていた。なんだか托鉢僧のような風体だった。さらには京介さんに怒られて、そのまま口答えすることもなく、すごすごと帰ろうとする有り様だった。そのころはまだ俺も、この喫茶店が師匠にとってどういう場所だったのか知らなかったので、首をかしげるだけだった。それももう、1年以上前のことだ。
「なんにする?」
店内にはほかの客はいなかった。マスターのほかに店員もいない。
「メープルトースト、まだある?」
師匠が訊ねると、マスターは残念そうに、「ごめんね。もうやってないんだ。いつも食べてくれてたのにね」と頭を下げた。
「そうですか」
師匠はサンドイッチとコーヒーを頼んだ。僕も同じものを注文する。
サンドイッチに包丁を入れながら、マスターがポツリと言った。
「あの時は驚いたけど、なんだかワクワクするような気持ちになったよ」
ドリッパーにペーパーをセットして、コーヒーミルで挽いたばかりの豆を入れる。そして、お湯を軽く注ぎ、膨らんだ豆の粉の表面に割れ目が出てくるのを見計らって、スッとお湯を回しながら落としていく。
「蓑を着て、入り口に立ったキミを見たら、なんだか思い出しちゃってね」
お待たせ、とサンドイッチとコーヒーが席に並べられた。マスターはカウンターの下を布巾でひと回ししながら、チラリと壁のほうを見る。
そちらに目をやると、ささやかな写真立てがいくつか飾られていた。
そのうちの1つには、京介さんが写っている。眼鏡をかけた知的な風貌の男性と、マスター、そしてエプロンをしたウェイトレス姿の京介さんの3人が、カウンターの前で並んでいる写真だ。男性は、ついさっき会ってきたばかりの服部調査事務所の所長だった。京介さんとマスターは営業スマイルだったが、服部さんはニコリともしていない。けれど、カウンターに置いた肘が、くつろいでいる様子を表していて、なんだか意外な気がした。
「あのころは、随分メチャクチャなことばかりあって、店を壊されそうになったり、胃薬が手放せないくらいだったけどさ。喉元過ぎれば、ってやつかな。懐かしくてね…… 蓑なんかを着て、みょうちきりんな格好の人が入ってきた瞬間に、あ、あの子が帰ってきたって…… 思っちゃった」
ははは、とマスターは照れたように笑った。
あの子、とは師匠のことではないのだろう。帰ってくるはずのない人だから、照れ隠しに笑っているのだ。
師匠はなにも言わず、じっと壁を見つめている。その視線の先には、1葉の写真がある。
京介さんの写真と同じように、カウンターの前に数人が並んでいる。右端には眼鏡の男性がいる。服部さんだ。表情は、判で押したように変らないが、今より少し若く見える。左端にはウェイトレス姿の女性がいる。白い髪留めをしていて、笑顔が爽やかな人だった。たぶんひかりさん、という当時のアルバイト店員だろう。その隣には、師匠が並んでいる。若い。目が今ほど死んでない。真っ直ぐにこちらを見ている。服部さんの隣には、ボサッとした頭の、くたびれたスーツ姿の男性がいる。含み笑いのような表情を浮かべて、首元に手をやっている。曲がったネクタイを直そうとしているような格好だった。服部調査事務所の前身である、小川調査事務所の所長だ。今では、タカヤ総合リサーチという大手興信所の所長を務めるかたわら、服部調査事務所のオーナーとして、忙しい日々を送っているそうだ。写真のなかでは、どこか捻くれたような、子どもじみた雰囲気をしていた。
写真のなかのマスターは、カウンターの内側に今と同じような格好で写っている。今より少し髪の毛が多いようだ。ショボショボした目つきで、心労のタネをいっぱい抱えているような様子だった。
「もう何年前になるのかな。いい写真でしょう」
マスターがこちらの視線の先を見て、話しかける。
コーヒーの柔らかな香りが立ち上ってくるなかで、師匠と俺は、じっと写真を見つめている。
いい写真、か。
ほかの写真立てにも、その時々の常連やアルバイト店員がマスターと一緒に写っている。けれど、その一枚だけはなんだか、ほかと違う。構図は同じだ。奇抜な格好をしているわけでもない。いったいどこが、違うのか。
悩むまでもなかった。ひと目でわかるのだ。これが、いい写真であることが。
写真の真んなかに、親指を立てて微笑んでいる人がいる。初めて見る人なのに、ずっと知っていたような気がする。その人がいるだけで、なにもかもが輝いて見える。その輝きのなかに、師匠の青春のすべてがある。
俺は、見ているだけで胸の奥が重くなり、つらくなった。俯いて、コーヒーカップに手を伸ばす。
師匠は目を逸らさずに、見つめている。
色あせることなく輝く、その美しい呪いを。
1 雑貨店
師匠から聞いた話だ。
大学2回生の夏だった。
その日僕はバイト先である小川調査事務所に朝から詰めていた。資料整理を頼まれたのと、昼から依頼人が来るからだった。
バイトの先輩であり、オカルト道の師匠でもある加奈子さんをご指名の依頼だった。ということはつまり、この興信所業界で『オバケ』という隠語で呼ばれる、おかしな依頼ということだ。
本来は「つかみどころがない」=「達成不可能」という意味のハズレ案件を指す言葉だそうだ。加奈子さんがその『オバケ』を解決してしまう、という特異な力を発揮するにつれて次々とそんな依頼が、この零細興信所に舞い込んでくるようになっていた。
所長である小川さんがかつて勤めていた大手興信所、『タカヤ総合リサーチ』の名物所長、高谷さんなどはかなり本気で加奈子さんを引き抜こうとしている節がある。
小川所長は、『オバケ』案件の依頼が多くなっている現状を愚痴りながらも、それが貴重な収入源になっている現実を鑑みて断固拒否している。
そして、「気楽にやれるところのほうがいいや」とは加奈子さん本人の談である。
その加奈子師匠は今、事務所の椅子にふんぞり返って、向かいの席にちょっかいを出している。もう1人のバイト、服部さんにだ。
「なあ知ってるか。忍者ハットリくんのあの顔って、お面なんだぜ。ニンジャは素顔を人に晒さないんだ」
ダンボール箱いっぱいの新聞の束から、小川所長がマーカーを入れている記事を切り抜いて、内容ごとに分類する作業をしている僕の背中に、そんな豆知識が飛んでくる。何度も聞かされたやつだ。
ゲコ。
ゲコ。
お尻にホースのついたおもちゃのカエルが、服部さんに跳びかかろうと跳躍を繰り返している。
もちろんホースの元は師匠の手のなかにある。このカエルも忍者ハットリくんの嫌いなものだったはずだ。子どもじみた嫌がらせだ。
当の服部さんは、師匠の嫌がらせを完全に無視して、淡々とワープロを打っている。
今日みたいな所長が留守のときには、互いに無視を決め込むことも多いが、師匠の機嫌のいいときには、このように服部さんイジリを敢行することもあった。実に迷惑な機嫌だ。
「だいたいだ。お前のコードネームはなんだ?」
「……坂本ですが?」
今度はなんだろう。コードネームというか、バイト用の偽名だ。興信所の性質上、脱法行為ギリギリのことにかかわることがあるので、バイトの僕らには偽名のついた名刺を渡してくれているのだ。
「おまえが『坂本』、私が『中岡』で、前にいた夏雄は『武市』だ。この3人は土佐勤皇党だ」
坂本龍馬、中岡慎太郎、武市半平太。確かに幕末の土佐藩出身の著名な志士だ。
「しかるにこいつは『服部』だ。服部だぞ! 服部半蔵って、初代は有名な伊賀の忍者の頭領だけど、時代下って幕末には十二代目服部半蔵正義ってのがいて、桑名藩の家老なんだ。桑名藩は会津藩と並ぶバリバリの佐幕派だ。勤皇の志士を弾圧した側だぞ。どうなってんだ!」
バンッ、と机を叩く師匠。
その言いがかりに、キーボードを叩く手を止めもせず、服部さんはただひとこと、
「本名ですから」
と言った。
「な、これだからな。職場の和ってものを考えてないんだ」
同意を求められても、返事に窮する。正直うっとうしい。今職場で仕事をしていないのは師匠だけだ。
「わたしは、この世界で生きていこうと思っています」
服部さんが発したその言葉には、おまえら学生の腰掛アルバイトとは違う、という拒絶のニュアンスが棘のように含まれていた。
「ちぇっ」
師匠は舌打ちをして、椅子の背にもたれかかり、足をガン、と机に乗せた。ホットパンツから伸びる太ももが眩しくて、僕はドキドキしてしまう。
「だったら、服部調査事務所でも立ち上げてくれってんだ」
師匠の憎まれ口に、服部さんが眼鏡を中指で抑えながら、さらに言い返した。
「そのときには、あなたが欲しい」
ゲコ。
ゲコ。
カエルが飛び跳ねている。
師匠はその言葉に虚をつかれて唖然としている。この間は、屈辱だろうと思った僕は、「モテモテですね」とフォローしてあげた。
「め、メシ喰いに行くぞ」
師匠は立ち上がり、僕を小突いた。
「ちょ、ちょっと待ってください。いま終わりますから」
せかされて、ちょうど整理し終わったファイルを棚に押し込み、僕は師匠の後に続いた。
階段を下りながら、僕は師匠の背中を見つめ、こういう意外な場面でのストレートなのも有効なのか、と心のメモにしっかりと記録していた。
「ちわぁ」
同じ雑居ビルの1階に入っている喫茶店『ボストン』のドアを開ける。
昼時なのに先客は1人だけ。あいかわらず閑散としている。
「いらっしゃい」
ヒゲのマスターが、カウンターで広げていた新聞を畳む。
「メープルトーストとサラダとオムライス。あとブレンド2つ」
僕の分まで注文しながら、いつもの2人掛けの席につくと、師匠は隣の座席に転がっていた女性雑誌を手に取った。
「あの野郎」
師匠は雑誌に目をやりながら、そんな舌打ちをしている。よほどさっきのやりとりが気に食わないらしい。
「小川さん来る?」
しばらくしてウェイトレスのひかりさんが、注文の品をテーブルに置いた。
「いま出かけてますけど、あとで来るかも」
僕はメープルトーストに手を伸ばしながら答える。
服部さんだけは誘ってもめったにボストンにはやって来ないが、小川調査事務所の面々はこの喫茶店の貴重な常連だった。
マスターがテレビをつけた。昼のニュースの時間だった。
相変わらず美味いメープルトーストを食べながら、テレビを見ていると、食べ終わるころにはローカルニュースになった。
市の東部で、中世の遺構が見つかったという。
それまで腕組みをして横からテレビを見ていたマスターが、興味をなくしたように厨房のほうに引っ込んだ。
画面では、日焼けした50歳くらいの作業着の男性が、七三分けの髪の毛を、ちゃんと七三になっているかと確認するかのように、しきりになでつけながら、興奮気味にしゃべっていた。
『これは、平安時代の軍馬の埋葬地だと思われます』
背後に、掘り出されつつある大量の骨が映っている。
『馬装も一部残っています。ここは当時、受領(ずりょう)の郎党の営地があったとされている場所ですが、これは死亡した軍馬を一箇所にまとめて葬った、いわゆる馬塚です。一緒に埋葬されていた、このような鉄剣も見つかっています』
土の中から掘り出されたばかりの変色した刀剣が、ブルーシートの上のトレーに乗せられている。
『鎮魂のための魔よけですね。人墓ではよく見られるものですが、馬塚ではほとんど見られないものです。貴重な資料と言えると思います』
ニュースは発掘の様子を遠景でとらえる画面になった。そして最後に、ここが市の土地開発公社の所有地であり、市営運動場の移転先として計画されていたが、この発見によって計画の変更を余儀なくされるだろう、ということを伝えていた。
CMに入ったとたん、師匠が空になったオムライスの皿をどけながら、ひかりさんに言った。
「別のチャンネルも回してくれ」
「ん?」
ひかりさんは言われたとおり、リモコンでチャンネルを変える。どの局も、ちょうど昼のニュースが終わるところだった。
師匠が左目の下を掻いている。
「あんなもの、公共の電波で流しやがって」
昼のドラマが始まった画面を見ながら、ぶつぶつと呟く。
「あんなものって、なんですか」
僕の問いかけに師匠は答えず、不愉快そうにコーヒーを口にした。こういう表情のときの師匠は、まず答えてくれない。もったいぶるのは得てして、オカルト絡みのことばかりだ。
(つくづく名探偵だねえ)
僕は皮肉を口のなかで転がした。そんな師匠が嫌いではなかった。
昼食を食べ終わり、僕らは3階の小川調査事務所に戻った。昼の1時に依頼人と待ち合わせをしているのだ。ほどなくして小川所長も外出から帰ってきた。
所長は服部さんにいくつか指示をしてから、事務所の壁の時計に目をやった。あと10分ほどで1時だった。
「時間通りに来るかな」
右手で腹を押さえていることからして、どうやらボストンに行きたいらしい。
「食べてきてもいいですよ。とりあえず、私が話聞いときますから」
師匠がそう言いかけたときだった。
突然、身体に寒気が走った。なにか来る。
嫌な予感を濃縮したようなものが血液に混ざって、全身を廻り始めたような感じ。
ガタンッ。師匠がふんぞり返っていた椅子から、一瞬で立ち上がった。
服部さんと小川所長は怪訝な顔で、入り口のドアと、反対方向の窓、そして師匠と僕の顔を交互に見ているだけだった。
僕と師匠だけ! 反応しているのは、僕らだけだ。
そういうなにかが、来る。それも、これは……。
身体が震える。ただごとじゃなかった。恐ろしい悪意……、いや、害意の固まりのようなものが、迫ってきていた。
「うわっ」
真っ黒な煙が、ドアや壁の隙間から溢れ出てくるような感覚に思わずあとずさった。呼吸が早くなる。
「どうした」
小川所長は、僕らの異変に気づいて師匠の肩に手を触れた。
ゴツン、ゴツン。
階下から、足音が上がってきている。このオンボロビルは、階段の足音がよく響くのだ。
来る。
「下がって」
師匠が鋭く言って、入り口のドアに向かって身構えた。小川所長はその指示には従わない、とばかりに師匠の横に立った。服部さんは無表情でドアのほうに顔を向けながら、ワープロのキーに手を置いたままだ。
僕だけがさらに1歩、いや、2歩下がった。床がキュッと鳴る。足音が、3階の小川調査事務所の前で止まった。
ノックの音。
「どうぞ」
小川所長がドアに近づかず、その場で声をかける。ノブが回り、ドアが開く。師匠が重心を落として、不測の事態に備えるのがわかった。
「や、どうも。少し早かったですかな」
ドアから現われたのは、小太りの中年男性だった。ボーダーのシャツに、青いサマージャケット。下はスラックス。髪の毛は短髪で、白髪が目立っていた。容姿はともかく、服装はちょっと小洒落た感じの男だ。
違う。一目見た瞬間わかった。あの黒い、もやのような気配は、するすると逃げるように遠ざかっていく。
師匠は男性に駆け寄ると、「だれかと一緒に来ましたか」と問いかけた。
「え、いや。1人ですけど」
男性はめんくらいながら人差し指を1本立てて見せた。
「失礼」
師匠は男性の横をすり抜け、ドアから飛び出していった。僕は一瞬迷ったが、その後を追った。
「なんですか、いったい」
男性のそんな言葉を背中で聞き流して、階段を駆け下りる。早い。師匠はもう見えない。
躓きながら全力で階段を下りきって、ビルの外に出ると右の方に少し離れた場所を師匠が走っている。
「おまえはそっち!」
振り向きながら師匠は、逆方向を指さして怒鳴る。小川調査事務所の入っている雑居ビルは、繁華街から少し離れた筋にあるので、昼間から人通りが少ない。
とにかく左のほうに走ってみる。通り過ぎる人の顔を覗きこんでみるが、なんの気配も感じなかった。むしろ不審そうな顔で見られただけだ。
結局何本目かの十字路で折れ、キョロキョロしながらぐるりと1周して元の雑居ビルに戻ってきた。
「逃げられたか」
師匠はもうビルの前に立っていた。ボストンに寄ってみて、マスターに変なやつを見なかったか訊いてみたが、首を振るだけだった。
「に、逃げたっていうか……」
僕は言葉に詰まった。
まだ足が竦んでいる。正直、探しているときも、いないでくれと思っていた。見逃してもらったのは、こっちじゃないのかという気がしてくる。
「なんですか、あれ」
「わからん」
師匠はもう息が整っている。僕はまだ喘いでいた。
「人間だと思うが、なにかおかしい。こないだの子猫ちゃんとはわけがちがうな」
子猫ちゃん? 風のなかに髪の毛が混ざっていた事件で出会った、あの女子高生たちだろうか。たしか師匠はそう呼んでいた。
「あれが、人間なんですか」
僕には、とんでもない悪霊が迫ってきているような感覚だった。
師匠はなにか考えている顔をしていたが、「依頼人に会おう」と言ってビルに入った。
事務所に戻ると、依頼人の男性は応接用のソファに座って所長と話していた。
「やあ、戻ってきましたな」
「すみませんでした。突然」
そろって男性に頭を下げたところで、すぐに師匠は顔を上げる。
「ところで、だれかにつけられる覚えはありませんか」
「つけられる?」
依頼人はきょとんとしていた。
◆
依頼人は緒方正人と名乗った。海外、主に台湾や、東南アジアからの輸入雑貨を扱う店を経営しているという。アーケード街の北のほうに店舗を構えているらしい。小川調査事務所のメンバーはだれも行ったことがなかった。
最近、緒方氏の店では、おかしなことが立て続いて起こっているという。
売り物のガラス細工が、さわりもしないのにリンリンと鳴り出したり、だれもない店の隅からすすり泣くような声が聞こえたり。天井の照明からの光でできた影が、奇怪な形に変化したり、という現象が。
このままでは、オバケが出る、という変な噂が立ってしまって、客足にも影響が出始めかねない、というのだ。
「たぶん、変なものを一緒に持ち込んじゃったんだと思うんですよ」
向こうでの買い付けは自ら行くそうで、エスニックで、少し怪しげな雑貨が緒方氏のお気に入りだった。台湾の先住民族のお面や、フィリピンで買った波紋のような模様のタペストリーなど、どこかピンとくるオーラを感じて入手したもののなかに、なにか良くないものが混ざっていたのではないか、と言うのだ。
「そういうことなら、小川調査事務所に専門家がいると、仁科さんに伺いましてな」
緒方氏は暑っつい、と悪気なく呟いて、懐から取り出した扇子で自分の顔を扇ぎはじめた。応接用のソファには、緒方氏と所長、師匠と僕の4人が座っている。
所長が目配せすると、服部さんがエアコンの設定温度を下げた。「や、すみません」と緒方氏は手を振った。
仁科、というのは以前、師匠が解決したオバケ絡みの事件の依頼人の老婦人だった。それ以来、師匠のファンになってしまったようで、頼みもしないのに、方々で熱烈にプッシュしてくれているのだ。
なんでも代々、商店を営む資産家で、世話好きが高じて地元の商工会や婦人会など、あらゆるところで役員をしているらしい。この仁科さんの紹介が、オバケ事案の依頼の、主要なルートになりつつあった。
「仕入れたものを全部捨てるのはさすがに大損するので、なんとかその原因になっている雑貨を、特定してくれないものですかな」
依頼自体は、よくある、というと変だが、加奈子さんに持ち込まれる事案としては、想定の範囲内のことだった。
師匠は正面に座る緒方氏の目をじっと見つめた。僕も同じように横からその目を覗き込む。なにか、霊的な気配をかすかに感じる気がするが、それが緒方の店にある妖しい輸入雑貨のせいなのか、それともさっきの何者かが撒き散らした悪意の残滓なのか、僕には判断がつかなかった。
「もう一度伺いますが、尾行される心当たりは?」
「ありません。ありません」
緒方氏は2度も言って、右手を大袈裟に振って見せた。人の良さそうな人物だった。
師匠は少し考えて、所長に目で告げてから、「お引き受けします」と言った。
ただし、と条件を出した。
「ちょっといま立て込んでいまして、そうですね」と手帳をパラパラとめくる。「1週間後ではどうでしょうか」
「1週間後ですか……」
緒方の顔が曇った。
「変な噂が立ったら困るので、早めにお願いしたいんですが」
「その店、晩は何時までやってるんですか」
「開店は正午からで、晩は9時に閉めます」
結構遅くまでやってるんだな。経営が苦しいのかも知れない。さっきまでニコニコとしていたが、今は渋面で、うつむき気味になっている。
「では、3日後、閉店後の午後9時では」
「3日後。それなら」
緒方氏は顔を上げた。
「あなたがいらっしゃるんですか」
緒方氏はなにか言いたげな口調だった。こちらはそういう態度には慣れっこだった。どだい、霊能力者なんていう触れ込みで、師匠のような若くて健康的な容姿の女性が出てくると、疑いの目を向けられるのは仕方のないことだった。
「そうですよ。仁科の婆ぁ……、仁科さんからはなんと聞いていらっしゃったんですか」
「あ、いえ、そうではなくて。すみません。よろしくお願いします」
緒方氏はまた手を振って、とりつくろうに笑ってみせた。
依頼人が去ってから、小川所長は師匠に「どうして3日後なんだ」と訊いた。
たしかに、立て込んでいる人間が、暇をもてあまして朝からカエルのおもちゃで同僚をからかったりしないだろう。
「調べたいことがあるんですよ。それで所長、服部を少し貸してくれませんか」
「ん。いいけど、どうするんだ」
「緒方さんの尾行をしてもらいたいんです。家まで。それで、だれか他に尾行をしている人間がいないか、確認を」
それを聞いて所長は、スッと服部さんに指で合図を出した。服部さんはすぐに立ち上がって、なにも言わずに事務所から出て行った。
「私もちょっと、別に調べることがあります。また連絡します」
師匠は愛用のリュックサックを背負うと、黒い帽子を被った。
「どこ行くんですか」
僕もついて行こうとすると、師匠は、「おまえは資料整理がまだあるだろ」と言って、そっけなく突っぱねられた。
師匠は、「じゃ」と言って事務所のドアに向かいかけて、「あ、そうだ」と振り返る。
「せっかくバイトが土佐勤皇党を結成してんだから、服部にもコードネームつけてくださいよ。『岡田』なんてどうですか」
じゃ。
師匠は眉を上げて笑顔を浮かべながら、事務所から出ていった。
◆
服部さんは1時間くらいで帰ってきた。家まで後をつけたが、ほかの尾行はいなかったそうだ。
結局その日は、師匠は戻ってこないまま、僕の資料整理のバイトは終わった。小川さんは所長なのに、バイトの身の師匠の秘密主義的行動を許している。逆に、所長の指示にきっちり従う服部さんなどは、師匠のそういうところを嫌っている。僕はその師匠の助手として、この事務所に転がり込んでいる立場上、服部さんからも距離を置かれている。
しかし、これだけは訊いておかなければならない。
「あの。服部調査事務所の話、どういう意味なんですか」
「どういう意味とは、どういう意味ですか」
僕の帰り際のひと言に、デスクの服部さんは静かに向き直った。
「いやその。……あなたが欲しいっていう、あの……」
ふっ。
服部さんは息を吐くと、「嫌味ですよ」と言った。
なんだ嫌味か。ホッとすると同時に、服部さんもそんな冗談を言うんだと思うと、おかしくなった。
「彼女は、ある種の人間にとっては梯子のような存在です。はたで見ていて、そう思います。足を掛けて登れば、日常と少し違う景色を見せてくれる。……そうでしょう?」
面白い比喩だった。けれどそれを語る目は、冷たかった。いつかの松浦というヤクザのような。
しかし決定的に違うのは、松浦が師匠を手元に引き寄せようとする人間なのに対し、服部さんはそんな師匠を嫌うのに十分なリアリストだということだった。
「けれど梯子は、けっしてだれかの居場所になることはできない」
それだけ言って、話は終わりだ、とばかりに服部さんは書類に目を戻した。
僕は腹にカッと燃えるものを感じた。師匠を嫌う服部さんが、僕以上に師匠の本質を捉えていたように思えたのだ。
「服部さん。詩人になれますよ」
それが精一杯の強がりだった。
翌日と2日後は大学の授業に出た。
一度師匠の家に電話したが、いなかった。忙しいのか。いったいなにをしているのだろう。
そうして約束の3日後がやってきた。
午後6時に小川調査事務所に入ると、師匠がまた服部さんをからかっていた。
「うまいなあ。ハンバーガーうまいなあ。あげないけど」
向かいに座り、ホットパンツから伸びた両足をだらしなくデスクの上に乗せて、ハンバーガーの包み紙を握り締めている。
あったな。ハットリくんにそんな設定。実にきめ細やかな嫌がらせだ。
服部さんはその嫌がらせを完全に無視して、帰り支度をはじめた。
「僕も帰るけど、今夜はよろしく頼むよ。大丈夫だな」
小川所長もネクタイを緩めながら、スーツの上着を肩にかけた。
所長と服部さんと見送ってから、僕と師匠は事務所で2人きりになった。約束の時間は、緒方氏の営む雑貨店が閉店する午後9時。まだ結構時間がある。それまで打ち合わせをするのかと思ったが、師匠は余裕の様子で、ソファに寝転がって漫画本を読んでいる。
「大丈夫なんですか」
「大丈夫、大丈夫」
生返事だ。
「呪いの雑貨を特定するんでしょう。いきなり行って、できるんですか」
どういう雑貨があるか、あらかじめ聞いて調べたりしないのだろうか。
結局師匠は時間まで漫画を読んだり、居眠りをしたりして過ごした。僕もしかたなく、事務所の掃除などをして時間を潰した。
そうして小川調査事務所を出て、午後9時ちょうどに緒方氏の雑貨屋の前に立った。『ジャガナート』という看板が出ている店だった。
夜のアーケード街は人影がなく、うら寂しい風景だった。電車通りから南にのびるアーケードだったが、『ジャガナート』のある辺りは、だいぶ奥のほうで、もともと人通りが少ない場所だった。そして午後9時ともなると、ほとんど通行人の姿は見えなくなっている。
店の紹介をしている手書きのカラフルな立て看板には、『本日は閉店しました』というボードがかけられている。
『CLOSED』
というカードがこちらを向いている自動ドアを通ると、御香の匂いが鼻を抜けた。夏向けの、どこか涼しげな香りだった。
「お待ちしておりました」
黒っぽい貫頭衣を着た緒方氏が、にこやかにやってきた。店内はアジア圏特有の雰囲気の雑貨でいっぱいだった。足をぶらぶらさせた人形や、灯篭のような形のランプシェード。象やアジサイの描かれた皿などが、ところ狭しと陳列されている。
「あ、お1人じゃ、なかったんですね」
師匠と並んだ僕を見て、緒方氏は微妙な表情を浮かべた。どこか不満げな様子だ。
「こいつは助手ですから、別に料金は倍にはなりませんよ」
師匠は笑って僕の肩を叩いた。
「で、この店のどこで、どんなことが起こるのか、詳しくお聞かせ願えますか」
「あ、はい」
緒方氏は、師匠と僕に、店内の紹介をしていった。
「で、こちらの牛の形をした陶器の鈴が、だれも触っていないのに、ひとりでに鳴りだしたり……」
「ほう、ほう」
丁寧に説明する緒方氏とはうらはらに、師匠はなぜか形ばかりの相槌を繰り返すばかりで、まったく身が入っていなかった。
僕のほうは精神を集中して、立ち並ぶ雑貨から、なにかの気配を感じ取ろうとしていたが、どうも思わしくなかった。
ほとんどなにも感じないのだ。キョロキョロと周囲を見回すが、先日感じたようなほんの微かな違和感があるばかりだ。
僕らの態度に、緒方氏は苛立ちを抑えたような表情をしはじめた。この調査に店の経営がかかっているのだ。さもありなん、だ。
「こっちは事務所ですか」
「事務所というか、私の控え室のような、あっ」
師匠は、店の奥にあったドアを開けて、勝手になかに入った。
「へぇ。結構広いですね。2人くらい寝られそうだ」
ドアの向こうには、仕事机や小さな冷蔵庫があった。奥には床のうえに畳が敷いてある。
「こっちは、特になにもないですよ」
緒方氏は怒ったように言った。師匠はそれを無視して、部屋の物色を続ける。
「お、これはいいカメラですね。こっちは、ほうほう。立派なレザーベルトじゃないですか。店のほうに置かないんですか。……おや?」
師匠は急に屈んで、床からなにかを拾い上げるような動きをした。
「アルバムが落ちてましたよ。緒方さんのですか」
こちらを向いて、花柄の写真アルバムらしいものを師匠は捲ろうとする。
「か、返せ!」
その瞬間、緒方氏は目を剥いて叫んだ。僕はビクッ、としてしまった。その豹変したような怒鳴り声に驚いたのだ。
緒方氏は師匠の手からアルバムをもぎ取ろうとする。師匠はその手をひらりとかいくぐると、部屋から店内へ出た。緒方氏はさっきまでの人の良さそうな姿が別人のように、唸り声を上げながら師匠を追いかける。
「なんだよ。怖いなあ。からっぽのアルバムじゃないですか。そんなに目くじら立てなくても」
師匠は店のなかで振り返ると、笑いながらアルバムを開いてこちらを向けた。写真が収まるはずのポケットはすべて空だった。
緒方氏はギクリと足を止めた。
「な、なぜ」
「まあ、少し落ち着いてください。あなたの大事なアルバムは、家にあるはずでしょう。こんなところに置きっぱなしにしてるはずはない」
うそだろ。
僕も驚いていた。師匠はこの、呪いの雑貨を探す、という依頼を、まったく別のものに作り変えていた。僕も、そして緒方氏も知らないあいだに。なにが起こっているのか、さっぱりわからなかったが、それだけははっきりしていた。
「友人にな。非合法の写真屋がいるんだよ。普通の店じゃあ、現像してくれないような写真を扱う、特殊な写真屋だ。おまえ、以前そんな写真を持ち込もうとしたな。やつは覚えてたぞ。ついてなかったな。結果的に客にならなかったから、守秘義務じゃ守ってくれなかったぜ」
『写真屋』こと、天野のことか。小川調査事務所ご用達の、変態的なアングラ男だ。
師匠の口調が変わっている。緒方を依頼客と見なさなくなったのだ。
「こないだのウチの事務所でも、私の足ばっかりエロい目で見やがって。脚線美なのは認めるけど」
師匠は扇情的な動きで、素足の太ももを自分で撫でた。緒方の顔に異様な量の汗が噴き出し始めていた。
「なにがどうなってるんですか」
態度のおかしい緒方を警戒しながら、僕は師匠に問いかける。
「この変態はな、閉店間際に店にいた女性の1人客を狙って、婦女暴行を働くのを趣味にしてる、人間のクズだ。さっきの部屋に引っ張り込んで、写真を撮ったりしてな。警察にチクったら、写真ばら撒くぞって脅してるんだろ」
僕は驚いて、師匠と緒方を交互に見た。
「他の店はみんなとっくに閉まってるこんな時間まで、流行らない雑貨店を開けてること自体、おかしいだろ。アーケード街に人がいなくなって、ちょっとやそっと騒いでもバレないようにわざわざ9時閉店にしてんだよな。そうだろ」
師匠が緒方を睨みつける。緒方の喉から、ぐぐぐ、という鈍い音が漏れている。僕はとっさに師匠を守れるように、すぐ側に寄って緒方に正対した。
「おーっと、もう観念したほうがいいぞ。写真はもうこっちが押さえてある。日中、留守の間に、ちょちょいっ、とな」
服部さんに尾行させたのは、家をつきとめるためか!
そして証拠を押さえる時間を確保するために、依頼日から3日間待たせたのだ。
「なんでわかったんですか」
「よく目を見てみろよ。こいつの。ドス黒い色情にまみれた霊がついてる」
えっ。僕も驚いたが、緒方もまた驚愕して自分の顔を両手で覆い、輪郭をなぞり始めた。事務所で会ったときから感じていた微かな違和感は、そのせいだったのか。たしかに、今はその人の良い笑顔の裏に隠れていた醜い魂が、むき出しになっているようだった。
「霊っつっても、おまえの店で起こるっていう怪現象とは関係ないぞ。店に入ってみて確信した。ここには、呪いの雑貨なんてない。本当にそんなことを体験したというなら、それはおまえの罪悪感が生んだ幻だ」
そうだ。緒方はたしかに、『変な噂が立ったら困るので』と言った。逆に言うと、客はまだその怪現象を体験していない、ということだ。緒方自身しかその現象に遭っていないのだ。すべては緒方の心の闇が生んだものだった、ということか。
「依頼のとき、私が来るのか、って確認してたな。もし今日1人で来てたら、どうするつもりだったんだ」
そうか。カメラと、拘束用のベルトは、あわよくば今日使うつもりだったのか。
怒りが腹から湧いてきた。僕の師匠に、この野郎。
「自首しろ」
師匠は冷たく言い放った。「その業を落としてこい」
「うう」
緒方の目の色が変ってきた。比喩ではなく、なにか混ざり始めたような感じ。ドロドロとした怨念のようなものが、外へ漏れ出ていく。
僕が身構えようとした瞬間だった。異様な気配が、爆発するように店内の空気を一変させた。
「なにっ?」
師匠と僕は驚いて、とっさに戦闘姿勢をとった。しかしすぐに、それが緒方からではないことに気づく。
「く……くるな。やめろ! うわぁああああ」
緒方が両手を前に突き出して、狂ったように振り回した。
後ろか。
僕は振り返る。カーテンを閉めた入り口のドア。その向こうは、暗い外。そこに、なにか、いる。
「ギャアアアッ」
悲鳴とともに、ガシャーン、と激しい音がして思わず振り向くと、緒方が店の奥の壁際にあったガラスケースに倒れ込んでいた。
ガラスが割れる音と、なかにあった陶器の商品が割れる音が混ざって、耳を打った。
「や、や、や」
緒方はガラスの破片まみれになって、頭から血を流し、ガタガタ震えている。それでも、上半身を起して、右手で頬を押さえながら、入り口のドアを左手で指差し、「や、や、や」と繰り返している。
「なんだ。なにが起きた」
師匠は緒方に叫んだが、すぐに入り口のほうを向くと、走り出した。僕も後を追う。
厚手のカーテンを開き、ドアを開けようとしたが、自動ドアはスイッチが切れたのか、動かなかった。2人がかりで隙間に指を入れてこじあけ、外に飛び出した。
「くそっ」
左右を見たが、暗い照明の灯るアーケード街は、どこまでも無人の空間だった。人影はどこにもない。
気がつくと、あの一瞬に店内で膨れ上がった真っ黒な気配は消え去っていた。
店内に戻ると、僕はまだ倒れたままの緒方に問いかけた。
「なにがあったんです」
緒方は小刻みに震えながら、恐怖に怯えた顔で、頬を押さえていた右の手のひらをどけた。そこには、抉られたような痛々しい傷があった。頬骨のところだったのか、白いものが見えていた。
うわ。
手のひらには真っ赤な血が滴っている。緒方はそれを見つめて、ぶるぶると声を絞り出した。
「や、やで……」
師匠はハッとして、緒方の目を覗き込んだ。そしてゆっくりと確かめるように言った。
「矢…… 弓矢で、撃たれたんだな」
「そんなバカな。どこから、そんな」
僕はうろたえながら、状況を確認する。緒方の正面は入り口のドアだ。厚手のカーテンも、自動ドアも閉まっていた。外から弓矢で撃たれるはずがない。散らばったガラスや陶器の破片のなかを探したが、緒方の頬を抉ったという矢は、どこにも見つからなかった。
「矢なんてないですよ」
「ない。矢を射掛けられて怪我をしたのに、矢がない…… 見つからない……」
師匠は目を見開いて呟いている。
緒方の頬の傷は本当に弓矢でついたのか? 転んで、ガラスで切っただけなんじゃないのか。
僕はしごくまっとうな言葉を吐こうとしたが、師匠のただ事ではない様子に、口をつぐんだ。緒方は震え続けている。さっきまでのむき出しの暴力的な性のエネルギーは霧散していた。憑き物がとれたようだった。
「弓……」
師匠は焦点のあっていない目元を、右の手のひらで覆った。
「ゆみ、つかい」
師匠はもう一度外のほうへ顔を向け、ひとこと、そんな言葉をこぼした。
◆
「弓使い?」
小川所長が呆れたように言った。
「そうだ」
師匠は真剣な表情で所長を睨む。
緒方の雑貨屋での事件から一夜明けて、僕と師匠は調査事務所で所長にことの顛末を報告していた。
その事件で警察沙汰に巻き込まれたくなかったが、緒方の怪我を放っておくわけにもいかず、救急車を呼んだ。そして警察にはその場で師匠から電話した。
当然緒方の罪状も説明することになるが、告発するための証拠となる写真の一部は師匠が持っていたものの、住居不法侵入の産物だった。師匠の立場がどうなるのか、不安でしょうがなかった。
けれどやってきたのは西署の1課の当直の刑事だけでなく、なぜか応援で2課の刑事もいた。
不破だ。不破は小川所長の刑事時代の元同期で、小川調査事務所、特に『オバケ』事案専門家の加奈子さんとは協力関係にある、素行不良刑事だ。
2課で暴力犯を担当しているはずの2係主任の不破は、やってきた1課の強行犯担当の2人を差し置いて、その場で1課長の丸山警部の自宅に電話し、なにごとか話をつけた。
それから師匠と僕は、西署に連れて行かれ、事情聴取を受けたが、状況説明をしただけで、日付が変るころには解放された。師匠の住居不法侵入及び写真窃盗のお咎めはなかった。
最後の、緒方が見えない矢で襲撃されたという部分は、犯罪を追及されてうろたえ、ガラスケースに転倒した、ということにした。
ただ、緒方が搬入された病院でも、雑貨店の外から弓矢で撃たれた、と言っているらしく、その部分だけ執拗に確認された。しかしそう言っているのは緒方だけで、状況から、その可能性はないに等しかった。僕自身も信じていない。師匠も淡々とそう説明していた。
なのに、である。
小川所長の前で、師匠は「弓使いが緒方を撃った」と言い切ったのだ。
「あー、ちょっといいかな。加奈ちゃん。自動ドアはスイッチを切られて、閉まっていた。カーテンも掛かっていて、外は見えない。なのに緒方は、店の外から弓で撃たれたっていうんだよね」
「そうだ」
「本人はそう言っています」と僕も加わる。
「で、カーテンにも自動ドアにも穴は開いてないし、矢も見つかってないと」
小川所長はタバコを胸ポケットから取り出して、マッチで火をつけた。
「妄想だろう。店で起きてるっていう怪奇現象もそうだったんだろ。自分の悪癖がもたらした罪の意識に苛まれて、おかしくなってたんだな」
「所長。西署で事情を聞かれているとき、担当の刑事たちが『弓使い』という言葉を、お互いに交わしていました」
それは、僕も聞いた。改めて彼らの会話を思い出すと、初めて使う言葉ではなく、日常で使っているようなイントネーションだったような気がする。
「去年の冬ごろから、弓矢を使った通り魔事件が続いていたでしょう。目立つ武器を使っていることと、被害者が犯人の姿を目撃しているにも拘らず、なかなか逮捕されなかった。最近あんまりニュースでも見なくなりましたけど、まだ捕まってないんですよ、あれ」
「ああ、あったな。そんな事件」
「県警では、その犯人を『弓使い』と呼んでるみたいですね。そして恐らく、今回の緒方の件と、共通点があるんですよ。『犯行に使われた、矢が見つからない』っていう」
「そんなこと、ニュースでやってなかったよ」
「隠してるんでしょう。マスコミ向き過ぎるから」
なるほど。矢で射られたはずなのに、その矢が見つからない。そんな事件が連続して起こっている。マスコミの恰好のネタだ。
「これまでの報道を拾ってみました」
師匠は、新聞の切抜きのコピーを数枚、所長のデスクの上に広げた。僕が所長の指示で、記事の分類ごとに整理したやつだ。役に立ってよかった。
「最初の事件は去年の冬。市内で古紙回収業を営む男、34歳が、深夜1時に友人宅へ行こうと家を出たところで、何者かに弓矢で撃たれ、上腕を貫通する怪我を負った」
師匠は次々と、記事の概略を読み上げていく。
「2番目の事件はその2週間後。27歳のOLが深夜12時ごろ、オールナイトの映画を観るために外出し、駅前に向かっていたところ、表から1本入った路地で襲撃されています。彼女は脇腹を撃たれ、全治2ヶ月の重症。そして3番目の事件では被害者が亡くなっている。深夜2時過ぎに市内南部のコンビニで、車を置いていた55歳の会社員の男が、道路を渡った先の自販機の前で胸を撃たれた。コンビニまでたどり着いたが、搬送先の病院で死亡。4番目の事件は30歳の無職の男性が、深夜12時半ごろ、駅近くの呑み屋に向かっていたところ、線路沿いのひとけのない通りで、暗がりから弓矢で撃たれた。とっさにかばった右腕と肩に重傷を負っている」
師匠はさらに2件を読み上げ、これまでに報道された6つの事件の概要を説明し終えた。
「いずれも目撃者はなし。犯人の心当たりも、襲われる心当たりもない。そして警察情報では、犯行に使われた凶器が見つかっていない。被害者が『弓矢で撃たれた』とはっきり言っているにも拘らず、だ。そして最後の事件から、3ヵ月ほど経つけど未だに犯人は捕まっていない、と、こんなところですね」
「師匠、その犯人ですけど、女だって言ってなかったですか」
「そう。被害者の供述によると、犯人はフード付きのコートを着ていて、顔ははっきりしないものの、体格から女性ではないかと言われている。身長は165センチから170センチと、女性にしては大柄。私くらいの背格好だな」
師匠は自分の頭のうえに手のひらを乗せた。
新しいタバコに火をつけながら、所長が口を挟む。
「犯行に使われた弓はともかく、矢が見つかっていないというのが解せないな。犯人が持ち去ったとしたら、被害者の身体に突き刺さった矢を抜いたことになる。たしかそんな供述なかったんだろ」
「そう。弓矢を撃って、そのまま犯人はその場を離れている。そのあたりの被害者の供述が、報道された情報でははっきりしない。ただ、どうやら、『矢は消えた』という噂もある」
「消えた? それは被害者が言ってるんですか」
「いや、これはある警察筋から仕入れた情報なんだがな……」
師匠はズボンの尻のポケットからメモを取り出した。
「1人目の被害者は、事件現場に近い民家に助けを求めた際、『腕の矢を抜いてくれ』と喚いていたそうだ。腕から血は流れていたものの、なにも刺さってはいなかった。にも拘らず、だ」
「警察筋って、不破か? 加奈子、おまえ昨日も不破に助けられてるだろ。借りを作りすぎだ」
「昨日は高谷さんからも、話を通してくれたらしいですけど」
師匠はそう言って口を尖らせた。高谷さんとは、小川所長の義理の父でもある、タカヤ総合リサーチの名物所長だ。
県警のOBで、在職中は将来の刑事部長を嘱望された、切れ者だったという噂。現在でも県警には太いパイプがあるらしい。パイプというより、『弱み』を握っている、というほうが正確なのかも知れないが。
「……」
小川所長は後ろ頭を掻いている。どうやら、昨夜の依頼中に警察沙汰になったことを聞いて、高谷さんにご出陣願ったのは小川所長らしい。僕らにことさらそれを言わなかったのは、恩着せがましくないように、というより、困ったときのパパだのみ、という姿を知られたくなかったのだろう。
「とにかく、最初の事件では被害者はかなり錯乱していて、刺さった矢が途中で抜けた可能性もある。しかし、他の被害者も、おおむね似たような供述をしているようなんだな」
「つまり、矢が刺さってないのに、刺さってるって主張してるんですか」
師匠は頷いた。
一瞬、狂言、という言葉が浮かんだ。目的はわからないが、被害者たちは揃って、通り魔事件を装っているのではないか。そう考えたが、実際に矢傷のようなものを受けて重症を負っているのだし、死んだ人だっている。その考えには無理があった。思ったより、はるかにオカルティックな事件だった。
「被害者たちは、お互いに面識はなく、これといった共通点も見つかっていない。完全に通り魔的犯行だとしたら、目撃者の少ない深夜帯に行われていることと合わせて、犯人にたどり着くのはなかなか難しいだろうな。凶器の特殊性を加味しても」
「でも犯行に使われたのは弓道で使う、あの大きな弓だって話じゃないですか。そんな目立つものを持ち歩いていたら、いくら深夜でもどこかで見られてそうですけどね」
「被害者はそう供述している」
師匠は意味深な口調でゆっくりとそう言った。
「弓も、持っていなかった可能性があると?」
小川さんが師匠に問いかける。刺さっていない矢を、刺さっていると騒いだように、被害者の供述が信用できないのなら、そんな可能性だってあるということか。
「どうでしょうか」
すましてそう言う師匠に、僕は我慢できず、「昨日の件は、結局なんだったんですか」と訊ねた。
「緒方は、見えない矢に撃たれたと言っている。この通り魔と同じだって、そう言いたいんでしょう。緒方は雑貨にくっついた悪霊のせいで、店で怪奇現象が起きている、という妄想にとりつかれていた。最後の弓矢で撃たれたっていう騒ぎも、妄想だった可能性が高い」
「本当にそう思うか」
師匠の視線に射すくめられる。同時に、あのとき感じた異様な気配を思い出す。カーテンを閉めた店の外から、漏れ出るような殺意を感じたことを。それは、3日前に緒方が依頼のためにこの事務所へやってきたときに感じたものと同じだった。
「……いいえ。あれは、なんだったんでしょうか」
師匠は僕のひとり言のような問いには答えず、デスクのうえの新聞記事の切り抜きファイルを指さした。
「さっき読み上げた、通り魔事件の概要のなかで、私がすべての事件で、わざと省略しなかった部分がある。なにかわかりますか」
僕は少し考えたが、わからなかった。所長も両手の手のひらを上に向けた。
「第1の事件は、『深夜1時に友人宅へ行こうと家を出たところで』、第2の事件は、『深夜12時ごろ、オールナイトの映画を観るために外出したところで』、第3の事件は、『深夜2時過ぎに市内南部のコンビニに車を置いて、道路を渡った先の自販機の前で』、第4の事件は『深夜12時半ごろ、駅近くの飲み屋に向かっていたところ』……」
そこまで師匠が繰り返したところで、ハッとした。それと同時に、えっ、と思った。奇妙な一致だったからだ。
「ええと。もしかして、外出した目的を省略しなかったってことですか」
「そうだ」
師匠はニヤリとする。しかしそれは、別のことを意味していた。
「逆に言うと、全員、帰宅中じゃなかった」
僕はそう呟いて、ぞわっとした。意味もわからず、背筋が。
「そう。いずれも事件は深夜に起こっている。だから通り魔なら、帰宅途中で起こる蓋然性が高い。なのに、1件も帰宅途中のものはなかった。コンビニに車を置いていた第3の事件も、被害者の実際の足取りでは、その30分前に家を出たばかりだったことがわかっている。つまり、全員が、外出した後に襲撃されている。おかしいと思わないか。そんな深夜に、外に出る用事がある人間ばかりが襲われているんだ」
「通り魔じゃ、ない?」
犯人は、狙ったのか。待ち構えていて? だとすると、被害者を知っていたことになる。
「緒方も、以前から狙われていた」
そうだ。そうだった。本人は気づいていなかったが、3日前も緒方は狙われていた。あの異様な気配は、今思い出しても寒気がする。
「でも緒方は結局、外出中に襲われたわけじゃなく、店のなかにいるときに襲われています」
「そうだ。店に、女性を呼び込んだところでな」
「女性を?」
緒方はこれまで、閉店間際にやってきた女性客を狙って、性的暴行を加えていた。それも口止め用に写真を撮るという、卑劣な犯行を。そこに、若い女性である師匠が、1人でやってくる。店で起こる霊的な被害の調査のためだったが、あわよくば、という気持ちもあったのだろう。思惑外れて、助手の僕がくっついてきた上に、あの結末だったわけだが。
「犯人は、緒方の犯罪を知っていたって言うんですか」
「ああ。そう考えたほうがしっくりくる。最初は被害者のだれかじゃないか、と思ったんだけどな。復讐のために。でもこれが、見えない矢を使った一連の通り魔事件と、同一のものだとすると、別の絵が見えてくる。緒方の事件の状況を、ほかの事件に当てはめてみるんだ」
僕は師匠の問いに、首を振った。小川所長は苦笑いのような表情を浮かべて、タバコをくわえながら僕らの様子を眺めているだけだ。
「緒方は、邪悪な目的を遂げようとしたところで、襲撃されている。他の被害者もまた、深夜に外出したところで襲撃されている。そして、その外出の目的は、全員が、自ら主張するだけで、いずれも裏づけがとれていない」
えっ。
その師匠の言葉に、驚いた。
「第1の被害者は、友人宅へ行こうと家を出たというけど、不破情報では、友人には事前に連絡してなかったそうだ。そして第2の被害者は、オールナイトの映画を観るために外出したというが、チケットはあらかじめ買っていなかったし、結果的に観ていない。第3の被害者は、同居の家族にもなにも言わずに家を出ている。そして死亡しているので、外出の目的はわからないままだ。第4の被害者は、呑み屋に向かっていたというが、これも結局行っていないので、本当にそうだったのかは、わからない。」
たしかに。たしかに、被害者は全員、深夜に外出しており、その本当の目的は本人しか知りえない状況だ。だからと言って……。
「被害者が全員、なんらかの犯罪に関わっていたっていうんですか」
「犯罪をする前に、阻止されたんだよ」
師匠はそう言い切った。
そんなバカな。
「飛躍しすぎじゃないですか」
「んー」
師匠は額を押さえて、自戒するように首を振った。
「そうだな。まだなにもわからない」
ふーっ、と息を深くついて、師匠は広げたファイルを片付け始めた。じっと聞いていた小川所長が、そこでようやく口を開いた。
「加奈子。警察が動いているんだ。わかってるんだろうな」
「わかってますよ。連続通り魔事件が発覚してから、半年以上経つのに、まだ動きっぱなしだってこともね」
所長は、やっぱりわかってない、という諦観をこめた手のひらを、自分の額にペチンと叩きつけた。
「うちは慈善事業じゃないんだ。依頼もないのに、警察が動いている連続殺傷事件をかき回して、なんの得があるんだ」
「ルパンが相手なら、天下御免で出動できるんでショ」
師匠は急に、色っぽい声を出した。カリ城の不二子の真似か。たしかそのセリフの意図するところは……。
「オバケが絡むとなると、私は勝手にやらせてもらう。個人的にね」
師匠は帽子を手に取って、キュッと被った。
「待て、わかったから、連絡は入れろ。昨日みたいなことになったら、手遅れになるぞ」
「うう~ん。ス・テ・キ。さすが所長」
師匠にしなだれかかられ、小川所長は食いしばった口の端を微妙にグニグニさせていた。僕はそれを見て、もやっとすると同時に、師匠の言葉の一部にひっかかるものを感じていた。
「オバケが絡んでるんですか」
「ああ。まだカンだけどな」
師匠は、つつつ、と所長のシャツの上から胸を指でなぞった。所長は妙な顔をしている。ヤメロ、妙な顔をするな!
「さあ、なにが出るかな」
師匠は遠くを見るような目をした。その瞳のなかには、青白い炎がたなびいている。瞳の先には、まだ見ぬ怪物の姿があるのか。
弓使い。
警察のあいだで、そう呼ばれている通り魔事件の犯人を、師匠は追うと言うのだ。
その、見えない矢を。
僕は、ゾクゾクした。
馬霊刀 2/4
2 弓使い
それから1週間ほどは、なにごともなかった。
小川調査事務所の師匠を名指しした依頼は、特になかったので、そのあいだ僕らは事務所のバイトから離れていた。師匠とは2回ほど一緒に飯を食べたが、その『弓使い』に関わる話はしなかった。訊こうとしたが、「捜査中」と言って教えてくれなかったのだ。
その食事のうちの1回は、昨年に引き続いての師匠宅での『そうめん祭り』だった。師匠は地元の消防団に入っているのだが、そこでもらった大量のそうめんを、家で茹でまくるのである。
「小西もっと食え」
「中西です。食べてますよ」
師匠の部屋の隣に住んでいる、卵のようなのっぺりした顔の隣人も、昨年に引き続いて呼ばれていた。職業不詳の男だが、ボロアパートの住人なのに加え、この師匠に食料をたかりに来るというつわものなので、よほどひどい暮らしをしているのだろうと思われる。
「今年の夏も暑いですねぇ」
隣人は大袈裟にそうめんを啜り上げながらも、正座を崩そうとしない。妙なところで律儀なところがある。対照的に師匠はホットパンツであぐらをかいている。
クーラーなどない部屋だ。氷をのせたそうめんの山は、見た目には涼しげだが、みんな汗だくだった。
「そういえば、お2人はいつごろご結婚なさるのですか」
僕は、ぶほっ、とそうめんを数本吹いてしまった。
この卵男、いきなりなにを言うのだ。
「いや、よくここへ通ってらっしゃるので、もうそろそろかと思いましたが」
「馬鹿じゃねーの中西、この野郎」
師匠が字面とは裏腹に、冷徹な声で突っ込みをいれた。しかしよく見ると、鼻からそうめんが出ている。
「私の名前は大西ですよ。あれ。まだなんですか。お似合いだと思いますが。まあ、旦那さんのほうはまだお若いですからね。大学卒業を待って、という感じでしょうか」
「こいつの卒業待ってたら、へたすると私30歳越えるぞ。ていうか、そういうんじゃないからこいつは」
「はあ」
グッジョブだ、卵男。名前も毎回違うし、ほとんどなにも考えずにしゃべっているテキトーな男だが、今回はグッジョブだ。
僕は卵男のノルマの皿から、お椀1杯分くらいのそうめんをもらってやった。すると卵男は、「なにするんですか!」とそれを奪い返す。
「まだ食えるんですか」
呆れてそう訊くと、「死んでも3日分は食い溜めます」とノロノロ箸を動かしていた。
その日も結局、そうめんだけ食べて解散だった。
師匠がいつもに比べて、ずっとどこか不機嫌そうな様子だったのは、『弓使い』の捜査がうまくいっていないのかも知れない。それもそうだろう。あれだけニュースになって、警察が去年の冬から懸命に捜査している事件なのだ。零細興信所のいちバイトの身に過ぎない師匠が、急に真犯人を見つけられるはずもない。
ただ、ことオカルトやオバケが絡むとなると、師匠はその能力を遺憾なく発揮する可能性もある。警察が犯人を見つけられないのも、オカルトじみたことが原因なのだとすると……。
『乗車券をお取りください。乗車券をお取りください』
「おっと」
考えごとをしていて、乗るバスを間違えるところだった。
足をかけた乗車口から下り、サイドミラーでこっちを見ているであろう運転手に、両手でバツマークを作って頭を下げる。
やがてバスはゆるゆると発車していく。排ガスが雨粒のなかに一瞬、生ぬるい空気の層を作る。僕は傘をさし直して、頭についた水滴を払った。
昨日から雨が降り続いている。空はまだ昼間の4時だというのにうす暗い。研究室の友人宅からの帰りだった。いつもは自転車なのだが、荷物があったので、濡れるのが嫌でしかたなくバスを使っていた。
友人宅は市内の南のほうで、医学部キャンパスに近かった。バスに乗って来るとき、途中で医学部の付属病院が見えて、少し気分が悪くなった。師匠が定期的に受診して、検査を受けていたことを知ったのは、先日のことだった。
いったいなんの病気なのか。結局本人に聞くことはできないでいた。
住んでいるアパートのほうへ向かうバスは、この次だった。バスの停留所には、自分ひとりしかいなかった。ベンチはあったが、申し訳程度の屋根しかついていないせいか、雨に濡れていて、座る気にはなれなかった。
傘をさして立ったまま、僕はいろんなことを考える。そのほとんどが、いや、すべてが師匠のことだった。なにもかもが、気になって仕方がなかった。最近服部さんをやけにからかっていることさえ、気になった。まさか、服部さんに取られることはない、と信じているのだが。
あの野郎。
師匠が、「服部調査事務所を作れ」とからかったときに、「そのときには、あなたが欲しい」などという、思わぬ返事を受けて戸惑っていたことが、我がことのように腹が立つ。あの陰険ヒョロ眼鏡が! そのときには、もれなく僕もセットだこの野郎!
そんなことを考えていたときだった。
自分の背後に、だれかがいた。
傘を、雨粒が打っている。その音が、急に大きくなった気がした。
首をわずかに捻ると、視界の端に、灰色のレインコートが見えた。
後ろを取られた。
とっさにそう感じた。
なぜそう思ったのか、考えをまとめる余裕もなかった。とにかく自分のなかの、危険を察知する能力がそう告げていた。
振り返ることができない。だめだ。なぜって、後ろを、取られたからだ。それだけが、脳にアラートを告げている。
雨のなか、周囲にはほかにだれもいない。目の前の道路を、車が途切れ途切れに走り抜けていく。
「あの女は、なにものだ」
女の声がした。
灰色のレインコートは位置的優位をあっさり捨て、スッと僕の横に立った。
深くフードを下ろしている。顔は見えない。
女だ。まだ若い。背は高め。体格はスリムだ。なぜか右手にだけ、厚手の手袋をしているが、手にはなにも持っていない。
「なにか、妙なものが混ざっている。あいつは、敵なのか」
最後はひとり言のようなイントネーションになり、同時に、ざわざわと空気がヒリつきはじめた。
緒方が依頼に来たときに、感じたあの気配。そして緒方の店『ジャガナート』で感じたあの、寒気のする気配。
こいつだ。弓使い。師匠が追っている、連続通り魔事件の犯人。
それが、直感でわかった。
師匠。こいつはだめだ。
足が震えて、涙が、涙腺の奥から湧き出てくる。
こいつは、無理だ。
生身の人間に、どんな心霊スポットでも味わえないほどの恐怖を覚えた。チリチリとうなじの毛が焼けるような、そんな恐怖を。
「お、おまえこそ、なんなんだ」
そんな言葉が、喉から自然と漏れ出た。自分でも驚いた。恐怖は麻痺してはいない。ただその奥から、別の感情が湧いていた。
これが、オカルト・ハイってやつか。ブレーキペダルの100分の1しかない大きさのアクセルを、わざわざ踏んだようなものだ。
レインコートは、首を少し傾け、考えるような素振りをみせた。そうしてゆっくりと口を開いた。
「敵になるか、どうかは、わからない。それを見極めたときには、わたしは…… 犬死だ」
いぬじに。たしかに聞こえた。
レインコートはフードをずらしながら、まっすぐこちらを向いた。下げられたフードの奥の素顔が、雨の筋の向こうに見える。
短く切りそろえられた前髪が濡れて、額に張り付いている。右目のあたりを、大きな引き攣り傷が覆っているのが見えた。右目は完全に潰れていた。鼻梁が高く、整った顔だちをしていたので、その部分が余計に目立って見えた。
僕は、正体不明だった相手の顔を見たことに興奮していて、自分の顔も相手に見られたことを完全に失念していた。
傘を握る手が緊張した。今、この傘を振り下ろし、フードの奥の顔を叩けば……。
僕のそのわずかな殺気を、塗りつぶすようなドス黒い害意が、周囲を包んだ。空から落ちる雨のその1粒1粒が、その濃密な空間でゆるやかに動いている。
邪魔をするな。
邪魔をしなければ、わたしは犬死だ。この街を……。
レインコートの人物は呟きながら、手袋をした右手で、フードを掴んで下ろし、顔を背けた。そして、ゆっくりと車の流れと反対方向へ歩き始めた。
僕は、その姿を見送ってから、自分が息を止めていたことに気づいた。
ハァッ、ハァッ……。
思わず座り込みそうだった。濡れた靴の先を見つめて、これが現実だったことを確認する。
わたしは…… いぬじにだ。
どこか文脈に沿わない、その言葉が頭のなかでガンガンと大きな音を立てて、リフレインされていた。
◆
「やつに会った?」
僕はその日の夜、師匠の家で報告をした。
『おまえこそ、なんなんだ』と、言ってやったことを、特に強調して。
言ったった! 言ったったんです!
喉元過ぎれば、というやつで、あれほど恐怖に慄いた体験だったというのに、師匠の前では強がって見せたのだった。
「弓使いか。目撃証言と背格好は一致するな。なにより、おまえをつけていたってところが、ピンとくる」
「なぜですか」
「私だと、隙がないからな」
師匠は腕組みをして、さも納得したように頷いている。
「それにしても、完全にこっちはマークされてるな。最初に緒方をつけ狙ってたときは、殺気を出しっぱなしだったのに、私たちに気づいてすぐに引いただろ。次に緒方の雑貨屋で襲撃してきたときは、直前まで殺気を消していた。今日に至っては、背後を取るまでまったく気づかせなかった。こいつは手ごわいぞ」
手ごわいってことは、その背後を取られた僕が一番感じている。思い出して、だんだん涙が出そうになってきた。
「今もいるんじゃないか」
師匠はそわそわして、アパートの玄関から顔を出して外を伺った。
うなーん、と師匠に懐いている野良猫が部屋に入ってこようとして、「しっしっ」と追い払われていた。
「殺気ってな、2種類あるんだよ」
師匠はあぐらをかきながら、そう言った。
「こういう……」
キッ、と鋭い目つきで睨みつけきた。身体は重心が前掛かりになって、今にも襲い掛かってきそうな感じを漂わせている。
「視覚的にわかるやつとな。あと1つが……。おい、あっち向け」
師匠は僕に壁のほうを向かせた。
「こんな、やつだ」
師匠はそう言って黙った。僕は壁を見つめたまま、じっとしていた。いったい師匠はなにをやろうとしているのだろう。ちょっと振り向いてみようか。そう思った瞬間、背中に、刃物がつきたてられたような感覚があった。
「あっ」
と驚いて、とっさに振り返って壁を背に身構えた。
師匠は、さっきと同じ格好であぐらをかいたままだ。背中に手をやってみても、刃物など刺さっていない。
「なんですか、今の。どうやったんですか」
「目に見えない殺気を出したんだよ」
師匠は原理を説明してくれた。
「いいか。目の前の人間を殴りつけるつもりで、じっと見るんだ。これから繰り出すパンチの軌道を、リアルにイメージする。そのイメージがマックスに高まって、もう殴る、って瞬間に、身体だけは動かさないでいる。実際に殴るときの運動神経の伝達物質を、ギリギリでフェイクに切り替えるんだ。これをひたすら練習していると、自分でも完全に殴った! って思っても、なぜか身体が動いていない瞬間がくる。その境界が曖昧になってきたら、こっちを見ていない相手にも、殺気が伝わることがある。幽体離脱みたいなもんだな。相手次第だ。鈍感なやつなら、こっちが完璧にこなしても、なにも感じないだろう」
うなーん。
玄関のドアの外で猫が鳴いている。師匠はそちらを見つめ、短く呼吸を繰り返している。
次の瞬間、猫はフギャギャーッと叫んで、逃げていく音がした。
僕には、隣にいる師匠が立ち上がって、ドアを蹴るという映像が、現実の光景と一瞬重なって見えた気がした。
「か、かわいそうですよ」
僕がそう言うと、師匠は「あいつ、こないだ暑くて窓開けてたら、晩飯の焼き魚くわえて逃げたからな」
武道の達人が至る境地も、こんなものなのだろうか。
僕は目の前の師匠が、ますます現実の世界と異なる場所へと、足を踏み出したような気がして、目の前が暗くなった。
「あの『弓使い』が出している殺気は……。あれは異常だ。人間というより、悪霊とか、殺気そのものの存在が出しているような、そんなレベルだ。あれは本当に人間なのか?」
師匠は何度か繰り返したそんな自問を口にした。
「噴き出すイメージが、他人の現実まで侵食している。あれに捕らわれたら、人間はどうなる?」
ぶつぶつと言う。
「邪魔をするな、って言ってましたよ」
一応、もう一度言ってみる。こんな脅しでやめる師匠ではないのは、重々承知しているが。
「そういえば、変なことを言ってたな。なんだっけ。邪魔をするな。邪魔をしなければ、わたしは犬死だ、って言ったんだったか」
「はい。あと、おまえたちの敵になるかどうかは、まだわからない。それを見極めたときには、わたしは犬死だ、って」
思い返しても、よくわからない言葉だ。肯定的な表現のあとで、犬死というネガティブな言葉がくる。文脈が変だ。単に凄く弱気、ともとれるが。
「犬死。……犬死ねぇ。なんで死ぬんだ?」
師匠は顎を右手で押さえて、首を傾げている。
「もう1回再現してくれ」
師匠のリクエストで、僕は立ちあがった。隣には、傘をさす振りをする師匠。
あのバス亭でのやりとりを、できるだけ忠実に繰り返した。
邪魔をするな。
邪魔をしなければ、わたしは犬死だ。この街を……。
最後は聞き取れるかどうか、という声でぶつぶつと言って、フードを深く被るポーズを取って、傘をさす師匠に背中を向けた。
「こんな感じですけど」
振り返ると、師匠の目が輝いている。
「この街を、浄化する」
師匠は叫んだ。
「そう言ったんだな、おまえは」
師匠は、僕には聞こえなかった最後の言葉を、見えない相手に向かって叫んでいた。
「犬死じゃないぞ」
僕の肩を両手で掴んで、揺さぶった。
「えっ、なんですか。どういうことですか」
戸惑う僕に、師匠は笑って言った。
「イヌジニ、じゃないんだ。そいつは、イヌジニン、って言ったんだよ」
どうだ。
そんな顔で、師匠は僕を見つめていた。
◆
次の日は晴れだった。ようやく雨模様もひと段落といったところか。僕は師匠につれられて、JRで2本西に行ったところにある町に向かった。
2人とも背中にバットケースを担いでいる。草野球でもしにいく途中、という風情を出すために、お揃いの野球帽まで被って。なお野球帽は師匠の趣味で阪神のものだ。
師匠のバットケースには愛用の金属バット。そして僕のバットケースには脇差が入っている。春に刀剣愛好家の依頼を受けたときにもらった、保存鑑定書つきのやつだ。
『邪魔をするな』
すでに数人を殺傷しているかも知れない相手から、そう警告を受けたので、護身用として持ち歩くことになったのだ。
「こういう持ち歩き方をすると、脇差が痛むんですけど」
「じゃあ腰に差していくのか」
「即、職質受けますよ」
「なら仕方ないじゃないか」
背に腹は代えられないが、そもそも、こうでもしないといけない恐ろしい相手に、まだちょっかいを出そうとしているのが正気の沙汰じゃない気がする。
だいたい、弓を使う相手に、金属バットと脇差で対抗できるのだろうか。なんかこう、盾的なやつのほうが良くないか?
ぶつぶつ言いながら師匠のあとをついていくと、古い日本家屋が並んでいる通りに、その家はあった。『宮内』という表札がでている。
「やあ、いらっしゃい」
迎えてくれたのは、短く刈り揃えた白髪の男性だった。黒縁眼鏡をしていて、柔和な印象を受けた。
「退官してから、めっきり人が訪ねてこなくなってね。研究室の学生たちなど、ついぞ顔を見ない。冷たいもんだ。顔を見せにくるのは、ゼミにいたわけでもない、君くらいだ」
宮内氏はそう言って、僕らに座布団をすすめた。書斎は本だらけだ。そこらじゅうに散らばった本屋や雑誌を少々整頓しないと、座る場所の確保も難しいありさまだった。
「そうだ、お茶、お茶。こないだのあれは、どこにいったっけな」
宮内氏は書斎と地続きになりかけている台所で、しばらくガサゴソとやっていたかと思うと、ようやくお盆に3人分のお茶を乗せて戻ってきた。
「女房にようやくあいそをつかされてな。まあ、よくもったほうだと思うよ」
宮内氏はうちの大学の元教授で、日本史研究室に所属していた人だった。3年前に退官してからは、郷土史家という肩書きで、好きな研究を続けているらしい。
「ほう、イヌジニンか」
そう言って立ち上がり、ダンジョンのようになっている本棚から、1冊の大きな本を取り出した。そうして、あるページを開いて、僕らの前に広げた。
『洛中洛外図』とある。
説明を読むと、京都の祇園祭の神輿の行列を描いたものらしい。
「これが、イヌジニンだ」
指さすところを見ると、神輿の先頭で棒を持って歩いている6人の男がいた。甲冑を身につけ、頭には白い布を巻いている。
「神の人と書く、神人(じにん)は、神社に仕えて雑役を行う、寄人(よりうど)のことだ。なかでも祇園社などの大社に仕える神人のなかには、犬神人(いぬじにん)といって、境内や道々の死穢を清掃する役目を与えられた人々がいた。彼らはまた、祭礼の警護を割り当てられ、こうして神輿の先駆けの役を行うこともあった」
「穢れに触れる仕事…… 武家社会における非人の役割ということですか」
「まあ大雑把に言うとそうだな。犬神人のことをツルメソと言ったりもする」
「つるめそ、ですか」
じっと聞いていた僕は、その響きが面白くて口を挟んだ。
「彼らはまた、弓の弦(つる)をね。売り歩いたんだ。そのときの掛け声が、弦召せ~、弦召せ~って。転じて『弦召そ(つるめそ)』」
弓……。
ここ最近のキーワードがここにも出てきて、ドキリとする。
「で、先生。今日お伺いしたのは、京都の犬神人のことではありません。このO市で、犬神人と呼ばれていた人々のことです」
「ほうほう。よく知っとるなあ。大したもんだ」
うんうん、と頷きながら、宮内氏はまた本棚のダンジョンから本を抜き出してきた。古い郷土史のようだ。
「O市では、古来より二条神社が中央にデンと構えていて、神職以外でも、その神域にたずさわる職業がいくつかあった。そのひとつが、この犬神人(いぬじにん)だ」
本には、白黒の写真で、法師のような格好をした人物が弓を構えている様子がうつっている。周りには、にぎにぎしい和装の人々が遠巻きにそれを見ていて、神主らしき人もいる。
「洛中の犬神人との関連はよくわかっていないが、このO市でも似たような役割を果たしていた人々がいたんだな。洛中と少し違うのは、こうして弓をもって穢れを払う、より洗練された職能を持っていた点だ」
どうやらその古い写真は、神社の祭りの始まりに際して、穢れを払う神事を執り行っているところらしい。
「戦後、二条神社の大祭が縮小していくなかで、犬神人の役割も終わった。たしか、20年くらい前に記念の祭りがあったときに、穢れ払いの弓神事が催されたのが最後だと思う」
写真はあったかな。と呟きながら、宮内氏は雑誌が詰め込まれた書棚を引っ掻き回し始めた。
「先生。その我がO市の犬神人ですが、京都と同じように、死骸の清掃を行うこともあったんですか」
結局写真は見つからなかったようで、宮内氏は残念そうに首を振った。
「O市の二条神社周辺で、死穢の掃除をしていたのは、犬がつかない、神人(じにん)だ。犬神人は、あくまで弓を使う、穢れ払いの職能集団だった」
そこで宮内氏は急に声を潜めた。
「いいかね。これはちょっと怖い話だがね。彼らは近代以前、弓を持って、神社支配地を練り歩き、あることをして回っていたと言われている」
…………。
その話を聞いて、師匠の顔色が変わった。僕もゾクリとした。師匠は、警察がたどり着けなかった、弓矢での連続殺傷事件の犯人に、通常の捜査とは全く違う方向から、たどり着こうとしていることが、わかったのだった。
「先生。その、20年前に弓神事をしたのはだれか、わかりますか」
「ああ、わかるとも。鳥井博一(とりい ひろかず)さんといって、今はいくつになられたかなあ。80歳にはなってないと思うが。私が以前調査したときには、この犬神人の一族で今も家系が残っているのは、この鳥井さんの家だけだった。鳥井流、という弓術を代々教えている。今もご壮健のはずだよ」
古くからの知り合いだと言うので、師匠は無理を言って、面会のアポイントを取ってもらった。
宮内さんの教え子のかたなら、ということで、さっそく明日訪問させてもらうことになったのだ。
お礼を言って、宮内氏の自宅を辞去する際に、師匠はふと思い出したように言った。
「そう言えば、先生。先週だったか、東のほうで、馬塚の遺構が見つかったっていうニュースがありましたよね。ご覧になられましたか」
「ああ、あったね」
「あの映像で、チラッと映っていた剣があったでしょう」
宮内氏は、そこで今日はじめて不快そうな表情をした。
「ああ」
「あれは、『馬霊刀』ではないでしょうか」
「さて」
快活だった口調が、鈍った。
「引退してからは、余計なことは言わないようにしているんでね」
師匠はそんな宮内氏の様子を、じっと見つめながら言った。
「あの発掘で説明していた人は、埋蔵文化財センターの人ですか」
やがて宮内氏はバツが悪そうに口を開く。
「三島君はね、少々軽率なところがあるよね。ま、怪力乱神を語らずってね、くわばらくわばら」
それから、宮内氏は引退した身だから、という言い訳めいたことを繰り返して、僕らを送り出した。
僕は最後の宮内氏の様子に、納得のいかないものを感じながらも、師匠がそれなりに満足げだったので溜飲を下げた。
帰り道、「馬霊刀って、なんですか」と訊いてみたが、師匠からは返事はなかった。やはり納得していないらしい。
つくづく、探偵体質だね。
僕はため息をついた。
◆
翌日、待ち合わせの時間に師匠は、わたあめを食べながらやってきた。まただ。いつもどこで、このわたあめを手に入れているのだ。僕の知る限り、この周辺にいつでもわたあめを買える場所はない。師匠の7不思議のひとつだった。7つどころじゃないけど。
「どこで買ってるんです、それ」
「うん」
また生返事だ。
「で、手に入れた?」
「はい」
僕は師匠に頼まれていたものを差し出す。
「ふうん。世帯主は鳥井博一。妻、敏子。長男、正太。長男の妻、英子。長男の長男、正和、か」
頼まれていたのは、鳥井家の住民票だった。どうやって手に入れたかは、ちょっと言えないやつだ。これもこの興信所業界に足を突っ込まなければ、知ることのなかった手口だ。
「なんだ。戸籍もO市なら、戸籍謄本も取ってこいよ。気が利かないな」
「出がけに急に言うからでしょ。戸籍のほうは高いんですよ! お金が足りなかったんです。立て替えた住民票の写しの代金も、経費で返ってくるんでしょうね」
「経費? これは別に小川調査事務所の仕事じゃないぞ」
えっ。
これ、自腹かよ。
僕は呆然として、ニヤニヤしている師匠を見つめた。
そりゃあ、たしかに僕が好きで手伝ってるだけですけど。
ぶつぶつ言いながら、大学の構内から自転車を発進させた。後ろに師匠を乗せた2人乗りだ。師匠は後輪の車軸に足をかけた、立ち乗りである。
そして今日も、僕らは護身用のバットケースを持っている。師匠のほうはともかく、僕のは職質されたらアウトなので、ドキドキしっぱなしだ。
「そういや、おまえ、単位は取れてるのか」
「まあ、ぼちぼち」
これだけ師匠につきあっていたら、果たして卒業まで何年かかるのだろうか。最近ちょっと、将来が不安にならないでもない。とりあえず、1留でおさめたいとは思っている。
「30歳にはならないように」
「ずいぶん気が長いな」
いや、あなたの年齢がですね……
そう言おうとして、もごもごした。
自転車をこぐこと20分あまり。駅前の大通りを東へ東へと進み、古い民家の立ち並ぶ、元の城下町のあたりにたどり着いた。
「鳥井。ここだな」
師匠が大きな門についた表札を読んだ。なかなか立派な日本家屋だ。
門にあったチャイムを鳴らしてしばらく待つと、右手側にあった木戸が開いて、背の高い老人が姿を現した。
「どうぞこちらへ」
案内されるままに木戸をくぐると、その先には石畳が続いていて、奥に大きな道場のような建物があった。道場の玄関は、家の前の角を曲がったところにあったらしい。
道場のなかに入ると、建物が半分切り取られたようになっていて、屋根がないほうには、運動場のような土の地面が伸びていた。その向こうには、砂が盛られていて、目玉のようにグルグルとした模様の的が据えられている。
道場の板の間で、座布団をすすめられて、僕らは座った。
向かいの老人は袴姿で、座布団もなしに正座をしている。背筋がピンと伸びていて、身体の正中線に鉄の芯でも入っているかのようだった。
「鳥井です」
鳥井博一、78歳。世帯主。住民票の記載ではそうなっていた。
師匠は、郷土史のフィールドワークをしている学生で、宮内元教授から紹介を受けての来訪であることを告げた。
「昔は、宮内さんもよくいらっしゃってましたよ」
痩せぎすではあるが、にこりと笑う姿は、年齢を感じさせない爽やかだった。
「犬神人だなんて、今では知る人もほとんどいない名前です。先祖代々、二条神社の聖域をお守りしてきたこのお役目も、私の代で終わりでしょう。いえ、もう終わっているのでしょうね」
寂しげな口調ではあったが、表情はさほどではなかった。すでに自分のなかで消化し終えたことなのだろうか。
「この弓道場も、先細りでしてな。若い人には弓道自体、人気がないようで。今では古くからの門弟が数人いるだけです。私の子どもの時分には、ここいらにも賭け弓をする賭場がありましてな。この道場も、賭けに勝てるよう、腕を上げたい不心得者たちで賑わっていたものですが」
鳥井流の看板も、もう近々下ろすつもりです。
鳥井氏は静かにそう告げた。
師匠は、かつての犬神人が執り行ったという、穢れ払いの儀式のことを訊ねた。
道場の壁に掛かっていた大きな弓を手に取って、鳥井氏は僕と師匠のためだけに、かつての弓神事の作法をいくつか見せてくれた。
ゆったりとした動きのなか、祈りの言葉をあげながら、鳥井氏は数歩歩いては弓を引き、また数歩歩いては弓を引く、ということを、3度、4度と繰り返した。
いずれも矢はつがえなかった。
「弓の音です。この音で魔を払うのです」
それが犬神人の作法なのだという。
ビンッ…………。
鋭い音が空気を振るわせるたびに、なにか引き締められるような、そんな感じがした。
「大昔は、矢も使ったと聞いていますが」
師匠が口にしたその言葉に、鳥井氏の顔色が変わった。
「宮内さんが、おっしゃっていたのですか」
鳥井氏は、弓を引いた姿勢のまま、厳格な口調でそう訊き返した。
「平安、鎌倉、室町…… かつての日本では、空き地や側溝、そのへんの道端に死骸が転がっている風景が、当たり前でした」
師匠は老人の横顔に話しかける。
「墓を作る財力のない人にとって、そうした路辺や河原などに死体を遺棄する、風葬、遺棄葬は一般的な行為でした。また、乳幼児などは、高い身分の家の子女であっても、まだ『人』とみなされず、遺棄葬をされるケースもあったようです。もちろん、行き倒れた者も、弔われることもなく、その死体は雨ざらしのままです。その死体が土に還る前に、掃除される場合もあります。豪族や貴族など、高貴な家柄の人が通るときや、神社の大祭があるときなど、道々の穢れを払う必要がある場合です。京都などでは、神社地でそうした死体清掃を行う、犬神人と呼ばれる人びとがいました」
ビンッ…………。
静止していた弓が、そのしなりを運動エネルギーに変えて、力強く跳ねた。鳥井氏の鋭い視線は、屋外に構えられた的のあたりに向けられたままだった。
「そしてこの街にもまた、犬神人と呼ばれる人びとがいました。京都のそれと違うのは、より、穢れ払いという儀式性に特化された集団だった、ということです。京都の犬神人は、つるめせ、つるめせ、と弓の弦を売り歩いたそうですが、この地の犬神人は、市中を歩く際、弓と、矢を持っていました」
僕は、ハラハラしていた。明らかに、鳥井氏は気分を害している。そして師匠は、それをわかっていて、なお火に油をそそごうとしている。
「二条神社の神域を守るため、穢れ払いを行うためです。しかし、彼らは、死体清掃で手を汚すわけではありません。彼らが払う穢れは、遺棄された死骸そのものではなく、そこから発生する、二次的な『ケガレ』…… つまり、悪霊です」
鳥井氏は、構えを解いた。身体から力みが消え、ただ立って、僕らのほうを向いた。そして先を促すように頷いて見せた。
「死後、道端にさらされた遺骸が、世を恨み、他者に祟りをなす悪霊を生ずる前に、この地の犬神人は、弓矢で穿ったのです。その骨を。……クロノス衝動、という言葉があります。遥か過去、アウストラロピテクスなどの初期の人類から存在した、遺体を破損する行動原理のことです。埋葬をする意図ではなく、遺体をただ切断し、分割し、石でつぶす。近親者などによる儀礼的なカニバリズムもまた、人類の初期から存在するクロノス衝動の1つです。石片で傷をつけられた人骨は、世界中で見つかっています。人は怖いのですよ。死が。いまだ経験しない、自らの死が。怖くてたまらないから、死を、さまざまな角度から『発見』するのです。犬神人の撃った矢は、遺骸を穿ち、骨に傷をつけました。その刻印は、穢れを払い、遺骸から悪霊を生じさせない、聖なる印です。穢れ払いの名の下に、弓に矢をつがえ、市中を歩くことを許された集団。それが儀式化される前の、本来の犬神人の姿です」
師匠は最後まで淡々と説明した。昨日、宮内先生に聞かされた話は、ここまで詳しくもなかったし、辛らつでもなかった。師匠は、自らの知識で補足して、類推して、それを鳥井氏に、かつての犬神人の子孫に、ぶつけたのだ。
「古い話ですよ。……私にも本当のところはわからない」
鳥井氏は壁に掛けられた、いくつかの弓を順に見上げた。一番高い位置にある弓掛けだけが、ぽっかりと中身が空いている。その上には神棚が設えられていた。
老人は目を閉じて、ゆっくりと首を振った。
「いずれにしても、そんな名前は、私の代で終わりです。息子も、その子どもも、弓などに興味を持たなかった。この道場も、もう閉めます。わが家では、だれも弓を持つことはないでしょう」
さて、そろそろ私も疲れました。
鳥井氏はそう言いながら、右手で自分の肩を揉んだ。
「この年では、弓を引くのもひと仕事でしてな」
「あ、そろそろ、おいとまします」
僕は空気を読んで、そう言った。
本当はちょっと、どんなものか弓を引かせてもらいたかったが、仕方がない。明らかにもう潮時だった。
腰を浮かせ、道場の隅に置いていたバットケースを手に取ったとき、まだ座布団の上にどっしりと座ったままだった師匠が口を開いた。
「去年の冬から世間を騒がせている、弓矢を使った連続通り魔事件をご存知ですか」
ビシリ、と空気にヒビが入った。
老人の目つきが再び鋭くなっていた。
「ありましたかね。それがなにか」
このタイミングでそれを口にするということは、犬神人の子孫である、というだけでこの人を、通り魔扱いするのに等しい。いくらなんでも面と向かって言うなんて、失礼過ぎる。
僕は師匠を止めようと、師匠のバットケースを抱えて、乱暴に差し出した。
「もう、おいとましましょう。ね」
「うるせぇ。なんのためにここに来たんだ」
師匠はバットケースを振り払い、なおも老人に食い下がった。
「犯人に、心当たりがあるんじゃないですか」
「さて。あれは洋弓ではなかったですかな。私にはさっぱり心当たりもありません」
「いえ、洋弓、ボーガンではありません。和弓ですよ。世界最大の弓である、和弓の雄大さ。それこそが、この事件に相応しい形です。穢れ払いには、和弓こそ相応しいのです」
「かえれっ」
突如、老人は一喝した。
僕は心臓が飛び出るかと思った。
「もう出て行きなさい。」
口調を改めたが、態度は硬直化していた。
師匠はしばらく老人と睨みあっていたが、やがて腰を上げた。
「私は、本当は宮内先生の教え子でありません。ウソをついて紹介してもらっただけです」
僕からバットケースを受け取りながら、師匠はそんなことを言った。鳥井老人を怒らせてしまったので、紹介してくれた宮内氏への配慮なのだろう。
「怪物と戦うものは、自ら怪物になることを畏れなくてはならない」
道場から出るとき、師匠は、ニーチェの言葉を口にした。険しい顔で腕組みをして見送る、鳥井氏には聞こえなかっただろう。それは、犬神人の一族のことを言ったようだった。けれど僕には、師匠が自らに言い聞かせている言葉にも聞こえたのだった。
馬霊刀 3/4
3 犬神人
鳥井家の敷地を出たあと、師匠は興奮気味に言った。
「おい。あのじじい、なにか知ってるぞ。大当たりだ。イヌジニンの昔の『仕事』がそんなにセンシティブなら、教えてくれた宮内先生が警告したはずだ。それがあんな過敏な反応をするってことは、なにか、それがセンシティブになる事情が、あのじじいの側にあったってことだ」
じじい、じじいと失礼なことを連呼しながら、師匠は自転車を運転する僕の肩を、後ろから嬉々として掴んだ。
「鳥井流の門弟じゃない。家族だ。犬神人は、技ではなく、血で受け継ぐ。あのじじいの心当たりは家族のだれかだ。今の住民票には、それらしい年齢の女子がいない。戸籍だ。戸籍を調べるぞ」
「僕、お金持ってないですよ」
師匠はチッと舌打ちをすると、ホットパンツのポケットから小銭入れを取り出してなかを確認した。
「よし。出張所だ」
師匠は市役所の窓口では面が割れつつあるらしく、こういう他人の戸籍を手に入れるような裏技を使うときには、出先機関の窓口を利用するようにしていた。
1時間半後、小さな公園のベンチで、僕らは人様の戸籍や住民票の写しを覗き込んでいた。当代である、鳥井博一に連なる一族のなかで、僕らの追っている『弓使い』と年齢的に合致する女性が1人だけいたのだ。
「山田、あすみ」
師匠が確かめるように言った。
山田あすみは、鳥井博一の長女、真佐子の一人娘だった。真佐子は博一の長男、正太の妹で、23歳のときに同じ市内に住む山田喜市という男に嫁いでいる。別の出先の窓口で、山田喜市の住民票を取ってみたら、父・喜市、母・真佐子、長女・あすみという3人世帯だった。念のため戸籍謄本も取ってみたが、子どもはこのあすみ1人だった。
22歳、女。鳥井博一の孫ということになる。あの、道場での過敏な反応は、この孫のあすみを守るためだったのか。
「山田、あすみ」
師匠はもう一度繰り返した。そしてなにかに気づいたように顔を上げた。
「もしかして」
師匠は戸籍や住民票の写しをかき集め、リュックサックに放り込むと、「事務所に行くぞ」と言った。
自転車で向かっていると、途中で「いや、あれは結構前だな。小川調査事務所ができるよりも前か」と言い出し、「パパ殿の事務所に行くぞ」と方向転換を強いられた。
小川所長の義理の父である、高谷氏が運営するタカヤ総合リサーチにつくと、さっそく師匠は市川さんというベテランの女性事務職員をつかまえた。
「古い新聞記事? いいわよ」
市川さんは、師匠のお願いをたいてい聞いてくれる。娘のような年の師匠を気に入っているのもあるのだろうが、高谷所長からできるだけ便宜を図るように、という指示がでているようだった。それはこの業界でも特殊な、オバケ事案を得意としている師匠を、いずれ引っ張りたい、という思いのためなのか。あるいは、娘婿である小川所長のところの調査員なので、塩を送っているのか、どちらかであろうと思われた。師匠もそうしたことを委細承知で、利用できるものはなんでも利用しようとしていた。
「いつぐらい? どんな記事?」
市川さんは、過去の記事を収めたキャビネットの端に差してあった、目次集のようなファイルを捲りながら訊ねた。
「7、8年くらい前。誘拐された女の子が、地下室に監禁されてた事件」
「……あった。たぶんこれね。ええと、このファイル」
市川さんはあっという間に、師匠が探していた記事を見つけ出した。
すごいな。小川調査事務所で、似たようなものを作っている僕だったが、さすが大手興信所はレベルが違う。
記事は、8年前のものだった。さらにその5年前に誘拐された少女が、地下室に監禁されていたのを発見され、救出された、という内容。
犯人と思われる男は、武藤仁志38歳。会社員。武藤は母親と2人暮らしであったが、息子の姿が見えないことを不審に思った母親が、武藤の私室となっていた地下室を探したところ、地階に下りる入り口が土砂で埋まっていたという。すぐに救急隊が駆けつけ、武藤は土砂のなかから心肺停止状態で発見された。のちに病院で死亡が確認されている。土砂を取り除いて、地下室のなかを確認すると、やせ細った少女がいた。本人の供述から、少女は同じO市内で行方不明者届けが出ていた、山田あすみ、14歳であることがわかった、という。武藤の母親は、息子が地下室で少女を、5年間にもわたって監禁していた事実を知らなかった。武藤家と山田あすみとの関係はわかっていないが、面識はなかったものと思われることから、誘拐については、たまたま目についた少女を攫ったものかも知れなかった。
「山田あすみ。やっぱりだな」
師匠は記事を読みながら頷いている。凄いな。よく名前だけでこの事件を覚えていたものだ。
そう感心していると、師匠は「これ、不気味な事件だったから覚えてたんだ」と言う。
「たしか、地下室の入り口を埋めていた土砂が、どこから来たのか、わからなかったんだよ。家は一軒屋だったけど、両隣にも民家はあるんだ。土砂はかなりの量だったから、重機で運び込まれたはずなんだけど、そんな事実を周辺住民は確認していない。武藤の死因は窒息死だったはずだ。状況から、なにものかに生き埋めにされて殺された可能性が高かった。母親が取り調べられてたけど、嫌疑不十分で立件されず、最終的に武藤は事故死で片付けられたんじゃなかったかな」
監禁。犯人は死亡。凄い事件だ。5年間ということは、9歳のときに誘拐されて、14歳になるまで、社会から強制的に切り離されて暮していた、ということか。
こんな惨たらしい事件の被害者が、本当にあの鳥井博一老人の孫なのか。それも、師匠が追っている弓矢を使った連続通り魔事件の犯人だと?
監禁されていた少女の両親の名前や、住所は、書いていなかった。
「同姓同名の可能性は」
僕がそう口にすると、師匠は、「目だよ。おまえがバス停で会ったっていう女は、右目が潰れてたんだろ」
「そうですけど」
「この記事には書いてないけど、私の記憶だと、救出された少女は怪我をしていたはずだ。詳細を書かない、いや、書けないような怪我だったとすると……」
「目が?」
「14歳の女の子だ。記事でも、そんな重い怪我については、配慮されたかも知れない」
ハローページで、僕らが住民票を取った、山田あすみの家の電話番号を調べると、『山田製作所』という表記になっていた。電話をしようとしたが、鳥井家のように、山田あすみの存在が、センシティブなものになっている可能性があった。師匠は、「アポなしで乗り込むか」と言った。へたに事前に電話して、警戒されるよりいいかもしれない。
気がつくともう夕方だった。師匠は、タカヤ総合リサーチのロッカーに置かせてもらっている服に着替えた。控えめなパンツスーツだった。今回の訪問にホットパンツはさすがにまずい、という判断なのだろう。
僕らは市川さんにお礼を言って、ビルを出た。
急いで自転車をこぎ、山田製作所の住所へ向かう。市内南部の、人口密度のゆるやかな地域に、その町工場はあった。
ギイーン、という金属が削られるような音が響いてくる入り口を抜け、僕らは事務所を訪問した。
「あすみはもういませんよ」
突然の訪問に戸惑いながらも応対してくれた男は、汗で濡れた額を手ぬぐいで拭きながらそう答えた。
この町工場『山田製作所』の社長、山田喜市は鳥井博一の長女、真佐子と結婚して22年前に1人娘のあすみを授かった。そして今から13年前に、そのあすみを武藤という見ず知らずの男に誘拐され、5年間も人目のつかない地下室で監禁される、という非道な事件に見舞われている。
「もう4、5年前に、あれが娘をつれて家を出てね」
パイプ椅子がキイキイと軋む音がする。山田喜市は、イライラした様子だった。
「あれ、とは奥様の真佐子さんですか」
「ああ」
師匠は、市の嘱託を受けた、犯罪被害者の心のケアをする支援員を名乗った。特に身分証の類も用意してなかったのに、あるのかもわからないそんな仕事の内容と意義を、ペラペラとしゃべり倒し、最初の壁を突破していた。たぶん、何度か使ったことのある肩書きなのだろうが、よくもまあ、と感心する。なお、お揃いの阪神の帽子は、師匠のリュックサックのなかに仕舞っていた。
山田あすみは、母の真佐子につれられて家を出ていき、父とは別居状態なのだという。
住民票はそのままだったので、離婚はしないつもりなのだろうが、それだけ別居が長いというのは、もう家族関係は完全に決裂しているのかも知れない。
喜市ははっきり言わなかったが、暗に別居の原因を、妻の真佐子の方の浮気だとほのめかした。
「あすみさんは、事件のあと学校は?」
「……小学校3年でかどわかされて、だからな」
「行かなかったんですか」
「いや、特別支援学校だか、そんなところに行ってたけど、途中でやめちまった。……行ってたのは2年くらいだったか」
「それからは、自宅にいたんですか」
「ああ」
山田あすみは、16歳くらいで学校教育から離れたということか。結局、小学校3年間と特別支援学校2年間、合わせて5年しか学校に行っていないことになる。その歯車が狂ったのは、すべて誘拐の被害者になったせいだった。彼女のせいではなかった。
僕は、一度だけ見た、あの強い意思を秘めた顔を思い出した。右目が無残に潰れていたけれど、それでもどこか触れがたい気高さを持っていたような気がする。
社会に復讐をしたいのか?
僕は、師匠とあすみの父が話しているその横で、記憶のなかの女に話しかけていた。
きみは、憎んでいるのか。きみの人生を壊した男を。その男のように、雑貨店の女性客を監禁して襲った緒方を。ほかのやつらもそうなのか。弓矢で襲撃された被害者たちは、当日の外出目的がはっきりしない。同じように、犯罪をおかそうとしていたやつらなのか。
きみは、いまどこにいる?
「あすみさんは、お祖父さんの弓道場には通われていたのですか」
僕は師匠の言葉にハッとした。
「子どものときはな。かどわかされてからは、行ってない」
師匠はその言葉が本当かどうか、吟味するように父の顔を見ていた。
「あと、事件のときに目を怪我されていた、ということですが」
「ああ」
喜市はそう言って、右目を押さえるように覆った。それから、ため息をついて、
「……不気味な、子だった」
と、いう呟きを漏らした。
「あのー、社長。ちょっといいですか」
事務所の入り口に、ニキビの浮いた顔の作業着の若者が立っていた。
気がつくと、金属を削るような音が止まっている。
「おお、いま行く。悪いな。そういうことだ。あいつは、もううちには、いないんでね」
そう言って喜市は、これを幸いと、僕らを追い出しにかかった。
「訪問しないといけないので、別居先だけ、教えていただけませんか」
師匠がそう言って食い下がって、いま母子が住んでいるアパートの住所を聞き出すのがやっとだった。
事務所の奥が自宅になっているようだったので、師匠的には、本当に山田あすみがいないのか、その痕跡でも探りたかったところだったようだが、しかたがなかった。
山田喜市は、ウソをついているようにも見えなかった。しかしなにか、肝心なことを言っていないような気配も感じた。
町工場を出ると、もう日が暮れかけていた。
「続きは明日にするか」
師匠がそう言った。
「山田あすみだと思いますか」
僕は弓を引く仕草をしながら、問い掛ける。
「たぶんな」
師匠は背中を丸めながら、答えた。その様子に、連続通り魔事件の核心に迫っている、という興奮はなかった。
「不気味な子、か……」
師匠はぽつりと、父が漏らした言葉を繰り返した。その背中には、静かな怒りが漂っているような気がした。
町工場からは、金属を削るような音が、また聞こえ始めていた。
◆
続きは明日にするか、と言ったものの、帰る途中で師匠が「いや、やっぱり今から行こう」と言い出した。
「探していることが、バレるかも知れない」
山田あすみの人生に同情的になっていたが、もし彼女が『弓使い』だとしたら、たしかに今の状況は危険かも知れない。
邪魔をするな、と警告されているのだ。すでに何人も死傷させているであろう、危険人物から。
「行くぞ」
別居先の住所をメモした紙を握り締め、師匠は僕の肩を叩いた。
目的地は市内の中心部に近かった。その古い木造2階建てのアパートにたどり着いたときには、もう日が暮れていた。
ギシギシと軋む階段を登り、2階の奥の部屋のドアをノックする。
「はぁい」
なかから返事があった。女性の声だ。師匠がドアの開く右側に立ち、僕は左側に控えた。そして顔を見合わせて頷く。担いでいたバットケースは、両方とも僕の足元に置いていた。僕は片方のケースのチャックに手を突っ込んで、金属バットのグリップを握り、いつでも師匠に渡せるよう
に身構えていた。
緊張で手のひらに汗が滲んでいる。
ガチャリとドアが開き、なかから中年女性が顔を覗かせた。
「なに?」
女性は肌着を身につけ、上にはなにも羽織っていない。化粧っ家のない顔の頬には、シミが浮いていた。
「市の嘱託を受けまして、犯罪被害者の方の心のケアをするために訪問させていただきました。本日、山田あすみさんはご在宅でしょうか」
師匠は、山田製作所のときと同じ設定で挑んだ。
女性はじろじろとパンツスーツの師匠の全身を見回し、それからドアの陰に僕がいるのに気づいて、一瞬ビクリとした。
「どうも」
僕はできるだけニコヤカに会釈した。壁に立てかけたバットケースからは手を離していた。
「入って」
思いのほか、あっさりと女性は僕らを部屋のなかに招き入れた。山田あすみがいるとも、いないとも言わなかった。
室内は、ゴミ屋敷というほどではないが、スーパーの袋や弁当の食べガラなどが散らかっていて、汚らしい印象だった。
六畳間には、その女性以外だれもいなかった。
「あすみは、いないわよ」
女性は畳の上に座り込み、目の前の背の低いテーブルから、タバコとライターを手に取った。
「真佐子さんですね」
「そうよ」
あすみの母、真佐子は煙を吐きながら言った。
「あの子はね、出て行っちゃったの」
どこか他人ごとのような言葉だった。僕はこの女から、普通ではないものを感じていた。見ず知らずの僕らを家にあげながら、彼女は着替えるでもなく、肌着のままだったのだ。
「どっかに男でも作ったのかねぇ」
いい子だったのに。
そんなことを言ってニタニタと笑っている。
「出て行ったのは、どのくらい前ですか」
「もう2年くらいかなぁ」
「2年……」
娘がいなくなって、2年間も放っているというのか。父親の喜市は知っているのだろうか?
子どものころに誘拐され、5年ものあいだ地下室に監禁されて、救出されてからも学校にもほとんど行かず、両親は別居。そして顔にも酷い傷を負っている、そんな子が、1人でどこかに出て行った、というのに、この親は……。
僕は理不尽な思いに、怒りが湧いてきた。握り締めた手に力が入る。すると師匠が僕の目を見て、眉間にシワを寄せた。抑えろ、というのだろう。
「こちらに来てからは、あすみさんはどんな様子でしたか」
「あの子は昔から、物静かでねぇ。いつもひとりでお人形遊びとか、積み木遊びとかをしてたのよ」
「こちらに来たのは、17、8のときですよね。2年前ということは、20歳くらいまでいらっしゃったんでしょう?」
「……いつも、なにしてたのかねぇ。あたしもそのころは、働いてたし」
「住民票は、喜市さんの家のままですよね。ということは、失礼ですが、生活保護は受けられないでしょう。いま生活はどうされているのですか」
「まあ、旦那からの仕送りもあるし」
もごもごと真佐子は言った。
その仕送りは、娘にも権利があるはずだ。父親も父親だ。同じ市内に住んでいたのに、自分の娘がいまどこにいるのか、知りもしないで、仕送りだけ送っているのか!
僕は怒りを抑えながら、口を開いた。
「こちらに来てから、お祖父さんの道場へ通っていた、ということはないですか?」
ここからなら、鳥井家にわりと近い。
「ああ、行ってたかもね。あの子は弓道が上手でねぇ。あたし、大会に出たらいいのに、って言ったけど、おじいちゃんがダメだって言うのよ」
「それは、小学生のときですか」
と師匠が訊くと、真佐子は首を振った。
「ナントカ学校に通ってたころよ」
「特別支援学校ですか」
「そう」
「お祖父さんは、どうしてダメだって、言ったんでしょうか」
「変な子だから、外に出したくなかったのかなぁ。いい子なのに」
変な子。父親は、「不気味な子」だと言っていた。あんな辛い目にあっても、弓道を頑張って続けていた子に、そんな仕打ちはないだろう!
僕の怒りの矛先は、あの道場で会った、厳しい老人にも向かった。
「こっちの目は、完全に見えないのですか」
師匠は、右目を触りながら訊ねた。すると、真佐子は「なによ!」と急に怒り出した。
「疑うの? ちゃんと手帳もあるんだからね」
そう言って、箪笥から赤い表紙の手帳を取り出した。
『身体障害者手帳』と書いてあった。
「視覚障害で、1級なのよ」
真佐子の言葉に、師匠は「えっ」と驚いた。
「たしか、視覚障害だと、片目が全盲だというだけでは手帳は出ないはずですよ。両目の矯正視力の合算で等級が決まるから。なのに一番重い、1級って、どういうことですか。ちょっと、見せていただいてもいいですか」
「ほら、1級でしょ」
真佐子は手帳を広げて見せた。
たしかに、1種、1級と書いてある。
「両眼の視力の和が、0.01以下のもの……」
師匠は内容を読み上げた。その言葉が意味していたものは……。
「全盲、なんですか」
師匠も、僕も絶句していた。全盲だって? そんな。バカな。
「たしかに、あの人です」
僕は、手帳に添付されていた写真を見て、そう言った。
右目のあった場所には、引き裂かれたような皮膚が張り付いている。そして左目は、どこか焦点のあっていないような角度で止まっていた。
雨の日のバス停で出会った女。やや幼い印象だが、あのレインコートのフードを取った、その顔が、そこにあった。
「監禁されてたときにね。左は、義眼なの。右は怪我が酷くて、整形できなかったから」
母親のそんな軽々しい言葉が、もうほとんど耳に入らなかった。
「そんな娘が、1人で出て行って、平気なのか」
僕は言葉を選ぶ余裕がなくなりつつあった。この女は、おかしい。普通の神経ではない。
「見えないけど、大丈夫なのよ。あの子は。自分のことは、なんでもできたから。弓だって、百発百中だったのよ」
目が見えなくて、そんなことができるのか。信じられない。
「だから、大会に出さなかったのか」
師匠が呟く。
『不気味な子だ』
父親のそんな言葉が、頭をよぎる。目が見えないはずなのに、見えているとしか思えないようなことが、日ごろからあったというのか。
「あんたたち、本当は年金の調査員なんじゃないでしょうね」
母親が、怒り出した。
「帰って。帰ってよ」
急に立ち上がって、師匠の肩を押し始めた。
「障害年金か」
師匠もハッとした顔で、立ち上がった。
「あんた、娘の障害基礎年金を、自分で使ってるな」
師匠は母親の手を掴んで言った。
「目が見えない娘に、障害年金も、父親の仕送りも渡さず、ここから出て行って2年だって? あんたそれでも母親か!」
「うるさいっ。出て行け」
真佐子は師匠の手を振りほどき、そこらにあったゴミや食器を投げ始めた。
灰皿が師匠の肩に当たり、なかに詰まっていた灰が、室内に拡散した。
師匠と僕は、しかたなくその部屋から出た。バタンッ。と乱暴にドアが閉められる。
そのドアをしばらく眺めながら、僕らは言葉もなくたたずんでいた。
翌日、僕らは鳥井家の玄関の前に立っていた。
いきなり訪問すると、博一老人は、不機嫌そうに追い返そうとした。それはそうだろう。昨日の今日なのだ。
「あすみさんが、お母さんのところからいなくなっていることを、知ってましたね」
師匠がそう言うと、老人は目を見開いて唸り、そして折れた。こっちへ、と言ってまた僕らを道場に招きいれた。
老人は、今日は袴姿ではなく、シンプルな夏服を着ていた。
僕らは道場の板張りの上に座り、向かい合った。ジワジワジワと蝉が鳴いている。切られたように開け放たれた道場の屋外から、陽光が差している。
「百発百中だったと、真佐子さんが言っていました。本当に、そんなことができたのですか」
師匠は陽の当たる屋外の的のほうを見ながら言った。「目が、見えないのに」
老人は苦悩するような表情で、深く息を吐いた。
「あの子は……」
そう言いかけて、言葉を探しているように口を閉じた。
「本当は見えていたのですか」
「いや、見えない。両目の眼球が、抉り出されていたのだ」
僕はそのえげつない言葉にゾッとした。
「監禁されていたときに、ですか」
「そうだ」
老人は、死んだ誘拐犯をその手で絞め殺そうとするように、膝の上の右の拳を左手で強く握っていた。
「では、ここにはなんのために通っていたのですか」
「……4射ずつ、続けて5回。合わせて20射。あの子は、20射を皆中(かいちゅう)できた」
老人の、喉に詰まったものを吐き出すような告白に、僕らは息をのんだ。
「あの子は…… あすみは、わしらの見ている世界とは、別の世界を見ていた」
「別の…… 世界?」
「目が見えないあの子は、自分の頭のなかで、周りの風景を想像している。ここに、扉があるのではないか。あそこに、的があるのではないか…… それらが、ほとんど現実の世界と一致しているのだ」
「そんなこと」
思わず僕は口走った。「あるはずがない」
「あの子の見ている世界では、人ではないものまで蠢いている。それは現実の世界にはない。わしらには見えないものだ。あの子も最初は怖がっていた。しかし、弓を習うにつれて、それらを射殺せることに気づいた」
師匠の顔つきが鋭くなる。僕も、その言葉の意味を、理解した。
「鳥井家に代々受け継がれていた、犬神人の本来の役割を、あなたが教えたのですね」
師匠が問いかけた。
「そうだ。鳥井流は、犬神人の最後の系譜は、あの子にこそ相応しいと思ったのだ」
老人は壁にかけられたいくつかの弓を見上げる。その一番上にある、弓のない台だけの場所を。
「油(あぶら)の弓という、代々穢れ払いに使ってきた弓があった」
「そこに、掛けられていたのですか」
老人は頷く。今はその弓はなかった。
「あの子に、やろうとした。だが、あの子は、油の弓を持って行ってしまったのだ。あの子の見ている、別の世界に」
「どういうことですか」
「もう、わしにはその弓が、見えなくなった」
ぽつりと老人は言った。
ぞわっと背筋に走るものがあった。繋がってくるのだ。その荒唐無稽な話が、連続通り魔事件の奇妙な謎と。
見えない矢。見えない弓。まさか。そんなこと。
師匠も絶句している。
「私は…… わしは、あの子が恐ろしい」
冷たい息を吐き出すように、老人は言った。蝉の声が、どこか遠くから聞こえてくるようだった。
「居場所に心当たりは」
師匠の問いかけに、力なく首を振った。
「あすみを、止めてくれ」
老人は、何者とも知らないはずの師匠の顔を見つめて、そう懇願した。師匠は口を引き結んで、なにも言い返さなかった。ただ、老人を睨みつけ、背後にある壁を睨みつけ、ここにいない、かつての誘拐事件の被害者であった少女を、 盲目の連続殺傷事件の犯人を、その過酷な人生を、睨みつけていた。
◆
師匠と僕は、鳥井家を出たあとで、西署の刑事、不破と喫茶店で落ち合った。
春に、幽霊物件にかかわる事件の際に不破と待ち合わせたのと同じ、『ジェリー』という店だった。
「なんだおまえら、草野球帰りかよ」
不破は僕らの格好を見て笑った。改めて僕らは、お互いの姿を確認する。阪神タイガースの帽子に、バットケース。師匠はいつもの脚線美を惜しげもなく晒した、ホットパンツだ。
不破のほうはあいかわらず、ヤクザにしか見えない服装だ。少なくともカタギには見えない。
「で、見つかったのか。弓使いちゃんは」
ボックス席にもたれかかるように深く腰掛けながら、不破は言った。
「捜索中だ」
師匠はそれだけ言って手のひらを振った。
不破からは、連続通り魔事件の情報を横流ししてもらうかわりに、こちらの得た情報も教える約束になっていた。
「頼むぜ。1課の連中も困ってんだ。俺のカンだと、あれは普通の捜査じゃ無理だな。お宮だ。お宮入り。おまえの得意な分野の事件だとすると、そうなるな」
「まだわからないよ」
「おい」
不破はずい、と師匠に顔を寄せた。
「犯人がわかったら、俺に教えろ。最初にだ」
冗談で言っているわけではなかった。真剣にもちかけているのだ。不破も、師匠の能力を信じている人間の1人だった。
「なあ、不破さん。例えばの話だけど、呪いでさ…… 呪いで人を殺したら、それは罪に問えるのか」
「はあ?」
「犯人が、呪いで殺したと言っている。被害者も呪い殺される、と怯えていた。で、呪いで殺したとしか説明できない状況での殺人が発生した。これは、殺人罪が適用できるのか」
不破は笑った。
「そいつはな、迷信犯ってんだ。不能犯、つまり犯罪意図と、結果が実証的に結びつかない行為の一種だ。丑の刻参りで呪われた相手が死んだとしても、藁人形を釘で打つ行為と、相手が死んだ結果の因果関係が科学的に立証できないから、罪には問えない。逮捕しても、まあ、あって脅迫罪くらいにしか持っていきようがないな」
「じゃあ、なんで犯人を訊くんだ。私の得意分野の事件なんだろ」
「今回は被害者が、実際に矢のようなもので重傷を負っている。どんなやつか知らないが、とっ捕まえさえすれば、凶器が見つからないことなんて、どうとでも説明はつけられるさ」
片方の眉を上げて、不破は不敵にそう言った。
「それ、冤罪みたいなもんじゃないですか」
僕がそう言うと、不破は「ああ?」と言って睨みつけてきた。怖い顔だ。僕はツバを飲み込む。
犯罪をでっち上げる、と言っているに近い。目的のために手段を選ばない。こういう刑事が、冤罪を生むのだろうか。
「不破さん、あんた、1課に戻りたいのか」
師匠の問いかけに、不破は、ふ、と表情を和らげた。
「暴力犯係はな、つまらんよ。やつらの頭のなかは、みんな同じだ。暴力、女、金、メンツ…… そいつらと四六時中やりあってるとな、だんだん頭のなかが麻痺してくるんだよ。麻痺して、同じ発想しかわいてこなくなる。ヤクザ相手の稼業は、ヤクザ者しか勤まらないってのはよく言われるがな。あれは逆だ。なっちまうんだよ。こんな風にな」
不破はジャケットを自分の両手で広げて見せた。そこには鍛えられた厚い胸板しかなかったが、なんとなく、言っていることはわかった気がした。
「ちっ」
不破は、余計なことを言った、というように視線を逸らし、頭をかいた。師匠は、くすり、と笑った。
「ここ、いいかな」
突然、そんな声がかかった。
昼時で混雑した喫茶店の4人がけのボックス席には、僕と師匠、向かいに不破、という3人が座っていた。その空いている不破の席の隣に、スーツ姿の男が返事も待たずに腰掛けた。
「なっ」
不破も、師匠も、僕も、驚いて腰を浮かせかけた。しかし、その男の身体から発せられる威圧感に、一瞬金縛りのようになっていた。
「松浦……」
不破が、驚愕しながら男の横顔にそう呼びかけた。
松浦。
地元の大規模暴力団、立光会の直系団体、石田組の若頭補佐。それがその男の肩書きだった。僕と師匠はこの春に、古い心霊写真にまつわる事件で、この男と関わり、その底知れない恐ろしさを感じたばかりだった。
松浦が、喫茶店の入り口に向かって手を振った。人目でカタギではないとわかる服装の男が、頭を下げて店から出て行った。組員か。あいつに、どこからかあとをつけられていたのか。僕らか、あるいは不破が。
「すぐに終わりますよ。話は、シンプルなものがいい」
松浦はテーブルの上で、両手の指を組んだ。黒縁の眼鏡の奥から、蛇のような薄い視線が僕ら3人を静かに威圧していた。
「お嬢さん。あなたが探している女は、私の石田組の親戚筋である、酒井興業の西野という男の情婦です」
「なにっ」
師匠が、周囲を凍らせるような松浦の威圧感に抵抗して、身を乗り出しながら睨みつけた。
「ヤクザの女を探し回るってことは、つまりそのヤクザを、ひいては組を、的にかけてるってことです。私たちの業界ではね。あんな風に派手に探されると、痛くも無い腹を探られる気にもなる、というものだ」
「ヤクザの女? だれのことだ」
「不破さん。あなたには話していない」
ぐっ、と不破は唸った。僕は、不破が怒鳴りだすと思った。しかし不破は口を引き結んで、席に深く沈んだ。意外な光景だった。この不破にも、松浦はアンタッチャブルな存在なのだろうか。
「西野はつまらないチンピラです。その女は西野のところに転がり込んでから、客を取らされていたようです。顔に大きな傷があるから、普通の店には出せない。だから……」
「シャク屋か」
師匠が言った。シャク屋。聞いたことがある。この街に特有の風俗の呼び名で、民家を使ったポン引きだ。まともな店を構えないから、値段は安い、最底辺の風俗だ。
「そうです。しかし、その女は数ヶ月まえに西野の元から姿を消しました。客のだれかと逃げたのかも知れない。西野は困っていましたよ。金づるがいなくなって」
ドシッ。
師匠が固いテーブルを拳の腹で打った。松浦は平然と続ける。
「とにかく、その女は消えました。あなたなら、西野までたどり着いてしまいそうだから、先に教えるのです。余計なことを探り回らないでいただきたい。西野も、酒井興業も、その女のことは知りません。それは私が保証します」
「おい、松浦。私は、ヤクザが嫌いなんだ」
師匠は押し殺した声でそう言った。
「知っていますよ。オバケが好きなこともね。……あなたが、その女を追っているのは、オバケが絡んでいるんでしょう? 私たちの業界の、余計なものを見ないようにしてもらえば、好きにしてください」
松浦は立ち上がった。
そして、師匠と、僕の顔を眺めなら、「怖いな」と言って、薄く笑った。
怖いだろうとも。
去っていく松浦の背中を見ながら、僕は隣の師匠が放つ殺気を痛いほど感じていた。僕もまた、自分の身体から同じ力が噴き出しているような気がした。
僕らの探していた弓使い……。
誘拐・監禁され、学校教育を半分も受けられず、両目を抉られ、生涯にわたる傷を負い、両親は別居し、母には経済的に搾取され、チンピラの情婦になり、客をとらされ……。
「おい、おまえら」
不破が、僕らの尋常でない様子に戸惑っている。
ちょっと、黙っててくれないか。
それでも、山田あすみは、弓使いは、この街を、悪霊から、守ろうとしているんだぜ。
ギシギシと、僕らの周りの空気が軋んでいる。
やり場のない感情が、僕の目から、涙となって流れ落ちていった。
馬霊刀 4/4
2016年7月31日 23:05
4 馬霊刀
喫茶店を出たあとで、僕らは留置所に拘留中の緒方に面会を求めた。雑貨店の事件のあと病院に運ばれ、1週間ほどで退院した緒方は逮捕されて、すでに検察に送致されていた。強姦は親告罪なので、被害者の告訴がなければ訴追できないが、被害者の女性が説得に応じて訴えたそうだ。起訴まで持っていけるだろう、と不破は言っていた。
拘留中は被疑者に基本的にだれでも面会できるが、本人が拒否した場合は無理だ。師匠は不破に、なんとか顔だけでも覗かせてくれないか、と言っていたが、思いのほか、緒方は面会に応じた。
西署の留置所で、署員立会いのもと、緒方に会った。
10日ほど前のことなのに、緒方はげっそりと頬がこけていた。頬の傷には、まだ痛々しくガーゼが当てられている。小さな穴のあいたガラス越しに、緒方は頭を下げた。疲れた様子だったが、目つきは穏やかだった。
「すみませんでした」
そして、師匠に感謝の言葉を述べた。
あのときの自分は、どうかしていた。こんなことはいけない、とわかっていてもなぜかやめられなかった。あなたにすべて暴かれて、ようやく正気に戻れた気がする。
僕には表面をとりつくろっただけの、つまらない言い訳に聞こえたが、師匠は緒方の目をじっと見つめて、「そうか」と言った。
留置所を出て、師匠は僕に言った。
「緒方から、とり憑いていた霊の気配が消えていた。あの、弓矢のせいかもな」
「油の弓、ですか」
山田あすみが持ち去ったという、鳥井家に伝わる穢れ払いの弓。
「幼少期に壮絶な体験をし、視力を失った山田あすみは、常人とは別の感覚で世界を『見て』いる。そしてその世界では、霊的な存在も蠢いている。犬神人の血を色濃く受けついだ彼女は、それらのなかでも、悪意をもった霊を、穢れ払いの弓で射殺すようになった。かつて、道端に放置された無数の遺骸の骨を、穿って歩いた祖先のように」
師匠はこれまでのことを整理しながら語った。
「母親の元を飛び出し、ヤクザ者の女になり、そしてそこからも姿を消した。去年の冬から、連続して発生していた通り魔事件。あれは、山田あすみが、悪霊を殺す穢れ払いを行っていたのかも知れない」
「緒方みたいに、他の被害者たちも、そんな悪霊にとり憑かれていたと」
「たぶんな。少なくとも、山田あすみ…… 弓使いの目には、そう見えたんだ。春に、国分川の向こう岸から、恐ろしい霊の群がやってくるのを見ただろう?」
「はい。死滅回遊だって、言ってたやつですね」
師匠は、消滅を待つだけの霊道を歩く霊たちのなかで、種が芽吹くように急に強大化するものがいる、と言っていた。
川を渡りながら、そんな恐ろしい悪霊になっていくものたちの群を、僕らは見た。見ていることしかできなかった。
「あのとき、私たちのほかに2人いただろ」
「いましたね。サラリーマンっぽい人と、あと1人」
「その、あと1人のほうは、攻撃しようとしていた。霊を」
「えっ」
そういえば、そんな風に見えたような気がする。たしか、師匠が止めたのだった。「やめろ、1体じゃない」と。
「あれが、弓使いだったのかも知れない。いや、たぶんそうだ。去年あたりから、この街でおかしなことが増えている。霊的な現象も、明らかに増加している。私には、それらを誘発する、目に見えない悪意が、この街に蠢いているように感じるんだ」
師匠がそんなことを言うのを、これまでも何度か聞いた。
「悪霊が川を渡ってくるのも、そうだと?」
「ああ。それは、山田あすみが姿を消し、弓使いが事件を起し始めたことと、恐らくリンクしている」
僕が直感でそう思っていたことを、師匠がすべて言葉にして整理していった。
「邪魔をするな。邪魔をしなければ、わたしは犬神人だ。この街を…… 浄化する」
師匠は、僕が雨のバス停で会った、山田あすみの言葉を再現した。最後の言葉は、雨にかき消されて聞こえなかったが、そんなニュアンスの言葉を言おうとしたのだろうと、今では僕も信じ始めていた。
「どうしたらいいんでしょう」
「どうしたら、とは?」
「僕らは、連続通り魔事件の犯人を追っていた。でも、弓使いは、悪霊を退治しているんでしょう? 街を守ろうとしているんじゃないですか」
「山田あすみの目には、悪霊にとり憑かれ、悪霊と重なっている人間は、見えていないのかも知れない。悪霊を撃った弓矢が、生身の身体も傷つけ、結果的に人を死に至らしめているんだ。このまま放ってはおけない」
「その人間が、緒方みたいに、他の人を苦しめるやつでも、ですか」
「……」
そうだ。緒方は、結果的に弓使いに襲撃されたことで、ようやく正気に戻れたのかも知れない。
僕は、弓使いを、その存在を、行為を、肯定し始めている自分に気づいた。
「犬神人に、どうして『犬』っていう言葉がついていると思う?」
師匠は急に話の矛先を変えた。僕は意表を突かれて、とっさに返事ができなかった。
「この街の犬神人は、死体の清掃を行う京都の犬神人と比べて、穢れ払いという、一見、本来神職が行うような崇高な役割を果たしている。でもな。同じ『犬』って言葉を頭につけられてるんだ。蔑みをこめた、卑しい称号を。結局、人々にとって、死体の清掃も、死体の骨を弓矢で傷つけて歩く行為も、同じように穢れた、忌まわしい仕事だってことだ。だれかがやらなければいけない、この街を清浄に保つために必要な行為なのに、手伝いもせず、それに後ろ指をさして蔑んでいる……。私には、山田あすみが1人で背負っているこの業を見逃して、見てみぬ振りをするのは、かつて『犬神人』と呼んで蔑んだこの街の人々と、同じじゃないかって気がする」
師匠は淡々とそう言った。僕は、頭を殴られたような気がした。
「山田あすみのジイさんが言ってたろ。孫を、あすみを止めてくれ、って。それでいいじゃないか」
そう言って、師匠は吹っ切れたような顔をした。
僕は黙って頷いた。
◆
しかし、それから山田あすみの捜索は進展しなかった。現時点で一番新しい情報は、酒井興業の西野という男のところから逃げた、というものだ。石田組の松浦から、西野を探るな、という警告を受けた僕らは、表立って西野の筋を追うことができなかった。小川所長に迷惑がかかる可能性もあったからだ。いくらこの件は小川調査事務所とは関係がない、と言っても、そんな理屈は通用しないだろう。ヤクザは、人の弱みを突くのに容赦はしない人種だということを、師匠はよく知っていた。
師匠は僕も半ば捜索から外していた。暴力団を担当している刑事の不破のルートから、慎重に松浦の言葉の裏を取っているようだったが、それがわかったところで、現在の山田あすみの居場所を突き止めるのは至難のわざに思えた。
長期戦を覚悟したらしい師匠は、これまでどおり小川調査事務所の依頼を受け始めた。ひとまず、弓使い側のアクションを待つ、というスタンスにしたようだ。プライベートでも、『オバケ』事案の依頼でも、霊現象と関わり続ける師匠は、いずれどこかでまた弓使いとカチ会うだろうと考えていた。
ある日、小川所長が師匠と僕を、自宅に招待してくれた。奥さんの律子さんが作ったという、創作料理の新作を披露すると言って。そこに所長の刑事時代の同僚でもある不破も呼ばれていた。
「お、トーマ。また大きくなったか」
不破は、7歳になる小川所長の息子を抱きかかえた。トーマは癖っ毛の頭を乱暴に撫でられて、それでも嬉しそうにしていた。
「これ美味いですね。なんの魚ですか」
師匠は律子さんに、皿の上の魚料理のことを尋ねている。
「それは、スズキのガーリックハーブソテーよ」
律子さんは物腰の柔らかな女性だ。タカヤ総合リサーチの高谷所長の娘で、その父親の事務所で働いていた小川さんと結婚し、小川律子になっている。
「あ、そうだ。このあいだ頂いた白ワインがあったわ」
そう言って杖をつき、席から立ち上がろうとした。律子さんは昔の事故で、右足が不自由だった。
「ああ。いいよ、いいよ。取ってくる」
小川所長は甲斐甲斐しく働く。仲むつまじい家族だ。
「ムニエルにしたら美味そうだな」
師匠は魚料理をほおばりながら、そんなことを言っている。
ちょっとしたコース料理のような豪華な夕食が終わって、僕らは窓際のウッドデッキのベンチで、憩いのひとときを過ごした。市内の中心部からは少し外れるが、2階建ての1軒屋で、なかなかの立派な家だった。これも僕らバイトをスズメの涙の時給で働かせて搾取している成果か、と思っていた。が、実際のところは、律子さんの持参金がわりで高谷所長が建ててくれたものらしい。固定資産税を払うのに必死、というところが小川さんの本来の甲斐性のようだ。
「またなにか不破と組んで、変なこと企んでるんじゃないだろうな」
小川所長はワインを片手に、ぼそりと言った。
「もう弓使いも諦めましたしね」
僕は師匠に語りかける。半ば嫌味で。
「大丈夫ですよ。迷惑をかけることはないです」
師匠の視線の先には、広い庭で転げまわって遊んでいる、不破とトーマ君の姿がある。
「トーマ君はお父さん似ですね」
僕は自分の髪の毛をくるくると摘みながら言う。「癖っ毛のところとか」
「……そうだな。将来は、跡を継がせようかな」
「あの零細興信所をか」
師匠が笑う。
「じゃあ、こんな風にならないように、お勉強させなきゃね」
隣の律子さんが微笑んで言った。
「ははは」
小川所長も笑っていたが、しばらくしてから、「あの、律子さん? 冗談ですよね」と強張った顔で訊ねていた。
そんなことがあった2日後のことだった。
僕は師匠のアパートで、晩御飯を食べさせてもらった。おかずはスズキのムニエルだった。心霊スポットのことなど、たあいのない話をした。部屋を出るときには夜11時を回っていた。
自転車にまたがって、ペダルをこぎ始めてしばらくすると、ゴロゴロゴロ、という音が空から聞こえていた。
ひと雨きそうだった。曇っているのか、月は見えない。風が湿っているようだ。傘を持っていない僕は、急いで帰ろうとした。
その瞬間だった。
ふいに、時間が止まったような感覚があった。身体が動かない。いや、意識ははっきりしているのに、「動きたくない」と、手足が動作を拒否しているようだった。
皮膚を、小さい虫が這い回り始めたような悪寒がする。ドロドロと、どこか遠くで、嫌な音が鳴っている。雷ではない。遠いその音は、糸電話のように、僕の頭蓋骨のなかで鳴っているのだ。
いつか感じたことがある。これは春に、恐ろしいものたちの群が、国分川を渡ってきた、あのときに感じた予感だ。しかし、あのときとは比べ物にならない。汗が全身から吹き出し始めた。
東。東だ。あのときと同じ。東から、なにかが来る。
やがてその感覚が、緩やかになってくる。とてつもなく恐ろしいなにかが、街のなかに溶けていくようだった。
金縛りから覚めたように僕はハッとした。そして自転車を反転させる。
師匠のアパートに戻り、玄関から転がり込むと、部屋のなかでは、師匠が電話をかけていた。
「もういいっ」
ガチャン、と乱暴に受話器を置いて、こっちを見る。
「馬霊刀だ。これほどとは」
いつになく、余裕のない表情だった。
「馬霊刀って、いつか言ってた、馬塚から出た刀ですか」
「たぶん、馬霊刀が、国分川の橋を渡ったんだ。渡り終わってから、感じなくなった。やばいぞ」
師匠は受話器に手を乗せたまま言った。「市の教育委員会に知り合いはいないか?」
「いません」
「いま役所に電話したけど、話のわからない宿直のジジイしかいやがらねぇ」
師匠は悪態をつきながら、イライラと自分の膝を叩く。
「ああいう埋蔵文化物が発見されたら、教育委員会に報告が行くんだよ。今現在、あれがどこにあったはずなのか確認したいのに……」
「土地の所有者のところじゃないんですか」
「文化財に認定されたら、所有権は国か、県に帰属されるんだ。だから、えーと……」
師匠は知識を総動員させて必死に考えている。
「あ、そうだ。警察だ。文化財に認定されるまでは遺失物だから、警察に遺失物届けが行くんだ。で、たしか認定の結果も警察に行くはずだから、警察でもわかるんじゃないか」
師匠は受話器をあげて、電話をかける。
「不破さん。よかった、家にいた。頼む。1ヵ月くらい前に東署に届けがあったはずの、馬塚から出た出土品がいまどこに保管されてるか、調べてくれないか。大至急で」
頼む、ともう一度師匠が言って、電話は切れた。引き受けてくれたようだ。
「ああ~」と師匠は悔しそうな顔をしている。「また不破に借りを作っちまった。マジで貞操の危機だぞこれは」
貞操の?
こんなときなのに、僕は色めき立った。
それなら、僕だって、師匠に貸しがある!
……いや、ないな。借りしかなかった。
「おまえ、あの脇差、持ってきてないよな」
そう聞かれて、僕は手をブラブラさせる。最初は、弓使いに怯えて護身用の脇差入りのバットケースを持ち歩いていたが、このところはその危機感も薄れて、持ち歩かなくなっていた。というか、外で急に職務質問されて、銃刀法違反で逮捕されるほうが怖かった。
「ちっ」と舌打ちをする師匠に、僕は「そんなにヤバいんですか」と訊いた。
いったい、馬霊刀とはなんなのだ。
「弓使いが、出てくるぞ」
師匠は短くそう言った。僕はハッとする。そうか。そうだ。この春に、悪霊がこの街に侵入してくる気配を感じて、川に向かったあのときのように、弓使いもまた、それを察知して動き出す可能性があった。穢れ払いの業を、その肩に背負って。
電話が鳴った。
「ああ、不破さん」
早い。東署の夜番に同期か、貸しのある後輩でもいたのか。ひとことふたことかわし、師匠は受話器を置く。
「やっぱり、市の埋蔵文化財センターだ」
師匠は地図を広げた。埋蔵文化財センターは国分川を渡った東側にあった。僕らが感じた異常な気配は、街のこちら側、つまり西側にやってきたはずだ。それを信じるなら、埋蔵文化財センターから移動したことになる。
不破は、センターの電話番号もついでに調べてくれていた。
すぐに電話をしたが、営業時間外だというアナウンスが流れるだけだった。
「とにかく、まずセンターに行ってみよう」
師匠は立ち上がった。車の鍵と、部屋の隅に立てかけていた金属バットを手に取って。
部屋の外に出ると、雨が降っていた。
この街では、自転車があればたいていの用事はこと足りるので、師匠は車にはめったに乗らなかった。
「おい、おまえの家に寄るぞ。あれを取ってこい」
師匠はボロ軽四の運転席の乗り込み、エンジンを掛けながらそう言った。
「あれって、あれですか」
僕は刀を振る真似をする。心臓がドキドキしてきた。いよいよ、ただごとではなくなってきた。
そんなもの持っていって、どうしようというのだ。僕は傷害罪で捕まりたくない。
そんな感じの文句を、早口で言うと、師匠はふん、と鼻で笑った。
「この騒動では、有効かも知れない」
そんな謎めいたことを言って、乱暴に車を発進させた。
車はあっという間に僕のアパートに到着する。僕は雨のなかを走って部屋に入り、すぐに飛び出してくる。
「なんだ。そのビニール」
助手席に戻った僕が手に持っている、黒いゴミ袋を被せた長いものを、師匠は見咎めた。
「バットとは違うんですよ。2重の意味で!」
「銃刀法違反と、骨董品ってことか」
「そうです」
夜とはいえ、こんなものを持ち歩いているのを、だれかに見られたらまずい。それにこんな貴重品を雨に濡らせたくなかった。
「馬霊刀ってのはな、この地方独特の風習なんだよ」
師匠は、車を運転しながら説明してくれた。
「おもに中世に行われたもので、発展段階にあった武士勢力…… 受領国司(ずりょうこくし)の郎党や、その支配に対抗する地元の富豪勢なんかがな、その宿営地に、死んだ軍馬をまとめて葬った墓を作ったんだよ。馬塚だな。その馬塚に、刀剣を一緒に納めたんだ。今までも何本か見つかってて、だれが付けたのか、馬霊刀って名前で呼ばれている」
「ニュースで言ってましたね。鎮魂のための魔よけじゃないかって」
「違うんだよ」
師匠は吐き捨てるように言った。
「そんなしおらしいもんじゃない。大正時代に見つかった馬霊刀は、発見者の考古学者が自分の腹に刺して、崖から身を投げた」
「な、なんでですか」
「正気じゃなかったのは間違いないだろう。ファラオの呪いみたいに、日本でも墳墓を発掘したとき、祟りとしか思えないようなことが頻繁に起こることがある。高松塚古墳の呪いなんて有名な話だ。どれも、どこまで眉唾なのかわからないが、たぶん馬霊刀は本物だ。発見者や、発掘に関わった人間たちにことごとく、異変が起きている。今、現存している馬霊刀はない。大正時代の事件みたいに、いずれも、事故で滅損・紛失している」
そんな話をしている最中にも、カーステレオからは稲川淳二の声が聞こえてくる。繰り返される、特徴的な擬音が。
「聞いたことないですよ」
「最後に見つかったのが、戦前だからな。もう60年も前だ。私も当時の記録で見ただけだ。でも、地元の史談会、考古学者界隈では、今でも知ってるやつは知っている。馬霊刀の呪いのことは」
「そう言えば、犬神人のことを教えてくれた宮内先生も、知ってる風でしたね」
知ってるけど、語りたくない、という様子だったことを思い出した。
「喋るだけでも呪われる、って話もあるからな。三島、って言ったっけ。あの、発掘してた埋蔵文化財センターの所長ってやつは、それを知らないのか、平気でテレビカメラに撮影させてやがった」
師匠は、くそっ、とハンドルを叩いた。
「弓使いのことばかり気にして、馬霊刀のほうは忘れかけてたけど、こんなにヤバイとは……」
「あ、そういえば。こないだ、遺跡の発掘現場で重機が倒れて作業員が怪我したって、新聞に出てましたね」
僕も今の今まで忘れていた。流し見をしていたので、それが市の東部で見つかった馬塚の発掘現場のことだったのか、はっきり覚えていない。
「本当か? くっそ。見逃してたな。どうもアンテナが鈍っている」
師匠は帽子の上から頭をガリガリと掻く。女性らしいとは言えない態度だ。
「なんで馬霊刀だって思ったんですか」
「あん?」
「いや、さっき、僕も感じましたけど、あのなにか嫌なものが迫って来る感じ。あれが馬霊刀だっていうのは、どうして」
「聞こえなかったのか」
「え」
「蹄の、音が」
ボロ軽四は、国分川にかかる橋を渡った。この橋を、馬霊刀も渡ったのだろうか。だとすると、車か。
川を渡ってから、途中で南に折れて、しばらく広い道を走る。
「ここだな」
左折して、狭い道に入った。ヘッドライトに照らされて、道路に迫るように、かなり先まで墓地が並んでいるのが見える。
「いい雰囲気じゃないか」
師匠の軽口に、カーステレオの稲川淳二が悲鳴をあげる。
「あった」
入り口の石門に埋蔵文化財センターという文字が見える。門のところには、蛇腹のシャッターがあったが、ちょうど車が1台通れるくらいに開いている。軽四はそこから敷地内に侵入した。
降り続く雨のなかに、どこか神社の社殿をイメージさせる3階建ての建物があった。
2階の窓から、光が漏れている。1階の入り口は真っ暗だった。すぐ前に車を停めて、雨のなかを走る。
玄関のガラス戸は鍵がかかっていなかった。貴重な文化財があるはずなのに、こんな夜中に玄関に鍵をかけていないはずはない。門のシャッターが開いていたことといい、なにかおかしい。
師匠を先頭に、僕らはドアのなかに入る。すぐ左手に受付があったが、真っ暗で人影はなかった。ほぼ正面に、上に伸びる階段があった。上の階から、光が漏れている。
階段の右手側には、展示コーナーがあった。かなり奥行きがある。暗くてなにがあるのかよく見えなかったが、ガラスケースが並んでいるようだ。
「行くぞ」
小声で師匠が言い、僕らは階段を登った。
2階に上ると、『研究室』とある部屋から、明かりが漏れている。なかを覗くと、事務机の間の床に、白衣の男が倒れていた。
「おい。大丈夫か」
師匠が抱え起すと、男は呻いた。眼鏡をかけている。30歳くらいだろうか。ガタガタと震えている。まるで寒さで震えているような小刻みな動きだった。
「力が入らない」
かすれた声でそう言った。
「怪我は、してないのか」
師匠が男の身体を調べる。白衣には血の跡などは見当たらなかった。
「ここにはあんただけか。なにがあった」
師匠がそう訊ねているあいだに、僕は研究室を見回して、外にも顔を出してみる。書庫や収蔵庫があるようだが、明かりはついていなかった。人の気配もない。
「怖い。なにか、影みたいなものが、いっぱい」
それを聞いて、師匠は周囲に鋭い目線を向けたが、なにも見当たらなかった。
「それに、触られたのか」
そう訊ねると、男は小刻みに頷いた。
「もういないな」
師匠はそう呟く。
「ほかにだれもいないみたいです」と僕が言うと、師匠は「所長は? 所長はいないのか」と男の肩を軽く揺さぶった。
「所長が、持っていった。あれを」
「刀だな。馬塚から出た」
「あれはおかしかった。最初から。田代も怪我をした。新田さんも。……あれが、なにか連れてきたんだ」
男は涙を流しながら震えた。
「所長はどこへ行った?」
「車の鍵を持って……」
「車に乗ったんだな。どこへ行ったんだ」
男は首を振った。わからないらしい。ここでその手がかりがなくなると、行き先を見つけるのは不可能に近い。
師匠は焦って訊ねる。
「なにか言ってなかったか。正気じゃない様子だったか?」
「……来月やる、展示室のリニューアルで、馬塚から出たあの刀の紹介コーナーを作ろうって話をしてたんだ。俺はやめたほうがいいって言ったんだ。おかしなことばかり起こるから。そしたら、所長の目つきが変になってきて。か、影が、まわりに見えはじめて……」
男は震えながら、それでも続けた。
「そうだ、見せるものじゃないな、って急に言い出して、出て行こうとしたんだ。あの刀を持って。俺は怖くて。でも止めたんだ。そしたら、いや、行かなければ、って。く、供物だから、って」
「供物?」
師匠は眉を寄せた。そして次の瞬間、目を見開くと、男を離し、自分のリュックサックから地図を取り出した。
市内の地図だ。師匠はそれをガサガサと広げて、ある一点を指さした。
「左手」
国分川沿いの城の近くに、人間の腕のような形のマークがある。春に、保育園で起こった奇妙な事件で、園庭から掘り起こされたマネキンの腕だ。師匠はその事件のあとこの地図を買って、マネキンの腕の絵を書き込んでいたのだった。
「頭」
そう言って、師匠は地図上に指を滑らせ、北のほうの、商科大学のあるあたりでピタリと止めた。そこには人間の頭部を模したマークが描かれている。
そのあとにあった別の事件で、マネキンの頭部が掘り起こされた場所だ。
「供物。馬霊刀が供物だと? 剣を持つ手。右手だ。右手の位置はどこだ」
師匠は呟きながら近くの机に転がっていた鉛筆を掴んで、地図の上をなぞる。
「頭を起点に、左手と線対称の位置……」
そう呟きながら、地図の上に、2つの丸を描いた。1つは、商科大学の北東。植物園の先のあたりだ。もう1つは商科大学の南西。柳ヶ瀬川のすぐそばだ。
僕はゾクゾクしていた。師匠は、結局解決しなかった2つの事件と、この馬霊刀が消えた事件とが、繋がっていると考えているのか。
「線対称って、角度はどこからでてきたんですか」
師匠が地図上でなにをしようとしているのかはわかった。しかし、頭と左手の位置関係はわかるが、このままでは中心線がどこにくるのか確定しない。
「マネキンの部品は、手首じゃなくて、腕だった。頭、左腕、右腕、左足、右足。そして胴体。末端は5つだ。保育園で地面に描かれていたのは、六芒星だった。しかし今度は5……。五芒星のはずだ」
師匠は2つの丸に、補助線を引いた。北の、商科大学のあたりを頂点とした、2つの五芒星が現われる。ひとつは、北が上になっているこの地図で、僕らから見て右側に横たわっているもの。そして、まっすぐ直立したもの。2つの五芒星は『頭』のマークと、『左手』のマークの地点を共有している。
「仰向きか、うつ伏せか」
五芒星を人体に見立てれば、右側に横たわっているほうは、頭部に対して左手が南側、右手が北側に、そして両足が東側にある。地図の上でそれを見下ろすと、うつ伏せになっているように見える。
もう1つの五芒星は、左手が東。右手が西。足は南側だ。これは、仰向けになっているように見える。
「こっちだな」
師匠は仰向けのほうの五芒星に大きく丸をつけた。
「仰向けだと、左手は国分川、右手は柳ヶ瀬川。そして左足も、ちょうど柳ヶ瀬川が河口に近づいて東に蛇行し始める場所で、その内側に入っている」
僕らの住むO市の中心部は、東を国分川、西を柳ヶ瀬川という2つの川に区切られた空間の内側にあった。川境はかつての『クニ』の境だ。今の行政区のように、歴史的背景や政治的な事情で区切られる前の、もっとも原始的で合理的な『ウチ』と『ソト』の分かれかた……。
僕も師匠も、国分川を渡ってくる悪霊に反応した。『ウチ』に侵入された、と感じたのだ。その『ウチ』に、大きく手足を広げて仰向けに横たわる、五芒星。
なんだ、これは。
なにか起こっている。この街で。それを直感でわかっても、いったいなにが起こっているのか、想像もつかなかった。
「小安寺の西だ」
師匠は最寄の駅の名前を言った。そして柳ヶ瀬川沿いの、「右手」と書いた五芒星の端に、ぐりぐりと丸をつけて立ち上がった。
「悪いな。もう行く。救急車は呼んどく」
師匠はようやく上半身を起したばかりのセンター職員の男にそう言って、地図をしまったリュックサックを背負いなおした。
心細そうな男をそのままにして、僕らは1階に降りた。僕は師匠に指示されるままに、入り口側の受付にあった電話を借りて119番にかけた。
「急患です。埋蔵文化財センターです。早く来てください」
そう言って、詳しい話を聞かれる前に電話を切る。イタズラと思われて出動してくれなかったら、悪いなと思ったが、震えていた男の様子も、大事はなさそうだったので、まあいいやと勝手に納得した。
玄関の前に停めてあった車に乗り込むと、すぐに発進した。
「所長は刀を持って、本当にそこへ行ったんですか」
「わからん。ほかに手がかりがない」
「所長って、ニュースで見た、あの七三分けのおっさんですよね」
「ああ、宮内先生が三島君って言ってたな。軽率なところがあるってな!」
師匠はアクセルを踏み込んで、かなりのスピードで飛ばし始めた。
時計を見ると、夜の12時を回っていた。道路上のまばらな車を、ボロ軽四が次々と追い抜いていく。
小安寺のほうということは、国分川を渡って市街地に戻り、西の端に行かないといけない。遠いな。
「供物ってなんですか」
「しるか。でも、思いついちまったんだよ。あのマネキンの部品を埋めるのは、なにかに捧げる、そんな行為なんじゃないかってな」
保育園の事件でも、埋めていたのは結局なにものだったのか、わからないままだった。
過去の事件と、今回のそれを結びつけた師匠の発想には、僕はついていけなかった。カンか。カンだとしても、僕には見えていない材料が、師匠のなかにあるからこその発想なのだろう。
「ついていけません」
そう言いながら、僕は師匠のカンが当たっていることを、半ば信じていた。
窓の外の闇のなかを、ときおり小さな明かりが流れていく。
知らない間にもう、国分川を渡ったのだろうか。夜の道路を、師匠の運転する車が、蛇のようにくねりながら走っていく。
かなり飛ばしているはずなのに、車内ではゆるやかに時間が流れているようだ。不思議と恐怖心はない。落ち着いている。とんでもないことに巻き込まれているというのに。
荒唐無稽すぎて、頭が麻痺しているのだろうか。
あれ。そう言えば、ビニールに入れて持ってきた刀はどこにいったのか。埋蔵文化財センターに入ったときは、持っていたはずなのに。忘れてきてしまったのだろうか。
「馬霊刀って、そんなに恐ろしいものなんですか」
後部座席から、卵のような顔の隣人がひょっこりと顔を出して、尋ねた。
「なんだ、小沢。びびってるのか」
師匠が茶化したように言う。
「私は中沢ですよ。馬のお墓に一緒に埋めてたってことは、あの所長が言ってたように、魔よけではないんですか」
「違うな。だったらあんなに、その刀自体に、呪いを誘発する力はないはずだ。はっきり言って、異常な力だ。発見された埋蔵物にまつわる呪いの話はたまに聞くけど、私が調べた限り、この馬霊刀はことごとく、とてつもない呪いを周囲に振りまいている。偶然じゃないんだ。なにか、存在の根源に、呪いが、怨念がまとわりついている」
師匠はゆっくりとそう言った。
「では、馬霊刀って、なんなんですか」
僕は何度目かの質問をした。これまでずっとはぐらかされていたけれど、その答えを聞いてもいいタイミングだと思った。
師匠はハンドルを握ったまま、タンタン、と指でハンドルをノックする。
「昔の日本人てのは、今よりもはるかに信心深かったんだ。特に仏教だな。不自由で、理不尽で、ままならない生活のなかで救いを求める心は、真剣で、真摯だ。六道(りくどう)って言葉を聞いたことがあるだろう。仏教で、苦しみから解き放たれない存在が惑う、6つの世界だ。天上道や、人間道、餓鬼道など、人はそれらの世界を輪廻転生して苦しみ、惑い続ける」
師匠の静かな声がゆるゆると車内に流れる。
「中世の日本では、それまでの国司よりも権限を強化された受領(ずりょう)による領地支配が、苛烈になっていった。それに対抗する、土着の富豪、富農たちによる暴力的な圧力。またそれに抵抗するために、受領は武装した集団を手勢として育て、また雇い入れ、紛争を収める力を手に入れた。武士の誕生だ。やがて武士は、力で既存権力を覆し、貴族社会を終わらせることになる。その黎明期、このO市では、受領の郎党と呼ばれる武士集団がいくつかあった。彼らはまた、市井の人々と同様に信心深かった。六道のうち、修羅道という世界がある。修羅となって永遠に終わらない戦いに明け暮れる、血塗られた世界だ。戦場で命を落とした武士はこの修羅道に落ちると、彼らは信じていた。命を散らし、奪い合う、自らの業のために。そんな彼らが、死んだ軍馬を一箇所に集めて弔った。その塚には、一振りの刀を添えた。なぜだと思う」
師匠が、こちらにチラリと視線を向ける。僕と卵顔の隣人は、2人とも首を横に振った。師匠が口を閉ざしたままだったので、仕方なく、といった様子で、卵男が言った。
「祟らないように、魔よけとして置いたのでなかったら、あれですか。成仏するように、ですか」
「違う」
師匠が冷たい声で言った。
「戦い、死んだ彼ら武士が、修羅道に落ちたあとで、永遠の戦いの世界で軍馬に乗るためだ。つまりその刀、馬霊刀は、馬たちの魂を、地獄に落とすために埋められた、呪物なんだ」
車は、音もなく走る。暗く、重層的な景色が窓の外を過ぎ去っていく。
空気が生ぬるい。僕は息苦しさを覚えて、助手席の窓を開ける。けれど新鮮な空気は車内に流れることはなく、ただ滔々と夜が染み出してくる。
「なるほど。やっぱりあの馬霊刀は、私にくれませんか」
卵男がぽつりと言った。
「なに言ってんだ中沢」
師匠が笑う。僕も笑う。そんなつるんとした顔で、急に変なことを言うから。
「私は中沢ではなく、角南ですよ」
ピィン――――。
瞬間、車内の光景が反転した。白いものは黒く、黒いものは白く。
「供物には、相応のものがいい。毒を飲むように、他者の人生を演じるように。美しいものはみな、己を破壊する。それらの朽ちた刀は、馬たちの魂を地獄に封じ続けることに抗い、自らを消し去ろうとするのですね」
どこにもいなかった。車には、僕と師匠しか乗っていなかった。いつの間にか、そいつは、あたかもずっと乗っていたかのように、僕らと会話を交わしていた。まったく、僕にも師匠にも、違和感はなかったのだ。記憶が改変されていたとでもいうように。
「おまえ」
師匠は、白黒が反転した世界で、金縛りに抵抗するように口を開く。僕は身じろぎもできない。
「そのなまえが、ほんとうのなまえか。わたしにきづかせも、しないなんて」
師匠の部屋の隣に住んでいた、奇妙な隣人は、滑稽で楽しい男だった。師匠も食べ物をたかりに来るその男を、時に部屋に上げ、僕らと一緒に語りあい、笑いあった。
僕らは、そんな日常の光景のなか、ずっと喉元に突きつけられていた刃物に、気づきもしなかったのか。
「おまえはなんだ」
師匠の声が、窓を開けた車内に反響する。まるで窓の外には、真っ黒な壁しかないかのように。
「私は、心臓ですよ」
バクン。
男が、一瞬膨張したように感じた。
バクン。……バクン。
大きな鼓動が聞こえる。
バクン。……バクン。……バクン。
その音に合わせて、男の胸が膨らみ、また収縮する。
「輝きを変える心臓です。あなたは気づきませんでしたね。私が、もっとも暗いときにしかお会いしなかったから」
バクン。……バクン。……バクン。……バクン。
男の胸が激しく脈打ちながら、キラキラとした光を放出しはじめている。
だめだ。死ぬ。2人とも。
師匠は、口を開くこともできなくなった。僕ももう、塑像のように白と黒の景色の一部になって、凍りついている。
冷たい時間が僕らの頭上に降ってくる。
死ぬ。
最後に、そう思った。
その瞬間だった。
窓の外を歩いてくる人影があった。
コツン、コツンという小さな足音が近づいてくる。
人影が大きくなる。レインコートを着ている。その左手は、こちらに突き出されている。半身になって、右手は大きく後ろへ引いている。
空気がどろどろとした粘性を持って、車内を押し包む。
その人影の思念が、空間を侵食していく。殺意が満ちていく。
見える。僕の目にも見える。開け放った窓の外に、引きぼった弓が。弓につがえられた矢が。その先端が。
「ようやく出てきたか。おまえを見つけるのは、難しかった」
レインコートのフードの奥から、静かな声が聞こえる。
卵男の胸が、鼓動を止めた。助手席の窓の外から狙いを定める矢の先端は、後部座席の卵男に向けられている。
「まいりましたね。先回りされていたとは。やはり、もっとも危険なのは、あなたでしたね」
卵男は、おどけたような軽い声を出した。
「ぐそうむどいと、ゆみつかい。2人に挟まれては分が悪いかも知れない」
ぐそうむどい。その言葉を聞いて、思い出した。去年の夏、今年と同じようにそうめんを食べた。僕と師匠と、隣人の卵男と3人で。そのとき、テレビを見ながら師匠が言ったのだ。沖縄の小さな島で、『ぐそうむどい』と呼ばれたことを。
意味はわからなかったが、その言葉は妙に心に残っていた。なにか不吉な響きがあったからだ。
視界の端に、光の粒子が見えた。はかなく舞う、輝きが。
「ではいまからあの……」
卵男が、なにか言おうとした瞬間、「死ね」という言葉とともに、収縮する弓が空気を振動させた。
放たれた矢は、空中で掻き消えていた。ただインイン……、という余韻だけが震える弦に残っている。
ザァァ……。
雨の音が耳に叩きつけられる。車内に冷たい飛沫が跳ねいってくる。
時間が動き出した。
車はいつの間にか停止している。いったいいつから?
ずっと降っていたはずの雨も、さっきまでの車内では存在が消されていた。
後部座席の卵男はいない。いなくなった。
急に現実感が戻ってくる。
「うわぁああ」
僕は腰を浮かせて喚いた。なにかに、ではない。なんだかわからないが、とにかく叫んだ。
「うるさい」
師匠に怒鳴られる。
「ここはどこだ」
そう言う師匠につられて、僕も周囲を見回す。小さな街灯に照らされて、体育館のようなものが目の前にあった。その駐車場に車は停まっているらしい。右手側の奥には、テニスコートのようなものも見える。ハッとした。地図で見た、あの場所だ。小安寺駅の西、柳ヶ瀬川の側にある武道館だ。師匠が推理して、地図に丸をつけた目的地。
到着していたのか。なのに、僕はずっと闇のなかを走り続ける車内にいたような幻覚に捕らわれていた。
幻覚?
窓の向こう。レインコートの人物が、雨のなかに立っている。これは、幻覚じゃない。
「斃したのか」
運転席から師匠が言葉を投げかける。
レインコートの人物は首を横に振る。
「逃げた。次は殺す」
「あれがなんなのか、知ってるのか」
「……」
師匠の問いかけに、無言で、レインコートのフードを取り払った。そして闇のなかに身構える。
いななきを、聞いた気がする。
息づかいと、体臭。蹄が地面を穿つ音。密集した気配が、窓の外を駆け抜けた。
馬だ。馬が走っていく。無数の影が。解き放たれたように。僕の目にも、その幻がはっきりと見える。
「なんだと」
師匠が運転席の横に寝かせていた金属バットを持って、車外に飛び出した。僕も驚いて、あとに続く。左手には黒いビニール袋で包まれた長いものを持っていた。さっき車のなかで、僕は自分が手に持っていたものを、見つけられないでいたのか。あらためて、さっきまで、思考がコントロールされていたような感覚に、吐き気を覚える。
降りしきる雨のなか、走る馬の群れの気配は、すぐに消えた。それでも力強い蹄の音が今も、頭のなかに残響している。
レインコートの人物は、構えを解いてこちらを見ている。いつか見た、あのときの顔だ。そして障害者手帳の写真のなかで、無表情にこちらを見ていた、あの顔。
短く切りそろえられた前髪が、22歳という年齢に相応しくない幼さを表しているようだった。けれど右目は無残な傷あとで覆われ、左目は、どこか焦点が定まらないでいる。それでいて、こちらのすべてを見透かしたような、そんな硬質な威圧感があった。
「山田あすみだな」
師匠が言った。
その女の手には、さっきまで握られていた弓はない。しかし、まっすぐ下げられた左手は、まるでなにを掴んでいるような指の形をしていた。
弓だ。弓を持っている。
そう思ったとき、僕の脳は握られた手のなかの弓の形を、勝手に想像している。それはすぐに色彩を持ち、重量感を持ち、実在の弓に変る。なんだこれは。
いつか見たテレビのショーで、催眠術にかけられたアシスタントが横たわり、まるで鉄の棒になったみたいに、頭と足の先だけで自分の全体重を支えているのを思い出した。
あれはきっと手品だ。思い込みの力が、人体の組成を変えるなんて、あるはずがない。だから、これも。この弓も、撃たれた人々の傷跡も、思い込みの力なんかではなく、手品であるに違いない。
ふいに、弓使いが視線をそらした。その向こうからは、冷たく湿った空気が漂ってきている。
川か。西の柳ヶ瀬川。東の国分川と、この街を挟むクニ境の川。
その方向は、馬たちの霊が駆けてきた場所だ。
師匠が雨のなかを走り出した。武道館の周囲は、畑ばかりだ。真夜中の道には僕らのほかにだれの姿もなかった。
すぐ先には堤防があった。そのそばに、車が一台停まっている。白いバンだ。人の乗っている気配はなかった。
僕は転びそうになりながら、堤防の下の河原に降りる。
いる。
白衣が、雨のなかにうっすらと浮かび上がっている。河原のなかにたたずんでいる。いや、しゃがんでいるのか。
影のようなものが見える。その周囲には得体の知れない、どろどろとした気配が揺れていた。目を凝らすと、それらは鎧を着た武者姿のように見える。カロカロと、甲冑が打ち付けあうような音が、いっせいに聞こえてくるような気がした。それはつまり、こちらを振り向いたということだった。
い?
来る。こっちに来る。揺れながら、その影たちは河原に降りた僕らのほうへやって来ようとしていた。怨念のかたまりが、顔に吹き付けてくるようだった。正視できないようなおぞましい恨みの感情が、こちらに向けられている。
彼らは、馬霊刀に軍馬の魂を地獄に落とさせようとした武士たちか。職業的な戦争屋として、命の奪い合いに明け暮れた彼らは、死してなお、戦いを望んでいる。そのための乗馬を求めて、さまよっている。発掘された馬霊刀に引き寄せられて、ここまでやってきたのだろう。
ザァァ……。
雨粒で僕らの身体はびしょ濡れだった。顔を手のひらで拭う。隣に立つ師匠は、金属バットを構えて大きな声を出した。
「先に来てたんだろう。あいつは、どうなってる。殺したのか」
弓使いに向けた言葉だ。振り向くと、堤防の上に、レインコートを着た女が屈み込んで、両頬を自分の手のひらで包んでいる。あいつ、とは白衣を着た男、埋蔵文化財センターの所長のことか。
「いや、見てただけだ。あの見えない悪意がやって来るのを、待ち構えていたから。……そいつは、刀を埋めていた」
女はそう言った。
埋めた? 馬塚から掘り出された刀をまた埋めた。
つまりそれは供物としてか。彼自身が言っていたように。
「うわっ」
武者姿の影たちが手を伸ばしてくるのを、師匠は避けた。僕の周りにも、そんなやつらが蠢いている。
彼らはあきらかに戸惑っていた。さっき走り去った馬たちに、逃げられたからだ。戸惑いながら、怨念を撒き散らしていた。
「くそっ」
師匠は金属バットを振り回しているが、影たちは反応しない。そんなバットなど存在しないかのようだ。
「やれ」
師匠が僕に命令した。僕は左手のなかのそれをぐっと握り締める。
「早く。おまえが使えるのは、知ってんだ」
ドキッとした。知っていたのか。
ビニール袋を外し、なかから一振りの刀剣を取り出す。
「あの脇差じゃないのか」
師匠が驚いて僕を見る。
僕の手のなかにあるのは、2尺4寸の居合い刀だった。『小』と呼ばれる脇差よりも長い、『大』。れっきとした刀だ。
家を出るとき、父親から押しつけられた刀だった。僕に古流の居合いを叩き込んだ、その父から。
僕は腰を落とし、左手で居合い刀の腹を握る。そして右手をじわりと柄の下に置く。
霊は、自らの記憶の残滓のなかで存在している。いつか、師匠のかつての相棒、黒谷夏雄がライブハウスに現われた霊を、壁ごと拳で殴りつけて消滅させたように。かつて知る暴力の記憶が、その存在を傷つけ、もう一度殺す。
刀や槍の切っ先の乱舞する世界で生きてきた彼らは、師匠の持つ金属バットは脅威として見えないのかも知れない。しかし、この居合い刀なら。
は、は。
全身に降りかかる雨音のなかで、自分の呼吸を感じる。
『この騒動では、有効かも知れない』と師匠が言っていたのは、このことか。
一閃。
子どものころから何度も繰り返し、身体に染み付いた動き。
狙いは首筋だった。武者姿の霊は、雨のなかに倒れる。ほかの霊たちも慄いて、後ずさった。
いける。
カロカロカロ、と甲冑の音が聞こえる。
次の瞬間、左前方にいた武者の右目に、矢が突き立った。
あっ、と思う間もなく、次々に矢が武者たちの甲冑のない場所に突き刺さっていく。
僕も、師匠も動けない。僕らの背後から、矢は飛んでくる。暗くて見えないはずなのに、その矢は見える。なぜか、見えるのだ。
武者の霊たちは、苦しみながら倒れていく。倒れながら、消滅していった。
僕が、なにをするのか見ていたのか。そして、もうわかった、とばかり、堰を切ったように弓矢を放ち始めた。
一方的な殺戮は続いた。矢が射掛けられていない霊たちも、怯えながら、どろどろと闇に溶けるように消えていこうとしていた。
やがて雨だけが残った。
渦巻いていた怨念はすべて消えた。安らぎなどではなく、暴力的な嵐のなかで。
師匠が走り出した。弓使いのほうを振り向きもせず、河原のなかほどに座り込む白衣に向かって。
「おい」
走り寄った師匠がその肩を揺さぶると、白衣の男はその場に崩れ落ちるように倒れた。
師匠はその胸に耳を当て、鼓動を確かめる。
「気絶している」
そう言った。生きているのか。
白衣の人物は、ニュースで見たあの日焼けした男だった。埋蔵文化財センター所長の三島だ。馬霊刀を供物だと言って、持ち去った男。
三島は、馬霊刀を持っていなかった。
師匠はその足元の砂利を手で掘り始めた。僕も駆け寄って手伝う。河原の砂利は、簡単に掘ることができた。
指先になにかが触れた。同時に触った師匠が、それを掴んで、引っ張りあげる。
マネキンの腕だ。それも、右の腕。
「刀はどうした」
師匠が叫んで、周囲の砂利を片っ端から掘り返していく。しかし、それ以上なにも出てこなかった。
降り止まない雨のなか、黒いマネキンの腕だけが残された。
師匠は無言でその腕を川に放りなげた。この雨で増水して、流れが速い。見ているあいだにも、水位が上がりつつあった。この河原もやがて水中に没するのかも知れない。
小さな水音を立てて、マネキンの腕は流れのなかに消えていった。
師匠と僕は2人で気絶した三島を抱えて、堤防を越えた。弓使いはレインコートのフードを深く被り直し、離れた場所で僕らをじっと観察している。視覚障害1級のはずの、その目で。
雨に濡れながら、武道館の駐車場に止めていた師匠の車の後部座席に、三島を押し込む。
ドアを閉じて、師匠は振り返った。
雨のなかに弓使いが立っている。左手にはなにも持っていない。右手には厚手の手袋をしている。
「緒方を襲ったのは、おまえだな」
師匠が鋭い口調で言った。
「去年の冬から、弓矢で通行人を襲っていたのも」
「通行人?」
弓使いは笑っているようだ。
「私は犬神人だ。この街を清浄に保つための。やつらはゴミだ。害悪を撒き散らす悪霊だった」
透明で、よどみのない声だった。自分の正義を、存在意義をまったく疑っていない。そんな声だ。
変質者に誘拐され、両目を抉られて、5年間にわたって監禁された。解放されたあとも、全盲の障害を負いながら両親から半ば見捨てられ、ヤクザの女になり、売春行為を強要されていた。
そんな過酷な生き方をしていた彼女に、どうしてそんな涼やかな声が出せるのだろう。
僕は彼女に、同情という共感を抱いていたが、こうして向いあってみて、なにか別の感情がわきあがってくるのを感じていた。
僕はその正体を知るのが怖かった。まるでそれは、師匠に初めて会った日から抱いているような……。
「自首しろ」師匠の声が、雨音を割って響いた。「お祖父さんも心配してるぞ」
くくく。
弓使いは、笑った。
「あのジジイは、わたしを抱いて、死んだババアの名前を呻いて果てるやつだぞ」
ぞわっとした。
全身が総毛だった。人間の、底の見えない業に。
師匠も絶句している。
「邪魔をするな。この街に潜んでいる、あの見えない悪意は、私以外の手には負えない」
弓使いはそう言い放った。
「てめぇ」
師匠が殺気を込めた低い声を出した。雨の降り続くなか、空気は凍りついている。向かい合い、お互いに隙を見せずに睨み合っている2人の頭上に、雷の光が走った。すぐに轟音が響く。近い。
その音にも微動だにしない彼女たちの顔が、白い残像を残して、また闇のなかに沈んでいく。
「協力できないか」
僕はとっさに叫んでいた。師匠が「おい」と怒鳴る。
「なにがなんだかわかんないよ! 魔方陣だとか、見えない悪意だとか、消えた大逆事件だとか! なにが起きてんだよいったい! 正直うんざりだよ。わけわかんなくて! でもなにかとんでもないことが起こってるっていうんなら、いがみ合ってる場合じゃないよ! 協力しろよ」
僕が喚き散らすのをじっと聞いていた弓使いは、
「おまえも、面白いな」
そう言って、フードの奥の、その見えない目を僕に向けた。
「やめろ」
師匠が鋭く言った。僕と弓使い、両方に向けた言葉のようだった。
弓使いは師匠に顔を向け、口を開いた。
「おまえたちは、このまちで……」
そう言いかけた瞬間、「ぐぐぐぅぅ」、という大きな音が鳴った。弓使いの腹から聞こえたのだ、ということに気づくのには少し時間がかかった。
「帰る」
弓使いは、くるりと背中を向けると、歩き始めた。
腹の虫か。僕は驚いてその背中を見送っていた。
「逃がさねぇよ」
師匠がそう言って、追いかけようとしたとき、弓使いの背中から、強烈な気配が沸きあがった。殺気だ。このあいだ、師匠が僕にやってみせたような、相手を害そうとする悪意。
それが、空間を捻じ曲げるような密度で、迫ってくるのを感じた。僕は思わず、師匠の腰にしがみついた。
「やめてください」
師匠は喉の奥から唸り声をあげて、それでも動きを止めた。
見まいとしても、見てしまう。弓使いの、なにも持っていない左手に、弓の形を想像してしまう。はるか昔から、この街で穢れ払いを行っていたという、油の弓、という名前の弓を。僕らはそれを、見たこともないはずなのに。
弓使いは、振り向きもせず、そのまま駐車場の隅に置いていた、スクーターにまたがった。エンジンがかかる音がする。
レインコートのフードを取り去り、ハンドルにかけていたヘルメットを構えて、弓使いは最後にこちらを見た。
薄暗い街灯の下で、にこり、と笑いかけているように見えた。動けない僕らの前で、弓使いはヘルメットを被り、スクーターを発進させた。そのまま、走り去っていく。
「離せ」
腰に抱きついていた腕を振り払われた。師匠は、濡れた髪をかき上げながら、深く息を吐いた。そして、手にした金属バットを構えて、その場でフルスイングした。
「うわっ」
風圧を感じて、僕は思わずのけぞった。跳ね飛ばした雨が、顔に当たった。
「なんだってんだよ」
師匠は雨の降り続く暗い空を見上げて、叫んだ。
◆
それから僕と師匠は、市内の救急病院へ三島所長を運んだ。後部座席で揺られていると、途中で気がついたようで、「いいいいいい」と怯えた声を出した。
三島は、これまでのことを覚えていた。傍観者のように。
『檻のなかにいた』
そう表現した。埋蔵文化財センターで部下の男と話しているときに、急に意識が朦朧として、まるで自分の手足や口が、自分のものではないように、勝手に動いていた、という。それを、檻のなかに押し込められた自分が、ぼうっと見ていたそうだ。
「あの刀は、河原に埋めたのか」と師匠が訊くと、「なぜかわからないが、埋めていた。埋めたら力が抜けて、檻が暗くなった」と言う。
「埋められた馬霊刀は、消えた。消えたから、馬の霊たちは解放された。だがなぜだ。どこへ消えた」
師匠はひとりごとのように呟いた。
「供物とはなんだ」
「わからない。なにもわからない」
三島はそう繰り返すだけだった。
「角南、という名前に聞き覚えは?」
師匠がそう訊ねると、意表をつかれたのか、妙な顔をして、「ああ」と言った。
「し、市の委託で、市営運動場の移転計画のための地質調査をしてたのが、角南技研だった。……その調査中に、馬塚が出たんだ」
「角南技研…… 角南建設の、関連会社か」
「こ、子会社だったと、思う」
三島はクシャミをした。夏とはいえ、ずっと雨のなかにいて、全身びしょ濡れだった。それだけではなく、センターに倒れていた職員のように、得体の知れない悪寒に苛まれて震え続けていた。
救急病院に着くと、三島を下ろした。あれこれ聞かれると面倒なので、付き添いもせずにそのまま立ち去ろうとした。
「ありがとう」
頭を下げられて、師匠は、「いまは名乗れないけど、ありがとうと思ってくれるんなら、そっちの名刺をくれないか」と言った。
三島は震えながら、ポケットを探り、濡れてクシャクシャになった名刺を1枚くれた。
「またなにか訊きにいくかも知れない。そのときはよろしく。あと、堤防のところにバンが停まってたの、あれ多分あんたが乗ってきたセンターのやつだろ。忘れないうちに取りに行っとけよ」
三島と別れて、僕らはまた2人になった。
あまりにも多くのことがあって、まだ頭は混乱したままだった。馬霊刀は消えた。弓使いは、恐ろしいやつだった。そして……。
師匠はボロ軽四を飛ばし、アパートに帰り着いた。僕らは車から降りても無言だった。確認すべきことがある。
心臓がドキドキと鳴っている。濡れた服も着替えないままで、師匠の部屋ではなく、その隣の部屋のドアノブを握った。
カチャリ。ドアが、少し手前に動いた。開いている。
まだ雨は降り続いている。
僕と師匠は薄暗闇のなか、ドアを挟んで見つめあい、頷いた。
師匠がドアを開け放つ。すぐに僕らは土足でなかに乗り込んだ。部屋は真っ暗だ。師匠の部屋と同じ間取りのはずだから、電灯の紐があるであろうあたりを、手探りする。すぐに紐は見つかり、引く。
パァッ、と部屋に明かりがつく。ずっと暗いなかにいた僕らの目には強すぎた。目を細めながら、部屋の真んなかに立っている僕と師匠に飛び込んできた光景は、信じ難いものだった。
なにもない。
部屋には、なにもなかった。家具も、人が住んでいた痕跡も。からっぽだった。いや、違う。ひとつだけあった。
それは、仮になにもなかったときよりも、奇怪で、薄気味の悪い光景だった。
部屋の隅に、百科事典の棚があった。去年のクリスマスに、僕が借りた百科事典だった。
『コロッケの何をお調べになったのです?』
その隣人の顔を思い出そうとする。百科事典はこうして、存在していた。そうだ。僕が借りたからだ。
「おまえ、こいつの部屋に入ったことあったんだろ」
師匠は押し殺した声で、そう訊いてきた。
そうだ。僕は隣人の部屋に入ったことがある。そのときに、百科事典があったのを覚えていたのだった。だが、それ以外が思い出せない。
自分の顔を手のひらで撫でる。まるで自分のものではないような気がした。なにも信じられない。
「埃が積もってる」
師匠は部屋の壁沿いを指でなぞった。畳の上には、たしかに埃が堆積していた。昨日今日、家具を持ち出したのではないのは、確かだった。
いったいいつから、この部屋はこんな状況だったのだろうか。
怖い。僕は恐怖に身体が縮こまりそうだった。
あの男の顔が、もう思い出せなくなっている。
卵のようにぺろりとした、特徴のない顔だった。その印象だけが、記号のように頭に残っている。
部屋の壁に、もう1つ、妙なものがあった。
白いパンティだ。1枚のパンティが、壁にピンで留められていた。
師匠がそれを毟り取り、「ふざけた野郎だ」と言った。
「師匠のですか」
「なくなってたやつだ。おまえが犯人かと思ってたけど」
「そんなことしませんよ!」
僕はさっきまでの寒気のする気分を引きずったまま弁明した。僕の部屋にあるのは、別の柄のやつだったはずだ。
「なんだ」
パンティの下から、小さな紙が落ちた。一緒にピンで留められていたのか。
師匠がそれを拾い上げる。メモ用紙のようだ。なにか書いてある。
「正応3年の客星について調べてみなさい」
師匠がその言葉を読み上げた。書いてあったのはそれだけだった。
「正応3年の客星?」
そう呟いて眉を寄せている。師匠にもなんのことがわからないようだ。
「角南って名乗りましたね」
僕は確認するようにそう口にした。ありもしないことを、僕の頭が勝手にそう記憶しているのでない限り。
小でもなく、中でもなく、大でもなく。
『あの見えない悪意は、私以外の手には負えない』
弓使いはそう言っていた。
地図上の、巨大な五芒星。マネキンの身体の各部。それと引き換えに消えた馬霊刀。供物?
いったいこの街で、なにが起こっているんだ。雨のなかの自分の叫びが脳裏に甦る。
僕の頭では、今日あったことの処理すらできない。混乱し、酷く疲れていた。ただ師匠は、真剣な表情で、じっと考えていた。たった1つ残された、百科事典の詰まった棚を見ながら。彼がたしかにいた、という痕跡はそれしかなかった。
そして静かに口を開いて、言った。
「あいつは、嫌いじゃなかった」
師匠のその言葉に、僕もそうだった気がして、頷いた。
(完)