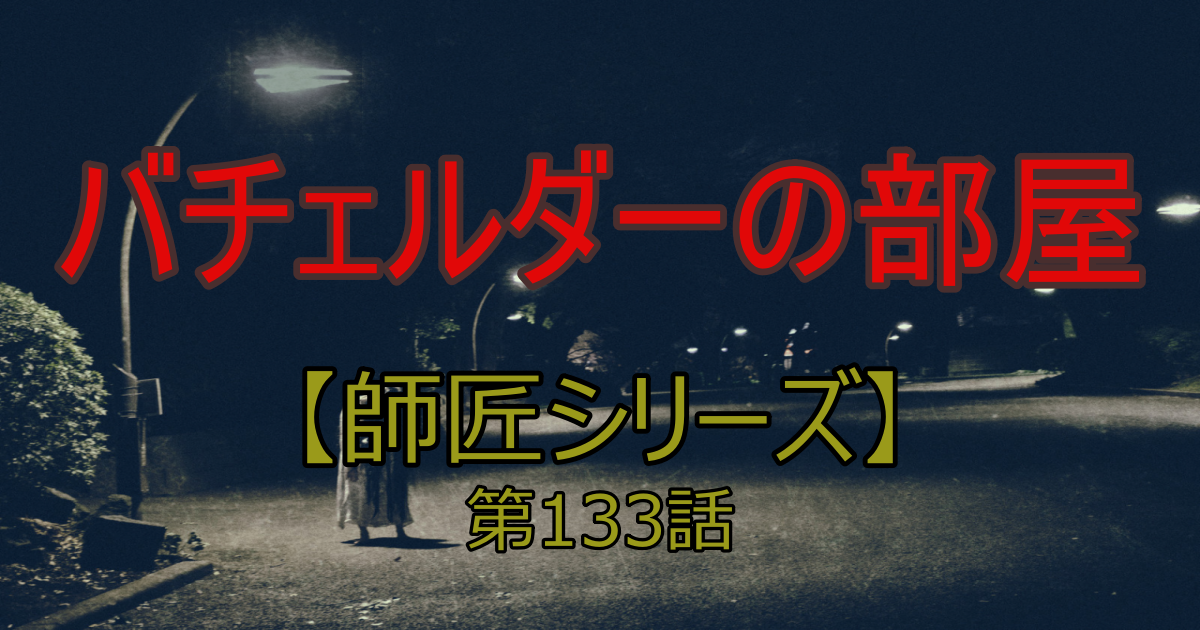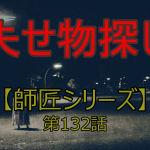『バチェルダーの部屋』
大学1回生の冬だった。
そのころ俺が出入りしていた地元のオカルトフォーラム『灰の夜明け』には、常連だけが参加している裏サイトがあった。
なにしろ一応黒魔術について語るというサイトの目的があったものの、もはやだれも守っておらず、オカルトよろずコミュニティーと化していたので、一時的に怖いものにハマッた高校生や大学生の一見さんがわんさか湧いては、すぐに消えてくという状況だったのだ。同じレベルで話ができる人だけが集う裏サイトができるのは、当然の流れだった。
俺は常連というには若輩だったが、オカルト道の師匠にあれこれ叩き込まれていたので、みんなから、ヘタレなりにかわいがってもらっていた。
その裏サイトに、常連の1人である伊丹さんが面白いことを書き込んだ。
『伊丹 : 俺の大学のツレで、《超能力研究会》っていうサークルの会長やってるやつがいるんだけど、最近困ってることがあるらしくて、相談に乗ってやってくれないかな』
超能力研究会?
PCの前で、俺は少しワクワクしてしまった。胡散臭いけど、ちょっと入りたいかも。
『みかっち : 超w能w力w』
『伊丹 : いや、ちゃんとした、つーと変だけど、まあ真面目にやってるとこだよ』
『みかっち : 超w能w力w藁藁』
『伊丹 : おまえちょっと黙れ』
『京介 : いいよ』
ツルの一声だ。京介さんが参加するなら、俺も参加する。あと絶対みかっちさんも。それからkokoさんも。
『koko :やめたほうがいい』
あれ? なんで。
kokoさんが反対した。ゾクッとする。なにか予知をしたのだろうか。
しかしそのあと、伊丹さんのお願い攻勢で、結局数人がその相談とやらに手を挙げた。
さて、超能力研究会の会長が、オカルトフォーラムの常連にいったいなんの相談をしたいのか。不安と楽しみが混ざりあって、その夜はなかなか寝付けなかった。
数日後の土曜日、4人で『永井』という表札のある家のチャイムを鳴らした。
昼の1時過ぎだ。閑静な住宅街にある、なかなか立派な洋風の家だった。
肝心の伊丹さんが来ていない。急用ができたと言っていたが、本当だろうか。逃げたのではないだろうか。やめたほうがいい、というkokoさんの言葉が脳裏をよぎった。
「こんにちは。はじめまして」
玄関から小柄な男性が顔を出した。
「商大で《超能力研究会》の会長をしている永井です。みなさんのことは伊丹君からよく聞かされています」
上品な口ぶり。そして切れ長の涼しげな目元に眼鏡をかけている。なかなかの好青年だ。
こちらを値踏みするでもなく、「どうぞ」と爽やかに家の中へ案内してくれた。
「今日は家のものはいませんので、くつろいでください」
長い廊下を抜けて、彼の部屋へ案内される。広々とした洋間だった。真ん中にあるテーブルに腰掛けると、永井はすぐに紅茶を持ってきてくれた。
自己紹介で、それぞれハンドルネームを名乗った。
「京介」
「みかっちでーす」
「ウニです」
「や、山下です。よろしく」
社会人の山下さんは眼鏡に右手をやりながら言った。今日もスーツにネクタイだ。午前中仕事をしていたらしい。
「超能力研究会って、どんなことをしてるんですか」
俺から、まずはそう訊いてみた。
「ええと、こういうのはご存知ですか」
永井は丸や四角、星型などの5種類のマークの描かれたカードをテーブルに並べた。テレビでよく見るやつだ。
「ゼナーカードって言って、ESPの実験で使うものです」
永井はカードを裏返し、左手で滑らかに混ぜながら、右手で手元の紙に『Zener cards』と書いた。器用なものだ。
そしてその裏返した5枚のカードを横一列に並べた。
「星型がどこにあるか当ててみて下さい」
透視能力の実験か。俺もじっと目を凝らしてみたが、灰一色の裏側からはなにも見えてこなかった。
俺は右端、そこから京介さん、みかっちさん、山下さんの順で指さして、左端の1枚だけが余った。
「さて、みなさんのESP能力はどうでしょう」
永井は右端の俺が選んだカードから順に開けていった。
波、丸、十字、四角。全員が外れた。ニコリと笑う永井に、ちょっと悔しい気持になった。
「外れてしまいましたね。でも仕方がありません。星は、彼が……」
永井はそう言いながら、最後の左端のカードをめくった。
「食べてしまったから」
あっ、と思った。
最後のカードは、さっき見た星ではなかった。ジョーカーだ。トランプのジョーカーが、星をスプーンで掬って食べている絵柄に変ってしまっていた。
「て、手品?」
山下さんが驚いている。いや、みんな驚いた。
「すごーい」とみかっちさんが興奮している。
「ははは、冗談です。いつもは真面目に研究していますよ」
永井はジョーカーのカードを左手で覆うようにテーブルに押し付け、右手をその下に滑り込ませると、なにかを摘んで引っ張り出した。
スプーンだ。スプーンが出てきた。ということは、カードの方は……。
案の定、手を広げて見せると、カードのジョーカーが持っていたスプーンが消えている。
永井はその本物のスプーンでコンコン、とテーブルを叩き、硬いことをアピールする。
「よく見ていてください」
左手でスプーンの柄を掴み、右手でなにかパワーを送るような仕草をする。だんだんとその動きに力が入ってきたところで、右手をスプーンの先にそっと添えると、スプーンはクニャリと背骨を折るように曲がってしまった。みんなが驚いた瞬間に、彼は両手でスプーンの両端を持ちながら柄の部分にフッと息を吹きかけた。
目の前で、見事にスプーンは元に戻ってしまった。
すごい。すごいけど、これって。
何度もテレビでマジシャンがやってみせた動きと同じに見えた。
「手品です」
永井は小悪魔的な笑顔を浮かべる。
「超能力研究会ってのは、マジックのサークルなのか」
京介さんが不機嫌そうに言う。俺も霊感商法的な胡散臭いのも困るが、こう割り切られるのも、それはそれでいい気分はしなかった。
「いいえ。手品は手段、目的はあくまで超能力現象の発現です」
これからが本題だ、とばかりに永井は姿勢を正した。
そのとき、みかっちさんが空気を読まずに口を開いた。
「あたしもできるぅ」
永井がゼナーカードの綴りを書いた紙の真ん中に折り目をつけ、テーブルの上に立てた。
「見てて」
そして右の手のひらで左の頬を2回叩き、すぐに右の頬を同じように2回叩いて、その右手を開いたまま指先を、手刀のように紙に近づけた。紙に変化はない。
「今度は右からね」
その言葉通り、さっきと同じ右手で右頬を2回叩き、ついで左頬を叩き、そのまま右の手刀を紙に近づける。
紙はふわりと揺れて、後ろ向きに倒れてしまった。
「右のほっぺから叩くと、念力がでるのよ」
そういうみかっちさんに、ちょっと感心してしまった。しかし永井は、ははは、と笑うと、「それはただの風ですね。最後が左頬だと、右手を伸ばすときに空気を払うから」
と言った。なるほど。そういう原理か。種明かしに、みかっちさんはむうっ、とむくれた。
「この手品のことを、僕らはアーティファクトと呼んでいます」
「アーティファクト? なにそれぇ」
「バチェルダー理論において、PK現象を誘発するもののことです」
永井はニコリとした。
「超心理学者、ケネス・バチェルダーが提唱した、超常現象を起しやすくするセッションがあります。暗くした部屋のなかで、超常現象を体験するために参加した人々が、リラックスして談笑します。そこでは、テーブルを動かす、手品で不思議な音を立てる、といった『仕込み』、すなわちアーティファクトが、暗黙の了解のもとに許されています。その場では、これからなにが起こっても不思議ではない、という期待感があり、常識的にそんな現象ありえない、という心理的抑制が働きにくくなります。人の心が生み出す力が、心に押さえつけられている、その鎖を巧妙に外した空間でこそ、本物のPK現象が生まれうるのです」
淡々と語りながら、永井はテーブルの上にスプーンを5本並べた。
「バチェルダーの部屋でこそ」
スプーンを見つめる永井の目が暗く輝いていた。
「PK……」
京介さんがぼそりと呟く。
じっと永井の顔を見ていた山下さんが口を開く。
「き、君さ。テレビに出てなかった? 子どものころ」
永井がハッとして顔を上げる。そうして取り繕うような笑顔を浮かべると、口を開いた。
「よく、覚えてらっしゃいますね」
「そ、そういう番組は、好きだったからね」
「なんのテレビです?」と俺が訊くと、山下さんは「スプーン曲げ少年だったんだよ」と永井を手で示した。
「夕方のローカル番組に何回か出ただけすよ」
永井はスプーンを右手で持ち、左手をかざした。グッと、なにか目に見えない力をこめるように、左手が震える。
みんな固唾を飲んで見守っていたが、スプーンは曲がらず、永井は深いため息をついた。
「小学生のころ、なぜか僕はスプーン曲げができたんです。最初は友だちに見せて驚かせていたんですが、大人たちが大騒ぎしはじめて。そんなテレビなんかにも出るようになって。……そうしたら、だんだん怖くなってきたんです。失敗することが」
永井は左手を握ったり開いたりを繰り返している。
「そんなとき、スーツ姿の大人たちが現われたんです」
「おー、メン・イン・ブラック!」
みかっちさんがはしゃぐ。
「ソニーの、ESP研究室をご存知ですか」と永井が言うと、山下さんが「ああ」と言った。
「そ、ソニーの創業者の1人、井深大(いぶか まさる)のき、肝いりで作られた、超能力研究機関だね」
山下さんが眼鏡をカチャカチャとずり上げながら答える。
「そうです。ソニーに限らず、いろんな大企業が超能力研究を真面目にやっていました。オウム事件が起きて、オカルトバッシングが強くなったのでバタバタと止めてしまったようですが。僕の前に現われたのも、そんな企業でした」
◆
少年がイスに座っている。白い部屋だった。
「君、そんなに緊張しなくていいよ。飴でもどうだい」
強張った顔でコロコロと飴を舐める少年。
「さあ、このスプーンを曲げてくれないか」
少年は手渡されたスプーンを右手で持ち、左手をかざす。
少年の頬に汗が流れている。スーツ姿の大人が腕時計を見る。
ギュッと目をつぶる少年。カラン、とテーブルの上にスプーンが落ちる。その首は90度背中側に折れている。
大人たちは小さな黒い箱のような機械をスプーンに近づける。そして首を振った。
「この子はだめだな」
ぐわーん、と世界がゆがむ。この子はだめだな。この子は。だめ。だめ。だめ。
◆
「メ、メタルベンディングがばれたのか」
山下さんが尋ねると、永井は頷いた。
「その日は調子が悪くて、どうしても曲がらなくて、ついやってしまったんです。そのころの僕は失敗できないストレスで、もうボロボロだった。うまくやれたつもりだったんですよ。いつもならバレやしない。でも彼らには見破られた」
永井は真っ直ぐなままのスプーンをテーブルのうえにカラン、と投げた。
「彼らは本物の超能力で曲げられたスプーンには、ある特徴があるというのです」
「特徴?」
「必ず着磁している、というのです。彼らが調べていたのは磁力でした」
「スプーンが磁力を帯びてるって?」
僕は少し驚いた。そんなこと、聞いたことがない。
「その日から、僕は一度もスプーンを曲げることができなくなりました。みんな手のひらを返して、嘘つき呼ばわりをし始めました。でも……」
永井は静かに机に鉄槌を落とす。
「いつか、もう一度あのころの力を取り戻したい。僕の力を」
搾り出すような声。爽やかな好青年だった彼が、暗い情念を覗かせていた。
「それで、サークルを作って、超能力セッションを繰り返してるってわけか」
京介さんが冷たく突き放すような声で言った。
「で、どうして私たちに相談をする必要があるんだ」
そうだ。その部分が見えてこない。
「……最近、バチェルダー理論のセッションで、おかしなことが起こり始めたんですよ」
「おかしなこと?」
京介さんが眉を寄せる。
「どうしてそんなことが起きるのか、まったく分からない。でも、みんな怯えてしまって、離れていってしまう。そんな状況です」
「なにが起こるんだ」
京介さんの言葉に永井は答えず、部屋の窓を閉め始めた。
「席についてください。みなさん初めてですから、まず、バチェルダー理論のセッションを体験してみましょう」
言われるままに、テーブルにつく。真ん中にはスプーンが並べられたままだ。
永井も席につき、「さて」と言った。
「最初に言ったように、バチェルダー理論では、本物のPK現象を誘発するために、リラックスした空間と、なにか不思議なことが起きても、だれかの仕業、イタズラかも知れない、という心理的安心感が重要です」
永井はリモコンのようなものを手に持った。
「テーブルが揺れるくらいの仕掛けはしてますので、その点は安心してください。では」
部屋の明かりが消えた。真っ暗だ。
「なにすればいいの」
と、みかっちさんの声がする。
「普通に楽しくおしゃべりしましょう」
永井がそう答えた瞬間だ。
始まったばかりだというのに、それは、現われた。まるで待ち構えていたかのように。
白い手が、みんなの頭上にあった。それは薄っすらと青白い光を纏っている。そして長い。関節がないかのようにくねくねと揺れながら、白い手が10本、15本、いやもっと。
「ひっ」
山下さんやみかっちさんの息を飲む声がする。俺もぐびぐびと喉のあたりに水分が逆流するような感じがあった。
どこからともなく伸びてくる白い手の群は、壁や天井、そしてテーブルを撫でていく。
「こ、これは、たしかに、ぼ、僕らの、領分だな」
山下さんが掠れた声をあげる。俺など、声も出ない。首を引っ込めて、身体を硬くしている。
触られたら、終わりだ。そんな強迫観念があった。
「これも手品じゃないの」
みかっちさんのそんな悲鳴が、よけいに現実感を煽る。トリックなんてもんじゃない。もっと恐ろしいものだ、これは。
「どうしてなんだ!」
永井の声だ。
「どうしていつも、こんなものが現われるんだよ!」
泣くように喚いている。
白い手はテーブルの上のスプーンを手に持った。玩具を見つけたように、弄り回していたかと思うと、それをグニャグニャと曲げはじめた。1つのスプーンに複数の白い手が群がる。寒気のするような青白い光が、闇のなかでうごめいている。
「きょ、京介さん」
俺は、こんなとき一番頼りになる人の名前を搾り出した。
そのとき、ポッ、とオレンジ色の暖かな光が闇のなかに灯った。京介さんのうしろ姿が浮かび上がる。俺は思わず椅子から立って、身を屈めながら手探りでそちらへ向かう。
京介さんが、目の前に迫ってくる白い手を、ライターの火で下からあぶっていた。
目を疑う光景だった。
「物体じゃないな」
ポツリとそう言ったかと思うと、「な、なにしてるんだ」という永井の声に、「ああ」と答えてから、振り向いた。
「こんなことしてたりして」
白い手にライターの火を近づけているところを、永井に見せた。その瞬間だ。
「うわああああああ」
と永井が叫び、同時に、白い手がうねうねと空中でのたうちはじめた。ライターで炙られている手だけではない。すべての手が。ぞっとする光景だった。
「電気つけろ」
京介さんが叫ぶ。山下さんが「あ、ああ」と言ってテーブルをベタベタと手探りする音がした。「リモコンあった」という声。そしてすぐに明かりがついた。
カランッ。カランッ。
テーブルにスプーンが落下した。
白い手はすべて忽然と消えていた。みんな息を飲んで周囲を見回している。
京介さんが身を乗り出して、テーブルの上のスプーンを覗き込む。胸元からアクセサリのチェーンがこぼれて、その先端の銀色の十字架が揺れている。
「なるほど。ぐにゃぐにゃだな」
京介さんの言うとおり、スプーンはすべてグチャグチャに曲げられていた。
「お前がやったんだな」
京介さんが鋭い目で永井を見つめる。永井は自分の肩を抱いてガタガタと震えていた。
「ち、違う」
「いや、お前だ。お前は右利きなのに」そう言いながら京介さんは右手で何かを書く真似をする。永井がゼナーカードの綴りを書いた時のことか。
「スプーンを曲げる力は、左手から出そうとしていた」
ぐにゃぐにゃになったスプーンの1つを手に持ち、左手をかざす。
「最初の手品のスプーン曲げは右手をかざしていたけど、次の失敗したときのは左手だった。おまえは、子どものころのスプーン曲げは、左手でしていたんだ。そうだろ」
永井は小さく首を左右に振っていた。否定しているというより、叱られた子どものような反応だった。
「そして、さっきの白い手は、全部『左手』だった」
えっ。みかっちさんも山下さんも、俺も、驚いた。あんな状況で、そんなことに気付いたのか、この人は。
「僕じゃない」
「ライターで炙ってみたけど、反応があったのは、お前がそれを見た瞬間だった。お前の手だったからだ」
永井の手? いや、それは比喩か。つまり。
「お前の力だよ。子どものころのトラウマかなにか知らないが、抑圧されてきたお前の力が、ああしてメチャクチャに出てきてるんだ」
山下さんもが、「僕らの領分」と言ったように、俺もさっきの手は心霊現象だと思った。なのに京介さんだけは、まったく違う見方をしていたのだ。
「昔、見たことがあってな。こういう力は」
京介さんがそう言うと、山下さんが「そ、そうか。あのときの現象か」と頷いた。
「違うんだ!」
永井が叫んだ。みかっちさんがビクッ、と小さく飛び上がった。
「僕は、超能力なんか使ってない。子どものときからずっと。最初から、手品だったんだよ! びっくりさせたくて、すごいって、言ってもらいたくて。それだけだったんだ! 超能力なんて、あるわけないだろ!」
永井はテーブルを叩く。
「なのに。あれは、なんなんだ」
怯えた顔を上げる永井の両目から、涙が流れていた。
「お前」
京介さんが、驚いた表情を浮かべる。
「帰ってくれ」
早く!
永井が強い口調でそう言い放った瞬間だった。
パチリ、という音がして明かりが消えた。
闇に浮かび上がる白い手が、部屋の隅の電気のスイッチを押していた。ギクリとして、そちらを見ると、その手はすぅっ、闇の中に消える。
僕は、ふたたび訪れた暗闇に、血の気の引くような恐怖を覚えた。
薄っすらと白いものが周囲を漂っている。僕らはそれに取り囲まれていた。
「やめろ、永井」
京介さんが押し殺した声で言う。
「もういやぁ!」
みかっちさんが半泣きで喚く。
「僕じゃない!」
バタン、と椅子が倒れる音がした。永井が床に倒れ込んだのだ。ばたばた、と床を這う音。
「つ、つけ、この」
リモコンを押しているのか、山下さんが焦った声を出している。
「あ」
急に明かりがついた。リモコンを持った山下さんが、口を半開きにして見上げている。
部屋の隅で、永井が口元を抑えてしゃがんでいた。そしていきなり立ち上がって、テーブルの端に避けていた紅茶を手に取ると、一気に飲み干した。ぶるぶると震えながら、口元を拭う。
俺は永井がいた場所に、紙袋が落ちていることに気がついた。そっと近づいて手に取ると、薬局で渡される薬の袋だった。
『内用薬』と印字されている、よく見る袋だ。様、とあるところには、名前は書かれていない。1日何回、という欄も空白だ。ただ、なになに錠、という薬の名前を書く欄にだけ、手書きの文字で『へゅエれを』と意味不明の文字があった。なぜかそれを見たとたん、ゾクリとした。
いきなり、その袋を奪われる。
永井が青白い顔で、僕を睨みつけていた。
「帰ってくれ」
俺たちは顔を見合わせる。
「か、帰ろ」
みかっちさんが半笑いで両手を擦り合わせている。
「本当に、最初から手品だったのか」
京介さんが訊いた。
なにも言わず、永井は頷いた。
見送りもなく俺たちは玄関を出た。4人で永井の大きな家を眺める。
京介さんは首につけたチェーンを握っている。俺の目線に気づいて、ボソリと言った。
「曲がったスプーンに吸いついたよ。カチンって」
本当に、そんな特徴があるのかな。
京介さんは銀色の十字架を見ながら、そうつぶやいた。