窮鳥懐に
1 窮鳥懐に
師匠から聞いた話だ。
大学2回生の秋だった。
去年にも増して、身の回りに様々な事件が起きた夏がようやく過ぎ去り、肌寒さを感じるようになったころ。キャンパスの妖精という変なあだ名で呼ばれていた師匠と出会ってから、これまでに体験してきた、おかしな出来事の数々を思い返すと、奇妙ではあったけれどそれらは個々の事象だった。だが、この春から夏にかけて発生した事件は、どこか繋がりを感じさせるものばかりだった。
保育園の事件で、園庭に埋まっていたマネキンの腕。戦前の心霊写真にまつわる騒動で知った、消えた大逆事件に関わる角南家。悪霊が群をなして川を渡ってきたあの夜。巨人感覚症候群の罹患者。国宝級の祟り神である面の呪いを、打ち破った存在。雲を抜けるような目に見えない巨人。悪霊を狩る犬神人。角南を名乗って消えた、かつての隣人。
なにかが起ころうとしている。それだけは感じている。それは師匠のちょっとした仕草にも、苛立ちのような形で現われる。そのどこか不穏な空気は、傍観者たる、いや、傍観者であると信じたい僕の日々にも、得体の知れない暗い影を落としていた。
ただ、そんな日々においても、喫緊の悩みは大学の単位だった。履修票を何度眺めても、留年はもはや待ったなしの形勢であった。僕の頭は悪くない、いや、むしろ同期の連中と比べてもずっと良いはずなのだが、いかんせん出席日数が足りていない。それというのも、師匠に連れまわされるオカルト道の日々に加え、小川調査事務所という零細興信所でのバイトが、有限である学生の時間を、ガリガリと削り節のように容赦なく削っているからなのだ。
その日も、教授から単位が欲しければこれだけは出せ、と命じられていたレポートを、部屋にこもって渋々ながら仕上げているところだった。
家賃3万円台の洋室8帖、1K、バストイレ付き。それが1回生のころから住んでいる僕の部屋だ。学生の多い学裏と呼ばれる地域に属し、夏は暑く、冬は寒い。ともあれ念願の1人暮らしを満喫する城であったのではあるが、師匠の部屋に転がり込んでいる時間が長すぎて、この部屋をあまり自分の部屋のように感じなかった。だから、レポートのために缶詰になっているあいだ、ずっと考えていたのは、はやくこの苦行を終わらせて、師匠のところに行きたい、という思いだった。
ダンダン。
エンピツを持つ手を止めて、僕は顔を上げた。もう一度、ドアを叩く音がした。
時計を見ると、夜の8時過ぎだった。
だれだろう。こんな時間に。
訪ねてくる人に心当たりのなかった僕は、なにかのセールスか勧誘だろうと思って、はあ、と大きく息をついてから立ち上がり、ドアに向かった。
「はい。なんですか」
たまにくる宗教の勧誘だったら、ソッコーで追い返してやろうと思いながらドアを開けると、そこにいたのは女性だった。それも、見覚えのある。
「今晩泊めてくれないか」
彼女はそう言った。疲れた顔だった。
「えっ」
僕は状況を理解できず、戸惑っていたが、気がつくと、「とりあえず生で」のイントネーションで、「とりあえずなかへ」と言っていた。
ホッとした表情を浮かべた彼女は、小さく頭を下げると僕のあとに続いて部屋に上がりこんだ。
「えーと」
座布団を用意する間もなく、壁際に座り込んだ彼女を前にして、僕は立ったまま自分の頭を抱えていた。
忘れるわけがない。この顔を。間違いなく彼女だ。だけど、なぜ彼女がここに。
混乱したままの僕に、彼女は言った。
「すまない」
「ああ、いや」
まだ僕はどう対応したらいいのか、頭のなかがぐるぐる回っている状態だった。
「すまないついでに、その。お願いがある」
「はあ」
「なにか食べるものを……」
「はい?」
「分けて欲しい」
僕は思い出した。あの夜の雨のなか、壮大に腹を鳴らして去っていった、この女性のことを。
弓使い。
県警が追っている連続通り魔事件の犯人。そして師匠が追っている、古来よりの退魔師の末裔、犬神人(イヌジニン)。
その怪物が、いま僕の前で膝を抱えて訴えている。空腹を。
冗談などではなく、本当に窮乏しているのは、たしかだった。疲労の色濃い顔に、頬はこけて見えた。
「とりあえず、パンなら」
部屋を見回して、あんパンを渡すと、すぐに袋を破って食べ始めた。
僕は冷蔵庫を開けて、なかを確認したが、ろくなものが入ってなかった。そういえば、最近自炊した記憶がない。作り置きの麦茶を出して、コップに注ぎ、持っていった。
「ありがとう」
もうパンを食べ終わっていた彼女は、コップを受け取ると、それもすぐに飲み干した。
「なにか食べるもの買ってきますよ」
「頼む」
彼女はうなずいた。
僕はあらためてその様子を見つめた。
今日は何度か出会ったときの、レインコート姿ではなかった。淡いグリーンのジャンパーに、紺色のソフトデニム。背中から下ろした小さなリュックサックを、そばに置いている。
ジャンパーやリュックサックには汚れが目立っている。顔も、疲労のほかに垢じみた汚れが浮いていた。それでも、彼女の顔には、どこかおかしがたい、気品のようなものがあった。みっともない姿をさらしながらもなお、失われない気高さが。
それを生み出しているのは、いったいなんなのか。
前髪は短く切りそろえられ、やや幼さを感じさせるような髪型だったが、その下にある左目はどこか焦点のあっていない視線を、僕に向けている。右目のあったはずの場所には、一面に引き攣り傷が広がっていて、彼女の体験した過酷な記憶をとどめている。
ありがとう。そう言ってコップを受け取った動き。スムーズで、けっして視力に重大な障害があるようには見えなかった。けれど僕は確認している。彼女は視力障害1級の身体障害者であり、誘拐犯に両目の眼球を刳り貫かれて以来、全盲なのだと。
『あの子は、自分の頭のなかで、周りの風景を想像している。それらが、ほとんど現実の世界と一致しているのだ』
彼女の祖父が言った言葉を思い出す。
そのありえない言葉も、こうして本人を目の前にしては、うなずかざるをえなかった。
22歳。僕よりも3つ年上。その半生は、数年間にわたる誘拐監禁生活と、そのあとに待っていた、親からも半ば捨てられた過酷な日々に覆いつくされている。ヤクザ者のところに転がりこみ、客を取らされていたとも聞いた。彼女の体験してきた過去を、僕は正しく想像ができないでいる。
「じゃあ、近くのコンビニに行ってきます」
とりあえず冷静になる時間が欲しくて、僕は外に出ようとした。ドアをくぐるその背中に、彼女は言った。
「あの女には、言わないでくれ」
ドキリとした。
心によぎった考えを、見透かされて。
ドアを閉め、外に出ると冷たい風が頬に当たった。もうすっかり秋の風だった。
師匠に言うべきだった。弓使い、山田あすみは殺人犯だ。警察にだって言うべきだ。けれど……。
『協力できないか』
あのとき自分の発した言葉に、僕は縛られていた。師匠が認めなかったその言葉に。
僕は思う。山田あすみの見ている世界では、殺人など起きていない。ただ街に潜む悪霊を射(い)殺しただけなのだ。祖先から受け継いだ、犬神人という呪いにも似た宿業を背負って。
僕は彼女の半生を知ったことで、感情移入をしすぎてしまっているのだろうか。どうしたらいいのか、師匠に判断を仰ぐべきなのだろうか。
コンビニまでの道すがら、考えていたが答えはでなかった。だが、確実に言えることは、師匠を伴って部屋に戻れば、山田あすみの姿は消えているだろう、ということだった。
彼女が寒気のするような悪意を撒き散らしながら、依頼人を追って小川調査事務所に接近してきたとき、師匠の存在に気づいてその場を去っている。そのあとに出会ったときも、すべてこちらが気づくよりも先に、僕らのことをとらえている。それは彼女の特殊な『目』のためなのか。はっきりとはわからないが、彼女は、この世界の理(ことわり)から逸脱した存在なのはたしかだった。
結局、選択肢はなかった。
僕はコンビニで弁当を買い込み、部屋に戻った。
ドアのノブに手をかけたとき、ふと彼女がまるで初めからいなかったかのように、消えていることを想像した。
「帰りましたよ」
ドアを開けると、彼女はいた。部屋の奥で、ベランダのカーテンの隙間から、外を覗いていた。
コンビニ袋を置いて、近づくと彼女は、「ありがとう」と言った。外を見たままで。
「なにかあるんですか」
並んで外を見ようとすると、「なにも」と言った。
そして続けて言うのだった。
「わたしの一番古い記憶は、鉄と油の匂いのする町工場の2階で、ひとり遊んでいるときのものなんだ。記憶には、父も母もいない。ただわたしは与えられた部屋で、ぬいぐるみたちと積み木をしながら、足元から断続的に響いてくる機械の音を聞いている。ぬいぐるみはクマと、耳が片方折れてしまったウサギだった。クマは言うんだ。
『三角の積み木がないよ』
ウサギが言う。
『三角のは、土台にならないから、いらないんだ』
わたしは言う。
『三角のは、お屋根になるのよ』
ガチャンガチャンという金属音が、夕日の差し込む部屋に響いて、わたしたちはやがて無口になる。
『夜に外をみてごらん。ひとつだけ黒い雲があるから』
クマがそう言って、四角い積み木を屋根のかわりに乗せる。
『うん』
わたしはそのとき、そんな雲を見たのかどうか、もう覚えていない。でもわたしは今でも窓の外を見上げて、空にひとつだけ黒い雲を探している」
カーテンを締めて、彼女は向き直り、かすかに笑った。
「そういうことなんだ」
僕と師匠は彼女の人生を追っていた。そのことを彼女は知っている。彼女は、僕の抱くであろう疑問のひとつに答えたのだ。そのことがわかった。ただ、僕にはどの疑問に対する答えなのか、わからなかった。そしてその答えの意味も。ただ、彼女なりの誠意、あるいは一宿一飯への謝意をこめていることだけはわかったのだった。
ふいに目頭が熱くなりかけて、僕は慌ててコンビニの袋をあけて弁当を取り出した。
「あ、どうぞ。冷めないうちに」
「ありがとう」
そう言って、座卓に置かれた弁当の前に座り、彼女は気まずそうにモジモジとした。
「あの、お金はいまないんだ」
「あ、はい。いいですよ、奢ります。これくらい」
僕のところに助けを求めてやってくる時点で、相当に貧しているのはわかっていた。
父親からの仕送りも、障害者年金も、母親に掠め取られ、家を飛び出したままの彼女が、どんな暮らしを送っているのか、想像するだけで辛くなってくる。
「すまん」
そう言って、弁当にがっつく彼女を見ながら、僕は苛立っていた。彼女の過酷な人生と、警察に追われながら、それでもこの街に災いをなす悪霊とたった一人で戦い続ける日々を思って。悪霊だのなんだのは、狂人のたわごとなんかじゃない。僕らは、僕らだけは、わかっているはずですよね。
僕は、心のなかで師匠に訴えていた。
弁当を食べ終わると彼女は、風呂を借りたいと言った。もちろんそうしてもらった。
風呂から出てきたあと、彼女は礼にと言って、裸で僕の前に立った。僕は腹が立って怒鳴りそうになった。彼女にではない。彼女の人生に。
僕が抱かないのを、汚れた女だからと誤解して理解した、彼女の人生にだ!
電気を消して、寝るときにも、もう一度彼女は「ありがとう」と言った。
僕は、押入れから出してきた毛布に包まり、部屋の隅でその言葉を聞いた。聞きながら、涙を流していた。
次の日の朝、毛布に包まったまま寝ぼけて目が覚め、ああレポートをやらなきゃ、と陰鬱な気持ちになったあとで、僕は飛び起きた。
山田あすみは?
部屋を見回すと、彼女は衣装ダンスについている鏡の前に立っていた。
まるで数年ぶりに鏡を見たとでもいうように、しげしげと見つめながら、その格好のままで、「おはよう」と言った。
やっぱり夢じゃなかった。
僕は安堵して、毛布を畳んだ。
「あの女は、美人だな」
「え?」
山田あすみがいう、あの女、とは師匠のことに違いなかった。
「わたしは、ブスだからな」
山田あすみは、鏡を見ながらそうつぶやいた。
僕から見えるその横顔は、傷がない半分のほうで、まるでアンティーク人形のように整っている。彼女が言っているのが、傷のあるもう半分のほうのことなのか、それとも、彼女が『想像して見ている世界の自分』のことなのか。きっと後者なのだろう。鏡を見ながら手で触っているのは、傷がないほうの頬だった。
僕は想像した。
傷のことで見栄えがどうだの、世間体がどうだのと言う母親。お前のツラで稼げるのは、こんなところだけだと罵るシャク屋――ポン引きの男。そしてそんな言葉を聞かされ続けた彼女の、『想像する自分』。
いま彼女が鏡のなかに見ているのは、そんな自分なのだ。
「ありがとう。もう行くよ」
山田あすみは僕のほうに向き直り、そう言った。
訊きたいことはたくさんあった。言いたいこともたくさんあった。
リュックサックを背負い、出て行こうとする彼女に、かける言葉がなにひとつ出てこなかった。
ドアをくぐり、靴のつま先でトントンと地面を叩いてから、彼女は振り返った。
「お前たちは、あいつに手を出すな。あいつは、私にしか殺せない」
そう告げたとき、もう彼女は懐に飛び込んできた窮鳥ではなかった。全身から炎のような殺気が溢れ出ていた。まるで空気を燃焼させるその音が、聞こえてくるみたいだった。
それでも僕は言うべきだった。歯を食いしばり。
「協力できないか」
彼女は炎のなかで表情を変えず、ただひとこと、「借りは返す」と言った。そして煙も残さずに去った。

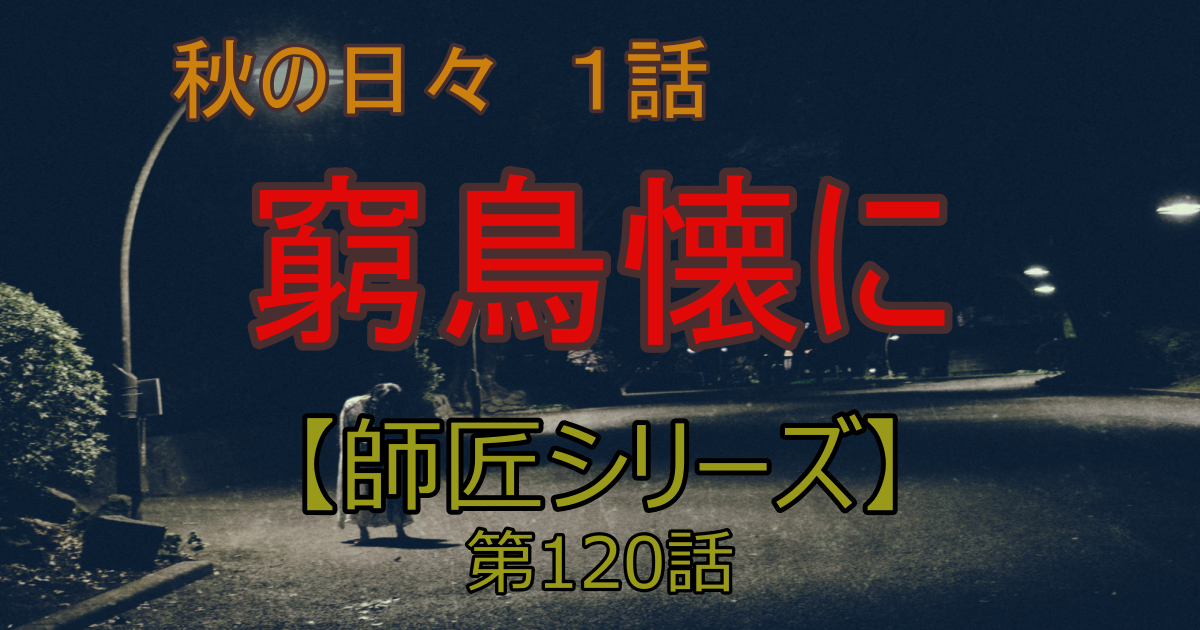

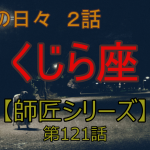

コメントを残す