大学6回生の夏だった。
そのころ俺は、卒業まであと数単位となっており、レポートさえ出しておけば単位はくれてやる、という教授のお言葉に甘え、ひたすら引きこもっていた。いまだにもらっている仕送りと、たまにやるパチスロで生計を立てており、バイトはやめてしまっていた。ネットゲームをしたり、2ちゃんねるにひた すらはりついたり、就職のしの字も頭には浮かばないまま、愉快な日々を送っていたのである。
「こうか! こうか!」
その日も、俺は大きなカエルのぬいぐるみと格闘していた。
アントニオ猪木がそのプロレスの技術を高く評価され、「モップと30分一本勝負ができる男」と呼ばれていたことに感銘を受け、我も、とばかりアパートの自室にてカエルと戦っていたのである。
そんなときに、音響から電話がかかってきた。俺をオカルト道の師匠と勝手に呼んで、つきまとってくる女だ。
「な、なんだ」
「ちょっと、出て来ないッスか。てか、なんか息が荒くないですか。昼間っから自涜っスか」
「じと……? 若い娘が、はあはあ。そんな古語を使うんじゃない。それに違うぞ。はあはあ。俺は、カエルのぬいぐるみと戦(や)ってたんだ」
「キモ」
そう言って電話は切られた。待ってもかかってこないので、こちらからかけ直した。
「なんだいったい」
「キモいからいいです」
こいつは!
俺は、自分が実はヒマでしょうがなく、だれかに構ってもらいたいのだ、という本心を、巧妙に隠しながら、音響と会う約束をとりつけた。
俺はついこの前までネットゲームにドン嵌りしていて、まともな生活が送れないところまできていたのであるが、最近はちょっとその熱が冷めていて、我に返っていたころだった。ネトゲ厨だったときは、ちょっかいをかけてくる音響をぞんざいにあつかっていたものだが、俺が真人間に戻ったとたんに相手をしてくれなくなったのだ。とかくこの世はままならないものである。
とまれ、外出先は、いや、デート先は久しぶりの学食だ。もし教授に見つかると気まずいが、近いし、メシが安いのでしかたがない。
音響は、白い半袖のブラウスに、細いブラックウォッチパンツという涼しげな格好で現れた。髪は、夏になってからは頬が隠れるくらいのショートボブだ。
「ヒマなんですか師匠」
「そうだ」
俺はいつものカレーLを注文したが、音響はサラダだけを食べている。最近は見るたびにこんな感じだ。あれだけいつもカレーをばくばく食っていた娘が、健康だか美容だか、スタイルだかを気にしているとは。時の経つのは早いものである。
「ロシアで、シュレディンガーの猫と同じ実験を、死刑囚を使ってやったんですってぇ。箱のなかのラジウムがアルファ崩壊するのをスイッチにして、青酸ガスが発生して猫が死ぬっていう、あれです。特定の時間内にアルファ崩壊する確率が50%だったら、外から観測している人間にとって、箱のなかの猫は、死んでいる状態と生きている状態が重なって存在している、ってのが量子力学の考え方なんですけどぉ。実際には生きてるか死んでるか、2つにひとつのはずなのに。そこでロシアの科学者が、人間の魂は21グラムだから、箱ごと体重計に乗せて、観察すれば、生きてるか死んでるか、蓋を開ける前に確定するんじゃないか、って試したんですって」
音響はこのところ、心なしか語尾が甘ったるくなった気がする。実に結構なことである。
「いろいろツッコミたいが、とりあえずどうなったんだ」
「10.5グラム減ったそうです」
相変わらず、音響はこういう都市伝説的な話が好きだ。俺はそれをいつものように話半分に聞きながら、昼飯を食い終わった。
「で、なにか用か」
「服部調査事務所で、面白そうな依頼が来たんスよ」
音響は興信所でバイトをしていた。それも、かつてのあの加奈子さんと同じ、『オバケ専門』の調査員のバイトだ。大学1回生の秋ごろから始めたので、2回生になった現在、まだ1年も経っていないが、だんだん依頼が増えてきたようだ。
かつて加奈子さんを気に入って、たくさんの依頼人を紹介してくれた、仁科さんというおばさんが、またあれこれ頑張っているらしい。所長である服部さんもそうだが、多くの人が、いまはもういない加奈子さんへの慕情を、この音響に投影しているのを感じる。期待されているのはいいことだと思うが、俺からしてみると、「こいつが~?」という感じだ。
「名木町(なきちょう)の町役場の職員からの依頼なんですよ。総務課の人なんですけどね、なんか防災無線から変な音が聞こえるって話で」
「そんなの、納品した業者の仕事だろ」
「それが、聞こえる人と聞こえない人がいるらしくて、地元の人が気味悪がってるらしいですぅ。おばけ無線なんて呼ばれはじめてるとか」
「ふうん。おばけねえ」
「仁科さんの遠縁の人らしいんです。それで紹介してもらったんですけどね。公務員とか、お堅い仕事の人って、経験上、こんなかわいい小娘が1人で来たら、うさんくさそうに見てくるんですよぅ」
「かわいいかどうかは知らんが、霊能者なんて触れ込みの人間は、みんなうさんくさいだろ」
「とにかく、師匠が一緒に来てくれたら、スムーズに進むんじゃないかなーって思ったんですぅ」
「なるほど」
俺は無精ひげを撫でた。そういえば何日剃ってないだろう。
「まあ、それはいいけど、俺は忙しいからなぁ」
パチンコの収支が書いてある手帳を開いて、そこに印刷されている、なんかよくわからん月ごとの格言っぽいものを目で追う。
「あ、じゃあいいですぅ」
「いや、待ってくれ。日によっては空いてるかも。日によっては。いつ行くの」
「明日です」
「明日? 急だなあ」
「あ、いいです。別に」
「待て、明日はたまたま暇なんだ。ちょうどその日だけ。よかったなぁ」
「あ、明後日でした。間違えましたぁ」
俺は、その2日後、音響と名木町に行くことになった。
JRに乗って西へ。ちょっとしたデート気分だ。
「それ、就活用のスーツですか」
「そう」
「一度も合戦で使われないまま家に伝わる、甲冑みたいなもんスね」
駆け出しの霊能者の心象を少しでも良くしてやろうと、付き添いの俺までスーツを着てきたのに、なんだこの言われようは。しかも本人は花柄のワンピースに、白くてツバの広い帽子など被ってきてやがる。デートかよ。
去年ゴスロリ姿で2位に終わった、ミスキャンパスコンテストで、今年は1位最有力候補だと情報筋から密かに伝え聞いている。そんな子とデートかっつうんだよ。
悪くない気分で電車に乗っていると、すぐに目的地に着いてしまった。
駅から出ると、のどかな田園地帯の風景が一面に広がっている。名木町は、駅の路線図でしか知らなかったが、こんなに田舎だったのか。
途中で鉄橋の上から見た川が、林の向こうに流れている。八代川(やしろがわ)だったか。そんなに山のなかでもないので、標高が高いわけではないが、明らかにO市よりも涼しい。風が爽やかだった。
時計を見ると、午後の5時だった。まだまだ空は明るい。八代川ぞいを町役場のほうへ上って行き、道の途中で見つけた喫茶店に入った。
地元の夫婦でやっている店のようだ。ほかに客はいなかった。2人ともコーヒーを注文する。亭主に、どこから来たのかと訊かれ、O市から、ちょっと友だちに会いに、と適当に返事をした。
「ここって、防災無線は聞こえますかぁ」
音響が訊ねると、人の良さそうな亭主が、「ああ、すぐそこの道の先にスピーカーがあるからね」と答えてくれた。
「なんか、その友だちが、最近防災無線から変な音が聞こえるっていう話を、してたんですけど」
「ああ。そんなこと言う人もいるみたいですねぇ。あたしらは聞こえたことないですけど」
亭主は店の壁にかかっている時計をちらりと見て、言った。
「毎日夕方の6時にね、防災無線から、『夕焼け小焼け』のチャイムが鳴るんですよ。夕焼け小焼けで日が暮れて~っていう、あれ。あれが鳴ったらね、あたしらは、ああ今日も一日が終わりだなぁ、って気持ちになるんですけどね。なんでも、そのあとで、妙な音がするっていうんです。近所の人でもいましてね、聞こえるって人が。それが薄気味悪い音らしいんですよ」
「町役場に苦情とかはなかったんでしょうかぁ」
「した人もいるみたいですけど、原因不明だとかで。まあ、そんなに気にすることないんじゃないですかね。夕焼け小焼けさえ鳴っていれば」
カウンターにいた亭主とその奥さんは、頷きあってあっけらかんとしている。
いま5時半か。俺たちはあと30分ここで粘ることにして、ホットサンドを追加で注文した。
音響と向かい合って、とりとめもない話をする。
「むかしタヒチの偉大な王様が神格化されてぇ、歩いた場所は、すべて大切な聖なる場所になったそうなんですぅ。そこは、ほかの人間が足を踏み入れてはいけない決まりになったとか。そんなことが続いていると、いったいどうなったと思いますか」
「そりゃあ、あれだろ。そこいらじゅう、聖なる場所だらけになって、みんな困ったっていうオチだろ」
「ちょっと違います。王様はみんなから『どこも出歩くな』って言われて、王宮でじっとしていたそうです」
そんな音響の得意の小話を聞きながら、時間をつぶしていると、ピンポンパンポンというスピーカーの音が外から聞こえてきた。
「これですね」
俺が訊くと、亭主が頷いた。
予鈴のあと、夕焼け小焼けのメロディが流れてきた。スピーカーが近くにあるだけあって、割れているところもなく、綺麗な音だった。
「特に変なところはないですね」
夕焼け小焼けが終わったあと、しばらくして音響がそう言った瞬間だった。外から、ボソボソという妙な音が聞こえてきたのだ。
「んん?」
耳を澄ましても、よく聞き取れない。
「なにか言っていますね」
音響のその言葉に、亭主が首をかしげる。
「さあ。なにも聞こえません」
奥さんも同じようだ。俺と音響は顔を見合わせて、食い逃げを疑われないよう、荷物を人質に置いたまま外へ飛び出した。
「あれがスピーカーだ」
道ぞいに、すぐにその柱は見つかった。田んぼに囲まれた見通しのいい道のなかに、ぽつんとある。
ボソボソ、ボソボソ。
あんなに綺麗に聞こえていたスピーカーから、だれかがつぶやいているような音が、かすかにしている。
ちょうど自転車に乗って通りかかった年配の女性に、「あれが聞こえますか」と訊ねると、「さあ」と首を振って去ってしまった。
スピーカーから聞こえていた音は、やがて途切れ途切れになり、最後に『プワンプワンプワン、プワーンプワーンプワーン、プワンプワンプワン』という、少し大きめのノイズのような音がしたかと思うと、ピタリと止んだ。
俺たちは顔を見合わせ、喫茶店に戻った。亭主に、最後のノイズのような音も聞こえなかったかと訊ねたが、やはり首を振るだけだった。
「なんなんだろうな」
「私は、人の声に聞こえました」
「俺もそんな気がするけど、なんて言ってるのかは、わからないな」
しかし、少ない情報を整理する限り、この音が聞こえるのは、霊感がある人間だけである可能性が高い。やはり、なにかの霊現象なのだろうか。
それから喫茶店を出て、町役場に向かった。まだ日は暮れていないが、6時を過ぎているので、業務時間外のはずだった。役場の庁舎は3階建てで、壁のところどころにツタが絡まり、年季の入った概観をしている。まだ正面玄関が空いていたので、そのまま入ってみると、1階フロアでは、まだ仕事をしている数人の職員の姿があった。
「末崎さんはいらっしゃいますか」
と訊いてみると、内線で呼ばれてすぐに当人が上の階から降りてきた。
こっち、こっち、と手招きされ、一緒に玄関から外へ出る。30歳くらいだろうか。依頼人はヒョロっとした痩せ気味の男性だった。
「すみません。まだ人がいるんで、夜まで時間をつぶしててもらえませんか。このすぐ裏に、うちの爺さんの家があるんですけど、いま入院してて、いないんで。そこでゆっくりしててください。あ、これ、カギです」
夜の11時に、玄関前で待ち合わせることになり、言われたとおり、俺たちは末崎氏のお爺さんの家に行った。
小ぢんまりとした家で、庭は雑草が生い茂り、荒れ放題になっている。
末崎氏がやったのか、部屋は掃除されていて綺麗だったが、壁のカレンダーが去年のままになっていて、主がいない家だということは感じた。
テレビを見ながら時間をつぶし、ちょうど11時に俺たちは役場に向かった。外は真っ暗だ。虫の鳴き声がやたら聞こえてくる。
正面玄関の前で末崎氏が待っていて、また、「こっち、こっち」と手招きする。庁舎の裏手に回ると外階段があり、そこから俺たちは3階のフロアに入った。
「すみませんね。いやあ、こういうことは、なかなか大っぴらにできないもんで。役場の予算も使えませんし。自腹なんですよ。実は。あ、依頼した末崎です」
「服部調査事務所の者です」
音響は名刺を差し出した。
「岡田蝶子さんですか。仁科の大伯母から、お噂を聞いておりました」
末崎氏はちらりと音響の格好を見る。観光に来たような涼しげな服装だったが、なに食わぬ顔でニッコリと会釈している。
「あ、私はちょっと名刺を切らしてまして。岡田の同僚の那須です」
「はあ、ナスさん」
俺はお辞儀だけして、ごまかした。
「ここが私のいる総務課です」
3階フロアはその総務課の上以外は、明かりが消えていて、薄暗かった。
「ほかの職員はみんな帰っています。今夜は日直が私なので、いまはこのなかに私たちだけです」
ガランとしたフロアを見渡す。大きな役場ではないので、デスクの数も少ない。見慣れたO市の役所に比べると、ずいぶんアットホームな感じだ。
「で、ご依頼の防災無線の件ですけどぉ。今日の夕方6時に私たちも聞きました。なにかボソボソと、だれかがしゃべっているようにも聞こえましたが、内容はわかりませんでした」
「聞こえましたか」
末崎氏は驚いたようだった。
「実は私はさっぱり聞こえないんですよ。だから、ほかの人が聞こえる聞こえるって、気持ち悪がってるのを見ても、首を捻るばかりで」
「無線機の業者には、相談したんですかぁ」
「しました。でも特に異常は無いようで。こちらに来てください」
末崎氏は、総務課の奥にある小さな部屋に、俺たちを案内した。そこには、広いテーブルの上に、大きな白い機械が置いてあった。壁際には、ヘルメットや防災服が並んでいる。
「ここで、防災無線用の録音をしたり、流すテープをセットしたりするんです。その端末がこれです。で、ですね、毎日午後6時に鳴らしている、夕焼け小焼けの録音がこれなんですけど」
末崎氏が機械を操作すると、すえつけの古いモニターの上部に、『夕焼け小焼け』の文字が表示される。ボタン式のスイッチを押すと、部屋の隅のスピーカーからその音楽が流れてきた。
「いまはこの部屋でしか流れない設定にしています。町じゅうに流したり、地区を選んで流したりもできます」
小さな部屋に、夕焼け小焼けの、どこか懐かしいメロディが流れる。心は夕暮れなのに、窓の外は真っ暗で、なんだか変な気分だ。
モニターに表示されていた残り時間が減っていき、メロディが終わった時点で残り3秒となっていた。そして0になったときに、「プツッ」という小さな音がして、完全に止まった。
「ね。これしか録音されてないんですよ。だから、夕焼け小焼けのあとに、なにか聞こえるなんてことは、ないはずなんです」
「続けて別の録音が流れる設定になってたりしませんか」
音響は天井を見ながら、部屋のなかをうろうろ歩いているので、俺が質問役になる。
「ないですねぇ。現在の設定もすべてこの端末で見られますから。この部屋でもそんな音は流れませんし、そもそも私や、ほとんどの人には聞こえないんですよ」
末崎氏はため息をついた。
「なのに、住民からは、『あれはなんて言ってるんだ』、『気味が悪いから流すな』なんて言われて。もうどうしたらいいか」
「職員でも聞こえる人はいるんですか」
「……います。町長なんかは聞こえないので、ほっとけほっとけ、なんて言ってますけど。職員でも何人かは聞こえるそうです」
「どんな音が聞こえるって言ってますか」
「やっぱりボソボソなにか聞こえるって。でもはっきり聞こえる人はいないみたいです」
「いつごろから聞こえてるんですか」
「はっきりとはわかりませんが、去年のいまごろではないでしょうか」
「結構長く続いてますね」
「ええ。だから困ってまして」
急に音響が顔を突き出してきた。
「聞こえる人は、幽霊見たりする人ですか」
はっきり訊ねられて、末崎氏は戸惑っているようだった。
「ま、まあ、いわゆる霊感ですか。それが強い人もいるようですね。聞こえる人のなかには。私など昔からまったくなくて、よくわかりません」
額に汗が浮かんでいる。それをハンカチで拭きながら、末崎氏は、ふう、と深く息を吐いた。
「消防署にもこういう機械があるんですか」
俺は念のために訊ねた。
「ええ。これは役場側の端末ですけど、消防署にも同じものがあります。でも6時のチャイムを鳴らす設定は、こっち側だけですし、夕焼け小焼けの録音もうちにしかありません。一応確認のために、その時間に消防で端末を見ていたことはあるんですが、作動はしていませんでした。でもそのときも、聞こえる人は聞こえたそうです。その妙な声が」
末崎氏は、声、と言い切ったあとで、ハッとした顔をして、右手で自分の顔をなでた。
俺は、その末崎氏の様子を見ながら、少し考えたあとで、口を開いた。
「ほかに、なにか異変は?」
その言葉を聞いて、末崎氏は、痩せ気味の顔を青白くして、生唾を飲んだ。
「実は……」
そう言ってから、しばらく迷っている様子だったが、自分の膝を揉むと、立ち上がった。
「こっちへ」
そうして、総務課のフロアへ戻った。窓際に、大きな古い棚があり、そこに書類のファイルなど、色々なものが詰め込まれている。末崎氏は、その棚の前でこちらを振り返った。
「これはですね。私の思いすごしだと思うんですが。ちょっと、その」
そう言いよどんだあとで、ふう、とまた、ため息をついた。
「私、消防防災の担当のほかに、建物の管理とかを行う、財産管理の担当も兼務していましてね。まあ、こんな田舎なんで、職員数も少ないから仕方ないんですが。その財産管理のほうでね、拾得物の仕事があるんです。庁舎内の忘れ物ですね。だいたい、ボールペンとか、ハンカチとかが多いです」
棚のガラス戸の向こうに、そういうものがたくさん置いてあるのが見えていた。
「財布とか、腕時計とか、印鑑とかの大事なものは1週間保管したあと、落とし主が現れなかったら、警察に届けます。そのほかのこまごましたものは、届けてもアレなので、ずっと置きっぱなしなんですよ」
「じゃあ、溜まっていく一方ですか」
「まあ、そうですね。担当が変わるタイミングで処分したりもしていたみたいですが、私が担当になったここ数年はしていませんね」
落し物には、それぞれ、拾われた日時と場所が書かれた付箋が貼られている。
「それで、思いすごしかも、というのは、なんですかぁ」
音響が棚のガラス戸に張り付いて、なかをキョロキョロ覗きながら言った。
「はあ、実は。……去年の秋ごろでしたか。こんなものが、落し物で上がったんですよ」
末崎氏は、棚のガラス戸ではなく、その下にしゃがみこみ、鍵のかかった戸を開けた。そこから、灰色の袋を取り出して、デスクの上に置いた。
「ええと、これだ」
袋から、靴下が出てきた。妙に黒ずんで汚れている。末崎氏は、気持ち悪そうにその端を持って、目の前にかざした。
『10月5日、1階ウォータークーラー横』
そんな付箋が貼ってあった。
「なんだか汚れてますから、落し物というより、捨ててたんじゃないかとも思いましたが、一応保管してたんです。それからなんですよ。こういうものが落し物で上がるようになりまして」
袋のなかから出てきたものが、デスクの上に並べられていく。
手袋の片方。帽子。キャラクターがプリントされた筆入れ。靴の片方。
どれも、小学1年生くらいの子どもの物のように見えた。
「男の子?」
俺は頭に浮かんだことを呟いていた。それを聞いて、末崎氏がビクリと肩を浮かせた。
「なにか、見えるんですか?」
怯えているようだ。
「いえ、男の子の持ち物のように見えたので。これが、どうしたんですか」
末崎氏はかすかに唇を震わせながら、やっと言葉を絞りだした。
「私、霊感はない性質(たち)なんですけど。こういうものが続くと、なんだか気味が悪くて。嫌な想像をしてしまうんですよ。この、男の子の落し物がだんだん増えてきて、全部そろったとき、なにかが起こるんじゃないかって。……先日、夜中にひとりで残業をしていたら、ふとこの棚のなかに、男の子が俯いて座りこんでいるのを見た気がして、ビックリしました。もちろん錯覚だったんですけど。怖くなってしまって。防災無線のこともあったし。嫌な想像ばかり浮かぶんです。落し物が全部そろったとき、スピーカーから、男の子の声が聞こえてくるんじゃないか、なんて」
はあ、と寒そうに息を吐いた。夜になって気温は下がっていたが、寒いほどではないはずだった。末崎氏はかなり精神的に参っているようだ。
俺は、並んだ落し物を眺めながら、なにか感じないか神経を研ぎ澄ませた。一瞬、ゾワッとなにか感じた気がしたが、それがなんなのか、はっきりしなかった。どうも師匠のようにはいかない。
音響のほうを横目で見る。落し物を見ていたかと思うと、フロアのなかをウロウロしはじめた。そして戻ってきて、落し物の小さな靴の片方を持って、廊下のほうへ向かった。
「これが、ここか。ふむふむ」
3階の階段のそばにあった給湯室の前に、靴を置く。
「で、筆入れが2階のトイレの前で、手袋が1階の給湯室の前。帽子が、靴下と同じ、1階ウォータークーラーの前、と」
どうやら、落し物に貼ってあった付箋の内容のことのようだ。ひとしきり、うんうん、と頷くと、くるりと振り向いて言った。
「どれも、床に落ちていて、しかも水の近くですね」
「はあ」
「この庁舎は、築何年くらいですかぁ」
「築年数ですか。たしか30年くらいかと」
「なるほど。古い建物。水のそば……」
音響はニコリとしたかと思うと、まったく別のことを口にした。
「防災無線ですけどぉ。サイレンも鳴りますよね。ウウゥ~ってやつ」
「え、はい」
「たとえば火事発生だと、どういう風に鳴るんですか」
「火事ですか。火災だと、消防団召集のサイレンですから、5秒を5回ですね。間に、3秒ずつあけます」
「ほかには、どんなときにサイレンを鳴らすんですかぁ」
「避難勧告とか、避難指示だと、たしか10秒を7回です。私になってからはないですけど。あと、ダムの放流でも鳴らしますね。10秒を2回です」
「ふむふむ。では、水難事故では」
「水難も消防団召集サイレンなので、火災と同じです」
「じゃあ、こういうのはありますか。プワンプワンプワン、プワーンプワーンプワーン、プワンプワンプワン。みたいな」
「さあ、それはうちではないと思います」
そう答えてから、末崎氏はハッと気づいたようだ。
「それは、防災無線から聞こえる例の音の、最後の部分のことですか。そういう風に聞こえるっていう話を、聞いたことがあります」
「私たちも今日、そう聞こえました。ですよね」
音響の言葉に、俺も頷いた。
「その防災無線ですけどぉ。緊急で鳴る場合で、一番多いのはなんですか」
「それは、やっぱり火災での消防団召集サイレンですよ。あと、水難ですね。川がありますから。夏の時期なんかはどうしても」
「じゃあ、住民にとっても、緊急で防災無線が鳴るときは、火災か水難、っていうイメージなんですね」
「まあそうですね」
「Ok. I almost got the answer」
音響は人差し指を立てながら、英語でそう言うと、ニコリと笑った。
「プワンプワンプワン、プワーンプワーンプワーン、プワンプワンプワンは、符合で表すなら、トントントン・ツーツーツー・トントントンですね。短点3回、長点3回、短点3回です。これがモールス信号だと、どういう意味になるか、ご存知ですか」
「どこかで聞き覚えのあるような」
そう言った末崎氏に、音響は頷いた。
「そうです。日本人に聞き覚えのあるモールス信号なんて、ひとつしかないですぅ。短点トントントンはS、長点ツーツーツーはOです。つまり、S・O・Sですね」
俺も、ハッとしてしまった。そうか。でもまだそれがどう繋がるのか、よくわからない。音響は、人差し指を立てたまま、ウロウロと歩く。
「防災無線を鳴らして、S・O・Sを伝える。この町で緊急で鳴らすときは、普通、火災か水難です。そして、S・O・Sはその危難がまだ続いていることを意味しています。去年から燃え続けているような火災はありえません。では?」
「水難、ですか?」
「去年の水難事故の記録はありますかぁ」
末崎氏は、自分のデスクからファイルを取り出してめくりはじめた。
「あった。去年の9月。八代川で、帰省中の海洋高校の男子生徒が溺れています。上流のほうで友だちと泳いでいて、行方がわからなくなりました。捜索しましたが、結局見つかっていません。去年の水難事故はほかにも2件ありますが、どちらも救助されて、命は助かっています」
「なるほどぉ。海洋高校の生徒ですか。それならS・O・Sの信号も知っているはずですね。そのまえに、なにかボソボソ聞こえて、はっきりしないのは、水のなかで発している声だからでしょうか」
ゾクリとした。溺れた男子生徒が、水の底でもがきながら助けを求めている姿を想像して。
「ちなみに、防災無線は設定したら、地区ごとに流せるって言ってましたよね。もしかして、この変な音が聞こえていたのって、川ぞいの地区だけじゃないですかぁ」
末崎氏は、思い当たったようで、「あ、は、はい。そう、かも知れません」と小刻みに頷いた。
「その子の声と、S・O・Sを、スピーカーが拾ってるのかも知れませんね。あと、その音がしているスピーカーの場所をよく調べたら、『現在の位置』がわかるかも知れません。事故があった上流って、もっと北のほうですよねぇ。それなのに、音が、役場の近くの下流付近まできていますから」
末崎氏は、目を見開いて、「はぁー」という感嘆のため息をついた。
「すごいですね。いや、驚きました。最初は、正直こんな……。あ、いや、すみません」
音響の見た目に関して、なにか余計なことを言おうとして、思いとどまったようだ。かわりに頭を下げて、感謝の意を表している。
俺も驚いていた。こいつは、かわいい顔をして、いつの間にこんな能力を身につけていたんだろう。俺のなかで、いつまでもゴスロリ姿の幼い印象のままだったのが、考えを改めなくてはならないようだ。なるほど、『オバケ専門』の調査員としての仕事は、けっして当時を知る人々の、自己満足のたまものばかりではないらしい。
「高校生でしたか。では、やっぱりこれは、私の思いすごしですね」
末崎氏はホッとしたように、デスクの上の落し物を見つめた。
どれも、高校生よりも、もっと幼い子のものばかりだった。しかし、音響は首を振った。
「古い建物で、水のそば……。もしかしてぇ、ネズミが出ませんか。この庁舎には」
「え、あ、はい。出ますね。たまに。太いのが。ネズミ捕りを仕掛けたこともありますけど、賢いのか、なかなか掛かりません」
「なるほど。では想像してみてください。夜中にネズミがおもちゃを咥えて、我が物顔で人のいない建物のなかを走り回っている。ふと、水の匂いに気がつき、おもちゃを捨てて、喉の渇きを潤そうとする。そんな場面を」
音響に言われ、俺と末崎氏は目を閉じて考えてみる。
「ネズミがどっかから拾ってきて、ポイしてるってのか」
「そうですねぇ。あ、末崎さん。この庁舎で、普段だれも近づかないような場所はないですか」
「近づかないような場所?」
末崎氏は考え込んでいたが、「うーん、旧ボイラー室とかですかね」と言った。
「いまからそこへ行けますか」
「行けますけど」
「じゃあ、案内してください」
音響は給湯室の前に置いていた小さな靴を拾い上げてから、末崎氏の背中を押してせかした。
「ほらほら」
「はあ」
俺たちは、明かりの消えて真っ暗な庁舎のなかを歩き、1階フロアまで下りた。末崎氏は、その奥へと俺たちを案内する。
「この先に、むかし使ってたボイラー室があるんですよ。廊下のこの辺から、荷物置き場になっちゃってて」
職場フロアを通り過ぎると、回りこんだところに、裏口らしきドアがあった。その横のほうに、真っ暗で狭い廊下が伸びていた。その床に、ところ狭しといろいろなものが置いてある。そのほとんどが大きなダンボール箱だった。
「どうしても捨てられない書類は、年々増えていく一方ですから。倉庫を増築しようにも、もう何年も前から、庁舎の建て直しの時期が近いからって、予算が下りないんですよ。その建て直しもいつになるのやらで。この一番奥が、むかしのボイラー室らしいですけど、私もほとんど入ったことはありません」
末崎氏は、廊下の電気のスイッチを押したが、反応しなかった。「あれ。ちょっと待ってください。懐中電灯取ってきます」
真っ暗なその廊下の奥へ、懐中電灯の明かりを頼りに進んでいく。奥まった場所に、ダンボールが山積みになっていて、行く手を阻んでいた。
「あーらら。どかしましょうか」
俺も協力して、なんとか人が通れるスペースを確保する。
「この先が旧ボイラー室ですね」
歪んでいて、開いたままのドアがあった。そのなかに入ると、むき出しのコンクリートの床が伸びている。どこかから水が漏れているのか、ところどころに水溜りができていた。ボイラーらしいさび付いた大きな機械の影が、懐中電灯の光に浮かび上がる。ボロボロのダンボール箱が、壁際にいくつか転がっていた。饐えた匂いが、鼻につく。
俺は顔をしかめながら、末崎氏に続いて歩いた。うしろを歩く音響も気分が悪そうだ。ワンピースがその部屋の汚らしいものに触れないように、自分の両肩を抱いてソロソロと歩いている。
「ありましたかぁー」
音響が、前に向かって小声でそう問いかける。
「なにがですか」
末崎氏が返答する。
「奥のほうにないですか」
「だから、なにがですか」
そう答えた末崎氏の足が、ピタリと止まる。俺は、つんのめって、その背中に鼻をぶつけてしまった。
「あったでしょう」
音響は嬉しそうにそう言った。俺は、背伸びをして、末崎氏の背中越しに前を見た。
懐中電灯に照らされた部屋の、一番奥に、小さな骨が転がっているのが見えた。
それから、ショック状態の末崎氏がやっと落ち着き、3階の総務課に戻った。
「発見するのは、明日にしてもらえますか。私たちも、面倒ごとに巻き込まれたくないし、あなたも部外者を夜中に入れていた説明をするのが、ややこしいでしょう」
俺がそう言うと、末崎氏は力なく頷いた。
「今夜は、あのお爺さんの部屋で泊まらせてもらっていいですか。朝イチのJRで帰りますから」
「わ、わかりました……」
末崎氏は、まだデスクに並んだままの落し物たちをチラリと見て、またぶるぶると震える。
「じゃあ、そういうことで」
そう言って、俺たちは名木町の庁舎をあとにした。
盛大に鳴いている虫の音を聞きながら夜道を歩き、末崎氏のお爺さんの家に上がりこむと、俺は両足を投げ出して、居間にひっくり返った。
「なんか疲れたなあ」
「そうスか」
音響は元気そうだ。
俺は時計を見た。始発までまだ3時間以上ある。
「おまえさあ」
俺は、座っている音響を見上げる。
「なんスか」
「いや、なんでもない」
おまえ、凄いな、と言おうとして、やめた。こいつと一緒にいて、俺が師匠と過ごした日々のことを思い出した、だなんて。なんだか、こっぱずかしくて。
「ねえ師匠」
「師匠って言うな」
最近は、もうめんどくさくて、そんなツッコミをしなかったが、今日はしたい気分だった。
「朝までヒマだし、またお話ししてくださいよ。オカルト道の話を」
「またかよ。もうほとんど話しただろ」
「いやいや、そう言いながら、出てくるんスから、まだまだ。さすがですぅ」
おだてられて、俺は少し気分がよくなった。単純なものだ。
「そうだな。どうするかな」
音響はきちんと座って、目を輝かせている。俺も起き上がり、頭をかきながら、向かい合った。
「……師匠から聞いた話だ」
そうして、また1つの物語が、未来に、繋がっていく。




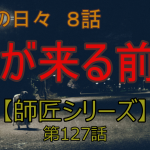
コメントを残す