狂心の渠
劇団くじら座の公演を見た2日後だった。
よく晴れた日で、見上げれば秋らしい高い空が広がっていた。僕は、久しぶりに洗濯をして干してくればよかったと思いながら、自転車をこいでいた。後輪の上には師匠が立ち乗りをしている。両手は僕の肩だ。
「えっ、行ったんですか」
昨日、劇団くじら座の座長に会うべく、師匠は稽古場に乗り込んだらしい。けれど、聞いていたとおり、座長は来ておらず、演出をつけている、副座長の吉崎という男に話を聞いたそうだ。
「なんか、キザな野郎でな。こんな、髪かきあげながらしゃべるんだぜ。気色悪い。結局、座長は今海外で、連絡取れないとよ」
「海外?」
「東南アジアかどこか。とにかく、たぶん海外だって言いやがる。本当に知らないんだろうな。金を出して、口を出さなきゃ、それで十分いい旦那さんだって思ってる」
「なにものなんでしょうね」
「さあな……。ただ、普段から仮面を被ってるんですかって訊いたら、『ああ、あの仮面。顔に火傷かなにかの痕があるから、って聞いたよ』ってさ。副座長も素顔を見たことがないんだよ。唖然としたね。顔も知らないやつに、劇団の運営を任されてるんだぜ」
「たしかに、おかしいですね」
奇妙な話だった。お金も絡む話なのに、そんなことでいいのだろうか。
「その仮面は、劇団で使ってる白い仮面とちょっと違ってて、ふちのところに、のたうつ蛇みたいな黒い模様が入ってるんだと。台湾で手に入れた、『偽悪者の仮面』という名前の仮面だそうだ」
「なんですかそれ。偽悪者の仮面?」
「悪趣味な名前だろ」
「善人が、わざと悪いことをしてるってことですか」
「いや、偽りの悪事を働く善人になれる仮面ってことだろ。だったら被る前は善人じゃないな」
「回りくどいですね。悪いことをするのに、偽悪者を装うんですか。わけがわからない。それで、どんな悪いことをするっていうんです」
「さあな」
師匠は黙った。僕は師匠が、その偽悪者の仮面の下の顔を、想像している、と思った。
それは僕の想像する、のっぺりした顔と同じなのかも知れなかった。
「見えてきたな」
向かう先に、こんもりと繁った林があった。市内で一番大きな神社、二条神社の敷地だ。
「いるかな」
駐輪場に自転車をとめて、僕らは境内を歩いた。大きな杉の木の群れが、晴れた空の光を遮って、敷地のなかはひっそりと落ち着いた雰囲気だった。
「あ、いた」
師匠が池の近くにいた老人を見つけた。
「東西(とうざい)せんせーい」
そう言って手を振りながら小走りに駆け出す。こちらに気がついた老人は、白いチューリップハットを取りながら、「おや、これはこれは」と頭を下げた。
「お久しぶりです。お元気でしたか。あ、これ弟子です」
僕はお辞儀をする。老人は僕にも丁寧に頭を下げた。
「東西です。どうぞよろしく」
やわらかい口調だった。目は細く、少し垂れていて、柔和な表情を浮かべている。そして、帽子を持っている手とは反対の手に、小ぶりな石が握られていた。
今日は、この老人を訪ねてきたのだ。
師匠が言うには、この変わった名前の老人は、知り合いのなかの変なおじさんシリーズの1人らしい。以前、気の力で雲を消す、雲消し名人のおじさんを紹介されたことがあった。同じような変な趣味趣向を持ったおじさんを、師匠は何人かキープしているらしかった。
雲消し名人のときには、紹介されたのみならず、「肋骨」という妙な名前をつけられて、強制的に弟子にされ、閉口したものだった。
あのときは、もう、見た目からして浮世を離れた仙人のような感じだったのだが、今回のおじさんは一見してまともそうに見えた。
「おうちに伺ったんですが、神社のほうに散歩に出てらっしゃると聞きまして」
「そうですか。それはわざわざすみません」
うーん、腰は低いし、いたって普通、いやむしろ良い人そうだ。
「この人はな、そのへんの石を見て、常人にはわからないことを読み取る人なんだ」
あ、ちょっと不穏な空気がしてきた。
「ちなみに、その石はどんなことを?」
東西先生は手のなかの石を見て、「いやあ」と首を振った。
「あまり良いことは、書いてなかったですな」
「書いてあるんですか? 石に」
僕が訊ねると、老人は頷いた。
「まあ、言葉のようなものではないので、私だけに通じる真理というか、道理というか。お恥ずかしいことです」
「えーと、それは石の種類とか材質でもって、いつごろ生まれた石だとか、どうやって生成されたものだとか、そういうあれですか」
違う違う、とばかりに師匠が苦笑しながら手を振っている。
「いいえ、私は鉱石などの専門家ではありません。ただの門外漢が趣味で遊んでいるだけです」
「はあ、そうですか」
これは、やっぱりあれな人だぞ。ごたぶんに漏れず。
僕はそう考えて、また弟子入りさせられたらたまらないと、身構えた。
「先生が読み取っているものは、不思議なんだよ。私も真似したけど無理だった」
「いえいえ、結局のところ、私にしか意味のないことですから」
謙遜した態度で首を振った。
師匠は、足元に落ちていた石を拾って、まじまじとそれを覗き込んだ。そして演技がかって言う。
「なるほど」
大きく頷いて、その石を戻し、また別の石を拾って、「なるほど」と繰り返した。
「すげえだろ。一日中、いや一年中、いやいや、一生ヒマが潰せるんだぞ、これで」
興奮してそう言った。本人を目の前にして、よくそんなことが言えるものだ。
「で、なんて書いてあったんですか」
師匠ははぐらかされたことをまた訊ねた。東西先生は困った顔をして、言った。
「身辺の整理をしておけと」
「えっ」
僕らは驚いて真顔になった。
「どういうことですか」
「いえ、冗談です」
師匠の問いかけに笑って答えた。だが、柔和な顔の奥に、心の底からは笑っていない、そんな空気が漂っていた。
「で、今日はなにか」
「あ、すみません。今日は先生の専門のことでお訊きしたくて、訪ねました」
「ほほう」
東西先生は石を地面にそっと置いて、後ろ手に組み、歩き出した。
「では、そこのベンチで」
僕らは池のほとりにあった木製のベンチに、並んで腰掛けた。
「この東西先生はな、星の専門家なんだよ」
「星って、あの空の星ですか。石の専門家じゃなく」
僕は驚いた。
「ああ、県内で、西のほうに、国立天文台があるの知ってるか。めっちゃでかい望遠鏡があんの。日本最大とかいう」
「いや、知らなかったです」
「東西先生は、その天文台のある天体物理観測所の元所長だったんだよ。もう引退して結構経つけど。偉い人なんだぜ」
それは凄い。知り合いの変なおじさんシリーズなんて言ってたのに。失礼だろ。言われるままに、なかばそういう目で見ていた僕もだが。
「いやいや、長年やってましたから、最後の最後に所長にしてもらっただけのことで。ご苦労賃のようなものですよ」
東西先生は謙遜して右手を振った。
「で、先生は古い天文史料とかにも詳しかったですよね」
「古いと言うと?」
「江戸時代、室町、鎌倉、あるいは、それ以前」
「ははあ」
師匠はメモを取り出した。パラパラとめくって、なにかを確認してから訊ねた。
「例えば、西暦の684年7月、日本書紀に『彗星(ははきぼし)、西北に出づ。長さ丈余』なんて記録があります。ハレー彗星ですね。こんな昔から、天文学についての記録が残っています。天武天皇の時代から、陰陽寮っていう、暦とか占い、天文に関する機関があって、こうした記録を残しています。彗星やら、日食、月食とかの星食に関する記録も多く残っています。これは、規則正しく運行する星の世界に、なにか異変が起こると、天変地異の前触れではないか、と畏れていたからですね。陰陽寮の博士たちが、その異変を飢饉や地震と関連付けて、なにごとか占ったわけです。で、天皇に奏上もうしあげるんですね。内容が不吉だとなれば、改元までしたりする。国家運営に関わる占いですから、おおっぴらにはしない。だからこれを天文密奏とも呼ぶとか」
「ええ、まあ、元になった唐の太史局(たいしきょく)、太卜署(たいぼくしょ)なんていう制度では、暦法が中心だったのですが、日本に入ってきた際には、占いが中心になったようですねぇ。もっとも、星食などは暦にも関わることですから、科学的な目的も多分にあったはずですが」
師匠はメモのページをめくる。
「とにかく、国家の一大事なわけですから、彗星やら隕石なんかの記録もしっかり残っているわけです。で、私、調べたんです。日本の天文史料に関する本を、図書館をまわって。土御門家の史料なんかも記録が残ってるんですね。ところが、どうも腑に落ちないことがあるんですよ」
「と言いますと?」
「正応3年、鎌倉幕府は9代執権、北条貞時の時代です。西暦で言うと、1290年。この年に、彗星や隕石などの記録は特にありません」
正応3年、という言葉がでてきて、僕はハッとした。それは、卵顔の隣人が部屋に残したメモにあった言葉だったからだ。
『正応3年の客星について調べてみなさい』
たしか、そう書いてあった。そういえば、師匠が調べてみる、と言っていたきり、どうだったか確認していなかった。ちゃんと調べていたんだ。
僕は師匠にまかせてすっかり忘れかけていたので、恥ずかしくなってしまった。
「そんなに毎年毎年、彗星や目立つ隕石が目撃されるわけじゃないですから、別段おかしいことじゃありません。地震の記録はほぼ毎年ありますけどね。ところが、です」
師匠はメモを閉じて言った。
「この年、うちの地方の古い地誌には、あるんですよ。天体現象の記録が。それはおおむねこうです。『客星見ゆ。光芒、天にあること十日』」
それを聞いて、東西先生は頷いた。知っているらしい。
「正応3年の客星ですね。あれは不思議なことです」
「あの、客星って、彗星とかとは違うんですか」
どうも言葉からイメージがわかなくて訊ねた僕に、師匠は言った。
「客星ってのは、天のなにもなかった場所に突然現れる、まろうどの星のことだ。一瞬で消える隕石、流星の類じゃない。一定期間見える彗星のことを指すこともあるし、あるいは短期間だけ激しく輝く、超新星爆発が正体のこともある」
「超新星爆発ですか」
「有名なのは、西暦1054年のかにパルサーだな。かに星雲の元になった超新星爆発で、世界中に記録が残っている。強烈な光で、2年間くらい見えていたらしい。日本でも藤原定家が記録を残している。ところがこのかにパルサー、ヨーロッパでは記録が残ってないんだな」
「え、なんでですか」
「キリスト教的宇宙観では、神のつくりたもうた天は永久不変なんだ。機械のように規則正しく運行されるべきもので、それにそわないもの、超新星爆発なんかは黙殺されたんだよ。天動説の時代には、地球を中心に規則正しく回っているはずの天体のうち、火星とか金星とかは、行ったり戻ったりして、不可解な動きをするから、惑う星、つまり惑星って呼ばれたりした。その説明をつけるために、天球の二層構造を提唱したり、無理やりなことをしてる。東洋では、天変占星術っていって、天の異変を占いに使うけど、西洋では宿命占星術が発展してる。天の星の規則性を使って、そこから人の運命を固定化させて占う発想だ。ここにも『天の不変』の意識が見られる」
「はあ、西洋的合理主義ってやつですか」
「とにかく、かにパルサーが世界中で目撃されたのに、ヨーロッパで記録が残っていないのはそういう理由があった。神への不敬だからだ。ところが、この正応3年の客星は、この地方にしか、記録が残っていない。世界にもないし、日本の中央、つまり京や鎌倉でも記録がない。これはおかしい。彗星でも超新星でも、一地方でしか見えないなんてことは、あるはずがないんだ。この現象の記録によると、夜間に星図のなかの特定の位置に見えたようだから、彗星じゃない。つまり超新星だ。ますます地理的な視差は関係ない」
師匠は両手を振って熱弁する。
「中央で記録がないのに、ここでは在郷の役人やら、神官なんかの記録にも残ってる」
「この二条神社の社伝にも伝わってますよ」
東西先生が補足した。
「ええ。それも資料にありました。これはいったい、どういうことなんですか」
ぐいぐいと胸を押し付けるように迫る師匠に、東西先生は慌ててのけぞる。
「いやー、それは研究者のあいだでも謎でして。まあ、中央で記録が残ってないのは、たまたまじゃないかってことで落ちついてます」
「たまたまなわけないでしょ。十日も見えてたんですよ。そんな天体現象、日本中で無視するわけないじゃないですか。イッコも残ってないって、そんなバカな」
「私に言われても。記録が散逸することは、ままあることですし」
東西先生は困って立ち上がり、あとずさった。
「あるいは、今のくじら座のあたりに見えていたその客星は、本当に超新星爆発だったんでしょうか」
師匠が、僕のほうをちらりと見ながら、あざけるような口調でそう言った。
くじら座。
僕は驚いた。くじら座。またくじら座だ。
『輝きを変える心臓です』
抑揚のない声が脳内にリフレインされる。もうその声色も記憶から失われつつあった。その持つ意味だけが、暗く輝きながら、からだのなかに浸透していく。
「ま、星の世界では不思議なことが起こりますよ。私もUFOを見たことがありますし」
「科学者がそんなもの見て、いいんですか」
「見ちゃったんだから、しようがないでしょう」
東西先生はあっけらかんとして言った。
「しょうがないですか」
話題がそれたところで、先生は空を見上げた。
「さて、そろそろ参拝して帰りますかな」
つられて僕も空を見たが、日はだいぶ傾いていた。
僕らは一緒に参拝しようと、社殿のほうへ歩いていった。「先生って、二条神社の氏子なんですよね」
「ええ、先祖代々、この地元に住んでますからね」
「二条神社で昔、大祭があったときに、当代の犬神人(いぬじにん)が弓で神事を行ったのをご存知ですか」
「懐かしいですねぇ。覚えてますよ。すぐ前で見ました。あっちの、今は駐車場になってますが、あのあたりでやってましたね。何十年ぶりかの大祭だというので、たくさん人が来て、賑やかでした」
僕はその会話のなかに犬神人が出てきて、緊張した。まさにその犬神人の系譜を継ぐ、弓使いとの関わりを、師匠に気取られているのではないないか、と。
「あっ」
話に気をとられていて、僕はなにかにつまずいた。転げそうになって、思わず地面に手をついてしまった。見ると、砂利道に石の土台のようなものが少し顔を出していた。たいした段差ではなかったが、靴のあたりどころが悪かったらしい。
「大丈夫ですか。すみませんねえ」
先生は我がことのように恐縮している。そして、立ち上がった僕に、こう語りかけた。
「いやあ、これは狂心の渠(たぶれごころのみぞ)の跡なんです」
「なんですか、たぶれごころのみぞって」
師匠が訊ねた。
「飛鳥時代に斉明天皇が、山から山へと人工的な運河を作らせたんですよ。有名な奈良県明日香村にある酒船石遺跡も、そうした人工的な水路で水を引いていたとか。この酔狂な大工事をあざけって人々が、酔狂な心、たぶれごころのみぞだと呼んだんですよ。この二条神社でも、大昔に、規模は小さいですが、同じように近くの柳ヶ瀬川から水路を引いていました」
東西先生は屈みこんで砂利を払い、石の土台をなでた。
「神事に使う水などを、わざわざ川から引き込んでいたんですよ」
「近くって、かなり離れてますよ」
師匠が川のあるほうを指さして言う。
「ええ、ですから、飛鳥の都になぞらえて、たぶれごころのみぞと呼ばれていたんですよ。この神社の敷地のなかに、かつては漏剋(ろうこく)の遺構もあったそうです」
「ろうこくってなんでしたっけ」
僕が訊ねると、師匠が答えた。
「水時計だ。日時計は、昼と夜、それから季節によって時間の長さが違う、不定時法を司っているんだけど、水時計のほうは正確な時間を計ることができたんだ。定時法の元だな」
「川から水を引くほどの水量が、必要だったんですかね」
「知らん」
「そう言えば、さっきおっしゃってた、犬神人も、狂心の渠に関わりが深いんですよ」
東西先生の言葉に、僕と師匠は「えっ」と驚いた。
「川というのは、昔の国境です。そこから水路を神社のなかにまで引き込む、というのは、本来あまりよろしくないことです。外の世界の災いも招くわけですから。そうした習俗的な理由だけではなく、当時の水路というのは死体や汚物が捨てられるものですから。衛生面からも忌避されるわけです。そこで、やってくる穢れや災いを祓うのが、犬神人の仕事なんです。ま、いわゆる神人(じにん)ですから、穢れ祓いの神事を行うだけでなく、実際に死体や汚物の処理もしていたはずです」
「川からやってくる穢れ……」
師匠はそうつぶやいて、目を泳がせた。僕の脳裏をよぎった、魚の死滅回遊のようにやってくる悪霊が川を渡ってくるさまを思い出しているのに違いない。
「なぜそこまでして、水を引いたんだ」
そうつぶやいて、師匠は考え込んだ。
「おっと、もうこんな時間だ。さあ行きましょう」
歩き出した東西先生に、師匠はついていかなかった。かつての水路の痕跡を見つめて、目を見開いている。
「どうしたんですか」
僕が訊ねると、師匠は俯いたまま、ひとりごとのように言った。
「日時計ではだめだった。水時計で、正確な時間を計る必要があった……。それは時間が……」
最後は、よく聞き取れなかった。その背中に、夕暮れが迫りつつあった。




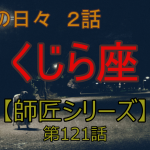
コメントを残す