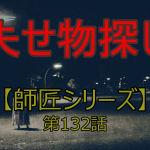注意!この作品はまだ未完です。(2022年6月現在)
『毒』 前編
師匠から聞いた話だ。
1 アンタッチャブルってことですか
大学2回生の冬のはじめだった。
僕は師匠に連れられて、タカヤ総合リサーチにやってきた。何度も来ているので、いまさら驚くこともないが、これが自社ビルだという。
「どうした。いくぞ」
見上げていると、ためいきが出そうになる。同じ興信所なのに、我らが小川調査事務所との格差を思い知らされるのだ。
なかに入ると、もう暖房が入っているらしい。ふわりとした空気の膜を感じた。まだ冬もはじまったばかりで、それほど寒くないというのに。僕は、小川調査事務所に暖房が入ったのは、去年のいつごろだっただろうか、と考える。
あいかわらず整然と並んでいるデスクと、忙しそうに書類を作っている数人の調査員の姿がある。見知った顔ばかりなので、僕らを見ても一瞬視線を向けただけで、そのまま仕事を続けている。
受付の奥にいる事務員の市川さんのところへ行こうとすると、向こうから大きな声が出迎えてくれた。
「あらぁ、加奈子ちゃんじゃない」
「いらっしゃい」
あとのほうがベテラン事務員の市川さんだ。先に声をかけてきたのは、大きく盛った紫の髪の毛に、大きな黄色い縁取りのサングラスがど派手な、おばさんだった。
「仁科さん、なにしてるんですか」
「なにって、市(い)っちゃんと、ちかごろの景気についてお話していたところよ」
仁科さんとは、いつも師匠に『オバケ』案件を紹介してくる女性だ。O市の中心街で代々手広く商店を経営している家に生まれ、婿養子をとってからその旦那に商売をまかせて、自分は婦人会をはじめ、商工会やらコミュニティ活動やらと様々な会合の役員をしている。世話好きで、噂好き。毎日たくさんの情報が仁科さんのもとに集まり、そのなかから、困りごとをよりすぐって、タカヤ総合リサーチや小川調査事務所に紹介しているらしい。もちろん、小川調査事務所に回ってくるのは、普通の興信所では扱えない、不可解な事案ばかりだ。
「加奈子ちゃん。あら、助手の坂本くんも。どうしたの2人して。あー、とうとう高谷所長のところに転職する気になったのね。そうでしょう、そうでしょう。あんなところにいたんじゃね。宝の持ち腐れだわ。小川クンにはかわいそうだけどね。なにしろ稼ぎ頭が引き抜かれたんじゃ、やってらんないもの。そうだわ、いっそ小川クンも戻ってくればいいのに。これだけ机あるんだから、どっかあいてるでショ。そうしなさいよ。ねぇ市っちゃん」
「そうねえ。所長もまんざらじゃないみたいだけど」
「ちょっと、なに2人で勝手なこと言ってるんですか。所長に会いに来ただけですよ。電話しておいたでしょう」
「あら、そうだったわ。パチンコでも打ちに行ってなかったら、いると思うけど」
市川さんはチラリとフロアの奥のほうを見る。
「なに言ってるんですか。奥の所長室から外に出ようとしたら、ここ通るでしょ」
たしかに、1階の事務室は見通しのいい吹き抜けのフロアになっている。
師匠のつっこみに、市川さんは怪談話でもするように身を乗り出し、声をひそめて言う。
「それが、ときどき、いつのまにかいなくなってるのよ。あれはきっとニンジャの血でも引いてるのね」
「なんスかそれ」
師匠はあきれている。
「ニンジャといえば、市っちゃん、あたしこないだ伊賀の忍者の里に行ってきたのよ」
「あら、お土産もらってないわよ私」
そんなかしましい2人の前を通り過ぎて、僕らはフロアの奥に向かった。
「あ、そういえば加奈子ちゃん」
まだ仁科さんがなにか言っている。
「なんですか、もう」
「よいしょっと」
仁科さんは、陣取っていた受付の横の椅子から重い腰を引っこ抜くようにして、立ち上がった。じゃらん、じゃらんと近寄ってくる。服装やアクセサリーの類もゴテゴテしていて、いったいどれがそんな音をたてているのか、判然としない。
「あなた最近疲れてるんじゃない?」
「はあ? なんでですか」
「あたし、人を見る目はたしかなのよ。なんというか、こう、生気がなくなってきてる感じ」
僕は一瞬、ドキリとする。脳裏に、主治医の鹿田教授の検査を受けにいく師匠の姿が浮かんだ。
「こんな若い子のお相手してるからじゃない? ほどほどにしなさいよ」
急に下品な声で笑いはじめる。
「僕はそんなんじゃないですよ」
思わず抗議する。
「そう。むしろそんななら、生気を吸収してるんじゃないの」
師匠は、アホくさ、と言って去ろうとする。そこに、仁科さんが笑いを引っ込めたかと思うと、肩に手をやって止めた。
「あたし、最近、この街がおかしいこと、気づいてるのよ。急にオバケの相談増えたじゃない? まわりにも、変なもの見たり、聞いたりした人いっぱいいるのよ。こないだの、空から聞こえたギィギィうるさい音もそう。あたしちょっと、反省してるのよ。そんなときにさ。あなたにいろいろ押し付け過ぎたんじゃないかって」
「いやいや、ありがたいことですよ。仁科さんからの紹介案件は、小川調査事務所の貴重な収入源ですからね」
師匠はやんわりとその手をどかした。
「なにか困ったことがあったら、相談してね。あたし、これでも顔が広いんだから」
「重々承知していますよ」
師匠は苦笑して、頷いた。
そうして、ようやく僕らは所長室に向かった。
重そうな扉をノックすると、なかから返事がきこえた。
「お邪魔します」
「やあ、儲かってるか、きみたち」
重低音の声が、僕らを迎えた。タカヤ総合リサーチのオーナー兼所長、高谷英明氏だ。もと県警本部の捜査第一課長で、途中退職してからこの興信所稼業に身を乗り出し、大成功をしてあっという間に自社ビルを持つまでに至った、立志伝中の人物である。
海外にもよくコースを回りに行くというゴルフ焼けで、もう冬だというのに、肌がテカテカと黒光りしている。
僕は、以前に師匠から、「ああいう色のゴキブリいるよな」と言われて以来、会うたびにそのシルエットが重なって見えてしまうようになっていた。
「まあかけたまえ。マカダミアナッツ食べるかい?」
60歳を越えているはずだが、年齢を感じさせない、精力的な印象を相手に与える人だった。その高谷所長が、マカダミアナッツの大きな箱を棚から持ってきながら、「お?」と言ったかと思うと、額から触覚を抜いた。僕は驚いてしまった。
僕には、Gの姿と重なってそう見えたのだが、実際のところは、オールバックの髪からツン、と前に1本飛び出ていた白髪が気になって抜いたようだ。
僕らは所長室のソファで、しばらく雑談をしていた。
「ははは、そりゃあ、市川さんがうたた寝でもしてるんだよ。僕はちゃんと声をかけてから出るから」
「パチンコにですか」
「いやあ、最近はこれさ」
そう言ってなにかを混ぜるように両手を動かす。
「フリー麻雀ですか。今度僕も連れて行ってくださいよ」
「いいとも。でも僕のやってるところは、レートがこれだからねぇ」
5本の指が見えるように広げられたそれが意味するのが、どんなレートなのか正直わからなかったが、僕は生唾を飲んでひるんでしまった。
そんなことを話しながら、ようやく師匠が今日高谷所長を訪ねようと思ったその本題を切り出した。
「所長。ヤクモ製薬の本社ビルをご存知ですよね」
「うん? もちろん知ってるよ。何度かなかに入ったこともあるけど」
「角南グループの系列だというのも?」
「それは情報商売の人間じゃなくても、知ってることだろう」
「ヤクモ製薬本社ビルに、地下があるのをご存知ですか」
高谷所長のにこやかな顔が、一瞬固くなったのが僕にもわかった。
「地下とは?」
「地下鉄ですよ。その遺構だと言っていましたけど。私たちはこの目で見ました」
「Oh」
高谷所長は大げさな身振りで額に手をやった。
「あれを見たのか」
「ええ」僕も頷いた。
「すぐに捕まって追い出されましたけど、あれはかなり遠くまで伸びているようにも見えました。いったいどこまで完成しているのか、ご存じないかと思って」
「なんてこった」
おちゃめな態度で首を振りながら、わざとらしいため息をつく。「どうしてそれを僕に?」
「捕まったあと、角南家の本家に連れて行かれて、そこで聞かされたんですよ。あれは、県や市や警察の幹部も知ってるって」
「ほう。それは大冒険だったようだね」
高谷所長ははぐらかすようにそう笑った。
「所長は県警本部の警視で、捜査第一課長だった人です。天領の本部長や警務部長には知らされないでしょうが、生え抜きの刑事部長には申し送り事項だったはずですよ」
「僕は刑事部長にはなれなかったんだけどなぁ」
「幹部の定義はわかりませんが、刑事部長以外にも現場指揮をするトップは知っていてもおかしくないでしょう。特に、キレ者で鳴らしていて、次期刑事部長確実って言われていた高谷さんなら」
「ううむ。もっと言ってくれよ」
「ハンサムにして、キレモノ!」と僕が合いの手を入れると、師匠に、「うるせぇ」と怒られた。
「ああ、知っていたとも」高谷所長は観念した、というように両手を広げた。「もっとも、この目で見るまでは眉唾物だと思っていたがね」
「見たんですか」
「隠された秘密の地下鉄、なんて聞いた日にはね。だって考えてもごらんよ。市内の渋滞に巻き込まれることなく、市電のダイヤや路線とも関係なしに、だれに目撃されることもなく、地下を通って、目的地に最短で行けるとしたら。この市内で起きる殺人事件のアリバイにも、関わってくる問題だ」
「あ、なるほど」
僕はいまさらながら、そのことに気づかされた。時刻表トリックもののミステリでもありそうな話だ。いや、秘密の地下鉄なんてトリックが、かつてあっただろうか。大都会ならまだしも、こんな地方都市で。僕ならミステリを読んでいて、いきなりそんなものが出てくると、怒ってしまいそうだ。
「それで、確認させてもらいに行ったんだけどね。もう10何年も前の話だ。もちろん、地下鉄の車両は地下に設置されてはいなかった。そして、線路だけど、東西どちらも150メートルほどで行き止まりになっている。壁にぶつかるんだ。地面を掘り進めている途中で、工事をやめたんだね。あるいは、最初からそこまでの規模の、実験的な事業だったのかも知れない」
「東西150メートル、あわせて300メートルか」
師匠が顎に手をやってつぶやく。
「地下鉄敷設の実験にしては、大規模すぎませんか。いったいどれだけ金がかかってるのか」
僕の問いに、高谷所長が答える。
「角南一族は、うなるほど金持ってるからねぇ。それに酔狂だ。金持ちのやることはよくわからないよ」
「でもとにかく、あの地下鉄は、路線としては1区間も完成してないということですね」
「ああそうだ。いまとなってはもうわからない経緯で、代々の秘密の申し送り事項になってしまっている。県警や行政側としては、そんなもの、とっとと埋めてしまってもらいたいさ。もっとも、そう迫って、強制執行でもしろと開き直られたら、そんな大工事の予算、とても捻出できないんだけどね」
高谷所長はため息をついた。
「それにしても、ずいぶん危ないところに首を突っ込んでるなあ。角南グループは、というか角南家は、県警でも相当にアンタッチャブルな存在だよ」
「所長は、『老人』と呼ばれる人を、ご存知ですか。角南大悟という人物を」
「……ああ、いまのグループ会長と、県議会議長の父親だね。僕も若いころに本人を見たことがあるよ。遠くから。あの当時で何歳ぐらいだったかなぁ。亡くなる少し前だと思うけど」
「どんな人でした」
「枯れ木のように細っていたけど、目が爛々としていて、迫力というか、一種異様な、魅力のある人物だった」
「その角南大悟を、いまでもどこかで見た、なんてことはないですよね」
「おいおい。死んでから何十年経つと思ってるんだ」
「じゃあ、その角南大悟の孫にあたる、角南大輝さんはご存知ですよね」
「もちろん。医療法人ヤクモ会の理事長だ。以前ゴルフで、コースをご一緒したこともあるよ。あれはなんの付き合いだったかな」
大柄で、日焼けした2人が並んでグリーンに立っているところを想像して、似合うなあ、と思ってしまった。
「大輝氏の子どものことを知っていますか」
「子ども? たしか2人いるという話だったなぁ。女の子のほうはゴルフ場で見たよ。まだ小さかったな。息子さんは会ってないけど」
「真悟というそうです。20代なかばで、いまはヤクモ製薬に入社しています」
「ほう。それがなにか」
「彼について、なにか噂を聞いたことがありませんか」
「ふうむ」
高谷所長は、腕組みをして、ソファに深く座りなおした。師匠の頭からつま先までを眺めて、質問の意図を読み取ろうとするような様子だった。
「ないね。悪いけど」
「ヤクモ製薬の超能力研究機関についても?」
「なんだいそりゃ」
「金持ちの酔狂ですよ。ご存じないなら、いいです。すみません」
「……」
高谷所長は、なにか考えているような表情を浮かべていたが、やがてゆっくりと口を開いた。
「2年前くらい前に、管内で不思議なホトケが上がったんだ。詳しくは聞いていないが、なんでも、身元不明の男が、コンクリートに埋め込まれるようにして、死んでいたらしい」
「コンクリ詰めですか」
「いや、それならヤクザのケジメでもたまにあることだ。そのホトケは、体の一部がコンクリートと同化しているみたいな、不思議な状態になっていたそうだ。一般には公表はされてないけどね」
「なんですかそれ、気持ち悪いですね」
僕がそう言うと、続けて師匠は、「犯人は捕まったんですか」と訊ねる。
「残念ながら、お宮入りだ。被害者も、どこのだれだか、結局わからなかったようだ。ただ、捜査線上に、ヤクモ製薬の社員が上がったと聞いたよ。最終的にその線は消えたらしいけど」
「どうしてヤクモの社員が?」
「胃の内容物に、薬の痕跡があったんだ。溶けきっていないカプセルが残っていたとか。そのカプセルがヤクモ製だったから、残っていた成分について問い合わせたら、開発中の新薬の可能性が浮上したそうだ。そうなると、話が変わってくる。ヤクモ製薬がこの件に、関わっているんじゃないかってね」
「それで、どうして疑いが晴れたんですか」
「それはよくわからない。捜査段階での疑いが晴れた経緯がよくわからないってことは、それは永遠にわからないようになるってことだ」
僕は高谷所長の、禅問答のような説明に、煙にまかれた気分になったが、師匠は顔を歪ませて唸っていた。
「アンタッチャブルってことですか」
所長は首をすくめて、なにも言わなかった。
「極秘の捜査情報なのに、よくご存知ですね。さすがいまでも県警に太いパイプがおありだ」
「いや、有効なパイプを持つには、細くて目に見えないパイプにすることがコツさ。さて、そろそろ次の約束があるんだ。もう失礼していいかな」
高谷所長はキビキビと立ち上がった。僕らもしかたなく立ちあがる。部屋を出るとき、師匠が振り返って、ぼそりと言った。
「所長。地下鉄の工事で、地面の下を途中まで掘ってやめているのに、どうして線路を敷いたんでしょうね。どこにもたどりつかない線路を」
「うん?」
「そうして、戦前に県議会にもはかった地下鉄計画の頓挫を、はっきり見える形で置いておく。まるで、なにかのカモフラージュみたいに思えませんか」
「なんのカモフラージュだね」
「……東京の地下鉄って、いろんな路線が入り組んでいて、ぶつかってしまわないように、多層化されているところもあるそうですね。地下鉄の地下に、さらに別の地下鉄が走っているなんてことも」
「えっ」
僕はそれを聞いて、師匠の考えていることが見えてしまった。
「なにを言っているんだね」
高谷所長も察したのか、困惑した顔で唸っている。
「さあて。金持ちの『たぶれごころ』は、よくわからないってことですよ」
師匠はそう言って笑った。
2 マリファナとハッシッシを少し
高谷所長と会ったその足で、僕らは小川調査事務所に向かった。今日は重要な依頼があるのだ。
「ギリギリになっちまったな」
早足で歩く師匠のうしろで、僕の足取りは重かった。なにしろ相手がヤクザだからだ。
「なんだ、元気がないな。嫌なら今日は、お前はいなくてもいいんだぞ」
「そういうわけにはいかないですよ」
「こっちは別にいいけどな」
あー、そうですかい。だったら、意地でもくっついていくけどね。
雑居ビルが近づき、喫茶店ボストンの看板が見えてくると、僕は周囲に怪しい車の影がないか見回した。やつらはたいてい、黒塗りのゴツイ車に乗ってくる。だが、いまのところは、それらしい車は見当たらない。
ビルの階段をのぼり、3階にある小川調査事務所のドアを開ける。
「遅かったな。もうじき来るってさ」
事務所にいたのは、小川所長だけだった。今日は服部さんはいないようだ。先日服部さんにスパイ疑惑が発生したばかりなので、いたらいたで気まずいところだ。
少しして、ドアをノックする音がした。外から派手な車の音は聞こえなかった。
「どうぞ」
入ってきたのは、黒いダブルのスーツを着た男だった。青白い顔に、眼鏡をかけている。このところやけに因縁深い、石田組の若頭補佐、松浦だ。黒い革製の鞄を小脇に抱えている。
「ようやく依頼を受ける気になりましたか」
松浦はカツカツ、と姿勢よく歩いて、事務所の所長の了解もとらずに、来客用のソファに腰掛けた。
「1人なのか」
師匠はその向かいにドカッと腰を下ろす。
「なにしろうちはいま、忙しくてね」
松浦は足を組んだまま答える。僕は、昨日の新聞で見た、暴力団の抗争の記事を思い出した。市内にある暴力団・立光会の2次団体の組事務所の玄関に、銃弾が打ち込まれたと書いてあった。先日、小川所長から、広域暴力団菱川組と立光会の暗闘の話を聞かされたばかりだ。自分には関係のないニュースだと、読み飛ばすような気には、とてもなれなかった。
「そのお忙しいのにわざわざ出向いていただきまして、ありがたいですねぇ。なんの依頼なんだよ」
師匠はあいかわらず、松浦への口の利き方をあらためない。横で聞いている僕は、多少慣れてきたとはいえ、まだヒヤヒヤする。
松浦はそばで立ったままの小川所長をチラリと見た。所長が口を開く。
「この件は中岡に任せています。受けたいか受けたくないかは、まず彼女が判断します。そのうえで、この事務所の責任者として、GOか、ストップをかけるか、決定させてもらいます」
中岡は、師匠の調査員としての偽名だ。ただ、仁科さんのように、親しくなってから遠慮なく本名で呼んでいる人もいて、なかば公然の建前のようになっている面もある。松浦も師匠の本名を知っているはずだが、そこではなにも言わなかった。
僕は小川所長が立っているので、師匠の隣に座っていいものか迷った。でも、少しでもなにかの弾除けになれば、という気持ちで、そっと隣に腰掛ける。いいんだよ。助手なんだから。と、自分に言い聞かせて。
「忙しいのでね。簡単に説明させてもらう」
松浦は鞄から小さな瓶を取り出した。それをソファの前のテーブルに置いた。
「なんだこれ」
素手で持っていた松浦の手つきから、危険物ではないと思ったのか、師匠はすぐにそれを手に取った。
透明なガラスの小瓶だ。市販の風邪薬の錠剤の入った瓶くらいの大きさだった。瓶は透明で、なんのラベルもない。白いフタも同様だった。なかに液体が入っているが、こちらも無色透明だ。ただの水のように見えたが、なにかの薬だろうか。
「これは?」
「クスリですよ。いまこの街の若者の間で流行っている」
「クスリ?」
師匠はもう一度瓶を上に掲げて、天井の照明に透かすようにして見ていたが、首をかしげてテーブルに戻した。僕もそれを持ってみたが、特に気がついたところはなかった。ただの透明な液体の入っている瓶だ。
「ドラッグなのか?」
師匠のその言葉を聞いて、僕はギョッとした。思わず瓶をテーブルに置く。ドラッグなんて、そんな怖いもの、一度もお目にかかったことがない。
「わかりません。それを調べてもらうのが、今回の依頼です」
「はあ? 私にわかるわけないだろ。お前らが専門家だろうが」
師匠の言葉に、松浦の眉がピクリと動いた。なにか気分を害した気配だった。
「8代目立光会は、クスリはご法度ですよ。シャブもマリファナも、もちろんヘロインやコカインもです」
「麻薬の売買に関わってないってのか。じゃあだれがこの街で、麻薬を売ってんだよ」
「ほかの小さな組の連中ですよ。まともなシノギがないから、クスリなんかに手を出すんです」
「ヤクザにまともなシノギなんて、あるもんか」
「ちょっと、師匠」
発言があまりに挑発的になりすぎていたので、慌てて止めた。松浦は、10秒ほど黙ってから、口を開いた。表情を変えずに。
「ほかにも、暴走族上がりの連中が半グレを気取って、覚醒剤の取引に手を出しているのもあります。最近では外国人も少し増えてきたようです。中国人や、イラン人などです。いずれも、小さな組織ですから、大口のブローカーと直接取引ができずに、あいだに何件も仲介が入って、粗利は少ないようですね。覚醒剤は1パケの相場が1万円、ポンプ付きで1万3千円。これが昔から変わっていません。だから儲けを出したい半グレどもなんかは、混ぜ物をしてカサ増ししているという噂です。だから、質は外国人のモノのほうがいいとか。マリファナ、つまり大麻も繁華街のクラブなどで、手に入るらしい。コカインやヘロインはほとんど取引がありません。単価が高いのでね。小さな組織ではなかなか捌きにくいようです。それから最近麻薬に指定されたLSDやMDMAといった、いわゆるサイケデリックス、幻覚系のクスリも増えてきています。やったことは?」
松浦にそう訊かれて、師匠は鼻白んだ。
「ねぇよ、そんなもん」
「そうですか」
師匠に続いて、僕も首を振る。
「嘘。ホントはあるけど」
「あるのかよ」
思わずツッコんでしまった。
「昔、マリファナとハッシッシを少しな。興味本位でだよ。興味本位。でもああいうの、私あんまり効かないんだよ。体質でな。それからはやってない」
師匠は体質で、というところを、わざとゆっくりと言った。
「なるほど。賢明ですね。それから、最近では欧米でデザイナーズドラッグとか、合法ドラッグなんて呼ばれるクスリが流行っているようです。ハーバルエクスタシーなどがそうです。まだこの街には入っていませんが、いずれやってくるでしょうね。植物などに由来するナチュラル系とは違って、化学物質を合成して作るケミカル系です。これらは、ハーブなどに直接、化学物質をまぶして流通させるものや、錠剤などです」
「シノギにしてないのに、ずいぶん詳しいじゃないか。ホントは、シノいじゃってるんじゃないのか」
「この業界では、親がご法度といえば、ご法度です。うちでは、先代のころからね」
松浦は静かに言ったが、穏やかなかに滲み出る迫力を感じたのか、師匠は黙った。
「なにごとも、調べるのが性分でね」
「……で、若者のあいだに流行ってるっていう、これは?」
師匠がアゴで、テーブルの上の小瓶を指し示す。
「最近になって、妙なクスリが出回っているという噂がありましてね。調べてみても、ほかの組や、半グレ、外国人なども関わっていないようなのです。どうも市内の高校生や大学生などのあいだでだけ、密かに出回っているらしい。今後だれかの大きなシノギになりそうなら、警戒しないといけないので、入手してみたんですが、モノがね、おかしいんですよ」
「おかしい、とは?」
「フタを開けてみてください」
「大丈夫なのか」
そんな前振りをされて、師匠はちょっと嫌そうに眉をしかめた。
「大丈夫です。どうぞ」
「気化するようなやつじゃないだろうな」
そう言いながら、師匠は僕を小突く。開けろ、ということらしい。
ええー、と怖気づいたが、師匠に睨まれて仕方なく、おっかなびっくり、小瓶を手に取った。
まあ、中身を知っているらしい松浦もすぐ目の前にいるんだから、開けてもヤバイものじゃないだろう。そう自分に言い聞かせて、僕はフタをひねった。
キュッ、という小さな音を立てて、フタは間単に開いた。外して、脇に置く。師匠が僕の手のなかの小瓶の口を覗き込んで、フンフンと匂いをかいだ。
「うーん?」と小首をかしげる。
僕もつられて、顔を近づけて匂いをかいだが特になにも匂ってこなかった。
「液体状のドラッグといえば、LSDのリキッドやケタミン、一部のデザイナーズドラッグなどがありますが、これはそのどれとも違う。覚醒剤などは、液体で流通させることもありますが、これは小売の状態でこうなのです。ちょっと、貸してみてください」
松浦は小瓶を手に取った。そして、僕らの前で、無造作にそれを口元にやると、一息に飲んでしまった。
「あっ」
師匠と僕と、少し離れて見ていた小川所長の声が、3つ重なった。
「おい、大丈夫なのか」
松浦はまったく表情を変えず、空になった小瓶をテーブルに置いた。
「ええ。なんともありません」
そして、鞄からもう1つ、小瓶を取り出した。同じ物のようだ。師匠はそれを受け取ると、一通り観察してからフタを取った。匂いをかいでから、瓶の口に小指を入れる。指先についた液体を目に近づけてじっと見てから、ペロリと舐めた。
「ただの……水?」
え? 僕も小瓶を借りて、同じようにして舐めた。無味無臭。ただの水だ。水道水の消毒液臭さもまったく感じない。ミネラルウォーターのようだ。
「どういうことなんだ」
「私も困惑しているんですよ。なぜただの水が、クスリだといって、密かに売買されているのか」
「みんな騙されてるってことなのか」
「ただの水だとわかっていて、こんなに口コミで出回るとは思えない。若者たちは、これをただの水だと思っていないようなのです」
「だって水じゃないか。あれか? イオンが入ってるとか、タキオンが頑張ってるとか、そういうやつか」
「いえ。噂ですがね、これを飲むと、『夢が変わる』と言われているようです」
「夢が、変わる?」
それを聞いて、師匠の表情が変わった。面白いものに出会ったときの顔だ。僕もその言葉に興味を覚えた。
「わざわざあなたに依頼しにきた理由が、わかってもらえましたか」
松浦は、かすかに笑みを漏らした。
「いままでに見たことがなかったような夢を、見るようになるそうです」
「あんた、飲んだのは、いまがはじめてじゃないよな。夢が、変わったのか」
「さて……。もともと夢はあまり見ない性質でね」
首を振った松浦を、信用できないという目で見たあと、師匠は小瓶を手に取った。
「いま手元にはあと3本しかありません。2本を、この調査に提供しましょう」
松浦が、もう1本を鞄から取り出してテーブルに置いた。
「どこで手に入れたんだ、これは。いったいだれが売っているんだ」
「これは傘下の組の若い衆が、暴走族の後輩からもらったものです。その後輩は、噂を聞いて買いに行ったら、実際に買えた、と言っているようです。繁華街の白町(しろまち)の通りで、夜にどこかの横道に入ると、仮面をつけた人物がいて、千円札を出すと、この小瓶1本と引き換えてくれるとか」
「仮面?」
「仮面ですって?」
僕と師匠の声が被る。ここでその単語が出てくるとは思わなかった。
「白くて、のっぺりした仮面か?」
「さあ。噂では、とにかくなにかの仮面を被っていて、素顔を見せない売人なのだそうです。我々も探しましたが、そういうときに限って、姿を現さない。用心深いのか、なんなのか……」
「千円てのは、安いのか」
「安いでしょうね。ドラッグとしては破格に。いまどき、売人から買うと、シンナーでももっとします。ただ、元がただの水だとすると、実質、瓶代を引いた残りが丸々利益ですからね。ちなみに瓶は、大量に出回っている市販品です。その筋からたどるのは難しいでしょう」
「名前はあるのか、これに」
「若者のあいだでは、Cと呼ばれています。ABCのCです。由来ははっきりしません」
「C……」
松浦は、手のなかの小瓶を見つめている師匠を見て、「飲んでみますか」と声をかけた。
「いや、とりあえず調べてみる」
「では、引き受けてくれるのですね」
「ああ。だけど、どこまでわかればいいんだ? この中身の正体か、それとも売ってる人間まで突き止めるのか」
「一応両方に成功報酬を設定しましょう。その2つは、結局セットになりそうな気がしますがね」
師匠が小川所長のほうを見た。所長は頷いて返す。どうやら、GOのようだ。
「OK。じゃあ、さっそく調べるよ。おい、いくぞ」
師匠は小瓶を2つ手に取ると、立ち上がって、僕に向かってアゴをしゃくった。
「あ、はい」
「この成功報酬の料金は……」
そう言いかけた松浦に、師匠は、「あとは所長と決めてくれ。私は、正規のバイト代しか受け取らない」と言い放った。
「前回のことを根に持っているのですか」
松浦は挑発的な言葉を投げつけてきた。心霊写真の事件で、リュックサックに大金をねじ込まれていたときのことを言っているのだ。
「ふん」
鼻息で返事をして、師匠はドアに向かった。僕もあとを追いかける。
「どうして引き受ける気になったんです」
背中に、松浦の言葉がかけられる。師匠は振り返らずに答えた。
「さあな。ただの気まぐれだ」
所長と松浦を残して、僕らは事務所をあとにした。階段を下りていく師匠の背中を見ながら、僕は複雑な気持ちになっていた。
師匠に気まぐれを起こさせたのは、松浦というヤクザの持っている、不思議な魅力のせいではないか、という気がしていた。心霊写真の事件のときも、結果的にやつは師匠好みの、オカルティックな謎を持ち込んできた。即物的な暴力の世界に身をおきながら、松浦は、どこか師匠と同じ価値観を持っているように感じる。
『私が見ている世界は、あなたの見ている世界と似ているだろうか』
いつか、松浦の言った言葉が脳裏をかすめる。そしてそれを思い出してしまった僕は、苛立ちを覚えている自分に気づく。
あんなやつに……。
師匠のかつての相棒である、黒谷夏雄に感じる嫉妬と、同じものが胸にわいている。自分がなに者なのか、証明をしなくては、同じ土俵にも上がれない。そんな気がして、視界が暗くなる。これは、良くない感情なのだろう。たぶん。僕は苛立ちが、足音になるのを聞いていた。
ビルから出ると、師匠が急に立ち止まった。向かいのビルと電信柱の陰のところに、だれかいる。
「おい。なんの用だ」
師匠が声をかける。その男は、煙草を右手の指に挟みながら現れた。あいつだ。松浦の部下で、僕をビルの空き部屋に連れ込んで、暴行した男。思わず背筋に緊張が走る。
「いやあ、松浦の兄貴の付き人ですよ」
茶髪の男は、前歯の抜けた顔を歪めて、ニヤニヤと笑っている。そして、つい、と煙草を口に持っていく。
見回したが、やはり車はない。運転手で来たわけではなさそうだった。
「お前、松浦を裏切ったんだろ」
僕は恐怖の記憶を振り払って、そいつに言葉を投げた。
「ああん? 裏切ってるのは、あいつのほうだよ」
茶髪は、ビルを見上げて言う。
「このクソ忙しいときに、なにやら、変なお遊びばかりしやがって」
お遊び……。こいつも、依頼のことを知っているのか。僕は師匠をチラリと見た。
「ま、いまのところは、好きにさせておきますがね」
茶髪は、ペッ、と火のついたままの煙草を吐き捨てる。
「素人さんが、こっちのことにあんまり首を突っ込まないことですよ。これは、忠告です」
「なにが忠告だ。ヤクザに脅されましたって、警察にチクるぞ」
僕の必死の抗弁を、男は笑って、意に介さないようだった。
「じゃあな、ボウヤとお嬢さん。俺は、西沢ってんだ。まあ、いずれ、この名前は変わるがね」
ククク、と笑いながら、男は歩き出し、去っていった。師匠はその背中を見ながら、毒づく。
「なにが付き人だ。松浦を監視してたのか、あの歯抜け野郎」
「あいつ、本当に危ないやつですよ」
散々殴られた僕は、本心で師匠に言った。ナイフを背中につきつけられて、師匠を呼び出されそうになったのだ。夏雄が助けに来てくれなかったら、どうなっていたか。思い返すと、ゾッとする。
「ヤクザは、嫌いだ」
師匠は吐き捨てるようにそう言った。
3 科学的検査を信じろ
僕と師匠は、西沢が去ったあと、大学へ向かった。師匠の提案で、この小瓶の中身が本当に水なのか、確認したほうがいいということになったのだ。
それもそうだった。そうなると、液体の検査ができる研究室があるところ、ということになる。
僕が、薬学部に知り合いがいます、と言うと師匠は首を振った。
「医学部と薬学部は、ヤクモのテリトリーだ」
学生に頼むのだから、そこまで警戒しなくても、と思ったが、師匠はあくまでも却下した。
「理学部に行こう。頼めるあてがある」
医学部と薬学部は、別キャンパスだが、理学部は僕らの通う同じキャンパスにある。ヤクモ製薬のテリトリーとは物理的にも離れているので、安心感があった。
「それにしても、なんなんでしょうね、これ。Cっていう名前に聞き覚えはありますか」
「さあな。名前は知らないけど、なんだか変なクスリが密かに流行ってるってのは、聞いたことがあったような気がする」
「僕は初耳ですよ」
僕はドラッグなんかとは縁のない人生を歩んできた。高校でシンナーを吸っているバカはいたが、いわゆる不良校ではなかったので、そんなやつも稀だった。やっていても、せいぜい煙草くらいか。
僕は師匠がマリファナをやったことがあると聞いて、驚いていた。ただ、興味本位で試してみた、というのには、妙に納得してしまう部分もあったが。
理学部棟に着くと、白衣を着た学生たちのあいだを縫って歩き、僕らは分子生物学の研究室を訪ねた。そこの男性講師で、師匠が懇意にしている人がいたのだ。
師匠は本当に、いろんな学部、学科に顔が広い。いや、広いというか、ポイント、ポイントでキーマンを抑えている感じだ。
研究室で、バナナを食べながらテレビを見ていたその講師は、そうは見えなかったが、「忙しいのにな」と、ぶつぶつ言いながら、小瓶の中身を調べてくれた。プレートに水滴を落として、顕微鏡で見るのかと思っていたら、思いのほか、大げさな装置を使っていた。
結果は、水。それも、塩素などを含まないため、水道水ではなく、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも含まない、純水だという。
「蒸留水だろうね。水を沸騰させて、水蒸気から液体に戻したものだ。僕らは洗浄や溶媒で使うから、業者から買っている。20リットルで3000円くらいかな」
講師はバナナの残りを食べながら、もぐもぐと説明してくれた。
「なにか、少量でも、おかしな成分は入ってなかったですか?」
「おかしな、って言われてもねえ。そこまで精密に調べるとなると、ここじゃあ設備が足りないし、ノーマネーじゃあ無理だよ。でもまあ、僕ら、これなら純水として、普通に実験用にも使うよ。なにか入ってたって、影響しないレベルだよ」
そう断言するのだ。専門家がそう言うのだから、僕らはとりあえず納得するしかなかった。
理学部棟をあとにして、いつもの学食で作戦会議をすることにした。
「モグモグ。とりあえず、噂をさぐってみるか。実際に買って飲んだってやつが見つかればいいけど」
「でも、ただの水だったんでしょ」
「だから、松浦だって最初からそう言ってただろ。ていうか、あいつ飲んでたし。ただの水なのに、どうして売人からドラッグを買うみたいな形で、出回ってるんだよって話。それもさあ。モグモグ。こんな小さいので千円だぜ。千円。このカレーが何杯食えるんだっての。なにかあるんだよ、裏が」
「Mサイズなら4杯食えますね」
「Lなら3杯だ。よし、手分けして探ろう」
僕らはいったん別れて、聞き込みに回ることにした。僕も2本ある小瓶のうちの1つを、預かった。さっき検査で使ったほうなので、少し減っている。
僕はとりあえず、自分の研究室に行った。最近師匠とばかりつるんでいて、こっちに顔を出してないので、多少気まずかったが、しかたがない。午後の講義が終わって、ダラダラしている連中に声をかけた。
「Cってクスリ? 知らないなぁ」
だれも、おおむねそんな反応だった。ついで向かった、同じく最近足が遠のいて久しいサークルでも、似たようなものだった。だが、ここでは、知り合いから聞いたことがある、という男が1人いた。このクスリなのかは自信がないけど、と言っていた。後輩の1回生だったので、飯をおごるから、その人に会わせてくれ、と頼むと、なんとか承知してくれた。
大学近くのファミレスで落ち合うと、知り合いとはそいつの彼女だった。コートを着ていたが、その下はブレザーだったので、高校生だというのはすぐわかった。
この野郎、高校生なんかとつきあってるのか。あまり話したことのない、ヒョロヒョロとしたモヤシみたいな後輩だったが、人はみかけによらないものだ。
「コレコレ。これあたし、買ったやつ」
ミサキちゃんというその高校生は、濃い化粧をしていたので予想されたことだが、平均的な女子高生と比べて少々軽そうな子だった。
「どうしてこれを買おうと思ったの」
「なんか、ガッコの友だちが先輩から聞いたって。なんかね、面白い夢を見るクスリなんだって。なんか面白そうじゃん」
「どこで、どんなやつが売ってたんだ」
「友だちから聞いたとおりに、白町で夜にウロウロしてたら、狭い道で変なお面被った人がいたの。黒いマント着てて、不審者丸出しのやつ。絶対こいつだーって、思って声かけたら千円だって」
「言ったの? 男の声だった?」
「喋ってはないよ。こうやって1本立てたの。人差し指を。まさか1万円なわけないじゃん。てか、そんな持ってないし。千円出したら、これくれたの」
「どんな仮面だった?」
「夜店で売ってるみたいなやつ。なんかのアニメのキャラ。あたしアニメ見ないから、よく知んないけど」
アニメ……。それを聞いて、なんだか、ガックリきてしまった。ずいぶん軽いなあ。これはどうも、僕と師匠が想像したやつとは違うらしい。
「で、それ買ってどうしたの」
「飲んだよ。普通の水みたいだった」
よくそんな怪しいやつから買ったものを飲めるなあ。そういう感想を抱いたが、面と向かってはつっこまなかった。貴重な体験者なのだ。と思っていたら、彼氏のほうがつっこんでいた。
「危ないよ。そんなことしちゃ。ていうか、まさか、クスリとか買ったことあるの?」
「ないよー。1回もないし。友だちに誘われて、葉っぱ吸ったことあるだけ」
「ちょっと待って、葉っぱってなに。大麻? 大麻なの? だめだよミサッち、まじでそんなのやったの? ウソでしょ」
「うっさいなぁ。いいでしょ別に」
そんなやりとりをしばらく見せられたあとで、ようやく続きを聞けた。
「飲んだけど、なんにもなかった」
「なかった? 夢は見なかったのか」
「うーん、よくわかんない。見たと思うけど、あんまり覚えてない。普段見てる夢と変わんなかったんだと思うよ。まじ金返せって感じ」
そんなこんなで、ファミレスで2人分のメシをおごったにもかかわらず、たいした収穫は得られなかった。ただ、そういう噂が現実にあり、実際に売っているやつも実在した、ということはわかった。それだけでも、まあ一歩前進だろう。
次の日、僕は師匠の部屋に行った。
「買った人の話を聞けましたよ」
一応の成果を話したが、師匠のほうは3件も当たりを引いていた。だいたいこうだ。こういうので、勝ったためしはない。
それどころか、師匠は小瓶が1つ増えている。
「1人は、買ったけど気持ち悪くて捨てたらしい。もう1人は、なんとなくそのまま置いていたそうだ。千円で譲ってもらったよ。それがこれ。同じだろ」
「そうですね」
手に取ってみたが、松浦から預かったものと、まったく同じ小瓶だった。
「最後の1人は飲んでみたそうだ。女の子なんだけど、南の島のリゾートに行く、楽しい夢を見たって。普段そういう、願望のかなうような夢を見たことがないから、夢が変わる、という噂は本当だったって思ったそうだ」
「はあ」
ずいぶんかわいらしい夢だ。
「ということで、お前、これ飲め」
師匠は、小瓶を僕に、ずい、と近づける。
「ちょ、ちょっと待ってください。え、これ僕が飲むんですか」
「ただの水なんだから、いいだろ」
「ただの水じゃないかも知れないから、こんな大げさなことやってんでしょ」
「科学的検査を信じろ。母校が誇る理学部の検査結果を。あのバナナ講師、ああ見えて、こないだ溺れた子どもを助けて、表彰されてんだ」
「本業で表彰されてないし」
「いいから」
「ただの水なら、飲む意味もないでしょ」
「詭弁か。私に詭弁で勝負を挑むのか、コラ」
「正論ですよ」
「正論もスリランカもあるか」
…………
小一時間の激闘の末、言い負かされた僕は、覚悟を決めて、小瓶の水を飲んだ。
無味だ。ミネラルウォーターとも、もちろん水道水とも違う、なにも感想がわかないような味だ。
「飲みました。水ですよこれ」
「じゃあ、寝ろ」
師匠は布団を敷きはじめた。
「いま寝るんですか」
「そうだ。ハッシャバイ歌ってやっから」
「観察されながら寝られませんよ」
「お前、前に私の寝言記録しながら、一晩中私の寝顔見てただろうが。いやらしい」
「命令でやったんじゃないですか」
そんなこんなで、僕は横になり、しばらく師匠の子守唄らしきものを聞いていると、いつのまにか眠ってしまった。
夢を見た。
野良猫が屋根の上のひなたで、寝転んでいる夢だ。それを見ている僕の視界が、ずっと上下にブルブルと震動している。なんだよこれ、と思って、まわりを見ると、あたりの家がどれも上下に小刻みに震えていて、街じゅうが揺れているようだった。そのなかを、だれも気づかずに人々が歩いていく。
これは、街が揺れているのか、それとも僕の視界が揺れているのか。どっちなんだろう。
そう思っていると、目が覚めた。
師匠の顔がすぐ目の前にあった。
「うわ」
「起きたか」
「なんですか」
「まぶたが痙攣してたからな。夢を見てたろ。つっついて起こしたんだ。いまならはっきり覚えてるだろ」
「はあ」
僕は、見た夢を説明した。変な夢だが、どうということもない内容と言えば、そうだ。
「そういう、視界が揺れるようなパターンの夢を見たことは?」
「ないです」
「夢が変わった、ってわけか」
なんとも地味な結果だ。千円の価値があったのだろうか。師匠も渋い顔をしている。
「売ってるやつをとっ捕まえるのが、一番手っ取り早そうだな」
時計は夜の12時を回ったところだった。ちょうどいい時間だったので、それから2人で、白町という繁華街へ向かうことにした。
サークルや、研究室に足が遠のいてから、あまり飲み会に縁がなかったので、白町へ来るのも久しぶりな感じがした。夜中の12時を回ってもまだまだ人通りが多く、すでにできあがった酔客たちが、次の店を探してウロウロしていた。
ここは、師匠とはじめて出会った場所でもあった。あのとき、師匠はジャージを着て、不機嫌そうな顔で歩いていた。そのうしろを、無数の人ならざるものたちが列を成してついて歩いていた。あんな光景は、いまでは見られない。あのときの師匠は、右の頬から、光る粒子を涙のようにこぼしていた。息が詰まるような、はかない光だった。その跡が、川のようにかすかな光の帯をつくり、霊たちがそれにそって歩いていた。
師匠はなにか変わってしまったのだろうか。僕はあのときの彼女を、自分と同じ人間には思えなかった。それほど、幻想的ななにかに思えたのだ。
いまはどうだ。目を閉じると、あの光の雫が、刻一刻と失っていく力を現しているように思える。それが尽きたとき、彼女になにが起こるのか。僕はそれを考えるのが恐ろしく、そして悲しかった。
「いねぇな」
しばらく歩いていたが、どの路地にもそれらしい人影はなかった。かなり外れのほうまで探索したが、結果は同じだった。
もう今日は諦めようか。そういう雰囲気になったとき、師匠がぽつりと言った。
「霊もいねぇ。繁華街には、よく集まるのに」
そういえば、師匠と出会ったとき以外にも、僕はこのあたりで何度も霊を目撃している。
あれから師匠と恐ろしい体験を繰り返し、さらに霊感が上がっているのに、いまは霊らしきものの姿はまったく見えなかった。そういえば、師匠は以前から、明かりのないランプを手に、「幽霊はいないか」と言って街を練り歩く、ディオゲネスごっこという悪趣味な試みをしていた。
そうして挑発をして、自分の家に霊を呼び寄せようというのだ。実際に、師匠の家には、よく幽霊やおかしなものたちがやってきていた。
それが、ここ最近、めっきり減っている気がする。
「弓使いが、倒して回ってたりして」
僕はそんな軽口を叩いたが、師匠は首を振った。
「あいつが狙う悪霊なんて、そうはいない。このへんにいるのは、ほとんどは人畜無害な霊だよ。ただ彷徨っているだけの。かわいそうな存在だ。それが、こうして消えている。なぜだ」
そう言って、キョロキョロとしながら歩いていると、居酒屋と、シャッターの閉まった文具店のビルのあいだの狭い路地に、師匠がなにかを見つけた。
「おい」
僕は、仮面の男が現れたのかと思って緊張したが、暗がりのなかに、それらしい姿はない。だが、師匠の指差す先には、うっすらと、だれかの足のつま先が見えた気がした。その上には、人の体は乗っていない。うつろな足だけがたたずんでいる。
こういうものが最近増えていると、師匠から聞いたことがあった。そのとき、師匠は続けて言ったのだ。「食われてんだよ」と。それを思い出した。
師匠はいまにも消えそうな足の先の前に座り込み、しげしげと観察していた。
僕はなんとも言えない胸騒ぎがした。師匠。やっぱりまずいですよ。これは。
そんな言葉を飲み込む。空を見ると、月が明々と出ていた。その月に、見下ろされているような気がした。
4 なんだいまの。かわいいじゃねえか
松浦から依頼されたCというクスリの件が、思うように進んでいないなか、僕は資料整理のバイトのために小川調査事務所に来ていた。
これまでに何度かタカヤ総合リサーチの資料ファイルを見せてもらって、その仕組みを自分なりに研究し、小規模ながらそれに似たやりかたができないか、試行錯誤をしていた。小川所長からは、「綺麗にできたら、金一封はずむよ」と言われていたので、多少やる気がでている。
その日は午前中からやっていたが、午後には師匠がやってきて僕の仕事の邪魔をしはじめた。僕に怒られると、今度は服部さんの仕事の邪魔をしていた。なにをしにきているのだろうか、本当に。
そうこうしていると、珍しく不破刑事が事務所に顔を見せた。近くまで来たから陣中訪問に来ただけだ、と言っていたが、師匠はこれ幸いと、不破刑事を1階の喫茶店ボストンに誘った。捜査経費という名目で、この手の食事に領収書を切ってもらっているのを知っているので、昼飯をたかろうとしているのだ。
「いい話があるんだって」
「本当かよ」
うさんくさそうに不破刑事はついてくる。
「マスター、いつもの!」
と言いながら師匠は機嫌よく喫茶店のドアを開けた。あいかわらず、昼時だというのに、客が少ない。よく見かける近所のおじいさんが1人、日替わりランチを食べているだけだった。
「あ、不破さんお久しぶり」
ウェイトレスのひかりさんがおしぼりと水を持ってくる。最近、ひかりさんは化粧がなんというか、入念になっている気がする。師匠はマスターとの仲を勘ぐっていたが、進展はなさそうな感じだった。そうなると、別の彼氏ができたのか。ひかりさんから注文を聞いているマスターの態度を横目で見ながら、僕はそのあたりを推理していた。
どうも小川調査事務所に来ると、探偵脳になってしまう。このあいだ、小川所長から遠まわしに、「お前はまだこの世界の土俵にも上がってない」と言われたのを、未だにひきずっていた。
「で、なんだって。言ったと思うが、弓使いの件なら、俺は降りたぜ。勝手にやれ」
不破刑事は、以前、連続殺傷事件の犯人と思われる、通称『弓使い』について、師匠に、「わかったら、一課より先に教えろ」と迫っていた。彼は元々、刑事としてそうした強行犯の担当だったのが、現在は暴力犯担当にされているのを苦々しく思っているらしい。超一級の容疑者を自分で挙げたい、という気持ちがあるようだった。
しかし、弓使いの件で、松浦が絡んできて以来、不破はめっきりそのことを口に出さなくなった。『不破さん、あなたには話していない』と、面と向かってけん制されてからだ。ヤクザの脅しなどに簡単に屈するとは思えない強面の不破だったが、松浦に関しては別のようだ。『丸山警部によろしく』という以前の脅しも効いていたのかも知れない。
僕は先日、小川所長から、この街の暴力団のあいだの不穏な現状を聞かされていたので、なんとなく腑に落ちるものがあった。
「これなんですよ、ダンナ」
師匠は小瓶をテーブルに置いた。例のクスリだ。
「なんだこりゃ」
「おや、ご存じない? いま若者のあいだで密かに流行しているドラッグを」
「ドラッグ?」
不破は小瓶を手にとって眺めた。
「名前は」
「Cって呼ばれてるみたいでゲスよ」
「妙なしゃべりかた、やめろバカ。聞いたことねえな。最近俺ァ、生安ともあんまり情報交換してないからな」
生安とは、県警で違法薬物の取締りを担当している、生活安全部の刑事のことだ。
「俺の担当のヤクザどもは、こんなポッと出のファッションドラッグになんか目もくれねぇよ。やつらはシャブだ、シャブ。覚醒剤を自分の血で溶かして打つような、筋金入りどもだよ」
不破は左肘を上に向け、注射を打つ真似をした。
「で、このファッションドラッグがなんだって?」
「いや、なにかご存じないかと思いましてネ」
不破はガクッ、と首を下げた。
「てめえの情報収集じゃねえかよ。なぁにが、いい話だボケ」
「えへへ」
「なんだいまの。かわいいじゃねぇか。もう1回言え」
そんな、不破と師匠のやりとりを見ながら、僕はふと思った。
そうだよな。ヤクザはやっぱり覚醒剤だ。若者のあいだで、新しいドラッグが流行ろうが、そんなものにいちいち戦々恐々としないのではないだろうか。まして、松浦のいる石田組は、その親組織である立光会から、クスリご法度の令が出ているという。密かに流行りつつある、という段階のこんなよくわからないモノを、そんなに警戒するものだろうか。
どうも、松浦はなにか隠している気がする。小川調査事務所に、1人で来たのもひっかかっていた。西沢という舎弟が、松浦のことを、「変なお遊びばかりしやがって」と言っていたのもそうだ。これは、組など関係なく、純粋に松浦の個人的な興味で行っている調査なのではないだろうか。その動機が、どこから出ているのか。
僕はテーブルの上の小瓶を見つめながら、ぼんやりとそんなことを考えていた。
『ヤークモ、ヤークモ、ヤクモ製薬♪』
壁際にあるテレビから、そんな歌が流れてきて、ちらりとそっちを見た。よく見る風邪薬のCMだ。地元出身の女優が、やけに元気そうに風邪薬の錠剤を飲んでいる。これを見るたびに、こいつ風邪なんか引いてないだろ、と思ってしまう。
『用法、用量を守って、正しくお使いください』
ピンポーン、という音とともに、女優が注意の言葉を読み上げて、CMは終わった。
捻っていた頭をもとの位置に戻すと、師匠がテレビのほうを見ながら、怪訝そうな顔をしている。
「どうかしたんですか」
「なんか……。いまのなにかおかしくなかったか」
「は?」
いつも見ているCMだ。僕は特になにも感じなかった。たしかに、ヤクモ製薬とは最近因縁めいてきたので、こうして普通にテレビのスポンサーをして、CMを流しているのを見ると、なんだか変な気分だ。あんな大きな企業を、僕らは敵に回しているようなものなのだと思うと、現実感が薄くなってくる。
師匠は真剣な顔で、なにかを思い出そうとするように目を見開いている。しかし、考えてもわからなかったのか、やがて首を振った。
「そういえば、不破さん。2年くらい前に、コンクリ詰めの変な死体があがった事件を知りませんか。ヤクモ製薬の社員が疑われたっていう」
「あん? ……ああ。チラっと聞いたことはあるが、ありゃあ本店のヤマだ。俺は知らねぇ」
本店とは、県警本部のことらしい。不破は所轄である西署の刑事だった。
「胃の内容物から、ヤクモ製薬の未認可の薬の成分が出たとか」
「だから、知らねぇって。だれに聞いたんだよ。高谷のおやっさんか。ったく。調べろっつっても、あれは無理だぜ。打ち切りは本店の上の判断だ。ヤクモ、っていうか角南グループ絡みはいろいろ難しいんだよ。昔から」
不破の態度から、これは望み薄だと感じた。師匠がなにか頼むと、たいていそっけなく断るのだが、なんだかんだ言って、最終的に協力してくれることがよくあった。だが、これは本当にだめなやつだ、という気がした。
「まあ、このCってやつのことは聞いておいてやるよ。あんまり期待するな」
不破は、ランチを食べ終わって、先に立ち上がった。僕らはまだ半分残っている。刑事は早食いだというが、本当にそうだ。
不破は伝票をひかりさんに渡して、領収書を、と言った。どうやら一応おごってくれるらしい。
「じゃあな。あんまり変なヤマに首突っ込むなよ」
カラン、というベルの音とともに、不破はボストンを出て行った。残された僕らは、黙々と残りのランチをやっつけた。食べ終わるころ、またボストンのドアベルが、カランと鳴った。
意外な人物が入ってきた。見覚えのあるコートを着ている。あ、と思った。
田村だ。心霊写真の件で、ヤクザ相手にうまく立ち回ろうとして失敗し、松浦に監禁されて酷い目にあった情報屋。あれ以来だ。どうやら松浦とのことはなんとか穏当に終わったらしい。
「やあ。いま小川さんに挨拶してたんだ。不破さんが来てたらしいな。君らだけで、よかったよ。あの人は苦手だから」
「お前、あのあと大丈夫だったのか」
「まあな」
田村は僕らのテーブルの向かいに座った。
「怪我は治ってたんだが、精神的にちょっと参っててな。ようやくまた、ライター活動を再開しようという気分に、なってきたところだ」
「ライターねぇ」
師匠はバカにするような口調で、ふんぞり返りながら水を飲んだ。
田村は、目が落ち窪んでいて、陰鬱そうな顔をしていた。あのときは、腹を刺されて重傷を負っていたからか、と思ったが、元からそういう顔立ちらしい。
「西沢に気をつけろよ」
田村がボソリと言った。
「西沢?」
「石田組のチンピラだ。会ったこと、あるだろ」
「ああ、あいつか」
「あいつは、ただのガキじゃねぇ。爪を隠しているぞ。石田の親分の一人娘をコマしていて、上を狙っている。松浦の寝首をかこうとしているって噂だ」
「噂ねえ。ヤクザに詳しいんだな、あんだ」
師匠の嫌味を、そう受け取らなかったのか、田村は神妙な顔で頷いている。
「なんでその西沢なんてのに、気をつけなきゃいけないんですか」
ちゃんと聞いたほうがいい気がして、師匠に代わって僕が訊ねる。
「松浦が、『オバケ専門』の探偵女にご執心なのを、知っているからさ。上を目指すのに、目の上のタンコブになっている松浦を叩くには、そういうネタを利用するのがヤクザってものだ」
田村の言葉に、師匠が気色ばんだ。
「うっせえよ、情報屋ァ。なにをてめえ、勝手に嗅ぎ回ってんだ」
「……そう怒るなよ。これでも、松浦とのことに巻き込んだのを、悪いと思っているんだぜ。わりと真剣に心配してんだよ」
田村は苦笑しながら、ボソリと言う。師匠は硬い表情のまま、彼を睨み続けている。
「ほっとけ」
僕は、師匠のその態度に、なにか複雑な思いを抱いていた。それは松浦というあのヤクザの存在が、師匠のなかで大きくなっているのを、感じていたからなのかも知れなかった。
その日の夜、謎のクスリCについての情報が、意外なところから舞い込んできた。僕は師匠に呼び出されて、一緒にそこへ向かった。
『写真屋』のマンションだ。僕は先日ちょっとしたことがあって、そこには正直入りづらかったのだが、仕方がない。何食わぬ顔で師匠と一緒に彼の部屋を訪ねた。
「本当だろうな、写真屋」
師匠はドカドカと、『写真屋』天野の部屋に上がりこむと、その辺にちらかっていた小物を、ガシャガシャと勝手にどかして座った。
「あ、ああ」
天野は僕の顔を見ると、少しビクリとしたが、すぐに視線をそらした。
「こういう仮面か」
師匠はそう言って、天野に写真を見せた。白い仮面を被って、なにか演技をしているような人物の写真だ。劇団くじら座の稽古風景のように見えた。僕の視線を見て、師匠は付け加える。
「一昨日だったか。またくじら座の稽古場に乗り込んでいったんだ。例のクスリの売人に関わりがあるかも知れないからな。でも、どうも望み薄だな。やっぱり副座長の吉崎も含め、なにも知らないみたいだった。座長の達樹蓮(たつき・れん)というやつがくさいが、あいかわらずつかまらない」
天野は写真を見て答えた。
「似てると思う。もっとこう、縁取りとかあって、不気味な仮面だけど」
「で、お前はそいつがやってる、変態パーティの会員なのか」
「『毒を飲む会』だよ。ひ。会員といっても、何回かしか、参加してないけど」
毒を飲む会? 聞いただけで危なそうな、アングラな響きだ。
「不定期で集まって、いろんな毒を、飲んだり、調理して食べたりして、楽しむんだ」
「そんなことしてなにが楽しいんだ。自殺志願者の集まりなのか」
「実際には致死量ほどは摂取しないよ。ただ、珍しい毒や歴史的な背景のある毒を。ひ。主催者の薀蓄を聞きながら摂るのさ」
「たとえばどんな毒だよ」
「砒素とか」
「本当に毒じゃねぇか」
「だから、ひ。ヤバイんだ。即死はしなくても、常連の連中は相当内臓とか壊れてるよ。たぶん。ひ。死んだやつもいるはずだ。そんな、薬事法とか、いろんな法律に違反してる、非合法な集まりだからね。会員になるには、ほかの会員の紹介がいるんだ。僕は知り合いのアングラ仲間から聞いて、紹介してもらった。ひ。最初は、人が死ぬところが見られるんじゃないかと期待してたんだけど。参加を続けてると、こっちまで死にそうだから、ひ。怖くなってね。行かなくなった」
「その主催者ですけど」
僕が口を開くと、天野はビクリとしたが、すぐに平静を装って、「なんだい」と言った。
「その人が、こういう仮面を被っているんですか」
「そうだよ。名前は知らない。みんな主催って呼んでる。大時代的な黒いマントを着ててね、まるで怪人二十面相の世界だ。でもそれが不思議と似合ってるんだ」
「探している売人に、似てるな」
師匠がボソリと言う。
「でも売ってるやつは、アニメの仮面を被ってたって話ですよ」
「いや、あのあとも何件か別の購入者の話を聞けたんだが、白くてのっぺりした仮面だった、っていう人がいてな。気になってたんだ」
それでは、その主催という人物は、白町でCを売っているという人物の目撃例と、合致している部分があるようだ。それにしても、この20世紀も終わりに差し掛かっている時代に、ずいぶん古風な怪人スタイルだ。いや、そういう怪人へのカリカチュアと言うべきなのか。
「ほかの会員もみんな仮面を被って参加するんだ。ひ。だからみんな、ほかのメンバーの顔を知らない。名前も偽名で参加するから、ひ。だれがだれなのかは、ほとんどわからない」
「みんなこんな仮面ですか」
「いや、会員の仮面はいつも、会場の入り口で配られるんだ。口から下が開いていて、飲み食いできるようになっている。ひ。ホストの主催だけが、口まで覆われた仮面を被っている」
「ふうん」
師匠は腕組みをして唸っている。
「で、どこでやってんだ、その変態パーティは」
「『毒を飲む会』だよ。会場は決まってない。たいてい、元バーがあったところみたいな、どっかのビルの地下とかでやってる」
「開催の情報はどうやって知るんだ」
「メンバーのところに、手紙が届く。こうやって」
天野は机の引き出しから、手紙を取り出した。住所と日時だけが記された、簡素なものだ。これじゃあ、なんのことかわからない。差出人も書いていない。
「いつもこの手紙なんだ。それでわかる」
手紙は、黒いくねくねとした模様で、独特の縁取りがあった。
「会費は」
「そういえば取られたことないな。主催が、趣味でやってるんじゃないか。人を毒殺したい趣味と、毒殺されたい趣味の、需要と供給だよ。金には変えられないね」
狂ってるなあ。
師匠はため息をついたあと、手のひらを打った。
「よし、私たちをそこに紹介しろ」
「えっ」
天野と僕の声がハモった。
「お前、まだ会員なんだろ。私とこいつが参加できるように、紹介してくれ」
やっぱりそうなるか。話の流れで、覚悟していたこととはいえ、少々、というか、かなり気乗りしなかった。嫌な予感しかしない。
「もう関わりたくないんだけど」と渋っている天野に、師匠は「な?」と言って、札を何枚か握らせていた。
「うーん、しょうがないな」
天野は、その札よりも、師匠の手の感触のほうに喜んでいるように見えた。
「電話番号は聞いてるけど、伝言サービスみたいだ。用件を伝えてから、折り返し連絡があるまで、ちょっと待ってもらうよ」
「たのむよ、天野チャン」
師匠は揉み手をしていた。
その次の日、天野から連絡があった。
「会員に空きが出たから、OKだってさ」
空きが出た、ということの意味を、できるだけ考えないようにして、僕らは5日後の、『毒を飲む会』に、参加することになったのだった。
5 いつもそれで赤点だったのね
京介さんから聞いた話だ。
高校1年の12月のことだった。
寒いのは好きじゃないので、毎年この時期はつらい。まして高校生にもなって、制服がスカートなのが納得いかない。ジーンズを穿いて登校したい。そう言うと、クラスメートの高野志穂は、こんなかわいい格好できるのは、いまだけだよ、と妙にババくさいことを言った。
気安くなるにつれて、志穂からは、どんどん説教じみたことを言われるようになってきたのだが、そう嫌でもなかった。そのくらいで、ちょうどいいのかも知れない。私たちの関係は。
夏休み気分を引きずったまま、気がつくと2学期も終わりに近づき、冬休みが迫ってきていた。それはつまり、学期末試験が近づいているということでもあり、クラスでも、休み時間にノートを見る子が増えてきた気がする。
私は、あいかわらずクラスにはなじめなかったが、それなりに女子高生としての日々を送っていた。
その、学期末試験も間近、というこの時期に、校長の発案で、タイムカプセルを校庭に埋めるというイベントが催された。学校創設何十周年だかの記念でだ。そこで、私たちには、『未来の自分への手紙』を書いてそれに入れる、というミッションが下された。
小学生じゃあるまいし、高校生ともなれば、私たちはもう大人だ。そんな手紙なんか書きたくはない。みんなしらけていたが、校長や一部の教師がノリノリで、やけに張り切っている。ゲンナリだ。
「ちひろちゃん、タイムカプセルの手紙、もう書いた?」
教室で志穂に訊かれて、首を振った。
「まだ」
「私、書いたよ。なに書こうか迷ったけど、やっぱり将来の自分が見たときに、元気が出るようなこと書いたほうがいいかなって思って、応援メッセージにしたよ」
「おまえは、真面目だな。生徒の鑑だよ」
そんなやりとりをしているとき、担任のザビエルに声をかけられた。
「このあと、放課後、ちょっといいか」
「あ、はい」
なんだろう。私は、最近煙草を吸った場所のことを思い出そうとする。またバレたのだろうか。
ザビエルが去ったあと、志穂が私の制服に鼻を近づけて、スンスンと嗅いだ。
「なんだよ」
「また煙草じゃないかな、って」
「今日はまだだよ」
そう言うと、志穂は膨れていた。
そして放課後、職員室でザビエルと向かい合う。まわりに、ほかの教師はいない。
「なんですか」
「いや、ちょっと聞きたいことがあってな」
そう言ったきり、ザビエルは話しにくそうにしている。私のことだとすると、煙草よりも深刻そうだ。そんなにまずいことをしただろうか、と少し不安になる。
「あー……。その、なんだ。最近、学校でクスリの噂を聞かないか?」
「クスリ?」
それはたしかに、煙草よりも深刻だ。しかし幸いなことに心当たりはなかった。
「やってないですよ、私」
「いや、お前じゃなくて、まわりでな。どうだ」
「さあ。聞かないです」
「そうか……」
ザビエルは腕組みをしてため息をついた。
「どうして私に?」
「お前は口が堅いからな。ほかの生徒にこういう話をすると、噂が10倍になって広がってしまう」
それはたしかにそうかも知れない。だが、口が堅いからこそ、仲間を売らない、という可能性もあるはずだ。それをあえてザビエルに指摘するほど、私は間抜けではなかったが。
「だれかやってるっぽいんですか」
「いや、最近このあたりで、なにか妙なクスリが流行ってるっていう話を耳にしてな。うちの生徒にも広がってやしないかと、不安なんだよ」
ザビエルは生徒指導の担当でもないのに、放課後や休日にゲームセンターや盛り場を1人で回っては、発見した学校の生徒に説教をして帰らせる、という活動をずっと続けていた。実に迷惑な教師だ。私も捕まったことは、一度や二度ではない。
「妙なクスリって、どう妙なんですか」
ザビエルの微妙な言い回しに違和感を覚えて、訊ねてみた。
「うん?よくはわからん。実物も見てないし。ただ、いわゆるドラッグじゃないみたいなんだ。気持ちよくなるとかじゃなくて、変なことが起こる、みたいなそんな噂を聞いた」
ザビエルはそう言ってから、しまった、という顔をした。私が、口が堅いだけではなく、占いなどオカルティックなことが好きな生徒だ、ということを思い出したらしい。その私の興味を引くような言いかたをして、やぶ蛇になってしまったんじゃないか、と思ったのだろう。
「話は終わりだ。もう帰っていいぞ」
そう言って、ぷい、と横を向いてしまった。
「はあい」
「返事は、はい、だ」
ザビエルから解放されて、私は思った。ご期待にそわなくちゃいけないかな、と。
次の日、私は別のクラスの吉永という子のところへ行った。
春にいろいろあってから、多少親しくなった子だ。彼女は他校の不良とつるんでいて、ドラッグを持っていたことがバレて、停学になっていた。戻ってきてからは、心を入れ替えたように勉強に打ち込んでいるらしい。元々賢い子らしいので、2学期の成績では私はかなり水を開けられそうだった。
「妙なクスリ?」
「そう。なんか、噂を聞かないかと思ってさ」
「さあ、知らないなぁ。ていうかあたし、もうそういうのやってないし」
「いや、それはわかってるんだけど」
「あ、そういえば、あれか。ジュンちゃんが言ってたやつかな」
「ジュンちゃんって、不良仲間だった子だろ」
「そういう言いかたしないでよ。幼馴染だったんだから。いまでも友だちだよ。お互いちょっと距離は置いてるけど」
「悪い、悪い。で、そのジュンちゃんがなんて?」
「なんかね、夢が変わるドラッグがあるって」
「夢が変わる?」
「そう。なんか水みたいなやつで、全然体に悪そうじゃないのに、飲むだけで、そんなちょっとした遊びができるんだってさ」
「ふうん」
やはり興味をそそられた。
「どこで手に入れるんだ」
「なんだっけなぁ。たしか白町の路地で売ってるとかなんとか。ああ、そうそう。千円で買えるらしい」
「安いな」
それならお小遣いで買えそうだ。
「クスリに興味あんの?」
「いや、別に」
「やめたほうがいいよ、クスリなんて。いいことないよ。絶対」
体験者からそう言われると、そうなんだろうな、という気になった。でも、水みたいなものなら、いいんじゃないか、と自分に訊いてみた。すると、私のなかの悪い私が、煙草のケムリを吐き出しながら、『ぜひもなし』と言った。よくわからない言葉だったが、私はそれを好意的に解釈することにした。
その次の日が、タイムカプセルを埋めるセレモニーの日だった。私は、結局未来の自分への手紙を、白紙で出した。自分に言いたいことなど、特になにもなかったからだ。私はやりたいようにやって、やりたいように生きていくし、未来でもきっと、やりたいようにやって、やりたいように生きているんだろう。
みんなの手紙を腹に詰め込んだ、銀色の巨大な球体が、校庭の隅に埋められていくのを見ながら、私はなんの感慨もいだかなかった。
その日の放課後、私は早く帰って試験勉強をするつもりが、なんとなく街をブラブラして、気がつくと雑貨屋などに吸い込まれていた。現実逃避というやつだ。
その雑貨屋で、意外な人間に出会った。間崎京子が、制服姿で猫の柄の便箋を手にとって、しげしげと眺めているのだ。まわりの中学生が、ひそひそと彼女のほうを見ながら話をしている。『モデルじゃない?』『足ながーい』などと言って。
間崎京子は私よりも背が高く、スラっとして、ショートカットの似合う子だ。だが、そのスタイルよりも、切れ長で、黒目がちな瞳の、妖しい煌きのほうが印象的だった。大都会ではないこの辺りでは、探してもちょっと見つからないような美貌だ。
その間崎京子が、私に気づいて、声をかけてきた。
「あら、山中さん。あなたも試験勉強はもうバッチリなの?」
会って早々、この嫌味だ。本当に小憎らしいやつだ。
「そーだよ。あとは答案に間違えないように名前を書くだけだ」
「あら、いつもそれで赤点だったのね」
「うっせぇ」
これでも、仲は良くなったほうなのだ。会ったばかりのころはもっとギスギスしていた。間崎京子のほうが、ずっとちょっかいを出してきていて、私はそれにキツい対応をしてきたつもりだった。それが、先月招かれた京子のお誕生日会で、いつも冷静沈着でクールな彼女の、隠された苦しみを知ってしまい、私もちょっと彼女への接しかたが変わってきた。
そのとき、彼女からまるで憐れみのように差し出された手を、私は拒否した。しかしそれは、いまでは、あの子なりの、ただ友だちになって欲しいという、不器用な意思表示だったのではないか、という気がしているのだ。
油断のできない相手ではあったが、私も、大人だ。それなりにつきやってやろうじゃないか。そう思っていた。
「京子。タイムカプセルは、なに書いたんだ」
嫌味のつもりだった。間崎京子が、未来の自分に向けて、手紙を書く!これはきっと内容にかかわらず、恥ずかしいことに違いない。ニヤニヤしていると、京子は平然と答える。
「短歌を書いたわ」
「短歌?」
あれ。ちょっと雲行きが怪しい。なんか、かっこいい気がする。私の白紙よりも。
「あなたは?」
「私は……。どうだっていいだろ」
なんだか、白紙で出したことを、言い出せない気分になってしまった。
「短歌ってどんなだよ」
京子は、フフフ、と笑うと、猫の便箋をかかげ、その上に、指ですらすらと文字のようなものを書いた。
「くずし字でね、全部繋げて書いたの。最後の文字だけ残してね」
「残して、ってのは、なんだよ」
「ちょっとした遊びよ」
京子は楽しそうに笑っている。一見すると、妖艶な美女が、相手を蔑んでいるような笑いだったが、付き合いが長くなってくると、それが単に楽しそうな笑いなのだとわかってくる。もっとも、一周して、騙されているのかも知れないが。
「最近、私の占いでね、良くない結果が出るのよ」
「良くないって、どんな」
「私自身の運命よ。たゆたっているわ。生と死の狭間で」
京子は真剣な顔だった。ただ事実を告げているような、静かな声で。
「この街でひそかに進んでいるカタストロフィと、なにか関係があるかも知れないわね」
そのころ、カタストロフィといえば、ノストラダムスの大予言が流行していたので、オカルト界隈ではよく耳にする言葉だった。それが、京子の口から出ると、なんだか変な気分だ。
「なんか、前にもそんなこと言ってたな。なんなんだ、そりゃあ」
「さあ、私もわからないわ。未来は、私にもわからない。でも、ちょっとしたおまじないを試してみたの。それがその短歌よ」
「おまじない?」
「ええ。紙に、ボタン電池を張って、ある薬品を塗って、それから別の薬品を溶いた墨で短歌を書いたのよ。最後の文字が前の文字とひと筆でつながれば、発火するようになっているの」
いきなり発火なんていう単語がでてきて、聞き間違えかと思ったが、どうやら本気で言っているらしい。
「私は最後の文字はつなげていない。でも、そこでおまじないをかけたのよ。私の命が尽きるとき、その文字がつながり、辞世の歌が完成するようにと」
「それをタイムカプセルに入れたのか」
「そうよ。あらかじめ校長先生にカプセルの大きさと、手紙の総量の推計を見せてもらって、計算しておいたの。かなり大きいカプセルだったから、酸素が尽きるまでに、ほとんどの手紙が延焼してしまうはず」
京子はニコリと笑った。本人は悪戯っ子のような笑顔のつもりだろうか。私には悪魔的ななにかに見えた。
「お前、なんてことすんだよ」
「どうせみんな、あんなもの書きたくなかったんでしょう。私も、自分の死後に続いていく他人の未来には、興味がないわ。すべて燃えて、あとかたもなく消えてしまえばいい」
「そのおまじないとやらが、本当に実現すると思ってるのか」
「ええ。私は、そう信じている。だから、あのタイムカプセルはいま、続いていく未来と、消滅する未来とが重なっている状態よ。それが、私の運命とともに、たゆたっている」
ああ、そうだ。こういうやつだった。こいつは。私は額を押さえて、ため息をついた。
「そういえば、山中さん。昨日、吉永さんになにか訊ねていたらしいわね」
急に話題を変えられて、めんくらった。なんで知ってるんだ、というツッコミの前に、答えていた。
「クスリのことで、ちょっとな」
「あら、面白そうね。私にも教えてくださらない?」
私は、京子をじっと見つめる。巻き込んでやろうか、と思った。その次の瞬間、よせよせ、ろくなことにならない、という思いもわいてきた。
思案していると、私のなかの悪そうな顔をした私が、キセルで煙草を吸いながら、また、『ぜひもなし』と言った。
なんだかその響きが面白くて、「ぜひもなし」と呟いた。
すると京子は、「あら、大河ドラマね。私も見てるわ」と言うのだ。
しまった。それで頭にこびりついていたのか。
有名俳優が演じる武将の決め台詞だった。私は恥ずかしくなってしまった。
「教えてくれるのね」
しかたがない。そういう意味の言葉だったはずだ。京子に、知っていることを話した。
「行ってみましょうよ。白町に、今夜にも」
京子はやけに乗り気で、そんな提案をしてきた。
「私も聞いたことがあったの。なんだか変なお面を被っている人が、売っているらしいわ」
「お前も知ってたのか」
「ちょっと興味があったけど、1人で行くのは怖いから、山中さんが一緒なら安心よ」
京子は、剣道の素振りをする真似をした。
「木刀なんか持っていかないぞ。そんなもの持ち歩いてたら、一発で補導される」
「冗談よ。でも、よろしくね」
そんなやりとりをしていると、気がつくと私は、間崎京子と夜の白町を探索することになっていた。家で真面目に試験勉強をするべきなんじゃないか、と思ったが、むしろそこから逃げるために、京子の提案を受けたのかも知れない。
はあ。まあ、しかたがない。ぜひもなし、というやつだ。
その夜、駅前の噴水のところで待ち合わせて、京子と合流した。もう12時近いので、待ち合わせスポットの噴水前も人影はまばらだ。
私は、いつも着ているジーンズに、赤いスカジャンという格好。京子は、グレーとホワイトのチェックのコート姿だった。こういう大人びた服装でいると、容姿もあいまって、まるで芸能人のようだ。私も、もうちょっとマシな格好してこなきゃ、悪かったかな、と一瞬気後おくれしてしまった。
「いきましょ」
いきなり京子は私の腕をとって、組んで歩こうとした。
私は無言でそれを振り払う。
「もう、ケチね」
なにがケチだ。
並んで歩いて、繁華街のほうへ向かう。学生向けのカラオケ屋などが並んでいる通りを抜けると、酔っ払いたちがうごめいているゾーンに入る。この辺りからが白町だ。私も昼間には通ることがあるが、この時間帯は高校生にはあまり縁のない空間だった。
「あれあれあれ。オネエちゃんたち、美人だねぇ。おっちゃんたちと飲もうよ」
そんな酔っ払いの、うっとおしい呼びかけを無視して歩き続ける。
「私、こういう夜遊びってはじめて。山中さんと一緒にいられて楽しいわ」
「うそつけ」
「本当よ」
「センコーに見つかったらアウトなんだぞ。もっと注意しながら、シャンと歩けよ」
私はいつにも増して、京子を邪険に扱っていたが、半分は照れ隠しなのではないか、と自分でも気づいていた。こんな美人な友だちと一緒に街を歩く、というのは、たぶん男性ならずとも、虚栄心を満たされるものなのだろう。私のなかにもたしかにそんな気持ちがあった。それは、胸をドキドキさせ、よくわからない緊張を私のなかにもたらしていた。
ヨーコとも、こうして街を歩いていたことを思い出す。なんの気負いもなく、じゃれあいながら、笑って歩いていた。あのころのことを、ふと懐かしく思った。
そうして、夜の繁華街を慎重に散策していると、ふいに、京子が立ち止まった。
「いるわ」
居酒屋の横にあった、狭い路地に視線を向けている。私は京子の前に出て、目を凝らした。
建物ぞいに、大きなコンテナがいくつか積み重ねられていて、その奥に人影があった。顔のところに、なにかお面のようなものをつけている。
「ハロー?」
私は小さな声で、そう呼びかけながら、様子を伺った。
人影は立ったまま、こちらを向いている。私は路地に足を踏み込み、近づいていった。
「千円で、売ってる人?」
その人物は、黒いマントを着ていた。見るからに怪しいやつだ。顔には、お面というか、白くてのっぺりした仮面を被っている。その仮面には、黒い波のような縁取りが描かれていた。えたいの知れない悪意を感じる、不気味な仮面だった。
仮面の人物は、マントの下から、小さな瓶を取り出した。
あれがそうなのか。
私は、ポケットのなかの財布から千円札を取り出そうとしたが、その前に、間崎京子が千円札を2枚、仮面のほうへ突き出していた。
「2人分、くださらない?」
仮面は、一歩前に進むと、京子の手から千円札を受け取り、かわりに2つの小瓶を両手にそれぞれ持って、差し出した。無言のままだった。
私たちは、頷いてそれを受け取る。
取引は終了した。拍子抜けするほど、あっさりしている。こんなものか。ドラッグの売買も、あんがいこんな簡単なものなのかも知れない。
仮面の人物に興味はあったけれど、ひとまず今日の目的は達成したので、なにか変なことに巻き込まれるまえに、帰ろう。そう思ったときだった。
京子が、仮面に話しかけた。
「あなた、劇団くじら座の人かしら」
劇団?そういえば、チラシや看板を何度か見たことがある。白い仮面を被っている演劇の看板だ。だが、目の前の仮面はそれとはちょっと違うようだ。
「それとも、毒を飲む会の人かしら」
暗い路地の奥で、仮面はかすかに揺れている。
「なんだよ、それ」
京子の服の端をつん、と引っ張る。
「船医をしている私の父が、日本にいたときに言っていたのよ。怪奇趣味のあるあの父よ。この街に、毒を飲む会という変な集まりがあるらしいって。仮面で顔を隠して、毒を飲む、耽美な会だって。これは、その会となにか関係があるのかしら」
京子は仮面から買ったばかりの小瓶をかかげる。私も小瓶を見てみたが、透明な液体で満たされている。毒、と聞いて、持っているだけで気味が悪くなった。
「私、どちらも興味があるのよ。劇団くじら座の公演は、去年一度見たわ。タイトルは『変身』だったかしら。いつか夢で見たような、不思議で、引きつけられるお話だった。あれを書いた脚本家にお会いしたいと思っていたの。脚本は座長さんだそうね。くじら座という名前も好きなの。座長さんはいつも仮面を被っていると伺ったわ。あなたがそうじゃなくて?」
京子の言葉に、仮面はなにか小刻みに震えているようだった。
笑っている?
私がそう思った次の瞬間、仮面から、不気味な音が聞こえた。
《毒を飲む会に、ご興味がおありで?》
一瞬ゾッとしたが、すぐにそれがボイスチェンジャーによる声だと気がついた。仮面の下に仕込んでいるのだろうか。
京子も、驚いた顔をしたが、すぐに表情を戻して、訊ねた。
「ええ。あなたが関係者なら、一度参加させていただけないかしら。まさか、すぐに毒殺されるわけではないんでしょう?」
「おい、よせよ。こんなうす気味悪いやつに」
「いいじゃない。こんな子どものなかで流行っているようなクスリよりも、ずっと面白そうでしょ」
仮面は値踏みするように、京子と私とを、交互に見た。そしてまた不気味な声を出す。
《いたって健全な会ですよ。毒を飲むといっても、希釈して、毒性を抑えてありますから。ときに、リシンやテトロドトキシンなどの猛毒を摂取するという、貴重な体験をしていただいたり、またときには、ソクラテスの刑死に使われた毒ニンジンや、神明裁判に使われたカラバル豆など、歴史的な赴きの深い毒物を口にすることで、人類史と毒物の関係に思いをはせていただく。そういう会なのです》
「気持ち悪りぃ」
私の正直な感想が、口をついて出ていた。自殺願望のある、変態の集まりじゃないか。進んで毒を飲むなんて、手首を切る自傷行為と、なんら変わらない、と思った。
「私も参加できるのかしら」
《本来ならば、会員の紹介が必要なのですが、あなたなら、特別に、ご招待いたしましょう》
仮面は、丁寧に腰を折り、手を胸にあてて、挨拶をした。
《かの五色地図をお持ちの、あなたならば》
その言葉を聞いた瞬間、私も京子も、ハッとしてあとずさった。
耳鳴りがした。超音波が叩きつけられているような感覚。
京子の着ているコートの胸元から、青い光が漏れている。そこから、ヒィーン、という、なにかが回転するような、甲高い異音がしていた。
京子は胸元を押さえる。顔面は蒼白だ。
「あなた、なに者なの」
声がかすかに震えている。京子のそんな余裕のない姿は、はじめてだった。
《それがわかるまで、今夜、だれも寝てはならぬ》
仮面はゆっくりと顔を上げながら、そう言った。黒い縁取りが、うごめいているように錯覚して、私は目をこする。
「どういう意味だ」
私は、京子と仮面のあいだに立った。京子を庇っていることに、自分でも気がついていなかった。
《いえ、今度の公演のセリフですよ。台本のとおりの質問をされたのでね、つい。お気になさらないでください》
「やっぱり、くじら座もあなたが?」
京子が私の肩に手を置いて、隣に並んだ。胸を押さえたまま、気丈に声を張っていた。
《ええ。座長を務めています。偽名ですが》
私は、仮面の首を見ていた。身長は私と同じくらいだが、声はボイスチェンジャーだし、男か女かは、よくわからなかった。喉仏がはっきりとあれば、男だとわかるのだが。仮面の下から布が垂れていて、喉のあたりを覆っていたので、それも不明だった。
《毒を飲む会の会合は、2日後にございます。招待状をお渡しいたしましょう》
仮面は、懐から封筒のようなものを取り出し、私たちの前に差し出した。
私は、挑発だと感じたが、それを手に取るのを躊躇した。しかし、京子はフッ、と笑うと前へ進み、封筒を受け取った。
またあとずさって、私の隣に立つと、その場で封を開けて、なかを見た。私も、覗き込んだが、日にちと時間と場所が書いてあるだけのようだった。
京子は、封筒を元に戻すと、右手に掲げるようにして持ったまま、言った。
「参加させていただくわ」
その次の瞬間、封筒が黒い炎のようなものに包まれて、燃え上がった。そのまま京子の手のなかで、封筒は灰になり、サラサラと砂のように消えた。
私は驚いて隣の京子を見つめた。
こいつがやったのか。
ゾクリとした。やっぱりこいつも、私たちみたいな普通の人間ではない、ということを再確認する。
《お1人では、寂しいでしょう。お友だちもご一緒にどうぞ》
仮面がそう言って私を見る。京子も私を見ている。
「山中さん」
《どうぞご一緒に》
おいおいおい。
どうしてそこで、2対1みたいになるんだ。
この異常なやつらに挟まれて、私は心臓がバクバクしていた。
どう考えても普通じゃない。毒を飲む会?おかしいだろ、そんなの。
京子が、潤んだ瞳で私を見ている。美人だなぁ、こいつ。違う。どうして、私がそんな変な会に。
「ぜひもなし、ですものね?」
思わず頷きそうになったが、さすがに思いとどまる。だが、次に、京子が私に、懇願するように手を伸ばそうとして、躊躇し、その手を引っ込めたとき、ああ、と思った。
どうしても、こうなるのか。私は、あの孤独な館で、京子から差し出された手を拒否したときから、こうなる運命だったような気がしてくる。いや、お友だちになってあげると言われたあの日から、そうだったのかも知れない。
観念して、「わかったよ、わかった」と、やけ気味に言う。
「ありがとう」
京子は嬉しそうだ。
《そのクスリも、試してみてください》
仮面はそう言って、路地の奥をチラリと見た。
《では私はこれで》
私は、手のなかの小瓶を見た。
「毒じゃないだろうな」
仮面は小さく首を横に振った。そして、そのまま路地の奥へ去ろうとして、ピタ、と足を止めた。
《そうそう。くじら座が、お好きだとおっしゃいましたね》
京子が小首を傾げながら、「ええ」と返事をした。
《わたしも好きなのですよ。だから、劇団の名前にしたのです。その名を耳にするたびに、暖かく冷たい感傷に浸れるのです》
ボイスチェンジャーの抑揚のない声が、感傷を語るという滑稽さに、私は「なーにが」と吐き捨てる寸前だった。
しかし、仮面の下から続けて出た言葉に私は凍りついた。
《……かつて、黄道より落ちし、哀れな怪物への……憧憬のために》
白い仮面は、溶けるように闇のなかへ消えていった。足音も残さず。
私の隣で、京子も固まっている。時間が止まったように。私も驚いていた。あの仮面の人物は、なに者なのか。あの館の夜、京子から告白された、彼女にしか知りえないことを、言っていたように思う。
黄道より落ちし、哀れな怪物……。
「京子」
声をかけると、時は動き出し、彼女は「ええ」と答えた。その目は、闇の奥を、うつろに見つめていた。
〈『毒 前編』完〉
『毒』 中編
1 シュレディンガーの猫って知ってるかしら
京介さんから聞いた話だ。
高校1年の12月のことだった。
2学期の期末試験がもうはじまるというころ。私は不本意ながら家で勉強をしていた。どうせいい点は取れないことはわかっているが、やらずにひどい点を取ると、のちのち面倒なことが次々とわいてくるのは、目に見えている。
数学の教科書と見比べながら、自分でノートに書いたことの意味を頑張って解読しようとしていると、普段は気にならない隣の部屋の音が、やけに気になってくる。
ポップスが、かなりの音量で漏れ聞こえていた。
「おい、うるさいぞ」
隣は妹の部屋だ。ドアを開けて怒鳴ると、ベッドに寝転がっていた妹は、「へいへい」と言って、ステレオにイヤホンのジャックを指した。
双子だというのに、妹はなぜか私よりも頭の出来が良く、進学校で知られる地元の公立高校に通っている。妹の高校も期末試験の時期のはずだが、ずいぶんと余裕を見せつけてくれるものだ。実にけったくそ悪い。
私は気を取り直して机に向かった。ようやく調子が出てきて、1時間ほど集中して勉強ができた。
「はあ」
目が疲れてきたので、一息入れようと、伸びをして、冷めてしまったコーヒーを飲んだ。
ふと、机の隅に置いてあった小さな瓶が目に入る。昨日の夜、白町で奇妙な仮面の男から手に入れた小瓶だ。担任のザビエルから、高校生のあいだで流行っているクスリだと聞かされて興味を持ったのだが、いざ実物を手に入れてみると、なんだ、こんなものか、という感想だった。
無色透明で、蓋は白。瓶にもラベルはない。一度、恐る恐る蓋を取って匂いをかいでみたが、無臭だった。もともと、煙草で十分な私は、ドラッグにはたいして興味がないので、良い物だと言われても、試してみたいとは思わない。ただ、『変なことが起こる』という話を聞かされたので、オカルト好きの血が騒いだのだった。
しかしながら、手に入れたときの経緯から、私には警戒感があった。路地で出会った仮面の人物に、一緒にいた間崎京子があれこれ話しかけ、気がつくと、私は京子とともに、『毒を飲む会』という怪しすぎる名前の集まりに、参加することになっていたのだった。そんなやつが千円で売っているクスリを、試してみようという気になるわけがなかった。危なすぎる。
「明日か……」
私は深いため息をついた。明日の夜8時がその集まりの集合時間だった。試験勉強もあるし、バックレようかとも思ったが、私を見つめて懇願する間崎京子の顔を思い出すと、どうにも調子が狂うのだ。
なにかあったら、責任取れよ
私はそんなことを思いながら、しぶしぶ、明日の分も頑張って進めておこうと、教科書を再び開いた。
翌日、すなわち『毒を飲む会』の当日、私は学校の授業の終わりに、生物部の部室に足を向けた。
本気度の高い一部の運動部を除き、この時期みんな部活は休みだ。
「お疲れ~」
と言って、さっさと下校していくクラスメートの流れから離れ、校内のひとけのない廊下を歩いていると、心地よい疎外感に包まれている自分がいる。ほかの人と、違う道を歩くこの孤独が、私の居場所だという実感が、胸に染みついているのだ。だが、この先にいるのも、そんな私と同じ感情を共有しているのかも知れない、そんな子だった。そのことが、私を少し、不安定にさせる。
「京子、いるか」
生物部の部室になっている教室のドアを開けると、間崎京子が机に座って、ひとりで本を読んでいた。今夜、どこで何時に落ち合うか、話しておこうと、待ち合わせをしていたのだ。
京子は顔を上げて、「いらっしゃい」と言った。私はその向かいに腰掛ける。
「本当に行くのかよ」
「ええ。一緒に来てくれるでしょう」
「まあ……。約束はしたけど」
いろいろと言いたいことはあったが、やはり本人を前にすると言葉にならなかった。私は、ハア、と息を吐いて、頬杖をついた。
「危なそうなら、逃げるからな」
「そうね。走って逃げましょうか」
京子はなにが楽しいのか、機嫌がいいようだ。
「あいつさ……。言ってたよな。くじら座のこと」
私の言葉に、京子の機嫌のいい笑顔が消えた。かわりに浮かび上がってきたのは、なにか深い意識をうちに秘めたような、微笑だった。
「黄道より落ちた、哀れな怪物だって」
「ええ」
「お前が言っていた、子どものころの話。あれに似てる」
京子のお誕生日会に招かれた日、私は幼いころに彼女を襲った、不可解な出来事のことを聞かされた。地震とともに、空の星座がみんな変わってしまったという、信じられない話だ。
たとえば、だれでも知っている今の黄道十二星座は、京子が知っていたものとは違うのだという。だから、京子は星占いなんて、くだらないと言っていた。彼女の生まれた11月20日の星座は、くじら座なのだ。
そんな秘密を、私に告げたとき、彼女の目はウソをついていなかった。少なくとも、私にはそう感じられた。それが、彼女が秘めている、だれとも共有できない恐怖であり、悲しみであり、孤独の根源だった。たとえそれが、彼女の妄想の産物だったとしても。
だが、あの仮面の男の意味深な言葉は、なんだったのだろう。占い師の使う、コールドリーディングかなにかだというのだろうか。いや違う。劇団くじら座は、以前からたしかに存在している。
あの仮面野郎は、危険だ。私の直感がそう言っていた。
京子は、持っていた本を閉じて、机の上に置いた。『量子論の世界』という題の本だった。
「山中さん。シュレディンガーの猫って、知ってるかしら」
なにを言い出すのかと思った。
「聞いたことはあるよ。箱のなかの猫が、生きてるのか死んでるのか、開けてみるまでわからない、ってやつだろ」
「まあ、そんな感じね。でもその言いかただと、常識的な発想ね。箱のなかのことがわからないだけで、どっちかの状態であることは、前提としている。ところが、ミクロな量子の世界では、本当に死んだ猫と生きている猫が、重なっていることがありうるのよ」
「重なっている?」
「その前に、まず量子論で有名な、スリット実験っていうのがあってね。縦長のスリットの入った板に、電子銃から電子を打ち出すの。電子っていうのは小さな粒、つまり粒子ね。だから、打ち出されるとまっすぐに飛ぶ。板に当たらず、スリットを抜けると、その先にあるスクリーンに、電子が当たった白い点がつく。何度も無作為に打ち出していると、スリットと同じような形をした、細長い白い点の塊が、スクリーンに現れるの。これは当然ね。電子は粒子だから、まっすぐ飛ぶのだもの」
「なんだ。物理学の話か。おまえ、生物じゃなかったのかよ」
「興味があるから、勉強したのよ」
京子は澄ました顔で言う。
「次に、スリットが2つ入った板で同じことをしてみるの。2重スリット実験と呼ばれているわ」
京子は立ち上がって、黒板に図を描いた。
「電子銃から打ち出された電子は、やっぱり一定の割合で2つのスリットを抜けて、スクリーンに向かう。すると、スクリーンにはどんな模様が現れるか、わかるかしら」
京子に、チョークを渡された。
私は、チョークのあの、皮膚にガサガサする感じが嫌いなので、正直受け取りたくなかったのだが。
しかたなく、スクリーンだという、四角い囲いのなかに、テンテン、と白いチョークを当てていく。2つのスリットと同じ形をした、点の塊を描いたのだ。そんなことは、わかりきったことだった。
「そうね。それが常識的な答えね。でも、この2重スリット実験の結果は、人類が、そのあたりまえに思っていた常識が壊れていくような、不気味なものだったの」
京子はそう言いながら、私の描いたものを黒板消しでひと拭きして、かわりに、同じものを等間隔に5つ描いた。それぞれ縦長なので、まるでシマ模様だ。
「これが、スクリーンに現れたわ」
「それはおかしいだろ。数もそうだけど、ど真んなかにテンテンがつくのは。スリットとスリットの間の板のところじゃないか。まっすぐ飛んだら、そこに当たるわけないだろう」
「いいえ。これは実際の実験の結果よ」
私は、納得のいかない気持ちで、それでも考えた。
「じゃあ、その電子がまっすぐ飛ぶっていうのが、間違ってたのか」
「すばらしいわね。いい発想よ。山中さんって、物理の成績良かったかしら」
「うるせぇ」
「このシマ模様は、干渉縞と呼ばれているわ。この干渉縞は、波を使った実験で同じ現象が起こることが知られているの」
「波って、あの海の波か」
「そうよ。波は物質そのものというより、エネルギーの伝わりかたね。同じ水がずっと進んでいるわけじゃなくて、水が進んでいくエネルギーを次の水に伝えて、波という形を先へ進めているの。その波は、空間の分布パターンを伝播させる過程で、簡単に言うと、放射状に広がろうとする。だから……」
京子は、またチョークを持った。
「波はスリットを抜けたあと、直進するんじゃなくて、放射状に広がって進む。2つのスリットから抜け出した波は、こうやって、おたがいに放射状に進んで、ぶつかりあう。ちょうど板の真んなかあたりの先では、2つの波がぶつかって、そこが高い波を作るの。そして左の波の山と、右の波のうちの1つあとの山は、やっぱりぶつかって真んなかよりも右側で高い波の山を作る。左右を逆にしても同じね。さらに、2つあとの山でも、その外側で同じようなことが起こる。こうして、高い波の山がスクリーンにぶつかって作るのが、この5つの干渉縞なの。5つというのは、たとえばの話だけどね」
私は図を見ながら唸った。なかなかわかりやすい。こいつは、意外と教師に向いているんじゃないかと、少し思った。
「じゃあ、電子は波だったってことか」
「そうね。そう考えたら、この実験の説明ができそうね」
「なにが不気味なんだ。大げさだな」
京子は、微笑んだ。
「でも、電子は波ではなく、粒子なの。打ち出された1つの粒子が飛んでいるだけなのよ。これは、事実よ。だから、1つのスリットのときには、細長いスリットと同じ形をした線が、スクリーンに現れたわ」
「なんだか、わけがわかんねえ」
「これは、たくさんの電子を電子銃から打ちまくった場合の話よね。だから、電子が波じゃないとしても、同時に左右のスリットから抜けたら、人類がまだ知らないなんらかの性質によって、お互いに干渉しあってシマ模様を作るのかも知れない。そこで、電子を1個ずつ、時間を置いて打ち出したら、どうなると思う?」
「いっこずつ? そりゃあ……スリットが1つのときと同じことが起こるんじゃないか。干渉しあわないんだから」
またチョークを渡されたので、私は黒板に2本の線を描いた。それを見て、京子は怪しい微笑を浮かべる。
「ところが、実験で実際に現れたのは、これよ」
京子は、さっきと同じ5つのシマ模様を描いて見せたのだ。
ちょっと、ゾクリとした。京子が不気味だといった言葉の意味が、少しわかった気がした。
「1つしかないものが、2つのスリットを同時に抜けて、干渉を起こしている。つまり、電子銃から打ち出された瞬間に、粒子だったものが、波のように振舞っているのよ。これはおかしなことだわ。さらに、2つのスリットのそれぞれにセンサーをとりつけて、1つずつ飛ばした電子が、そこを通るかどうかを観測する実験も行われた。電子は粒子という1つのものなんだから、片方が反応すれば、もう片方は通っていないということね。1個の粒子が、同時に2つのスリットを通ることはありえないから。これは、そのとおりの結果が出た。どちらかのセンサーで粒子が通る反応があり、両方のセンサーが反応することはなかった。粒子は、波にはなっていなかったようね」
「なんだかホッとしたよ」
私的にはちゃかして言ったつもりだったが、わりと本心だったのかも知れない。
「でも、おかしいでしょう。だったら、波が描いたような、あの5つの縞模様はなんだったの、という話になるわね。ところが、そのセンサーによるスリットの観測をはじめたとたんに、スクリーンに現れる縞模様が、変わったの。電子が波じゃなく、粒子だとしたときの、さっきあなたが描いた、2つの線が現れるようになったのよ」
「なんだそりゃ」
「電子は、観測されたことで、『2つのスリットを同時に抜けて、左右からお互いに干渉しあうかもしれない』という、可能性を失ったのよ。つまり、飛んでいたのは、いま電子がどこにあるのか、という可能性そのものだったの」
京子の説明は、なんだかもう、科学の分野からかけはなれた世界の話のように聞こえる。
そう。まるでオカルトだ。
「私たちの知っている世界の常識が、電子を含む、量子というミクロの世界では通用しないの。私たちの好きなオカルトの世界みたいね」
私の心理を読んだように、京子は笑ってみせた。
「ミクロの世界では、量子は観測されるまでは、可能性でしかないの。そこにある可能性が高いかどうか、ということしか予測できない。つまり、量子は観測されるまでは、可能性として、複数の場所に多重に存在している。言葉遊びではなく、これは、実験で導き出された、事実よ」
「量子論とやらの主張する、事実だろ」
我ながら気の利いた言葉に、一矢報いたような気になった。京子は「そうね」と素直に頷いた。
「この量子論のミクロ世界の事実を、現実世界に持ってきたのが、シュレディンガーの猫の思考実験よ。細かいことは省くけど、簡単に言うと、1つの箱のなかに、ラジウムと、ガイガーカウンターと、毒ガスと猫を入れる」
「あと、セックスと嘘とビデオテープと部屋とワイシャツと私も入れる」
私のジョークを、なにもなかったようにスルーして、京子は続けた。
「一定量のラジウムが一定時間後にアルファ崩壊して、アルファ粒子を出す確率が、50%だとする。もし、アルファ粒子が出て、ガイガーカウンターが反応したら、毒ガスが噴き出して、猫が死ぬ、という装置になっている。こういう状況を、箱の外で、あなたが見守っている。箱も猫も毒ガスも、現実世界のものよ。常識が通用しない、不思議なミクロの世界の話じゃない。だからあなたは、こう考える。一定時間後に、猫が死んでいる可能性は50%だ。箱を開けてみるまではわからないけど、生きているか死んでいるか、2つに1つだと」
「だから、最初にそう言っただろ。開けてみるまではわからないって話だって」
「いいえ。箱のなかのものでは、アルファ粒子はとても小さい、量子よ。だから、量子論の法則に従うの。量子は、観測されるまでは、可能性として振舞う。一定時間後に、ガイガーカウンターが反応する位置に、アルファ粒子が存在する確率が50%なら、それはそこに存在しない可能性と存在する可能性が、等濃度で同時に重なり合っている状態ということ。どちらか、ではないの。その結果を元に決定される猫の生死も、同じよ。あなたが観測できない箱の密室のなかで、生きている猫と、死んだ猫が、1対1で、重なり合って存在している」
「だから、それはミクロの世界の話だろ」
「思考実験として、ミクロの世界の法則が、マクロの世界に影響する装置を、シュレディンガーが考案したのよ。量子論に批判的な立場でね。そんなこと、現実にあったら、おかしいだろって。だって、実際に箱を開けてみたら、猫は、生きてるか、死んでるか、どっちかなんだから。でも、のちの多くの物理学者の手によって、量子論に基づく実験が進んでいくにつれて、そのミクロの世界の法則が無視できなくなってきたのよ。『神はサイコロを振らない』なんて言って、アインシュタインが納得しなかった、電子のスピンの『量子もつれ』も、実験によって何度も確認されたわ。ミクロの世界なんて言っても、私たちの体を構成する物質も、顕微鏡の倍率を上げて覗いていけば、つまるところ、原子などの量子でできている。この宇宙のすべてのものがそうよ。量子論の法則のなかに、私たちはいる。私たちはみんな、そこにあるかも知れないという、可能性のまま、多重に存在しているのよ。だから……」
京子が歩いてきて、両手を、私の肩に置いた。綺麗な顔が正面に近づき、私はドキリとする。その唇が、なまめかしく開かれる。
「あなたが、観測することで、いま、私は、わたしでいられるの」
顔が、さらに近づいてくる気配を感じて、私は思わずあとずさった。
雰囲気に飲まれて、変な気分になりそうだった。
「だから、なんだっていうんだ」
私は、吐き捨てるように言った。この妙な雰囲気から、逃げ出したかった。
京子は、うふふ、と私には真似できない笑いかたをして、机の上にそのまま腰掛けた。スラリと長い足を組んで。
「プリンストン大学のヒュー・エヴァレットという人が、このミクロの世界の解釈を発展させて、人間にも量子論を適用するべきだと主張したの。観測者もまた、その全身が量子で構成されている存在なのだから。箱のなかのシュレディンガーの猫は、実際に蓋を開けてみれば、死んでいるか、生きているか、2つに1つ。でも、箱をあけて猫を見ているあなたは、だれかに観測されるまでは、『死んだ猫を見ているあなた』と、『生きている猫を見ているあなた』が重なり合って同時に存在していると、考えることができる。いいえ、そう考えなければ、おかしいのよ。れっきとした、事実としてね」
京子の言葉に、量子論とやらの事実だろ、という突っ込みは入れられなかった。なんだか、こいつの言葉が真実のように感じられたからだ。
「これが、エヴァレットの多世界解釈よ。あなたにとってのこの世界は、あなたに観測されるごとに確定されていく、無数の可能性を持ったパラレルワールドでできている。それは重なり合って同時に存在している。そして、そのパラレルワールドは、時の経過とともに、『異なる観測結果に終わった可能性』という枝葉に分かれ、こちら側のあなたにはもう干渉できない、無数のパラレルワールドに分岐していく。その、あなたを含む世界はまた、あなた以外の他者によって観測されるまで、無数の可能性を持つパラレルワールドを構成し、重なり合っている。この宇宙全体が、少しずつ違う、無数の別の宇宙と重なりあって、存在している。たったひとつの量子が、ある瞬間に、広大な宇宙のある一点にあった場合、なかった場合という、偶然によって分岐していく世界。あるいは、誕生の瞬間に、この宇宙が異なる物理定数を持っていたかも知れない、という可能性から生まれる、途方もない数の宇宙。これが理論物理学における、Mltiverse(マルチヴァース)。多元宇宙論ね」
「そんなもの、あるわけが、ないだろ」
「知覚できないことは、存在しないことと同義ではないわ。あなたは、私たちの宇宙と重なり合った多元宇宙が、存在しないことを絶対に証明できない」
「……おまえは、そこから来たってのか」
京子は、イエス、とも、ノーとも言わなかった。
「星座の違う世界という、パラレルワールドは、今のこの私の観測世界とは、異なる分岐の先にある可能性の世界よ。それは、観測され、可能性が閉じられた今ではもう、記憶の保持なんていう、物理的干渉の一切及ばない場所。なのに、私は記憶している。あの星たちを。これをどう解釈していいか、正直よくわからない。もし、多元宇宙世界を作った神様がいるのなら、私は、バグのようなものなのかも知れない」
かすかに浮かべた微笑の表情を変えず、京子は淡々とそう言う。
私なら、どこかで、子どものころの夢だと、割り切るかも知れない。そのほうが、健全だ。そんなだれとも共有できない孤独を、抱え続けるなんて。それは、私の愛する疎外感の孤独とは、まったく違う。私のは、甘えみたいなものだからだ。
「仮面のあいつも、そこから来たのか」
京子は頭を振った。
「そんなわけは、ないわ。もっと、ありえない」
その言葉を最後に、沈黙が私たちを包んだ。
夕暮れが、生物部の部室である教室に迫っていた。差し込む夕陽が、私たち2人の影を長く伸ばしている。
この1年のあいだ、私の身の回りで、不思議なことがたくさん起こった。楽しいこともあったけれど、悲しい思いも、怖い思いもした。それらはどれも、私のオカルト趣味が招いたものだと思い、自業自得なのだと達観していた。しかし、そのどれもが、いまこの目の前で微笑む女と出会ってから起こったのだ、と思うと私は、めまいのようなものに襲われる。
そのアンティーク人形のように整った顔立ちと、スラリとした長身。切れ長の瞳。この唇からこぼれる言葉は、蠱惑的な響きで、私のなかに侵入してくる。
いつの間に、私はこいつとこんなに親しくなったのだろう。あれほど、警戒していたのに。間崎京子という存在が、知らず知らずのうちに、まるで毒のように染み込んで、私をおかしくさせているような気がする。
「もうこんな時間だ」
私の言葉に、京子は腕時計を見た。
「そうね。今夜だから、もう帰って準備しないと」
私たちは、待ち合わせの場所と時間を決めた。鞄に本やノートをしまう京子を見ながら、私は考えていた。
もしも神様ってやつがいるのなら。いるのならさ。そのバグも含めて、世界を作ったんじゃないのか。
運命だよ。おまえの。
京子。
「行きましょう」
先に立って、教室の扉に手をかけたとき、軽いめまいとともに、その扉の向こうに、無数の世界が少しずつ重なり合って、どこまでも続いているような気がした。
2 ケーティではなくてよろしいのね
夜の7時半。私は、駅の西口にやってきた。地下の東西連絡通路の入り口のそばに、街路樹があり、その周りを囲むように設置されている石のベンチに、京子が座っていた。
京子はスリムな体のラインがわかるような、薄手のチェスターコートを着ていた。丸いサングラスをしていて、まるでお忍びの芸能人のようだ。
私は、と言えば、スカジャン姿というあまりに不釣合いだった前回の反省を踏まえ、当たり障りのないダッフルコートを着てきた。去年、背が伸びるのが止まったところで、親に買ってもらったものだ。
京子に手招きされて、隣に座った。石の冷たさが、デニム生地越しに、お尻に伝わる……。かと、思ったが、妙に暖かかった。
見ると、京子の横には缶コーヒーが2つ置いてあった。どうやら、直前までそれで暖めていたらしい。まるで戦国武将の小姓のような気配りだ。
「取ってくださる?」
京子が缶を見ながらそう言った。同じ銘柄だったので、私は、片方を手に取った。ちょうどいい暖かさが、じわりと手に移ってくる。
すると京子は、「ありがとう」と言って、手を差し出した。私は思わず、その缶を渡した。
「あなたもどうぞ」
そう言われて、残ったもう片方を手に取った。冷たい。コールドドリンクだ。そう気づいたとき、京子は、自分の缶を私のものに軽くぶつけ、「乾杯」と言った。
「おい」
なんだ、この子どもじみた嫌がらせは。
私の睨む目を、京子はサングラスで防ぎながら、「いま、あなたは死んだわ」と言った。
「どういう意味だ」
「毒杯パズルよ」
「毒杯?」
「あなたは毒の入った杯を自分で選んだの。2人とも同時に飲み干して、あなただけが死ぬ」
どうやら、冷たい缶コーヒーのほうを毒に見たてているようだ。だが、見た目は同じ缶だ。ハズレを手に取ったのは、完全に偶然だった。
「偶然だ」
そう言ったが、京子は小さく笑う。
「いいえ。もう一度置いてみて」
そう言われて、元の場所に置いた。京子も同じように置く。
「取ってくださる?」
今度は、さっき自分の置いた、冷たいほうを取った。そして京子に渡そうとしたが、その前に、彼女は暖かいほうを手に取り、私の手のなかの缶にぶつけた。
「乾杯」
自然な動きだった。これが最初だったなら、まったく違和感なく、私は缶の蓋を開けただろう。もちろん、冷たくなければだが。そして、本物の毒には温度なんていう、わかりやすい違いはない。
私はあっけに取られて、缶コーヒーを飲みはじめる京子を見ていた。
「毒杯パズルか」
「ええ。どういう集まりなのかわからないから、用心しないとね。毒を飲む会……。こういうこともありうるってこと。気をつけましょうね」
暖かい缶コーヒーと、冷たい缶コーヒーを飲み終わって、私たちは目的地に向かった。並んで歩いて行き、西口から近い、宝冠町というところのアーケード街に入る。
栄えている東口と比べ、こちら側は古い町、という風情だった。年の瀬だというのに、人通りは多くない。前回のように酔っ払いに絡まれることもなく、私たちは、じきに目的のバーの看板を見つけた。
看板は、電飾が切れているらしく、暗いままだ。その看板を回り込んだところに、地下へ降りる階段があった。
顔を見合わせてから、私を先頭に、降りはじめる。暗がりの先に、小さな電灯が灯っていて、扉が見えた。
『売り店舗』という、煤けた張り紙がしてあった。かなり前からこの状態らしい。
本当にここで合っているのだろうか。不安になりながら、ドンドン、と扉を叩くと、なかから、ガチャリと鍵が開いたような音が聞こえた。
向こうに人がいる。
恐る恐る取っ手を捻ると、扉は手前に開いた。薄暗い店内の入り口に、あの仮面の人物が立っていた。白い顔を縁取るように、黒い模様が波打っている。前回見たときとは、微妙に模様が違うようだ。
《ようこそいらっしゃいました》
ボイスチェンジャーを通した声が、仮面の下から聞こえてきた。仮面の下は、厚手のマントだ。体型などはよくわからない。
《これをどうぞ》
スッと、仮面が両手を前に出した。マントの下がちらりと見えたが、黒いスーツのようだった。金色と、銀色をした2つのマスクが、手のひらのうえに乗せられていた。顔の上半分だけを覆うような、マスクだ。目のところは開いていて、その周りに花をモチーフにしたような飾りがついている。映画かなにかでこういうものを見たことがあるような気がする。貴族趣味的だ。
《参加者は、みなさんこのマスクをつけていただくルールになっています。なにぶん、集まりの趣旨が、趣旨なので、お互いが、どこのだれなのかは、詮索しないようにお願いします》
私は京子と視線を交わしてから、金色のマスクを手に取った。京子は銀色のマスクだ。ゴムではなく、紐がついていて、後頭部で括って固定するようになっていた。
「これでいいかしら」
京子がサングラスを外して、マスクをつけた顔を上げる。
《結構です》
「でもあなたは私の素顔を知っているのに、私があなたの素顔を知らないのは、不公平ではなくて」
京子の言葉に、仮面は動揺した様子も見せず、首を振った。
《私の顔には、あまり意味がありません》
仮面の目の部分に開いた穴の奥に、光のない黒目が覗いている。
「どういう意味?」
それには答えず、仮面は、《どうぞこちらへ。みなさんお揃いです》と店の奥へ入っていってしまった。仕方なく、私たちもそれに続く。仮面のうしろ姿を見たが、後頭部は黒い布で覆われていて、髪型もわからなかった。
店内は思ったより広かった。右手側にカウンターがあり、左手側のスペースに、黒いクロスのかかった、大きなテーブルがあった。4人がけのテーブルを、いくつかくっつけてあるようだ、
カウンターにはだれもいなかったが、テーブルには6人の男女が座っていた。
全員がマスクをつけている。私たちのものと似たようなマスクだ。色がそれぞれ違っている。そのマスク越しの視線が私たちに集まっていた。
軽く頭を下げると、仮面が、《コートクロークはそちらに》と、店の奥を示した。店内は暖房が効いている。私と京子は、言われるままに、上着をハンガーに掛けた。
テーブルを振り返ると、仮面が、カウンター側の席の前に立って、《そちらの席に》と言った。テーブルのうち、カウンター側から見て、左手側の奥に、2人分の席が空いていた。
私と京子は椅子を引いて、席についた。テーブルには、それぞれの目の前に、白いコースターだけが置かれている。
《時間ですので、今宵も、毒を飲む会をはじめさせていただきます》
仮面の言葉に、パラパラと拍手が起こる。
《いつもはあまり堅苦しいことは抜きに、ざっくばらんにはじめるのですが、今夜は新しいかたが4人もいらっしゃいますので、簡単に趣旨説明をさせていだきます》
仮面が、コンコン、とテーブルを拳で叩いた。手には白い手袋をしている。その音で、拍手が止んだ。
《ルール1。この会のことを、趣味を同じくしないものに、話してならない》
《ルール2。この会の参加者は、提供されたものを摂取するかどうか、自由意志により判断するものとする》
《ルール3。この会の参加者は、提供されたものにより、どんな状況に陥ろうとも、自己の責に帰することを、あらかじめ承諾する》
《ルール4。主催の正体を勘ぐってはならない》
最後のルールは、定番の笑いどころらしい。常連らしい数人が肩を揺らしている。
《そして、もちろん、お掛けいただいたマスクが示すとおり、参加者の皆様におかれましても、お互いがだれなのか、詮索しないようにお願いいたします》
そして仮面は、私たちと、私たちの向かいの席に座っている2人を、両手で示した。
《さて、参加者からのご紹介により、参加された4人のかた。あ、ここでもどなたからのご紹介かは、伏せさせていただきます。この会では、全員がナナシでは、ご歓談もできませんので、それぞれこちらでお名前をつけさせていただいております。この会だけの呼び名ですので、お気に召さない名前でも、どうかご容赦ください。では、そちらのかた》
仮面は、右手で男性を指した。
《あなたは、キャプリコーナス様。そしてお隣のかたは、パイシーズ様です》
パイシーズと呼ばれた女性が、仮面の下の口元をニヤニヤさせ、キャプリコーナスとパイシーズだとよ、と隣に笑いかける。2人は連れらしい。
《そして、あなたは》
仮面は左を向いて、京子に話しかけた。
《タウルス様。お隣のあなたは、ジェミニ様です》
私がジェミニで、京子がタウルス。ふたご座とおうし座。どちらも星占いの誕生星座ではなかった。
《お気づきのとおり、黄道12星座を順番につけております。退会なさるかたがでますと、その空き番号に新しいかたを入れています。本日の参加者はそのほか4名。全員を含めてご紹介しましょう》
仮面は、自分の右手側から順に名前を呼んでいった。
《まず私の右から、アーズ様》
緑色の仮面をつけた大柄な青年が軽く頭を下げる。彼はおひつじ座だ。
《そして、キャプリコーナス様、パイシーズ様》
キャプリコーナスと呼ばれた男は、まだ若そうだ。大学生くらいかも知れない。緊張している様子で、落ち着きがない。パイシーズと呼ばれた女のほうは、ふてぶてしく手をひらひらさせて、笑っている。それぞれ、やぎ座とうお座だ。
《私の向かいのお2人は、ヴァーゴ様と、この会の最古参のスコーピアス様です》
カウンター側の向かいの席に座っているのは、ヴァーゴと呼ばれた、妖艶な雰囲気を漂わせている赤い服の中年女性と、スコーピアスと呼ばれた、恰幅のいいスーツ姿の初老の男性だった。それぞれ、おとめ座と、さそり座。
《そして、左手側に来まして、奥からジェミニ様、タウルス様、最後に私のお隣、こちらも古くからの参加者、リブラ様です》
私はふたご座、京子はおうし座、そしてリブラと呼ばれた男は、てんびん座だ。彼は痩せぎすで、頭が禿げ上がっている。その貧相な見た目には、貴族趣味的な仮面が似合っていなかった。しかし、ベテランらしく落ち着いた様子で、ゆっくりと会釈をした。
《今夜は以上8名様での開会となります。本日ご欠席の会員様は4名ですので、新しいかたを含めまして、ひとまずのところ、欠番なしとあいなりました》
黄道12星座にちなんだ呼び名のとおり、12人が定員ということらしい。
「あんたは、なんて名前なんだ?」
仮面に向けて、無遠慮な声がかかる。パイシーズとつけられた女だった。
新人の無礼な態度に反応したのか、最古参と呼ばれたスコーピアスがゴホン、と咳払いをする。
急に隣の京子が顔を寄せてきて、耳打ちした。
(あのパイシーズという女性。見たことある気がするわ)
そう言われて、向かいのその顔を見たが、顔の半分を覆うマスクで印象が変わっているせいか、よくわからなかった。ただ、私にもなにか声に聞き覚えがある気がして、記憶をたどろうとしたが、どうにもはっきりとしなかった。
《皆様私のことは主催とお呼びくださいますが、皆様の呼び名に合わせて、ゾディアックとお呼びいただいても結構です》
ゾディアックとは、黄道12星座の黄道のことだ。なるほど、そのままだな。そう思ったが、そこに不吉な響きも感じた。たしか、アメリカの実在のシリアルキラーの呼び名だ。再現ドラマで見たことがある。
「では、ケーティではなくてよろしいのね、ゾディアックさん」
京子が口を開いた。くじら座の英語読みだ。私は、仮面がどんな反応をするのかじっと見ていたが、《ええ》と言って、かるく頷いただけだった。
自分以外に不敵な態度を取っている者が、気に食わないのか、パイシーズがこちらを睨んでいた。
《いま飲み物をお持ちしますので、少々お待ちください》
ゾディアックが、カウンターのほうへ行った。
京子がまた顔を寄せてきて、ささやく。
(ねえ、あの紳士とマダムと、あちらの涼しげなかたの3人は、常連みたいね)
涼しげなかたというのは、リブラと呼ばれたハゲのことらしい。ちらりと横目で見ると、マダムは、隣の紳士と顔を寄せてなにごとか話している。
(そうだな)
(あの3人、名前が並びになってるわよね)
(ええと、マダムがヴァーゴで、ハゲがリブラで、紳士がスコーピアスだっけ。おとめ座、てんびん座、さそり座。12星座の順番だな。初期メンバーなんじゃないか)
(あの紳士は、最古参なのに、第8宮のさそり座よ。名前をつけるのに、途中からはじめたりするかしら)
そういわれてみればそうだ。その意味を考えて、少しゾクリとした。
(それよりも順番の若い人たちは、いなくなったってことか)
(一見、常連の3人が並んでるようだけど、おそらく第6宮のおとめ座のマダムと、第7宮のてんびん座の涼しいかたは、第8宮の紳士とのあいだが、1周あいているのよ)
(そうか。そのあいだも全員、一度欠番になっているんだな)
(いったい、何周目なんでしょうね。私たちは)
京子はおかしそうに笑ったが、笑える気分じゃない。そんなに入れ替わりが激しいということが、どういうことを意味するのか……。
《新しい4人のかたにおたずねします》
ゾディアックがカウンターに、グラスを並べながら言った。
《毒とはいったいなんでしょうか》
「人体に有害なものだよ」
パイシーズが言った。
《そうですね。いい答えです。人体に、というところがポイントです。たとえば、殺菌に使うアルコールは、人体に影響がなくても、細菌や虫などにとっては有害です。さかのぼれば、太古の昔、地球に存在した生命は本来、酸素のない環境で生きる嫌気性生物でした。それが、海中の酸素濃度の上昇にともない、多くの種が絶滅しました。彼らにとって、酸素は毒だったのです。やがて、その大量絶滅のなかから、酸素という毒に耐性をもった生命が誕生し、エネルギー源として使用するようになります。いまでは人間にとって、酸素はなくてはならないものです。私たちにとっては、なんでもないものでも、ほかの生物にとっては、有害かも知れません。どこかに主体を置かないと、定義できないのです。つまり、人体にとって、という定義があって、はじめて私たちは、毒を語ることができるのです。もちろん、ネズミにとって、猫にとって、とそのつど、主体を変えることもできますけどね》
私は、なるほど、と思って聞いていたが、隣の京子は頬に手を当てて、なにげないふうを装いながら、ゾディアックの手元をじっと見ているようだった。
《では、人間にとって、酸素は毒ではないと言えるでしょうか》
ゾディアックは自問するように言った。
《いいえ。純粋な酸素は、人体にとっても有害です。高濃度の酸素を吸引すると、酸素中毒を起こし、意識障害や困窮困難を引き起こすことがあります。大気中においては、21%という濃度でこそ、人体に影響がないだけです。水はどうでしょう。水なんか無害だとお思いかも知れませんが、これも大量に摂取すると、中毒症状を起こします。血のなかのナトリウムイオン濃度を低下させ、頭痛や嘔吐、痙攣、そして呼吸困難を引きこし、死にいたらしめることがあります。つまり、基本的に人体に入る、あらゆる物質は、生物活性を持ち、毒となりうるということです。重要なのは、量なのです。これは、薬においても同じです。皆様は、毒と薬をまったく逆のものだとお考えかも知れません。しかし本来、毒と薬には明確な違いはありません。どちらも人体に入ると、生物活性に影響を与える物質です。人体に有用な効能を持つ薬でも、副作用として害をもたらすものもあります。また、薬として処方されるものは、必ず用量が定められていますが、これを超えて摂取すると、中毒や副作用の危険性が増してしまいます。逆に、毒として、日本でよく知られているトリカブトですが……》
ゾディアックは、そこでカウンターから皿を持ってきた。テーブルに置かれた皿のなかには、乾燥した赤黒い植物片のようなものがいくつか入っている。
《これは毒草として知られ、毒殺事件などを扱ったドラマなどでおなじみですね。トリカブトはアコニチンという物質を含み、摂取すると神経細胞のナトリウムチャンネルを開き、アセチルコリンという神経伝達物質の活動を阻害します。これにより、神経回路の信号が弱まり、呼吸困難や臓器不全などを引き起こして、死に至る、という仕組です。しかし、トリカブトは、附子(ぶし)とも呼ばれ、漢方の生薬としても知られています。成分のアコニチンは加水分解されることで、弱毒化します。昔の人間は、このことを経験で学び、塩水などに漬けて、加熱処理をするなどして食用にしたのです。アコニチンの働きによる、神経伝達物質の抑制は、たとえば、危険な興奮状態にある人を、鎮静化させることもできます。漢方で、この附子(ぶし)は、強心剤としても使われています。このように、毒と薬は表裏一体なのです》
ゾディアックは、《どうぞ、試してみてください》と言って、みんなにすすめた。
《これは、食用の塩附子(しおぶし)です》
シオブシなら昔、田舎の祖父の家で食べたことがある。でも、呼吸困難だの臓器不全だのと聞かされたあとでは、どうも……。
私が躊躇していると、紳士やマダムら常連たちがひょいひょい、と手を伸ばして摘んでいった。そして、匂いをかいだあと、パクリと口に入れた。
「なるほど」
とハゲが咀嚼しながら言った。
紳士は、「私は生姜とまぜた、乾姜附子湯(かんきょうぶしとう)が好きだな」などと言っている。
パイシーズと連れのキャプリコーナスも、恐々としながら、食べたようだ。残された私と京子も、顔を見合わせたあとで、塩附子を手に取った。
口に入れると、辛味が広がり、舌が軽く痺れた。それほど嫌なものではなかった。ああ、こんな味だっけ、と思い出していた。京子は顔をしかめて、小さな舌を出している。普段見られない、かわいらしい仕草だった。
《ちなみに、世のなかには毒島(どくしま)と書いて、ぶすじま、と読む、お名前のかたがいらっしゃいますが、毒をぶす、と読むのはトリカブトの附子(ぶし)からきています。日本において、それだけ代表的な毒物だった、ということですね》
ゾディアックがカウンターから、トレーを持ってきた。トレーには、液体が入ったグラスが8つあった。そのトレーのまま、テーブルの上に置かれる。
《コカインという麻薬を、聞いたことがおありでしょう。あれは、南米原産のコカという木の葉から抽出した成分を使用しています。南米のインディオたちは、古くからこのコカの葉を、疲労回復などの作用があるとして、噛んでいたそうです。やがてインカ帝国を征服したスペイン人が、ヨーロッパにコカの葉を持ち帰り、ワインとまぜた、ビン・マリアーニという飲み物を考案します。これがアメリカにも輸入されてブームを起こしますが、19世紀末の禁酒法の時代になり、流通が困難になります。そこで、ジョン・ペンバートンという薬剤師が、ノンアルコール飲料として、コカの葉の成分を使用したものを開発しました。コーラの木のナッツのエキスと混ぜたそれは、『コカ・コーラ』と名づけられ、販売されるようになります。当初のコカ・コーラは100ミリリットルあたり、2.5ミリグラムのコカインを含み、鎮痛作用や覚醒作用を持つ薬用飲料として扱われていました。しかし、コカインの中毒や禁断症状が、よく知られるようになると、コカ・コーラも規制の対象となり、20世紀初頭には、コカインの成分は取り除かれるようになりました。皆様もコーラはお好きでしょう。コカ・コーラにもそんな歴史があったのです》
「今も、コカインの成分が入ってるっていう、都市伝説がありますけどね」
アーズ、おひつじ座と呼ばれた大柄な青年が、ボソリと言う。陰気そうな声だった。
「私はペプシのほうが好きだけど」
私もためしに発言してみた。するとゾディアックは笑いながら言った。
《ペプシ・コーラも、もとは消化を助けるペプシンという薬用成分の入った薬用飲料ですよ。……さて、コカ・コーラのように、麻薬という人の害になるものも、用法用量次第では、薬にもなる、という好例ですね。本日は、そんなアメリカの歴史に思いをはせていただきながら、当時のコカ・コーラを再現したものを、飲んでいただきましょう》
私たちは、あらためてテーブルの中央に置かれたトレーのグラスを見つめる。黒い液体が、プツプツと泡を浮かべていた。
「コカインが入ってるってことか?」
パイシーズが言った。
《ええ。でもごく少量ですよ。当時は薬用飲料という名目で、実際は清涼飲料として、広く飲まれていたものです。毒を飲む会という、アンダーグラウンドなこの場に、麻薬取締法が気になるかたは、いらっしゃらないかと思いますが》
挑発された形になったパイシーズは、ムッとした様子で、グラスに手を伸ばした。
それを見た京子が、私に素早く耳打ちする。
(どれでもいいから、早く手に取って)
せかされて、私は身を乗り出し、手前のグラスを取ろうとして、やっぱりやめて、もうひと伸びして反対側のグラスを掴んだ。京子も同じようにした。
そして、ゆっくりと、残りのグラスを常連たちが手に取る。全員にいきわたってから、京子がまた私に耳打ちする。
(まだ飲まないで)
京子は、紳士たちの動きをじっと見ている。やがて彼らが、グラスをかたむけ、それぞれ感想を口にするのを見計らってから、(大丈夫のようね)と言った。
OKが出たので、私も飲んでみる。最初のコカ・コーラといわれると、ちょっと興味もあった。
普通のコーラのつもりで口に含むと、思わずむせてしまった。なんというか、いつもよりもクスリ臭い。なるほど、薬用飲料というだけある。だが、コカインの成分とやらはよくわからなかった。体にも特に異常はないようだ。
口のなかで、当時のコーラを味わいながら、私は京子の言葉の意味を考えていた。
わかるよ、京子。毒杯パズルだろ。
もし飲み物に、なにか危険な毒物が入れられているとしたら、私たちが狙い撃ちされる可能性がある。たとえば、常連にだけわかる目印や、置きかたがあって、先に安全なものを取られてしまうと、私たちが残った毒杯を取らされることになるのだ。そこで、常連よりも先に取ることで、それを防ぎ、さらに全部のグラスに毒物が混入されているようなことがあっても、先に飲ませることで、様子を見ることができる。
さっきのシオブシのように皿に盛られて出てきたものと違って、グラスの飲み物なら、内輪の決まりごとを設定しやすい。
私は、周囲の参加者たちを順番に見回して、気を引き締めた。
《さて、常連のかたは、そろそろ退屈してくるころかも知れませんが、もう少しだけ初心者向けのご説明にお付き合いください。最初に私は、あらゆる物は毒になりうる、重要なのは量だ、と申し上げました。これも真実なのですが、もちろん、量だけではなく、毒性の強さも重要な要素です。量次第だとはいっても、水とトリカブトが同じ毒だという括りは一般的ではありません。常識的には、毒とは、『少量で健康を害する物』という定義がしっくりくるのではないでしょうか。つまり、毒性の強さですね。この毒性の強さを表すものとして、致死量という言葉があります。ただ、これはあまり正確な言葉ではありません。なぜなら、人には個体差があるからです。数人が同時に、同じ毒を同じ量摂取しても、死ぬ人と死なずに済む人が現れます。遺伝的体質や体重などによって、影響が異なるからです。なので、我々はよく、LD50という基準を使います。これは特定の生物の集団に投与して、おおよそ半数が死亡する量、という意味です。半数致死量とも言います。ほかにもLD0(ゼロ)は最小致死量で、もっとも弱い個体が死ぬ量。LD100は絶対致死量で、もっとも強い個体でも死ぬ量です。これらは特定の集団内で、飛びぬけた耐性の強弱があった場合、あまり意味のない数値になることがあるので、LD50、半数致死量が、毒性の強さの表現として、より信用度が高い基準と言えます》
ゾディアックはそう言いながら、テーブルのグラスを片付けていった。
《この世に存在する毒のなかで、人間に対し、最も強い毒性を持つものとは、いったいなにか。ご存知ですか》
その問いかけに、私は考えた。一番強い毒か。
「青酸カリなんて、殺人事件でよく聞くけど」
こないだ見たサスペンスドラマでも使っていたので、そう言ってみた。すると、紳士やマダムら常連が、小さく笑った。なんだ、バカにしやがって。
《そうですね。とても有名な毒です。化合物ですので、植物毒や動物毒と比べて歴史はありませんが、近年では毒物を使った事件などで、知られるようになりました。青酸というのが、シアン化水素のことで、カリウムと反応させたものが、青酸カリ、ナトリウムに加えたものが、青酸ソーダ、という具合です。青酸ソーダは、グリコ森永事件でも使われましたね。青酸カリは、11人が殺された帝銀事件が有名ですね。医者だと偽った銀行強盗が、赤痢の防止薬だといって行員に飲ませました。恐ろしい事件です。人間にとって毒性があるのは、この青酸カリという固体、もしくは液体自体ではなく、それがなんらかの物質と反応して発生する、青酸ガスなのです。ラスプーチンという帝政ロシア末期の怪人物の名前を、お聞きになったことがあると思います。彼は暗殺の対象となり、この青酸カリを混ぜた料理を食べさせられました。しかし、青酸カリは効かず、結局銃で撃たれ、最後は溺死させられました。これは、ラスプーチンが無酸症という特異体質で、胃に酸がなく、体内で胃酸と反応して青酸ガスが発生することがなかったためだ、とも言われています。ただ、この青酸ガスは、たしかに発生すれば猛毒ですが、それを発生させるための青酸カリの量は、かなり必要です》
ゾディアックが、口直しのミネラルウォーターだと言って、市販のペットボトルと、換えのグラスをテーブルに置いた。一応、常連たちが飲むのを見てから、私たちもグラスに注ぐ。
《青酸カリの毒性は、先ほどのLD50、半数致死量の基準で言うと、おおよそ体重1キログラムあたり、10ミリグラムほどです。体重が60キロの成人男性なら、600ミリグラム、つまり、0.6グラムになります。小さじ1杯の10分の1の量ですね。それを飲んだ人の半数が死ぬ程度、ということです。これを聞くと、少ない、少量でも効く毒だ、と感じるかも知れません。しかし、並みいる猛毒のなかに入ると、毒性は弱いと言わざるを得ません。たとえば、タバコに含まれるニコチンは、キログラムあたり7ミリグラムで半数致死量です。ニコチンのほうが、青酸カリよりも毒性が強いのですよ》
それを聞いて、飲みかけた水を、むせてしまいそうになった。ニコチンは友だちだ。あいつ、そんなに悪いやつだったのか。
私をチラリと見て、京子が笑っている。
「リシンじゃないか」
パイシーズが言った。「一番強いのは」
《素晴らしい。よくご存知ですね。リシンはトウゴマという草の種子に含まれるタンパク質です。トウゴマは観葉植物としても育てられていますが、山のほうに行けば自生しているものもよく見られます。このトウゴマの種からとれる油は、ヒマシ油と呼ばれ、下剤として使われることもあります。リシンは、ヒマシ油精製時の副産物として生まれます。大変強い毒で、このトウゴマの種を数個食べただけでも、含まれるリシンの作用で嘔吐や痙攣を起こし、死亡することがあります。経口摂取よりも、血中に直接流し込んだほうが、より強い作用を及ぼします。その毒性の強さは、先ほどの青酸カリとは比較になりません。リシンのLD50は、キログラムあたり、0.1マイクログラム。青酸カリのおよそ10万倍の毒性ということになります。これは、耳かき一杯の量で3千人を殺せる毒性です》
なんだそりゃ、と思って、私はツッコミを入れた。
「そんな毒を持った草が、そのへんに生えていていいのか。危なすぎるだろう」
これには、マダムが答えた。
「口にすれば危ないものなんて、世のなかにあふれてるわ。もっと簡単に手に入る、身の回りのものでもね」
「毒キノコも、毎年のように人を殺している」
と、ハゲ。
「モチなんて、毎年千人単位で殺してますよ」
これはアーズという青年。
定番のジョークだったらしく、常連たちが笑っている。
《そうですね。モチはともかくとして、身近なものでも、非常に強い毒性を持ったものがあります。フグ毒などもよく知られていますね。フグの毒はテトロドトキシンといい、LD50はキログラムあたり10マイクログラムほどです。青酸カリの1000倍ですね。毒物のなかでも、10指に入る強さです》
「前にやった、サバフグとドクサバフグの見分けかたゲームでは、死にかけましたよ」
ハゲが笑っている。紳士も頷いていた。
「笑えないな」
とパイシーズが言った。
《フグの毒は、体内で生成しているわけではありません。フグが食べる海草に付着したプランクトンなどがその起源です。フグがその毒を体内に溜め込み、生物濃縮によって強い毒性を獲得しているのです。このメカニズムは、シガテラという食魚介類の中毒でも同様です。シガテラを引き起こすシガトキシンという毒は、テトロドトキシンとは作用は異なりますが、とても強い毒です。下痢や血圧降下などの症状のほかに、ドライアイスセンセーションと呼ばれる知覚異常を引き起こすことで知られています》
ゾディアックが紳士のほうを、チラリと見た。紳士は頷くと、両手を広げて、ダンディな声で言った。
「私は、現在そのシガテラ中毒からの回復期でね。おおむね良くはなったのだが、水などが非常に冷たく感じられる、知覚異常の症状がなかなか治らないのだ」
両手には手袋がはめられている。そういえば、さっき冷えたグラスを手にするときも、やけに慎重に、全員の最後に取っていた。
「グラスを素手で持ったら、飛び上がってしまうよ」
当人はハハハ、と笑っている。しかし、私は、その姿に不気味なものを見た気がした。この毒を飲む会の異常性が、少し見えてきた気がしたのだ。
常連たちを改めて観察してみると、マスクの下の顔に、ある共通点が見出せた。肌が荒れているのだ。いやに黒ずんでいたり、カサカサとした見た目だったり。これは、毒を体内に取り込み過ぎて、血管やら内蔵やらがやられているのではないだろうか。
毒を飲む会、と聞いたときに連想した、自殺願望の変態集団というイメージが、再度湧いて出てくる。
京子は、いったいこんな危ない集まりの、どこに興味を引かれたのだろう。
無理やり誘われたが、やっぱり断るべきだったんじゃないか、という気持ちになってきた。向かいに座っている、新人の2人のうち、パイシーズに引っ張られているらしい連れの男も、終始オドオドとした様子だ。
《さて、先ほどの、最も強い毒はなにか? という問いの答えはまだ出ていません》
ゾディアックが、左側の席のハゲに問いかけた。
《リブラ様、お願いできますか》
ハゲは頷いた。
「ボツリヌス菌だね」
《そのとおりです。現在はダイオキシンやVXガスなど、大変な猛毒が化学合成で生み出されていますが、人間に対する毒性では、自然界に存在する最強の毒にはいまだ及びません。ボツリヌス菌は土のなかに、芽胞(がほう)の形で広く存在する細菌です。ボツリヌス菌を含む食物を摂取した人間の腸管内で発芽して、ボツリヌストキシンという毒を出します。乳児に蜂蜜を与えてはいけない、ということを聞いたことがありますでしょうか。それは、乳児の腸内細菌が未発達であるため、蜂蜜に含まれていたボツリヌス菌の発芽が起こりやすく、乳児ボツリヌス症を起こす可能があるためです。ボツリヌストキシンの毒性は、先ほどのパイシーズ様がおっしゃったリシンの、数百倍から数千倍。生物兵器としても研究されており、たった500グラムで世界人口の半数を死に至らしめることができる、とも言われる、最強の毒物です》
ゾディアックが、裏から取り出したトレーをカウンターの上に置いた。そのカンッ、という音にビクリとする。
おい。ウソだろ。
全身に緊張が走り、思わず立ち上がりそうになった。
しかし、ゾディアックは仮面の下の変声機越しに、クスクスと笑う。
《失礼。さすがに、ボツリヌス菌はお出しできません。とはいえ、そろそろ常連のかたは初心者向けの説明にも飽きてきたでしょうから、次のものをお出ししますね》
ふたたび、グラスがトレーに乗せられて運ばれてきた。今度は赤黒い液体が入っている。
《こちらはコブラ毒のワイン割りです。かのプトレマイオス朝最後の女王、クレオパトラ7世が自害に使ったという伝説が残っているのが、この毒蛇、コブラの毒です。彼女は蛇に乳房を噛ませて自殺したと伝えられていますが、使ったのはコブラではなく、クサリヘビだという説もあります。ただ、神経毒のコブラに対し、クサリヘビは出血毒です。その毒は血管や内臓を破壊し、皮膚はただれ、傷口からも多くの出血を伴います。絶世の美女と呼ばれたクレオパトラの散りざまとしては、似つかわしくないでしょう。そこで、今回はエジプトコブラの毒を使用させていただくことにしました》
「マムシ酒みたいなものかしら」
とマダム。
《蛇の毒はタンパク質なので、熱やアルコールなどで簡単に変質します。毒蛇のマムシを漬け込んだ酒を飲んでも平気なのは、度数の高いアルコールによって毒性が変質し、弱まっているからです。コブラ毒のLD50は青酸カリのおよそ20倍と、かなり強力な毒ですが、今回のものは、毒性を調整してあります。もっとも、安全なマムシ酒とは違い、会員のかたに楽しんでいただけるようにはなっていますが》
ここからが本番だ、という言葉に聞こえた。会員たちが手を伸ばすなか、隣の京子は動かなかった。さっきは真っ先に取れと言ったのに。そして、ゆっくりと動く紳士の手が届く前に、ようやくグラスを持った。私もそれに続く。
澄ました顔で、液体の匂いをかいでいるその姿を横目で見ながら、私はその意思を受け取っていた。
グラスを傾ける常連たちに続いて、私もグラスを口に持っていく。だけど、飲むフリだけだ。京子も同じだった。
口元をぬぐって、グラスを置いた。
「グッフ」
という、むせるような声がした。アーズという青年がうめいている。しばらくしてから顔をあげ、「アルコールは苦手なんですよ」という、言い訳めいたことを言った。
ほかの常連たちは平然としている。そして、体の変調をたしかめるように、目を閉じて深く息をしていた。
「なるほど」
しばらくして、紳士が静かに頷いた。
なにがなるほどなのかわからないが、わかりたくもなかった。
パイシーズと、連れのキャプリコーナスは神妙な様子であたりを伺っている。グラスのなかの飲みものは、ほとんど減っていないようだ。彼女たちも飲まなかったのかも知れない。
そのあと、主催のゾディアックの毒に関する薀蓄を聞かされながら、数品の飲み物と食べ物が提供された。
秦の始皇帝が求めた不老不死の妙薬とされる『丹薬』の伝説や、ルネッサンス期のメディチ家やボルジア家の繁栄の陰で暗躍した、『貴婦人の毒』と呼ばれるトファーナ水の逸話など、オカルト好きとしては心ひかれるものもあったが、それにちなんだ提供物は、口にする気にはなれなかった。
飲んだフリ、食べたフリばかりしていて、感想を聞かれたらどうしようと思っていたが、主催者だけでなく、他人に興味がないのか、常連たちもこちらに話しかけてこなかった。
そうして、いままで私が経験したことのない、異様な空間で時間は刻々と過ぎていき、やがて、毒を飲んでいないはずの私の頭がじんわりとぼやけてきたころ。
パンッ、という音がして顔を上げた。
ゾディアックが両手を叩いたのだ。みんなの視線が集中する。
《さて、皆様。本日の催しは、残すところ最後の1つとなりました。ここまで、お楽しみいただけておりますでしょうか。はじめて参加されたかたは、戸惑いもあったかも知れません。いたらない点につきまして、主催者として申し訳なく思います》
慇懃に頭を下げたその姿には、なにか意味ありげなものがあった。
私は、飲んだフリが気づかれているのだと思った。私たちに向いた常連たちの視線も、それを物語っている。
まあいい。これでこの変態たちの宴ともおさらばだ。あとは、好き勝手にやって、中毒で死ぬなりなんなりしてくれ。
そんな開き直った気持ちで、私は椅子にふんぞり返った。
京子もこれで満足だろう。世のなかには、自分以外にもアングラな趣味を持つやつがいっぱいいて、体を張ってその世界にどっぷり漬かっていやがるんだ。ここは、高校生の出入りするような場所じゃなかった。背伸びもここまでだ。
な? という意思を込めて、私は京子を見た。この1歳年上の同級生は、なにを考えているのか、かすかに微笑み返した。
《最後は、常連のかたがたにも馴染みのない、一風変わった種類の毒をお目にかけようと思います。毒物を口に入れることが、なかなか躊躇われる初心者のかたにもご参加いただけるものです》
黒い敷物で覆われたテーブルのうえは、すべて片付けられている。
「末端の枝葉の違いはともかく、たいていの種類の毒は、経験してきたつもりだがね」
常連たちを代表して、紳士、スコーピアスが言った。
《もちろん、皆様の毒物への好奇心や興味、そして愛情からくるこれまでの経験は、並々ならぬものであると承知しております。それでも、これは恐らくご覧になったことがないものでしょう》
ゾディアックの言葉に、スコーピアスは、「ほう」と言って、お手並み拝見、とばかり椅子に深く腰掛けた。
《では、はじめます》
ゾディアックが両手を広げた瞬間、店のなかの明かりがいっせいに消えた。
3 もう死んでる
突然真っ暗闇になったことで、そこかしこから息をのむような気配がする。私も驚いた。無意識に、テーブルの端を掴んでいた。
天井に小さな光の粒が現れた。それはまたたくまに頭上を覆うように広がり、夜空が生まれた。
プラネタリムだ。そういえば、部屋の四隅に、なにか黒い機械が設置されていた。あれがそうだったのだろうか。
「あら、綺麗」
マダムの声がした。
たしかに綺麗だった。でも、こんなものを見せて、どうしようというのだろう。
天井で輝く星々のなかに、薄っすらとした緑色の線画が現れる。それは、見覚えのある動物などの形をしていた。その上に、白い文字で名前が表示される。
おひつじ、おうし、ふたご、かに、しし、おとめ、てんびん、さそり、いて、やぎ、みずがめ、うお。
黄道12星座だ。横に長い楕円形をした宇宙を、右から左へ横断するように、12の星座が並んでいる。
どこからともなく、ゾディアックの声が聞こえる。
《皆様につけさせていただいたお名前の、星座たちが並んでおります。一直線ではなく、波打つように見えますのは、中央のラインが天の赤道、そしてそれを春分点と秋分点の2箇所で、黄道が跨いでいるためです》
プラネタリウムに、宇宙の中央を割るように真横に延びる赤い線と、その上下で揺れるように並ぶ12星座に沿った、黄色い線が補足で現れる。
どこかで見たことがある図だ。
また、緑色の線が描画された。かなり大きい。かに座、しし座、おとめ座、てんびん座のあたりに渡って、細長い生き物が現れる。それは巨大な怪獣のように見えた。
《これは、うみへび座です。星座のなかで、もっとも広い領域を持つものです。英語では、ハイドラと言います。どこかで聞いたことがお有りでしょう。馴染みのある古代ギリシャ語では、ヒュドラと呼ばれます。ギリシャ神話に出てくる、とても有名な怪物ですね》
ヒュドラ。私の記憶の片隅に、なにか嫌な感じのする重いものが湧いて出るような感覚があった。あれは、まだ暑い、夏のころだ。
プラネタリムを見上げたまま、抑揚のないゾディアックの声を聞く。
《ヒュドラは大変強い毒を持っていることで、知られています。ヒュドラはアングモアの魔王に遣わされて、地上を荒らしまわっていましたが、やがて勇者リュケイオスに倒されました。リュケイオスはそのヒュドラの毒を使って、ほかの多くの怪物を倒したといわれています》
そこで、天井の星の光が弱くなり、かわりに、私たちの囲むテーブルの上に、光が集中しはじめた。
SF映画で見たホログラムのように、なにもないテーブルの上に、映像が浮かび上がる。周囲から、「オオッ」という声がした。それは、装飾のついた豪華なカップに見えた。カップのなかには、液体が満たされているようだった。
《それが、ヒュドラの毒です。多くの怪物を屠った、神話のなかの猛毒。毒物に造詣の深いかたがたも、この実物はご覧になったことはないでしょう》
ハハハ、と笑う声がする。紳士だろうか。
《神話という、物語のなかの毒だからです。人間の生み出した想像の産物です。しかし、ヒトの想像力は、ときに、有りもしないものを、本当に存在したものよりも、長く後世に伝えることがあります。おかしなことではありません。過去から未来へ連綿と続く、神話の世界においては、これは実際に有ったものだからです。エリュマントスの猪を倒し、ケートスを倒した、恐るべき毒。いま私たちの目の前に現れたこの杯のなかの毒も、のちの世界のなにものかの記した記録のなかでは、投影された映像ではなく、実在しているかも知れません。この世界は、無数の可能性を持った、パラレルワールドでできている。パラレルワールドの確定者であり、観測者たる人間にとって、実に都合よく出来ているこの宇宙の法則は、そうでなければ観測者が存在できないという逆説的な理由により定められる、人間原理的ランドスコープのなかにあります》
淡々としたゾディアックの言葉は、不思議なリズムを刻みながら、私の頭をかき乱した。なんだこれは。同じようなことを、京子が言っていたような、気がする。
なにか嫌な予感がする。ぞわぞわと、浮き足立つ気持ちが、体を駆け巡っている。
《ごらんなさい。この聖なる毒杯を。観測と互換する想像力が、無数の可能性の世界を、確定させる。あなたの頭脳は、頭蓋という密室のなかに閉じ込められている。光の届かない部屋のなかで、脳は視神経から送られてくる信号をとらえ、あなたに幻を見せる。嗅覚受容体からは、活動電位による匂いを、内耳神経の興奮は音を、皮膚の受容体からは圧力や振動を、味覚受容体からは膜電位の活性化により、5つの味を、それぞれに受け取り、密室のなかに、世界を、再構築する》
ぐらん、ぐらんと、世界が揺れる。天の星はすべて消え、目の前の杯だけが、たしかなものとして、そこにあった。
《脳は孤独です。それゆえ幻を愛している。信じている。世界がそうであるようにと。とても、他愛なく》
ギィーンンンン…………。
頭を締め付けるような金属音がした。
すべての光が消え、やがて音も消えた。
なにもない、真っ暗闇のなかに、私は取り残される。
暗い。
寒い。
なにも、ない。
そう思った瞬間、綺麗な黄金の杯が、現れた。
目の前、ではない。
どこだ。どこにあるんだろう。
たしかにあるのに、位置がつかめない。目で見ているわけでもない。物質的な空間ではなく、どこかよくわからないところにあるようだ。ただたしかなことは、それは真んなかに、この私の世界の、中心にあるということだけだった。
頭の……なかに?
「あっ」
眩しさに目がくらんだ。
店内の明かりがついたのだ。暗闇に慣れた目が、その明かりに拒否反応を示している。手で顔を覆って、私は唸った。
「なんだこれは」
怒鳴り声が聞こえる。パイシーズの声だ。
「もう茶番はたくさんだ」
椅子が倒れた音がした。指の間から、薄目を開けると、パイシーズが立ち上がり、カウンターのほうへ歩み寄っている。
「この野郎」
カウンターの前に立っていたゾディアックに、パイシーズがつかみかかるのが見えた。
「やめろ」
とっさにそう叫んでいた。
頭のなかの杯が、消えていなかったからだ。目の前の光景に、想像上のものを重ねることができるように、黄金の杯はたしかにここにあった。
でもそれは、日常で浮かべるイメージとは、かけ離れた実在感で、かつ、けっして自分の自由にはならない存在の強固さで、ここにあるのだ。
そして、やっかいなことに、それは、恐るべき毒で満たされた杯だった。
私の制止になど構わずに、パイシーズはゾディアックのマントの胸元をひねりあげて、怒鳴る。
「私はな、おまえが毒を飲む会なんていう胡散臭い組織を作って、人体実験まがいのことをしているのを聞いて、潜り込んだんだよ。おまえ、笹原悠真(ささはらゆうま)を知ってるな。ここの会員だった男だ。2年前、おまえに毒を飲まされて死んだ、笹原だ」
そう言いながら、ぐいぐいとゾディアックの体を、カウンターに押しつける。
《およしになったほうがいい》
胸元を捕まれながらも平然とした様子で、仮面の下から変声機越しの声がする。
《そんなふうに、頭を振るのは》
「なにがだこの野郎。催眠術か、これは。このペテン師が。インチキだろうが、なんだろうが、おまえがやってることは立派な犯罪なんだよ」
「よせっ」
私はもう一度叫んだ。
パイシーズはまるで頭突きをするように、顔を仮面におしつけてすごんでいた。女性ながらすごい迫力だった。他の会員たちも、うろたえながら立ち上がって、その成り行きを見ているだけだった。
次の瞬間だった。
「ウグッ」
パイシーズが呻いた。
「アガ……ガ……」
ゾディアックのマントを掴む手の力が抜けていくのがわかった。
その格好のまま、頭だけが天を仰いでいる。
「……てめェ。なニ……しやガッた……」
マスクに開いた目の穴から、血が流れてきたのが見えた。その血が、頬を伝って、足元にポトポトと落ちていく。
次の瞬間、パイシーズが床に崩れ落ちた。血が、バシャンと跳ねるのが見えた。
私は思わず目を閉じた。だが、顔を伏せることはできなかった。
毒で満ちた杯が、頭のなかにあるからだ。パイシーズは、それを傾けたせいで、毒が頭のなかに撒けたのだ。そのことが、この目に見なくてもわかった。
「さくらさん!」
連れの男、キャプリコーナスが叫んで駆け寄る。
「おまえ、さくらさんまで!」
《まで?》
ゾディアックが首を傾げる。思わず、ヒヤリとした。とうの主催者の頭には、あの杯が入っていないのだろうか。
「俺は笹原悠馬の、お、弟だよ。おまえの人体実験の材料にされて、こ……コンクリートと一緒に溶けて混ざった、あんな、残酷な……ざ……ざんこく……」
最後は言葉にならない嗚咽だった。
あっ。
止める間もなかった。キャプリコーナスは振り向くと、うつ伏せに倒れて痙攣しているパイシーズを助け起こそうとして、屈み込んだ。
そして、ウッ、と呻いたかと思うと、自分の顔と頭を交互に触りながら、「ああああああ」とわめいた。そして、目元と口元から血を滴らせながら、倒れた。
店内には、倒れた人間からかすかに聞こえる、ううううう、という、断続的なうめき声だけが響いている。
私は、壁際で立ち尽くす京子のそばに近づいて、その手を握った。
「大丈夫か」
「……ええ」
京子の色白の顔が、いつになく白く見えた。
「とんだ騒動がありましたが、これはすばらしいですな」
紳士が、ゆったりとした口調で言った。
「ええ。こんなものは、はじめてよ」
マダムがどこを見ていいのか、わからない、という様子で視線を虚空にさまよわせている。
「あー、びっくりしたなぁ」
大柄な青年は、動悸を止めようとするように、胸を抑えている。
ハゲがつまらなそうに言う。
「しかし、これでは飲めませんよ」
頭の上を探るように、手を振り回している。
なんだ、こいつらは。
私は信じられないものを見る思いだった。目の前で人間が2人も血を吐いて倒れたのだ。どうして、そんなに平然としていられるんだ。
京子が、私の手を握り返しながら、口を開いた。
「いまのは、この会のルールに違反しているのでは? 『ルール2。この会の参加者は、提供されたものを摂取するかどうか、自由意志により判断するものとする』だったかしら。彼女たちは、自由意志で摂取していない」
京子の抗議に、ゾディアックは淡々と返答する。
《毒は杯に入っています。気化するものでもありませんし、安全です。それを本人のミスでどこにこぼそうが、私の関知するところではありません》
「詭弁ね」
「詭弁かどうかはともかく、このままでは飲めないのはたしかだな」
紳士が不満げな口調で言った。
《では、そろそろ片付けましょう》
ゾディアックがそう言った瞬間、また店内の明かりが消えた。
真っ暗な闇のなかで、あの金属が鳴り響いた。
ギィーンンンン…………。
私は思わず耳を塞いでいた。
気がつくと、照明がついていて、かわりのない店内の様子が見えた。
杯が、消えている。
消えてしまった今では、頭のなか、としか表現できない、あの場所から。
私は両手で自分のこめかみのあたりを覆った。
なんだったんだ、あれは。幻覚だと言われたらそうなのかも知れない。でも、たしかに、さっきまで、それは存在していた。
床を見ると、倒れた2人はそのままだった。ピクリとも動かず、もう呻き声も聞こえてこない。
《さて、私は、倒れられたかたがたを、治療しなくてはなりません。本日の会合は、これでお開きとさせていただきます》
ゾディアックの言葉に、常連たちから拍手が上がる。
「最後のは素晴らしいな。もっと研究して、よりよいものを見せていただきたいものだ」
紳士の言葉に、ほかの3人が頷いている。
彼らは、クロークからそれぞれ外套を取り、ゾディアックに挨拶をして、なにごともなかったかのように、店から出て行こうとした。
京子がその背中に、言葉を投げつける。
「あのヒュドラの毒杯が手に取れたら、あなたがたは飲んだのかしら」
一番うしろにいたハゲが振り向いて、「もちろん」と言った。
「神話に伝えられる、歴史的な毒だ。味見くらいしてみたい」
「それでもし、死んだら?」
「運命だったということだろう」
ハゲは、ハンチング帽子を被り、マスクを取ると、目元が見えないよう、すぐにサングラスをしながら、軽く会釈をした。
「では、ごきげんよう」
「そんなもの、運命なものか」
私は、去っていく彼らに叫んだ。もう、だれも振り返らなかった。
《いかがでしたか、はじめて参加されたご感想は》
残っているのは、私と京子と、この頭のおかしい集まりの主催者だけだった。
京子は、それには答えず、うつ伏せに倒れているパイシーズの体の下に手を入れた。まったく抵抗なく、ひっくり返されたその姿は血まみれで、顔や皮膚に生気が感じられなかった。
京子が血のついたマスクを取る。その下から現れた顔は、たしかに、どこかで見たことがある気がした。
「やっぱり。昔テレビのローカル番組に出ていた、占い師よ。天道さくら、とかいったかしら。最近は見なかったけど」
あ。
それで思い出した。
私が占星術を習っているアンダ朝岡という、占い師のおばさんの店で、チラッと見たことがあった。たしか、昔の弟子だと言っていた。店の奥でなにか話していたが、どこかよそよそしいような雰囲気だった。覚えているのはそれだけだ。
彼女は、さっき、ゾディアックに詰め寄っていたときに、なにかわけのわからないことを言っていた。笹原悠馬という男が、殺されたとかなんとか。
私は、額を押さえた。毒が回ったわけではないが、頭が痛い。もうたくさんだ。こんなことは。
「救急車を呼ぶ」
私は短くそう言った。ゾディアックは首を振る。
《私の持つ、解毒剤でなければ助かりません》
「じゃあ救急隊員にすぐそれを渡せ」
《いまここにはありません》
「無駄よ」
京子が言った。「もう死んでる」
倒れた2人の首筋を触りながらそう言うのだ。私は足が震えた。
なんなんだ、これは。人が、目の前で死んだ?
私の脳裏に、夏に見た、女の子の死に顔が浮かんだ。ゴミ袋のなかに、その小さな顔が土気色をして覗いていたのだ。
「こんなとき、あなたはいままでどうやって処理してきたのかしら」
京子が立ち上がって、仮面の人物を真正面から見据えた。
《よく効く解毒剤があります》
ゾディアックは、死んでいる、という京子の言葉を無視して、そう繰り返した。
「京子、帰ろう」
こいつは、おかしい。仮面の縁を飾る黒い模様が、いつのまにか大きくなっているような気がする。目のところに開いた小さな穴の奥から、潤んだような黒い瞳が、こちらを見ている。
これ以上もうこいつに、関わらないほうがいい。
そう思ったが、私の口は、意思に反して開いていた。
「ギリシャ神話のヒュドラを退治したのは、ヘラクレスだ。さっきおまえが言っていた、勇者リュケイオスなんてやつじゃない。それに、ヒュドラは、蝮の女エキドナと巨人テュポンの間に生まれた怪物だ。その、アングモアの魔王だとかいうやつの手下なんて話は、はじめて聞いたぞ。たしか、女神ヘラが、ヘラクレスを倒すために育てたんじゃなかったか。どうして、そこだけ、デタラメなんだ」
私は、夏に起きた事件で、ヒュドラについて調べたのだ。そもそもそれを私に教えたのは、京子だった。京子も、こいつがおかしなことを言っていたのは、気づいていたはずだ。
こんな調子では、さっきまで毒についてあれこれと薀蓄を語っていたことも、どこまで本当なのかわからない。今日出されたいくつかの毒も、本当に、説明のあったその毒だったのか、信用できない。
口にしなくてよかった。改めてそう思った。
仮面が、下を向いた。かすかに震えている。
笑っているのだと気づくまで、少し時間がかかった。
《いいえ》
ゾディアックは、俯いたまま首を小さく振った。
《ヒュドラを倒したのは、リュケイオスです。ミュケナイの王アーマリオスと、妃ユラの息子。そういう神話が残っています。少なくとも……》
仮面が、顔を上げた瞬間、また店の明かりが消えた。
《私の知っていた世界では》
その瞬間、天井に、星が現れた。プラネタリムがまた作動したのだ。空に散りばめられた小さな星たちが、キラキラと光っている。
黄色い線で示された黄道の周囲の星を囲むように、緑色の線が空に絵を映し出す。
さっきまでの黄道12星座とは、ほとんどが違っていた。
なんだこれは?
私は、息をのんだ。
いつの間にか、隣の京子が私の手を握りしめている。
《ごらんなさい。8月のくるみ座や、おおねこ座から、10月のてんびん座のあたりまで伸びる、うみへびの姿を。あれがヒュドラ。7月の星座、まおう座が地上に遣わした悪魔です》
赤い星がいくつも集まって、不気味な顔のような模様を空に描いている。
《ヒュドラを倒したのは、12月の星座、じゅうし座のリュケイオスです》
京子の、握る力が強くなる。私も、握り返した。
《おや。銃士座の勇者の名前は、ご存知ありませんでしたか》
仮面の声が、まるで空から聞こえてくるようだった。
《リュケイオスは、自ら倒したヒュドラの毒で、そのあと魔王アングモアの遣わした怪物たちを、次々と倒しました。ケートスもその1頭にして、最後の使徒です。ケートスは毒を込めた石火矢で心臓を射抜かれ、倒されました。そして空に昇ったのです。11月の星座として》
プラネタリムが一度消え、全天球ではなく、一部の空を映し出した。細かかった星が、今度は少し大きく見える。そのなかのいくつかの星を緑色の線が結び、しっぽのある不気味な怪物の巨体を、キラキラと映し出している。
《劇団にくじら座という名前をつけたのは、その星座からきています》
星座の下に広がる小さな世界でいま、姿を見せずにゾディアックは、京子に語りかけていた。
その京子は、目を大きく見開いて、異邦の星々を見つめている。
危ない。
私はそう思った。
こいつは、京子を狙っている。
だが、私も動けなかった。京子が、繋いでいた私の手を離していた。その手を取って、ここから逃げようとしても、京子は動かないだろう。それが、想像できるのだ。
《この世界の星占いは好きではないでしょう。自分の星座が載っていないから。11月31日に生まれた人間も同じです。クラスメートのだれとも違う星座、そしてだれとも違う誕生日。孤独。疎外感。仲間はずれ》
近づいてくる。
暗闇に紛れて、あいつが。
《しかし、そんな日々も、いずれ終わります。この見慣れない世界における、使命を知ったときに》
ゾディアックの、気配のない声が近づいてきたとき、青い光が放射状に広がった。同時に、ヒィーン、という回転音がする。京子の胸元からだ。
プラネタリウムに浮かび上がる、くじら座の怪物の心臓が、それと同調するように明滅しはじめた。
《それだ。それが、あなたを、重なり合った2つの世界の間で惑わせている》
機械の声が、震えて聞こえる。
そのとき、京子の声が響いた。
「これは、あの地震の夜に、父がくれたものよ。このタリスマンは、いつも私を守ってくれた。私に触れれば、ただでは済まない」
緊張した声。でも、凛とした言葉だった。
「あなたと、お友だちになれるかも知れないと思ったけど、無理そうね。あなたは、なんというか……。そう、人間ですら、ないみたい」
《きっと、友だちになれますよ。あのクスリは、飲んでくださいましたか》
「飲んでないわ。あれはただの水だった」
あの千円の瓶のことか。水に見えたが、やっぱりそうだったのか。
「だけど、とても嫌なものが入っている」
京子の言葉は矛盾している。ただの水だと言ったのに。
《あなたは、どうですか》
近くで声がした。私の顔のすぐ横で、暗闇のなか、プラネタリムの頼りない光に照らされて、白い仮面だけが宙に浮いているように見えた。
「その子に手を出さないでっ」
京子が叫んだ。なにか、大きな力に、全身を掴まれたような感覚があった。全身の血の気が引いた。
心臓を引き抜かれるイメージが、走った。
絶対に抗えない、破滅のイメージ。
しかし、次の瞬間、不思議なことが起こった。
どこだかわからない場所で、なんだかわからないものが、急に大きくなっていくような感覚があった。熱を出して寝込んでいるときに感じたような、あの感覚。そして、それが突然、私の胸のなかから噴き出してきた。
その真っ黒なものが、私に迫っていた白い仮面を押し戻した。
ガシャン、という音がした。ゾディアックがカウンターにぶつかったのだとわかった。
その黒いものは私の周囲をくるくると渦を巻くように回っている。
「それは、なに?」
京子が、驚いた声で私に問いかけた。そんなもの、私だって知りたい。でも、なぜか、懐かしい気がした。
再び仮面が宙に浮かんだ。また、感情のない機械音がする。
《素晴らしい。それは、あの夜に生まれた力だ。怪物の誕生に立ち会ったあなたに、その一部が残っていたのだ。それがいま、あなたを守っている》
私の体を巻くように、宙を回っている黒いもののなかに、にび色の魚の鱗のようなものが見えた気がした。
「やめなさい」
京子が緊迫した声を出した。その声が、私の置かれた状況を示していた。それは守ろうとしている人間の声だった。いま、仮面に狙われる対象は、私になったのだ。
ハハハハハハハ
部屋中に、笑い声が鳴り響いた。
宙に浮かんだ白い仮面を縁取る黒い模様が、波打つように激しく動いている。
私は身構えた。しかし、次の瞬間、聞こえてきたのは、いままでのボイスチェンジャーを通した声ではなかった。『それは、たしかにあなたを守っている。しかし、それは呪いでもある。その力が、あなたに、あなたの望まない悪いものを引き寄せる』
仮面越しに聞こえてきたのは、静かで、優しげな声だった。
『水槽を買うといい。大きな水槽だ。自分の部屋に置きなさい。それが、きっとあなたを守るでしょう』
その言葉の最後に重なるように、別の声がした。
《だめだ。水槽を置いてはいけない》
ボイスチェンジャーの声だ。同じ仮面から、2つの声がしていた。
ハハハハハハハ
また部屋中に笑い声が響く。ビリビリと体に振動が伝わってくる。
私は混乱していた。混乱しながら、ただ、呆然と立っていた。
空に浮かんだプラネタリウムの星が、ますます輝きを増している。しっぽとひれのある怪物の胸の辺りで、心臓の星が激しく輝きながら脈打っていた。その光が大きくなり、目がくらみはじめた。
ハハハハハハハ
危険だ。でも、逃げられない。
私は、目を閉じかけた。
そのとき、突然前触れもなく、すべての光が消えた。空の星は消滅し、完全な暗闇があたりを覆っている。
《なんだ》
ボイスチェンジャーの声。そして、カウンターのほうに走る足音。
明かりがついた。マント姿のゾディアックが、カウンターの脇にあった照明のスイッチを押していた。
明るくなった室内で、京子の胸から出ていた青い光も、私の周囲を回っていた黒いものも、なにもなかったかのように消えている。まるで幻覚を見ていたようだった。
そのことよりも、私は、部屋の隅を見て驚いた。さっきまでいなかった人間がいるのだ。それは小さな女の子で、黒いコードの束を手に持っている。そのコードは、それぞれ部屋の四隅にあるプラネタリムの装置から伸びていた。
電源コードか。
それを壁のコンセントから引き抜いた女の子が、イタズラがバレたときのように目を見開いて、私たち3人を交互に見ていた。
《またおまえか》
ゾディアックがそう言って、女の子に近づこうとした。すると女の子は、コードを投げ捨ててコートクロークのほうに走り、私のコートの裏にもぐりこんだ。
ゾディアックがコートを手で押しのけると、奥の壁だけが見えた。女の子は忽然と消えていた。どこにも逃げ場はないのは明らかだったのに。
すると、今度はカウンターの奥の調理場らしい部屋から、小さな顔がぴょこんとこちらを覗いた。
「Hey! Fucking bastard. Try to catch me!」
かわいい顔から、口汚い感じの英語が飛び出した。その顔は、どこかで見たことがあるような気がした。
占い師のアンダたちに出会った夜にいた、あの子だ。
そう気づいたときには、ゾディアックがカウンターの奥の部屋へ、女の子を追っていこうとしていた。
「早く。逃げるのよ」
京子が私の手を引っ張った。クロークのほうへ。我に返った私は、コートを手に取り、脇に抱えたままで出口のほうへ走った。
視界の端に、血を流して倒れている2人の姿が映った。それで、さっきまでここで開かれていた恐ろしい集まりが、現実のことだったのだと思い出した。
部屋から出るとき、振り返ると、ゾディアックが首を振りながらカウンターの奥から出てくるところだった。
《また逃げられました。あの小さなお客様には、困ったものです。いいでしょう。今夜のところは、これで。あなたがたにも、またお会いすることもあるでしょうから》
ゾディアックは、こちらを追ってくる様子を見せなかった。
「Fuck」
カウンターの奥から女の子が顔だけを出して、かわいい声で言った。
ゾディアックはもうそちらを見なかった。じっとこちらを向いている。ひゅっと女の子は引っ込んだ。
「京子」
私は前にいた京子の肩を、行け、と押す。
京子は、その手をそっと上から押さえ、ゾディアックに向かって言葉を放った。
「最後にあなたが片付けた、目に見えない金色の杯の数は、ちゃんと数えたのかしら。足りないと大変だものね」
ゾディアックの動きが止まる。京子は、いつもの冷たい微笑を取り戻している。
「怪物を倒した、ヒュドラの猛毒なんですから」
私は、驚いて京子の横顔を見た。
「いったい、半数致死量はどのくらいでしょうね。でも、たった1頭しかいない生き物には、使えない基準かしら」
その捨て台詞を最後に、固まったままのゾディアックを無視して、私と京子は、入ってきたドアから外に飛び出した。
外はしんしんと冷えている。深夜の寂れた街は静かで、私たち以外、だれの姿もなかった。
細かな粒の雪が、薄っすらと夜の空を舞っている。
私と京子は、その音もなく降り続く粉雪のなかを、コートを抱えたままで走った。
駅が見えてきたところで立ち止まり、顔を見合わせて笑った。2人とも、あの妙なマスクをつけたままだったからだ。
マスクを投げ捨て、セーターについた雪を払ってから、コートを着た。走ってきたので、体は冷えていない。
それから、駅前の公衆電話に入り、私が代表して110番通報をした。店の名前を告げ、なかで人が死んだようだ、と言っておいた。こっちの名前は言わずに受話器をフックに戻した。もう関わりたくなかったからだ。
公衆電話から出ると、京子がコートのポケットに手を入れたままで、私に言った。
「怪物の誕生に立ち会ったって、なあに?」
私は、その顔を見つめながら、ゆっくりと答えた。
「おまえも、覗いていたんじゃないのか、あの夜のことは」
京子は首をかしげている。
「知らないなら、いい」
思わず突き放した声を出した。なにか嫌な予感がしたからだ。
「そうなの」
京子は私の顔を見ながら、つまらなそうに言った。けれどその目は、私の瞳の奥にあるものを、探ろうとしているように見えた。
◆
怖い夢を、見ていた気がする。
私は布団から起き上がった。
動悸が、呼吸を早くする。
真っ暗だった。自分の部屋であることを確認する。時計を見ると、夜なかの2時半だった。
私は、深く息を吸って、吐いた。それから起き上がって、部屋を出て、階段を下りた。台所の電気をつけ、冷蔵庫から水のペットボトルを出して、コップに注ぐ。
満足するまで喉の渇きを潤してから、2階に戻ろうとすると、居間からなにか聞こえた気がした。
そのとき、デジャヴのような感覚が、脳でぐるりと回った。これから、なにが起こるか、知っているような気がする。
私は、そっと居間に入る。
真っ暗ななかに、キキッ、という小さな声がしていた。部屋の隅にある棚のうえに、布を被せた鳥かごがある。鳥かごのなかには、ピーチという名前の九官鳥がいるはずだった。
「ピーチ?」
明かりを消して鳥かごに布をかけると、いつもピーチはわりとおとなしく寝ているはずだった。それがいま、布のしたで、なにかおしゃべりをしているようだ。
これと同じことがあった気がする。
私は、おさまっていた動悸が、再びはじまるのを感じていた。
ドクンドクンドクン……。
その音がいやに大きく聞こえる。
私はそれに負けまいと、耳を澄ます。
夜の闇のなかに、声が流れ出した。
…………グソウムドイ……………
…………ユミツカイ………………
…………ゴシキチズ………………
…………ヨルノサンポシャ………
…………ネムラヌウオ…………
ピーチの声だった。でもピーチの言葉ではなかった。
…………グソウムドイ……………
…………ユミツカイ………………
…………ゴシキチズ………………
…………ヨルノサンポシャ………
…………ネムラヌウオ…………
同じ言葉が、繰り返されている。私は息を殺してそれを聞いていた。
やがて、ウルルルル……という、喉を鳴らすような声に変わった。ピーチのよくやる仕草だ。
ホッとした瞬間、布の下から、機械のような声がした。
…………キイテ、イルナ…………
…………ソコデ……………………
私は身震いして、逃げるように居間を出た。
階段を駆け上り、自分の部屋に入って、鍵をかけた。ドアに背中を押し付け、口元を押さえる。
期末試験が終わったあと、クリスマスに、ホテルで過ごした夜のことを思い出す。
あの夜、まどろんでいるときに、恐ろしい夢を見た。どんな夢だったか、いまも覚えている。思い出したくもない夢だった。
私は、ドアから背中を離し、重い足取りで、さっき起きたばかりの自分のベッドに向かった。
壁際のタンスの上にあるものを、チラリと見る。クリスマスの次の日に買った水槽だった。なぜか、買わなければいけない気がした。
いまそこに、なにか見えた気がして、目を擦った。
なにも入っていない、カラの水槽だ。
私に、なにか起こっている。それは、体に押された烙印のように、ついて回るものだ。なぜかそう思う。それがわかるのだ。
「京子」
私は、そう呟いていた。
私に起きていることを知るには、あいつの力を借りるしかない。そう思った。けれど、それが正しいことなのかは、わからなかった。
おまえと会ってから、こんなことばかりだ。京子。
私は、拳を握り締め、やがて行き場のないそれで、自分の額を叩いた。
(『毒』中編 完)