アポカリプティック・サウンド
その音を聞いたのは、大学祭の大騒ぎのすぐあとだった。
福武さんという、師匠の知り合いが描いた不気味な絵をめぐって、人の群にもみくちゃになり、散々な目にあってから僕らは師匠の家で落ち合った。
師匠はその絵を、サークル棟のそばにある焼却炉で燃やしたという。ばけものの絵だというそれを。
「あれが、くじら座のくじらだとは知りませんでした」
福武さんの描いた絵には、手や足や目など、体の一部だけが大きい裸の人間たちと、彼らがまるで崇拝するように囲む怪物が描かれていた。
その怪物は、トドのような胴体から、爪の尖った短い腕が突き出ている。横たわる下半身には足がなく、毛の生えていない尻尾は、くるりと巻いて天を向いている。鼻の大きな頭。裂けた口には鋭い牙が並び、目は肉食の爬虫類のように小さく、酷薄な表情をしていた。僕らの想像する、海のクジラと、まるで似ても似つかない。
師匠が説明してくれた。
「日本でくじら座と呼ばれているのは、ケートスといって、テュポーンとエキドナのあいだに生まれた怪物だ。エチオピア王国の王妃カシオペアが、自分の美しさを奢りたかぶったせいで、ポセイドンの怒りを買い、その手先として、エチオピア王国に送り込まれたんだ。大暴れするケートスを沈めるには、娘のアンドロメダ姫を生贄に捧げないといけない、という神託が下った。そしてアンドロメダ姫が海のなかの岩辺に鎖で縛り付けられることになった。そこに、ペガサスに乗った英雄ペルセウスがやってくる。ペルセウスは倒したばかりのメデューサの首をかかげて、ケートスを岩に変え、みごと姫を助けて妻に迎える。こういう筋の神話だ」
「それがなんで、日本ではくじらなんですか」
「ケートスが本来、くじらを意味するギリシャ語だからだよ。ここではお化けくじらとして出てくるけどな」
このあいだ、夜の公園で師匠と見上げていた星座は、同じくじら座でも、お互いの思い描いている姿は違っていたわけだ。
「なぜこれを、福武さんは幻視したんでしょう」
福武さんは言ったのだ。これを見たのだと。彼女は、この世のものではないものを見る人だった。見たものを絵に描いて、その災いを閉じ込めようとするのだと言っていた。
「……さあな」
師匠は口を歪めた。
僕にも、偶然とは思えなかった。
『私は、輝きを変える心臓です』
卵顔の隣人の残した言葉は、くじら座の心臓の星、ミラを示す言葉だった。そして巨人感覚症候群のことを調べていた僕らを、先回りするように姿を現した仮面の男。その仮面は、劇団くじら座で使われている白い仮面に酷似していた。
くじら、くじら、くじらだ。
これが偶然なわけはない。けれど、その符合の持つ意味が僕にはわからなかった。
しばしの沈黙が下りた、そのときだった。
師匠の部屋の窓ガラスがカタカタと振動しはじめた。そちらに目をやると同時に、僕の耳は不思議な音を拾っていた。
なにか金属音がこすりあわされるような、不気味な音だった。
師匠も気がついて、すぐに駆け寄り、窓を開け放った。
夕方近くになり、空の半分を覆っている雲の底が、暗い色に染まりつつあった。その空の下に、得体の知れない音が響き渡っていた。
ぎぃいいいん。ぎぃいいいん。
とっさにサイレンの音だろうか、と思った。けれど、それはなにかを告げようという意図を感じられない、ただ空間が軋むような不快な音だった。
「なんですかこれ」
「わからん」
かなりの音量だ。近くの家からも、玄関から出てきて外をうかがっている人たちがいる。みんな不安そうな顔をしていた。
僕は耳を研ぎ澄ませた。いったいどこから聞こえてくるのか、方向をたしかめようとしたのだ。けれど、わかったのは、どこからともなく聞こえてくる、ということだけだった。
こんな音を立てる工場なども、近くにはない。正体不明の音は途切れ途切れながらも、ずっと続いている。
僕は想像していた。
空のうえに、巨大な列車が走っていて、それがブレーキをかけてなお停止せず、わずかずつ進み続けているところを。重い金属の塊が、ギシギシという軋む音を上げながら、いつまでも緩やかに動き続けている。
「アポカリプティック・サウンドってやつか」
師匠がぼそりと言った。
「なんですか、それ」
「ヨハネの黙示録に出てくる、7人の天使が吹くラッパだよ。人の世が終わり、最後の審判が始まることを告げる、終末の音だ。世界中で観測されてる、こういう正体不明の金属音みたいな音が、そう呼ばれてるんだ」
「正体不明って、本当にわかってないんですか」
「聞いた話だと、上空の放電現象にともなう電磁波の音だとか、地下の空洞に響く音だとか、はたまた地盤が軋むことで生まれる音だとか、いろいろ言われてるな」
「じ、地盤って、まさか大地震の前兆とかじゃないですよね」
僕はゾッとして、思わず腰が引けた。
「さあなあ」
今にも地面が揺れだすのではないかと身構えていたが、しばらく待ってもその気配はなかった。
やがて、師匠がアポカリプティック・サウンドと言ったその不気味な音も、途切れがちになり、ほとんど聞こえなくなった。
空は赤みが増し、夕暮れが近づいていた。風が出てきて、冷たい空気が窓から入り込んできた。
「終わりかな」
師匠がそう言って、窓を閉めようとしたときだった。
さっきまでの金属音とは異なる、なにかが唸るような音が突然鳴り響いた。
ガァー…… イィー…… ガァー……
ガァー…… イィー…… ガァー……
そんな3つの音節だった。それが腹に響くような重低音で繰り返されている。
窓から身を乗り出したが、空にも、周囲にも異変はない。音はさっきと同じく、上空からとも、地の底からともつかない場所から響いてくる。しかし、その音は金属音ではなく、なにか生々しい響きを持っていた。まるでなにかが吼えている、あるいは呻いているかのようだった。
「なんだよこれ」
僕が思わずそうつぶやいたとき、師匠は耳を手のひらで塞いだり、またどけたりして、なにかをたしかめようとしていた。
「これ、実際の音じゃないかも知れない」
「実際の音じゃない、って。幻聴だっていうんですか」
「見ろ」
師匠が窓の向こうを指さすと、外に出て不安そうに周囲を見回していた住人たちが、家に帰っていくところだった。不思議な音の現象が終わったと思って、窓を閉めようとした師匠と同じように。けれど、今はさっきまで聞こえていた金属音とは違う、別の不気味な音が聞こえてきているのだ。まるでそれが聞こえないかのように、住人たちはさっさと家に戻ってしまった。
「僕らだけに聞こえてるんですか。どうして」
「しっ」
師匠は耳を澄ましている。
ガァー…… イィー…… ガァー……
ガァー…… イィー…… ガァー……
さっきまで窓ガラスが微かに振動していたが、いまは静かだ。ただ、どこからともなく、唸り声が響いていた。
終末の音、と呼ばれた無機質な不協和音に対して、今度のものはなにか、それを発しているものの意思のようなものを感じた気がした。それは金属的ではなく、生物的なものだったからだろうか。
「止まる」
師匠がそう言った。音はもう聞こえなくなった。
僕は玄関から外へ出て、あたりを見回した。昼間、高かった空は、今は低い。雲の底が重そうに夕日に照らされている。
なにが起きているんだ。
得体の知れない恐怖心が、僕の体の奥底からじわじわと浸みだしていた。
◆
翌日の新聞に、不気味な音のことが載っていた。
市内のかなり広い範囲で、その現象が起きていたようだ。夏に起きた、街路樹や電信柱が引っこ抜かれたり、石の雨が降ったりといったイタズラとも怪奇現象ともつかない、数々の不思議なできごととの関連を疑う記事になっていた。記事のなかでは、『金属音のような』とされており、僕と師匠が最後に聞いた、唸り声のような音のことは指摘されていなかった。
師匠が、実際の音じゃない、と言ったことが、ますます現実味を帯びた。
それから1週間のあいだ、ほぼ毎日のようにその金属音のような音が聞こえてきた。決まって夕方だった。市民は気味の悪い音に動揺して、僕の知人のなかにも、市役所や気象庁に苦情電話を入れる人がいた。そうした騒動がニュースになり、大地震との関連性を疑う声を取り上げたせいで、ますますパニックは加速するかに見えた。しかしそれも4日ほどで沈静化しはじめた。地面はピクリとも揺れることはなく、音もだんだんと小さくなっていった。
結局正体は不明のままだったが、ローカルニュース番組のなかで、電話が繋がった気象学の専門家が語った電磁ノイズによるものだろう、という解説に、なんだかよくわからないまま、みんな一応の納得をしたようだった。
そうして1週間が経ち、街は日常を取り戻していた。夕方のひととき、どこからともなく聞こえてくる、かすかな金属音を聞きながら、中高生は家路を急ぎ、サラリーマンは残業を決め、主婦は夕飯の買い物に行った。
アポカリプティック・サウンドが、そんな環境音の1つになりつつあったころ、夕方のローカルニュース番組は市内の南の地区で起きたガス爆発事故を伝えた。
ショッピングモールの改築工事中に、地中に埋まっていた古いガス管が突然爆発を起こしたという。作業員が数人ケガをしたが、幸いにして死者・重傷者はおらず、県警では詳しい原因を調べている、という速報だった。
僕はそれを師匠の部屋でだべっていたときに、たまたま見たのだが、テレビに映された現場周辺の地図に、師匠が跳ね起きた。
「左足だ」
ひとことそう言って、外出の準備をしはじめた。僕も慌ててついていく。
「あの地図につけた印の、左足の位置だ」
久しぶりにボロ軽四を運転する師匠が、そう言った。
「あのマネキンのですか」
保育園の魔法陣騒ぎ以来、すでに3ヵ所でマネキンの手足が地中から出てきている。師匠の推測どおりなら、それぞれの位置は、巨大な五芒星の形をしているはずだった。市内の広い範囲に仰向けに横たわる巨人の姿のように。
その左足のあたりに、事故の起きたショッピングモールはあったのだ。
現地に着くと、非常線が張られ、その周辺に野次馬たちが集まっていた。もうあたりは日が暮れかけていて、薄暗闇のなかに警察車輌のライトと、投光器のオレンジの光がちらちらと見えている。
「近寄れませんね」
「ああ」
建物のそばに消防車が見えたが、もう活動していないようだった。煙も上がっていない。非常線の近くに、小さめのポンプ付積載者が止まっていて、その周りに暇そうに座り込んでいる人たちがいた。消防署員ではなく、地元の消防団員だろう。地区は違うが、師匠も消防団に所属しているので、知り合いがいたらしい。なかの1人を手招きで呼び寄せて、話し込んでいた。
やがて戻ってきた師匠は、「事件性はないみたいだってよ」と言った。
「ただのガス爆発だ。モールの建物自体に引火しなかったから、大した事故にならなかったらしい。もちろん、妙なものも、今のところ見つかってない」
師匠は妙なもの、とボカして言った。自嘲気味に笑っている。
「とりあえず、帰るか」
「はい」
軽四は、ちょっと離れた場所にあるコンビニに停めていたので、そこまで歩く。
横目でチラリと見たが、師匠がただのガス爆発という説明に納得していないのは、ありありとわかった。心ここにあらず、という様子で目は景色を追っていなかった。
「あっ」
僕は立ち止まった。
音が、聞こえてきたからだ。
ガァー…… イィー…… ガァー……
ガァー…… イィー…… ガァー……
あのいつも聞こえていた金属音、アポカリプティック・サウンドではない。なにものかの呻き声のような生々しい音。あの最初の日にあって以来、聞こえていなかった音だ。
それがいま、空にドロドロとした響きをあげている。
「おい、なんだあれは」
師匠も気づいたようで、立ち止まって呆然としている。
路地を歩く人々は、みんな無関心でスタスタと歩いていた。まるでそんな音など聞こえていないかのように。
幻聴?
僕は耳を塞いだ。けれど音はやまなかった。
ガァー…… イィー…… ガァー……
ガァー…… イィー…… ガァー……
やまないどころか、だんだんと大きくなっていくようだ。
そのとき、「なんだあれは」と言ってから、立ち止まったままだった師匠の様子が、おかしいことに気がついた。
変な方向を見上げて、固まっている。
僕もそちらを見て、思わず総毛立った。
日の落ちて薄暗い北西の空に、巨大な人影が立っていた。
透明な巨人の、うっすらとした輪郭が、天を衝く姿でそこにあった。
いつか、雲消し名人の山で見た、雲を纏う透明な巨人を思い出した。あれは、雷と嵐が迫るなかで見た、恐怖心の生んだ幻ではなかったのか。
目をこすっても、いま、僕らの前にいる巨人は消えていかなかった。何百メートル、いや、何千メートルになろうかという巨体は、ただじっとそこにある。根が生えたように微動だにせずに。まるで紀元前の昔から、そこにいたように、だ。
僕と師匠以外には見えていない。通行人はだれもかれも、立ち止まりもせず、僕らのわきを通り過ぎていく。
僕と師匠の2人だけが、透明な巨人の威容を見上げていた。
「な、なんですかあれ」
「…………」
のっぺらぼうだった巨人の顔に、口のような輪郭が生まれる。そうしてはじめて、巨人がこちらを向いていたことがわかる。
巨人の口がゆっくりと動く。
ガァー…… イィー…… ガァー……
ガァー…… イィー…… ガァー……
あの音がガンガンと響く。
その音は、もうはっきりと巨人の口から漏れ出ている。
Gaaa…… Iiii…… Gaaa……
Gaaa…… Iiii…… Gaaa……
僕は両手で耳をおさえた。音は消えない。異常なできごとに、頭のなかがグルグル回っている。
師匠が右手で口元を覆い、なにかに気づいたような表情をした。
「違う」
「えっ」
師匠は口元から手を離し、両手の人差し指と親指で四角形を作った。そのファインダーのはるか彼方に、巨人の顔がある。
師匠の唇が、巨人の声にあわせて、ゆっくりと動く。
バァー…… イィー…… バァー……
Baaa…… Iiii…… Baaa……
巨人の声とは違う発音で、師匠が声を出した。
「な、なんですか」
「見ろ」
師匠が巨人の口を指さした。その透明な輪郭が、ゆっくりと動く。
「あ」
たしかに、『ガ』じゃない。口が開いたままではなく、一度閉じた。破裂音だ。パイナップルの『パ』か、あるいはバカの『バ』。どちらかの口の動きに見えた。
師匠は真剣な表情で巨人の口の動きをなぞっている。さんざん繰りかえした、読唇術の練習のときと同じだった。
「間違いない。バ、イ、バ、と口が動いている」
慎重に師匠は言った。そして、僕の肩を叩いて引き寄せた。
肩を組むようにして、頬をくっつける。
「いいか、よく見ていろ。口の動きを。見ながら、先入観を捨てて聞け。なんと言っているのか」
僕は師匠の頬のやわらかさを直に感じながら、ドキドキと鳴る心臓をおさえつける。
顔をくっつけて、北西の空を見上げる僕らの視線の先で、巨人の口がまた動き出した。
Daaa…… Iiii…… Daaa……
Daaa…… Iiii…… Daaa……
そう聞こえた。
さっきまでと違う。
ガ、イ、ガ、ではない。
そして師匠が口の動きで読み取った、バ、イ、バでもない。
ダァー…… イィー…… ダァー……
ダァー…… イィー…… ダァー……
ダ、イ、ダ
そう言っていた。
その音節を最後に、巨人は口を閉じた。そして口の輪郭が消えていく。口が消えると同時に、顔の輪郭がスーッと空に溶けるように消えていった。そしてその溶解が、胴体に、全身に広がっていく。
僕らの目の前で、巨人は跡形もなく消えてしまった。
ふいに、雑踏の喧騒が耳に戻ってくる。道の真ん中で顔を寄せ合って立ち止まっている僕らを、奇異の目で見ながら、通行人が通り過ぎていく。
「マガーク効果だ」
顔を離した師匠が言った。
「な、なんですかそれ」
「人間の認知機能の障害だよ。Ga(ガ)の発音をしながら、Ba(バ)の口の動きをする人を見たとき、人間は、その音を、Ga(ガ)でもBa(バ)でもなく、Da(ダ)と聞こえたと認識するんだ」
「そんなの、はじめて知りましたよ」
「音だけじゃダメだったんだ。一般人には知覚できないあの音を聞き、なおかつ、あの透明な巨人を見ることのできる人間。それが揃ってはじめて、言葉の正体がわかる」
師匠がぶつぶつと言う。
「ダ、イ、ダ。ダ、イ、ダ……」
噛み締めるように、師匠はその音節を何度も繰り返した。そして眉をひそめて、ぽつりと言った。
「ダイダ坊……。ダイダラボッチ?」
「だ、ダイダラボッチって、あの昔話の巨人ですか」
とんでもない名前が出てきたことに、僕はさほど驚かなかった。いま目の前で起きていたことに、思考がすっかり麻痺していたのだ。
「だいだらぼっちだと」
師匠が、巨人の消えた空を見上げながら、たしかめるようにもう一度そう言った。



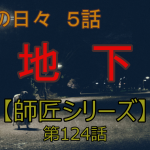
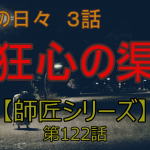
コメントを残す