地下
巨人を見た次の日、僕らはJRに乗って、となりの町へやってきた。
うちの大学の日本史研究室の元教授で、退官した今では、郷土史家という肩書きでのんびりと好きな研究を続けている、宮内氏を訪ねてきたのだ。
「だいだらぼっち?」
宮内氏は面白そうに、黒縁の眼鏡をずり上げた。
「ええ。このあたりで、だいだらぼっちの伝承があるのか知りたくて。先生ならご存知かと」
僕らは書斎で向かい合って座っていた。季節はずれの麦茶が、本だらけのテーブルのわずかなスペースに置かれている。
「ほうほうほう」
宮内氏は立ち上がって、書斎の一角をごそごそと探りはじめた。
「あなたは、いつも面白いことを訊きにきますね」
嬉しそうにそう言いながら、宮内氏は一冊の本を引っ張り出した。
「おっとっと」
本を抜いた勢いで、土砂崩れが起きそうなところを、慌てて3人でおさえつける。
「おう、ありがとう、ありがとう。よいしょ。で、ね。このあたりじゃあね、だいだぼう、とか、だいらぼうって名前で言い伝えが残っているね」
古そうな資料のページをめくると、山の上から巨人がこちらを覗いている絵があった。
「だいだらぼっちの伝承は、でいだらぼう、とか、でぃだらぼっち、とか、大太法師とか色々な名前で呼びならわされているね。関東とか中部地方に多いんだけど、それらに限らず北は北海道から南は九州まで幅広く分布している。多くは民話の形で言い伝えられてきて、様々なパターンがあるけど、よくあるのが手をついた場所や足跡が窪地や沼になったというものだね。土を掘ったところが盆地になって、盛ったところが山になったというパターンも多い。甲府盆地と富士山なんかが代表例だね。とにかく、大きい、ということを誇張した伝説ばかりだ」
宮内氏は、ええと、と言いながらパラパラとページをめくり、「ここだ」と開いてみせた。
「このO市では、こんな伝承がある。大昔、だいだぼうという大男が、山をつぶしたり、谷を埋めたり、好き放題暴れていたそうだ。その行いに怒った神様が、天の鳥船(アメノトリフネ)を使わして、従わせようとした。しかし、だいだぼうは言うことを聞かず、こともあろうに、神の使いの天の鳥舟を手で叩き落としてしまうんだ。いよいよ神の怒りに触れただいだぼうは、雷に打たれ、ついに、どどう、と仰向けに倒れてしまった。それが今の国分川と柳ヶ瀬川のあいだだ。平らになった地面は豊かな平野になり、今のO市の中心として栄え、今日に至る。というお話だ。叩き飛ばされた天の鳥船は、県北に落ちて、今の新城村の加賀美湖ができた、とされている」
宮内氏の語った、だいだぼうの伝説に、僕と師匠は顔を見合わせた。
「その、天の鳥船が出てくるのは、だいだらぼっちの伝説ではよくあるんですか」
「いやあ、珍しいねえ。ほかでは聞かないと思うよ。だいたい、だいだらぼっちというのは、のんきな大男なんだ。悪さをして、人間や神様にたしなめられる、というのはあまりないパターンだ。そしてこの天の鳥船というのは本来、出雲の国譲りの神話に出てくる神様だ。高天原の天津神が国津神に、地上、つまり葦原中国(あしはらのなかつくに)を譲るよう要求する際に、正使として使わしたのが、タケミカヅチだ。その副使としてお供したのが、この天の鳥船。船というけど、立派な神様だ。天鳥船神(アメノトリフネノカミ)とも呼ばれる。地元の言い伝えに当てはめてみると、つまり、だいだぼうが国譲りを迫られる国津神、そして天の鳥舟が、天津神の使い、という役どころになっているわけだ。面白いだろう」
宮内氏は満面の笑みで僕らを見つめている。
「先生。新城村の加賀美湖って、隕石湖だって言われてますよね」
「そうだよ。安和元年、西暦で言うと968年に起きた隕石落下だ。これは非常に興味深いことだね。実際に起きた隕石の落下が、民話の形で伝承されてきたという可能性があるわけだ。そうなると、この隕石を落とした原因である、だいだぼうというのは、なにか史実に関わるものを、象徴しているかも知れない」
「それは?」
「ううん、まあ普通に考えれば、中央政権にまつろわぬ、豪族といったところかな。実際にそのころで該当しそうな勢力もある」
「……」
僕は、宮内氏とは、別のことを考えていた。それはつまり、なんかの象徴などではなく、そのままこれが史実だった、という突拍子もない話だ。
師匠のほうをちらりと見たが、なにを考えているのはうかがい知れなかった。
「この雷で打たれた、というのは、タケミカヅチの力を表していると思われる。国譲りの神話と、だいだらぼっちの伝承をくっつけようと思った知識人がいたんだろうね。民話というより、神話といってもいいかも知れない」
宮内氏にお礼を言って、僕らはその家をあとにした。収穫があったと言えばあったのだが、なんだか様々なものがカチリカチリとはまっていく感覚とは裏腹に、その全体像が未だに不透明なままだった。
帰りのJRのなかで、師匠は黙っていた。なにかイライラと考えているようだった。
「ダイダラボッチが、国分川と柳ヶ瀬川のあいだで、仰向けに倒れたんですってね」
その姿は、師匠が地図にマーキングしている巨大な五芒星と一致しているのかも知れない。いや、きっとそうなのだ。
僕はそんな話をしたかったのだけれど、師匠はなにも答えなかった。ただ不機嫌に塞ぎこんでいるままだった。
◆
その2日後だった。僕は師匠に呼び出され、自転車に2人乗りで、市内の南のほうに位置する大槻町へ向かっていた。
そこには、株式会社ヤクモ製薬の本社ビルがあるのだ。
「あれだな」
駅から南へ南へと自転車をこいで、ようやくたどり着いた先には、20階建て以上はありそうな大きなビルがそびえ立っていた。市の中心地からは離れており、周囲には背の高い建物はほかにない。そのおかげで、遠くからもその威容をのぞむことができた。
そのビルは、緩やかな四角錐の形状をしており、前方が全ガラス張りになっていて、まるで巨大なメトロノームのような外観だった。
「金かかってそうなビルだな」
後輪の上に立ち乗りをしながら、師匠がつぶやいた。
来客用の駐車場に自転車を停め、僕らは大きな正面玄関ホールに入っていった。
だだっ広いフロアには、顔がはっきりと映るほど磨き上げられた黒い床の上に、妙な金属製のオブジェや観葉植物がいたるところに置かれている。気後れしてしまうような雰囲気だった。僕らのほかに歩いている人の姿はない。大きな木を描いた壁画の前に、受付があり、そこにスーツ姿の女性が立っていた。
「あのー」
僕らが近づくと、受付嬢はお辞儀をして、笑顔で、「いらっしゃいませ」と言った。顔は笑っているのだが、まるで作り物のような表情だった。だがこれも、変な先入観のせいかも知れない。
なにしろ、このヤクモ製薬というのは、あの角南グループの関連会社で、いわば角南家の傘下にある企業なのだ。ヤクモ記念病院など、多くの病院や薬局を従える、医療法人ヤクモ会の中核企業でもあった。
ヤクモ製薬は、僕や師匠の通う国立大学の大学病院に、多額の研究助成金などを出す大スポンサーであり、実質的に医学部の人事権を掌握していると言われていた。
そして、師匠が言うには、大学病院が持っていた、師匠の『ある病気』についてのデータを、入手している疑いがある、というのだ。
今日は、いきなりその敵の本陣に殴りこみをかけようという腹だった。戦の準備などなにもない。出たとこ勝負だ。
「顧問の角南大輝氏に面会をしたいのですが」
角南大輝というのは、医療法人ヤクモ会の理事長で、次期衆院選に出るという噂を、最近耳にしている。
「失礼ですが、お名前をお伺いしてよろしいですか」
師匠が名乗ると、受付嬢は淡々とした態度で言った。
「本日はお約束をいただいていないようです。申しわけありませんが、アポイントメントのないお客様は、お取次ぎできません」
あっさりとそう言われ、師匠は鼻白んだ。
「大輝氏は、今日はここにいらっしゃってますか」
「お答えいたしかねます」
ムッとして、師匠の表情が固くなる。相手は営業スマイルを崩さない。こういう、いきなり来てVIPに会わせろ、という手合いには慣れているのだろう。だいたいが、師匠にしても、お付の僕にしても、私服の学生然とした格好をしていて、とてもそんなお偉方に面会するような人間には、ハナから見えないはずだった。
「あー、じゃあね。だれでもいいから、話のわかりそうなヒトに、こう伝えて。ナイト・セルの本体が来てるから、って」
「は?」
「Night Cellだよ。研究主任とか、そういう肩書きの人ならわかると思うよ」
はいはい、早く、とばかりに師匠は両手を振って、せかした。
受付嬢は困惑しながらも、「少々お待ち下さい」と言って、どこかに電話をかけはじめた。
「よろしくねぇ」
師匠はふざけた態度で両手を頭の後ろで組み、僕のところへやってきた。
「いやだねえ。融通のきかない受付は」
「無理もないと思いますけど」
「あ?」
そんなやりとりをしていると、受付嬢が受話器を下ろし、こちらを見た。
「申しわけありませんが、わかるものがおりません。お手数ですが、今日のところはおひきとりください」
「おいおい。マジで言ってんの」
「アポイントメントを取っていただいた上で、再度ご来訪願います」
「アポイントメントって、どうやってとるんだよ」
喧嘩腰の師匠をいなすように、微笑を浮かべて受付嬢は言った。
「しかるべき手順でおとりください」
取り付くシマもない、という態度だった。
「しかるべき手順ってあれか。うちの医学部の教授あたりに紹介状を書いてもらってこいってか。そんなに敷居が高いのかよ、ここは」
つかみかからんばかりの勢いの師匠を、僕は慌てて止めた。
「師匠。いったん出直して、鹿田教授にでも書いてもらいましょうよ。紹介状を」
「鹿田教授は敵なんだよ、ここの」
師匠は僕の手を振り払った。
「まあいいや。今日は帰ってやるよ。べろべろべろーん」
師匠は、捨て台詞を吐いてから、舌を派手に動かすアカンベーをした。
「帰るか」
歩き出す師匠について行きながら、振り返ると、受付嬢は顔を引き攣らせていた。師匠の傍若無人な態度に、さすがの彼女も冷静なままではいられなかったらしい。
「あー、つまんねえなあ」
玄関を出ながら悪態をつく師匠に、僕は訊きたいことがあった。
「さっき言ってた、ナイト・セルってなんですか」
「ああ、お前知らなかったっけ。まあいずれ教えてやるよ」
またこれだ。色々と思わせぶりなことを言いながら、いつも肝心なことを教えてくれない。
ぶつぶつ文句を垂れながら、駐車場に戻ろうとしていると、ふいに前を歩く師匠が立ち止った。
「おっと」
背中にぶつかりそうになって、体を反らす。
どうしたのか、と思って師匠の肩越しに前を見ると、真っ白い、人の形をしたなにかが通り過ぎるところだった。 首がちぎれそうなくらい、ぶらんぶらんと左右に揺れている。
ざわざわ、と血管のなかに氷がまざったような感じがした。
霊だ。それも小さい。人間の背丈の4分の1もない。
僕らの見ている前を、小さな霊はするすると歩き、駐車場の奥へ進んでいく。師匠が、『静かに』というジェスチャーをしながら、ゆっくりとあとをつける。
ビルの側面に回りこんだ場所に、資材搬入路のような一画があった。コンテナや昇降機が並んでいる奥に、開いた扉が見える。霊は、そのなかへと消えていった。
「小人の霊だ」
師匠が壁際に身を隠しながらそう言った。
夏に、小人の霊の目撃談が増える、という不思議なことがあった。師匠の解き明かした秘密によると、それは自らが巨人であるかのような感覚を得てしまった霊が、己の体を縮めた結果である、というものだった。
それから、めっきり聞かなくなったし、僕らもそういう霊を見なくなっていたのだが、まさかこのタイミングで出くわすとは。
「師匠」
なにか偶然ではないものを感じた僕は、生唾をのんだ。
「わかってる」
搬入路の周囲を確認すると、人の姿はなかった。物陰が多いので、だれかが近くにいる可能性はあったが、師匠は思いきったようだ。身をかがめながら、壁沿いに近づくと、いっきに扉のなかに飛び込んだ。僕も急いでそれに続く。
扉の内側は、白い廊下に養生シートが貼られている空間だった。目の前は壁で、右手側は倉庫のような場所になっている。そちらから物音がしたので、慌てて左手側に進む。
曲がり角になっていて、首を伸ばして覗き込むと、守衛室らしいものが見えた。その手前には、地下へ伸びる階段がある。僕はその階段の先へ、白いもやのようなものが下りた痕跡を見た。小人の霊はそこへ行ったのだ。
こちらからなら、守衛室から見られずに、階段を下りることができそうだった。師匠と僕は目配せをしあい、足音を忍ばせて階段フロアに入り込んだ。
階段は、床も壁も真っ白だった。目がチカチカする。そして製薬会社だけあって、どこか病院のような匂いがした。
人の気配はなく、慎重に階段を下りていくと、折り返した先にドアがあった。そこで行き止まりになっている。
師匠がドアノブを握ると、ガチャガチャと数回ひねった。
「だめだ。開かない」
鍵がかかっていた。
師匠はドアに耳をくっつけ、物音を探っていたが、特になにも聞こえなかったようだ。
「なあ、守衛室ならカギがあるよな」
「ちょ、なに考えてるんですか」
ニマ、と笑うと師匠は階段を上りはじめた。止める間もなく、1階に戻ると、辺りをうかがった。
廊下にはだれもいない。
コソコソと足音を忍ばせて、師匠は守衛室のそばまで来た。僕もしかたなくついていく。
開け放たれたドアからなかを覗き込むと、師匠はひとつうなづいた。そして次の瞬間、「痛たたたた」と言いながら、お腹を押さえて、守衛室へ飛び込んでいった。
ガタリ、と椅子から立ち上がる音がする。
「どうしたんですか」
「お腹が。お腹が」
師匠が苦しそうな声を出したかと思うと、「あっ」と男性の声がした。バタバタという、床を踏む音。
僕が守衛室を覗き込んだときには、師匠のスリーパーホールドが、仰向けになった守衛の背後から、首筋にガッチリと食い込んでいた。
やりやがった。
僕は驚愕した。同時に、取り返しのつかないことをした、という思いが去来した。
動かなくなった守衛を離して、腰についていた鍵束をもぎ取った師匠が、「行くぞ」と言って走り出す。
マジでどうすんだ、これ。
階段へ飛び込み、師匠を追って駆け下りるが、頭のなかには、『暴行傷害』、『窃盗』、『不法侵入』といった単語がグルグルと回っていた。
師匠が行き止まりのドアに飛びつき、鍵をかたっぱしからはめ込む。
何個目かの鍵で開いた。
ドアを開けると、白い壁の狭い廊下があった。右側にはすぐまた別のドアがあり、左側にはエレベーターがあった。
「こっちだ」
僕にはわからなかったが、師匠は直感でエレベーターを選んだ。
壁には下向きのボタンしかない。それを押すと、すぐに扉が開いた。2人して乗り込む。
業務用の大きなエレベーターだった。かなり奥行きがある。操作パネルには、BF1とBF2の2つのボタンしかなかった。
BF2を押すと、箱がゆっくりと下に向けて動き出す。
すぐに止まり、扉が開いた。外を覗くと、またさっきと同じような廊下が広がっている。人の気配はない。近くに窓のない頑丈そうなドアが見えるが、師匠は首を捻っている。
「おかしいな。ここじゃない」
あの白い小さな霊の痕跡をたどってやってきたが、ここでそれが途絶えていたようだ。僕にはもうわからなかった。
「ん」
と言って、師匠は操作パネルの上についている鍵穴に気がついた。
「もしかして」
よく見るような、操作パネルの下の、配電盤かなにかを管理するための小さな鍵穴とは様子が違った。
師匠は守衛から奪った鍵束で、それに合う鍵を探した。
ガチリ。
小気味のよい音がして、鍵が回ったかと思うと、止まっていたエレベーターが再び動き出した。
下に向かっている!
終点のはずの地下2階から、さらに下っているのだ。
今度はさっきよりも長い。なかなか箱は止まらない。
おいおい。どれだけ下るんだ。
なんだか得体の知れない予感に、僕は手のひらに汗をかきはじめた。
シュイーン、という音を立てて、エレベーターは止まった。心の準備が整う間もなく、すぐに扉が開く。
「なんだよ、これ」
外は真っ暗だった。師匠が慎重に足を踏み出す。僕もおっかなびっくりそれに続いた。
そこには想像もつかない光景が広がっていた。
だだっ広い空間だ。エレベーターの室内から漏れる光の反射で、目の前には壁らしきものが左右に伸びているのがうっすらと見て取れる。それも15、いや20メートルは先だ。そして左右の空間は、どこまでも漆黒の闇で塗り固められていて、先の様子がまったくわからなかった。
「ここはいったい、なんだ」
師匠の声が、ゆるやかに反響する。途方もなく巨大な空間がそこにあった。
上を見ると、天井も高い。目を凝らすと、ダクトのようなものが、天井を這っているのが、うっすらと見える。照明らしいものもあるようだが、暗いままだ。
黴臭いような濃密な、空気が周囲にみっしりと詰まっている。
「おっとぉ」
前に歩こうとした師匠が、つんのめるようにして立ち止まる。暗くて見えなかったが、崖のような段差があった。
師匠がそのへりにしがみつくようにして、屈む。
「おい、これは……」
僕も師匠の横で、それにならう。
「うそでしょ」
自分の目を疑った。
暗順応が少しずつ進んでいく。だんだんと闇に慣れていく目が、段差の下に敷き詰められている砂利石を認めた。 そしてそのなかで左右に伸びる、鉄のレールを。
線路だ。線路がそこにあった。
僕は混乱した。なんでこんなものが、こんなところに?
「地下鉄?」
師匠が口元をおさえて呻いた。
地下鉄だって? そんなバカな。大都会じゃあるまいし、O市には地下鉄なんて存在しない。そんなことは地元民じゃない僕にだって、当たり前の知識、常識だ。
しかし、いま、僕らの目の前には、地下鉄の路線としか思えない空間が、たしかに存在していた。
呆然としていると、師匠が、「あっ」と言って横を見た。 そちらに目をやると、白い小さな人型のなにかが、ゆらゆらと揺れながら、線路の右のほうへ進んでいくのが見えた。線路はどこまで伸びているのか、とても先は見通せない。果てしなく、闇が広がっている。白いなにかは、その闇の奥へと消えていった。
「いったい、どうなってやがる」
師匠がそうつぶやいた瞬間だった。背後で、光が瞬いた。
振り返ると、エレベーターの扉が閉まるところだった。箱が上昇していくのが一瞬見えたあと、すぐに僕らは完全な暗闇のなかに取り残された。
「ゲームオーバーだな」
師匠がなげやりにそう言った。
侵入に気づいた連中が、すぐに下りてくるのだ。
「どうすんですか」
「なるようになるだろ」
それから間もなく、エレベーターが戻ってきて、どやどやと数人の男たちが下りてきた。さっき師匠が絞め落とした守衛の姿もある。
「投降しまーす」
師匠があっけらかんとそう言って、両手を上げた。僕も慌てて両手を上げて、抵抗の意思がないことを示す。
どうか、なるだけ穏便にすみますように。
祈るような気持ちで、迫ってくる男たちを待った。



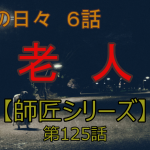

コメントを残す