星型要塞都市
角南家での老人との会合から2日が経っていた。
その日、僕はバイトで小川調査事務所にやってきた。特に調査の依頼は入っていない。ただの資料整理だ。情報が命の興信所は、最近の様々な事件を常に整理している。タカヤ総合リサーチなどは、その辺がかなりシステマティックに整備されている。わが小川調査事務所も、スズメの涙の賃金で働く物好きなバイトが増えたおかげで、所長の古巣であるタカヤ総合リサーチの真似をして、情報整理にいそしみはじめた、という具合だ。
久しぶりの雑居ビルを見上げて、ため息をついた。
あのヤクモ製薬に乗り込んだ日、わけのわからないうちに角南家の本宅へ連れていかれ、師匠と角南盛高老人との対決を傍観することになった。会合は老人の言葉に激高した師匠が、「帰るぞ」と言って席を立って終わった。
警察行きをなかば覚悟していた僕だったが、すんなり帰してくれたことに驚いた。師匠のほうは、貸しを作ったのはこっちだ、という態度で、足音も高く、案内してくれた執事っぽい人に悪態をつきながら屋敷を出た。
またスーツ姿の男たちに拉致されはしないかと、ドキドキだったが、屋敷のすぐ外に置かれていた自転車を見てほっとした。ヤクモ製薬本社ビルに停めていたものを、わざわざ持ってきてくれていたのだ。
どうやら本当にこのまま帰れそうだ、と思って僕は急いで自転車にまたがった。しかし、焦る僕を尻目に、師匠は出てきたばかりの屋敷を見上げて、いつまでも睨みつけていた。
あれから、師匠と少し気まずいのだ。
老人と師匠との会話は、正直わけのわからないことばかりだったが、師匠にとってはテキに重大な秘密を握られていた、ということに、怒りを覚えていたようだ。
訊きたいことはたくさんあった。けれど、師匠は、いまは訊くな、という態度ではっきりと僕を牽制していた。
そのときに聞いた、印象的な単語が猛烈に頭のなかをめぐっていた。
今日は、師匠も来ると聞いている。どうやら小川所長に、ヤクモ製薬の一件がばれたらしい。こってり絞られるのだろう。好き勝手に危ない橋をわたっていることを。それも憂鬱の種だった。
タンタン、と階段を上り、小川調査事務所のドアの前に立つ。
「こんにちは」
なかに入ると、小川所長の姿はなく、かわりに意外な人物が、師匠のデスクに座っていた。
「ま、松浦」
思わず、そう呻いてから、「……さん」と付け足す。
見間違いじゃない。暴力団、石田組の若頭補佐、松浦がたしかにそこにいる。黒いダブルのスーツ。黒縁の眼鏡。そしてオールバックの髪。いつも現れるときの格好だ。
「やあ、お邪魔している」
松浦はこちらをちらりと見てから、机のうえに視線を落とす。その視線の先には、机いっぱいに広げられた地図があった。
「あ、なにしてやがん……ですか」
僕は歯切れ悪くつめよった。どうも師匠のようにはいかない。
松浦は、師匠の机の引き出しにあった地図を、勝手に出して見ていたのだ。それは、保育園の事件からはじまる、黒いマネキンの手足にかかわるできごとをマーキングしたものだった。
そこには5つの点が描かれている。北の頂点は商科大学の近くにある。それはマネキンの頭部が出てきた事件のときのものだ。
そして、その右下、南東のほうにいくと、国分川がちょうど蛇行するところの手前に点がある。保育園で、園庭からマネキンの左手が出てきた事件だ。その右側、西の線対称の位置は、柳ヶ瀬川の手前、馬霊刀の事件のときの、マネキンの右手が出た場所。そこから南東の方角、地図上で斜め右下には、先日ショッピングモールでガス爆発が起きた事件のあった場所がポイントされている。ここは、事件が起こる前から、師匠が予測して書き込んでいたものだ。
最後にその西、線対称の位置には、柳ヶ瀬川の手前に点が落とされている。二条神社の近くだ。ここはまだ何も起きてない。少なくとも僕らはなにも知らない。だが、師匠は、これを含めた5つの点をそれぞれに結び、地図上に巨大な五芒星を描いていた。
対角線をそれぞれに結ぶと、五芒星。そして辺を結ぶと五角形が現れる。対角線の1本が、約6千メートルあまりの大きな星だ。
師匠はそれを、仰向けに倒れた巨人だと言った。途方もなく大きな巨人の姿だ。そのあとで、郷土史研究家の宮内氏にダイダラボッチの伝承を教わった。かつてこの地には、だいだぼうという巨人がいて、暴れまわっていたが、神の怒りに触れて雷に打たれ、大地に倒れたという。
それを聞いたときには、背筋に嫌なものが走った。あまりに出来すぎている。偶然とは思えなかった。だが、その先に待っているものは、とても信じられない、人智を超えたものだったのだ。僕は考えを保留していた。精神衛生上、そうするしかなかった。
「勝手には見ていない。許可はとっているが」
松浦がそう言ったときに、はじめて僕は、その向かいの席に服部さんが座っているのに気がついた。ずっといたのに、あまりに存在感が薄くて目に入らなかったのだ。
「許可って、服部さん、なにを勝手に」
僕が怒りかけると、服部さんはスッと顔を上げて、ふん、と鼻で笑い、また手元の書類に目を落とした。
松浦が地図をなぞりながら言った。
「所長が留守だったので、待たせてもらっている」
まずいな。師匠ももうすぐ来るぞ。
ヤクザを心底嫌っている師匠がこの場に来たら、ひと悶着ありそうだった。そう思っていると、案の定、タンタンタンという、リズムのよい足音が階段を上ってきた。
「おおっす」
元気よくドアが開いて、師匠が顔を出した。
「まっ、つうら」
師匠も驚いたようだが、僕のように「さん」をつけなかった。
「元気そうだな」
松浦は地図から目を切って、顔を上げた。
「地図を見せてもらいましたよ。面白いな」
「なにしに来た」
師匠は最初から喧嘩腰だ。
「正規の依頼に来たんですが。所長が留守のようだ。さっき連絡があったようですが、急用ができたそうです」
ホワイトボードを見ると、服部さんの字で『所長帰所時間不明』と書いてある。
「あなたが来るというので、挨拶をしてから帰ろうと思ってね」
松浦は立ち上がった。そして地図を手に持って、応接テーブルのほうへ歩いていった。
「まあ掛けたまえ」
松浦はまるでこの事務所の主のような態度で、僕らに声をかけた。
「こちらも面白い話をしましょう」
師匠は松浦を睨みながら、松浦の向かいのソファに座った。僕もその隣に腰かける。服部さんはワレ関セズ、という姿勢で、自分の仕事を淡々とこなしていた。
「おまえ、あの写真はどうなったんだ。まだ手を引いてないのか」
「ああ、あの写真はまだ手元にあります。角南一族のことを調べていると、なかなか奥が深くてね。切り札はまだとっておきたい。それより、角南盛高会長に会ったそうですね」
「なんで知ってるんだ」
「言ったでしょう。角南一族を調べていると。そちらにも情報源が色々とありましてね」
松浦は青白い顔をニコリともさせずに、よく通る声で答える。
「あなたたちがヤクモ製薬に乗り込んで、暴れた話も聞いています。無茶をするものだ。ですが、おかげでこちらも知らなかった情報を得ることができた。あなたたちが、藪を叩いてくれるおかげで」
「なにが藪だ」
「師匠」
僕は師匠の袖を引いた。この男にあまり強い態度に出ないほうがいい。先日の写真に関するいざこざで、ボコボコにされて酷い目にあった僕は、このヤクザどもに必要以上に関わりたくなかった。
「消えた大逆事件のことで、あなたは、角南大悟が青年将校たちを決起させたイデオロギーは、もうだれも知らない。そんなものがそもそも本当にあったのか、と言いましたね。どうも、その片鱗が見えてきたような気がする」
「なんだと」
「あなたたちが、ヤクモ製薬の地下で見たという、地下鉄のようなもの。それを知って、驚きました。ちょうど私は、角南大悟が戦前に計画していた、地下鉄建設のことを調べていたところだった」
松浦はそこで、手帳を取り出した。
「日本における最初の地下鉄は、地下鉄銀座線。昭和2年、1927年に開通しています。早川徳次率いる東京地下鉄道と、五島慶太率いる東京高速鉄道の2つの私鉄が路線の東西を担っていた。地下鉄計画自体は、大正の時代から、小田急や三井財閥、渋沢栄一などが次々と申請していました。しかしこれらが、なかなか通らない。さまざまな目論見が絡んでいましたが、東京市と内務省の軋轢があったり、軍部の横槍などもあったようです。いずれにしても、この時代の地下鉄計画は、いずれも人口の増え続ける首都圏の人々の移送のためのものです。首都圏以外で次に早いのは、1933年の大阪の御堂筋線。やはり、人口密集地域に敷設されたものでした。だが、この時期、首都圏や大都市圏から離れたこのO市で、地下鉄建設計画が持ち上がった。地上の交通網だけで十分だ、といえる状況であったにもかかわらず。それも、当時、とても人口や人の流れが集中している場所とは言いがたい地点を繋ぐ計画でした。これを主導したのが、われらが角南財閥、というわけです。それも陸軍士官学校の教官の職にありながら、角南財閥を裏で差配する立場になっていた、かの角南大悟が中心となっていたようです。1934年のことです。1939年に起こった大逆事件の5年前でした。角南家の強力なゴリ押しがあってもなお市議会は紛糾し、結局却下されました。最終的な認可を行う内務省へも、頭越しに働きかけていたようですが、無駄骨に終わっています。それはそうでしょう。だれが考えても、必要性がないのだから。ただ、角南大悟は、阪急東宝グループの創始者、小林一三の知己を得て、様々な助言をもらっていたようです。小林一三流の、あえて人口的に未発達な地域に線路を通すことで、沿線を開発していく手法を採ろうとした、とも、とれる動きです」
そこで師匠が口を挟んだ。
「ちょっと待て。地下鉄計画は頓挫したっていうんだな」
「そうです。O市の地下鉄は、現在にいたるまで、建設されていない」
「じゃあ、私たちが見たのは、いったいなんだ」
「・……ここからが、さらにキナ臭い話なんですが。市議会に提出された資料に、特に極秘扱いされたものがあります。議事録など、公式な記録自体は残されていませんが、当時の議員の覚え書がありました。なかば偶然入手できたのですがね。なかなに凄まじいものでした」
松浦はもったいぶるようにそう言った。はじめて会ったときには、会話はシンプルに、という信念を他人にも押し付けるような男だったのだが、いまはこういう、時間をかけた会話を楽しんでいる様子だった。師匠とのやりとりが楽しいのだ、このヤクザは。
「地下鉄計画は、首都移転計画の一部だと言うのです」
「首都移転計画だって? このO市にか」
「そうです。角南大悟は、盧溝橋事件も起こっていないこの時期に、日本がいずれ中国のみならず、アメリカ、イギリスなどと全面戦争にいたることを予見し、さらには大敗の末、国家の解体危機にまで及ぶ可能性を考えていたらしい。その際に、敵軍に蹂躙され復興困難となった首都東京から、首都機能をスムーズに移転すべく、その受け皿として、このO市を、ただちに再開発すべきだと主張したのです」
「無茶苦茶だ」
「そう、無茶だ。だから、その時点での人口動態や人やモノの流れなど無視した計画でした。場合によっては、O市から住民をすべて追い出してから、新首都建設を行おうというものだったから。こんなもの、通るわけはない。計画はつぶされ、角南大悟は失意のもと、ふたたび士官学校の教官の職に専念することになる」
松浦は、テーブルに広げた地図に、とん、と手のひらを落とした。
「この地図に落とされた5つの点」そう言って、僕らの顔を見る。「これは、角南大悟の地下鉄建設計画の起点となる5つの地点と一致しています」
「えっ」
僕は驚いてもう一度地図を見た。
「角南大悟は、この5つの場所を、それぞれ対角線上に結ぶ形で、地下鉄網を敷こうとしていました。ちょうど、ここに描かれた、五芒星の形に」
「そんなバカな」
師匠が口元をおさえる。
「ヤクモ製薬の本社ビルがあるのは、この地図でいうと、ちょうど五芒星の両足にあたる対角線の交差するところ。人の体でいうなら、股のところです。その地下に、地下鉄の遺構があった。それを知って、私も驚きました。まさか、角南家は、認可を受ける前に、あるいは却下されてから、勝手に地下鉄を敷設していたのか、と。どこまでそれが伸びているのか、実に興味深い。まさか完全にすべての計画路線が設置されているわけはないでしょうが、たとえ一部分でも、市民に知られずに、この街の地下を刳り貫いていたとなれば、驚愕を禁じえないですね」
僕も唖然としていた。こんなこと、本当にあるのか。噂話として聞かされたら、きっと鼻で笑っただろう。けれど、僕と師匠は、実際にあの地下空間を見てしまっているのだ。
「とんでもねぇな、角南家ってのは」
老人の息子である、角南盛高との邂逅も踏まえたような感慨で、師匠はつぶやいた。
「これこそが、狂心の渠(たぶれごころのみぞ)じゃねえかよ」
師匠は、東西先生に聞かされたことを口にした。なるほど、思った。
「ただ……、あの音を聞きましたか。ちょっと前まで、夕方に聞こえていた、あの気味の悪い音を」
「アポカリプティック・サウンドか」
「あの音は、地下の空洞の空気の流れで反響する音が原因だ、という説があるそうですね」
「まさか」
「さて、どれほどの規模の空洞があれば、市内のあれだけの地域にわたって、あんな音を出せるのでしょうね」
松浦は話を戻そうというように、手帳をめくった。
「この地下鉄計画が五芒星の形をしているのは、どうやら、星型要塞都市論というものが関係しているらしい。函館の五稜郭を思い浮かべればわかりやすいですね。あのような星型をした城は、ヨーロッパ、特にイタリアやオランダで発達した築城理論が元になっているそうです。五角形の要塞を造り、その頂点にそれぞれ砲台を配置し、連携して全方位に砲撃を浴びせる砲術理論がその原理だとか。その5ヶ所はそれぞれ地下道で結ばれ、物資や人の移動が流動的に行うことができたといいます。東京も、皇居を中心にこの星型要塞の形を成している、という説もあります。東京、秋葉原、飯田橋、四ツ谷、虎ノ門の各駅がその頂点だそうですよ。眉唾物の説ですがね。ただ、このO市では、角南財閥が現実に、地図の5ヶ所を頂点として、巨大な要塞を形作り、それぞれを地下鉄で結ぼうとしていました。そして、要塞の中央には、角南家の本家がある」
松浦が指さしたところは、五芒星の中央だった。そこは、僕たちがつい2日前に連れて行かれた場所だ。
「おい、首都を移転するなら、そこは天皇の住まいがあるべき場所だろう。要塞はその内側を守るためにあるんだから。角南家の邸宅を、皇居として進呈しようとしてたってのか」
「それは、のちの歴史が語っているでしょう」
師匠と僕は、ハッとした。そうだ。大逆事件。地下鉄計画の失敗のあと、角南大悟は、陸軍士官学校の教え子だった青年将校を扇動して、天皇の暗殺を試みている。
ぶわあ、と嫌な汗が湧き出す感じがあった。
これは、想像以上に、とんでもない話だ。とても一大学生が関わっていい話ではない。
僕はもう、この場から逃げ出したかった。
「飛び神明、という言葉があります。伊勢神社から、天照大神の御神体が各地に飛んでいって、神明社という神社が次々と作られたそうですね。天照大神が出て行くなど、伊勢神宮が認めなくても、日本各地で勝手にそう主張された。終戦後、天皇陛下が人間宣言を行った際にも、天皇家に代々伝わる天照大神から受け継いだ神の血脈の力が、そこで途絶えたとして、飛び神明を主張する輩がいたそうです。人間宣言をした天皇から、天照大神の本体が抜け出して、自分にやどった。だから私が正統な天皇だと。バカバカしい話ですが、角南大悟の行動にいたっては、冗談ではすまされない」
「神代の時代から続く、天照大神や、天津神の神々たちの力の、受け皿になろうとしたってのか。暗殺によって」
師匠もさすがに血の気の引いた顔をしている。
さて、と言って、松浦は立ちあがった。
「そろそろおいとましますよ。本当は、依頼をしにきたのですが、所長の頭越しにあなたに頼むと、また首を縦に振ってくれなそうなのでね。出直すことにします」
「なんだその依頼っての」
「最近、若者のあいだで流行っている、おかしな薬のことで、ちょっとね」
松浦は、それ以上は説明しないつもりのようだった。ドアから出て行くとき、こちらを振り向いて言った。
「そうそう、春にあなたはこう言いましたよね。覚えていますか。あの写真のことで、角南家に関わろうとした私に、『化け物に、喰い殺されろ』と」
「ああ、言った」
「あなたも、もうその尾を踏んでいるのではないですか」
では、また。
そう言って松浦は去った。
師匠は、松浦の消えたドアを、いつまでも、睨みつけている。
僕は、松浦の言葉に少なからず衝撃を受けている師匠に、「大丈夫です」とも、「僕が守ります」と言えずに、そのかたわらで、ただ立ちつくしていた。
「化け物に、喰い殺されろ、だって?」
ふいに、師匠がぼそりとその言葉を反芻すると、急いだ様子で自分のリュックサックの中身を取り出しはじめた。
「どうしたんですか」
「その捨て台詞は、あいつのいない場所で言ったんだよ! 田村の隠れ家からの帰り道で」
「あ」
そういえば、そうだ。気づかないうちに松浦からリュックサックに金を入れられていて、師匠が怒ってつぶやいたのだった。夜道の途中だ。僕と師匠本人しか、聞いたものはいない。どうしてそれを松浦が?
「これか」
リュックサックの中身を全部出して、口から裏返してみると、底のあたりに布地と同じ色のテープが貼ってあった。
師匠がそれをはがすと、黒っぽい小さな板状の機械がテープの裏に仕込まれていた。
「それは?」
「盗聴器だな。それから、たぶん位置情報の発信機もセットだ」
「盗聴? あの時ですか」
「田村の隠れ家から、あそこにいたヤクザのだれかに尾行されてたんだ。盗聴器で拾った会話を録音されてたわけだ」
「発信機はどうしてですか」
「前にあったろ。松浦に居場所を知られてたことが」
「え。あっ。喫茶店で不破さんに会ったとき……」
弓使いを追っていた事件で、喫茶店で不破刑事と情報交換をしているときに、急に松浦が現れたことがあった。あれは、たしかに不思議だった。師匠がそうと知らずに発信機を持ち歩いていたのか。
「さすがに電池切れか」
板状の機械を調べていた師匠がそう言うと、床に落として踏みつけた。機械はプラスティック片を散らばらせて、砕けた。
「中身の入ってるリュックサックの底に、テープでこんなものを貼り付けたんだ。私たちの目の前で、気づかないうちに金を入れたのとはわけが違う。どんな手品師でも、あのタイミングでできるわけがない。その前に貼り付けられてたんだ」
師匠は吐き捨てるようにそう言うと、デスクのほうを振り向いた。
「服部! お前だな」
僕も驚いてそっちを見る。服部さんは机に向かって、黙々とワープロのキーを叩いていた。師匠の呼びかけに動じた様子はない。
「お前、ヤクザなんかに買収されやがったのか」
服部さんはピタリと手を止め、眼鏡をそっと触りながら言った。
「証拠でもあるんですか」
「お前しかいないんだよ。私が人前でリュックサックを放り出すのは、この事務所のなかだけだ。こいつも」
そう言って師匠は、僕の首に腕を巻きつけた。
「所長も。松浦なんかの言うことを聞く道理がない」
服部さんはふっ、と息を吐いた。笑ったようだった。
「だとしたら、なんですか」
開き直ったようなその言葉に、師匠は罵る言葉を探しているように、一瞬口ごもった。
「だとしたら、お前の」
師匠は低い声で言った。
「服部調査事務所には、入ってやんねーよ」
すねた子どものようなその言葉に、服部さんの頬が一瞬こわばったのを、僕は見たような気がした。



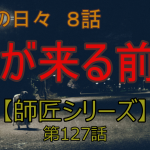
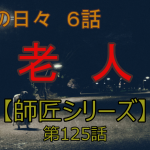
コメントを残す