老人
目の前に、深い皺の刻まれた老人がいる。彫りの深い顔は、まるで往年の映画俳優のようだ。ただ映画を撮るには、少し痩せすぎているように見えた。
年季の入った黒檀の机のうえに、和服のそでからのびた細い腕が置かれている。その腕が、大きな灰皿を引き寄せて、もう片方の腕がタバコの灰を落とす。
老人は値踏みするように、さっきから一言も発せずに僕と、その隣に座る師匠を見つめている。
空調のきいた和室は明るく、向かいあう老人と僕らの左手側の、開け放たれた障子のうしろには全面の大きなガラス窓がある。その外には広い縁側が、そしてその向こうには色鮮やかな庭園が広がっていた。築山に紅葉、そして控えめなししおどし。広大な庭は、ここが建物のなかだということを忘れさせる。そう。この和室と、それを囲む庭自体、とてつもない大豪邸の建物に囲まれた空間にあるのだ。
「で、どうしたらいいんですか、私たちは」
老人のだんまりに痺れを切らして、師匠が言った。
「し、師匠。なるべく、なるべく穏便に」
僕は小声でささやいたが、師匠はまったく気にしていないようだった。
つい先ほど、ヤクモ製薬の本社ビルの地下に広がっていた謎の空間で、僕らは守衛や社員たちに捕まった。師匠など、絞め落とした守衛にお返しにとばかり、うしろ手をつかんで捻り上げられ、地面に組みふせられた。僕も抵抗の意思はなかったが、かなり乱暴に取り押さえられてしまった。
それから、エレベーターに乗って、1階の相談室のような個室にしょっ引かれて、外から鍵をかけられた。警察に通報されるのかと思ったが、どうやら様子が違うようだった。助かったと思うべきか、それとも見てはならない秘密を知った僕たちに対し、警察を介さずに、懲らしめようよというのか。スチール机と椅子だけの殺風景な部屋に閉じ込められ、これからやってくる不透明な運命に、僕は気が気ではなかった。
一度、ドアが開いて、さっき師匠と問答を繰り広げた受付嬢が姿を見せ、僕らの顔を確認しながら、スーツ姿の男たちになにごとか説明していた。
またドアが閉じ、鍵がかけられる。僕らに対する尋問はまだなかった。
いくらなんでも、この法治国家で、しかもテレビCMも出しているような大きな企業が、まさか一市民に酷いことはしないだろう。
そう考えながらも、僕はドキドキしっぱなしだった。外から一方的に鍵がかかる部屋ってなんだよ。
「やーくも、やーくも、やくもせーいやくー」
師匠はそのヤクモ製薬のCMソングをのん気に歌っている。風邪薬のバージョンだ。
「ピンポーン」
そう言ったあと、僕に、なあ知ってるか、と訊いてきた。
「色んな製薬会社薬のCMで、いつもピンポーンって鳴るのは、あれ、薬事法で決められてるんだぜ。風邪薬とか鎮痛剤とかを広告するときは、『使用上の注意をよく読んでお使い下さい』、って注意喚起しないといけないんだけど、そのときに視聴者の注意を喚起するよう、音声等で警告するようにってされてるんだ」
そんな豆知識を披露する師匠に、僕は恨みのこもった眼差しを向けた。
そうこうしているうちに、再びドアが開いた。長身で細身のスーツ姿の男がひとり、入ってきた。30歳くらいだろうか。向かいの椅子に座り、三白眼で、こちらをにらむように見つめてくる。
「ナイト・セルの本体だと名乗ったとか?」
「名乗ったよ。名乗ったんだから、そっちも名乗れよ」
「ちょっと、師匠」
けんか腰の態度に、僕は机の下で上着の端を引っ張る。
「二岡(におか)だ」
「どちらの二岡さんだよ」
「会長秘書をしている」
「会長ね。江藤さんだっけ。ヤクモ製薬の会長は。私が用があるのは、顧問の角南大輝さんなんだけど」
「……」
挑発するような師匠の態度に、反応を示さず、二岡はじっと師匠を見つめている。見るからに頭のキレそうな顔だ。
そんな男の冷たい視線を、師匠は真っ向からにらみ返している。
「浦井加奈子本人だよ。真下教授が提供したファイルに、患者の写真くらい載ってるだろ」
「なんのことかわからないが、君たちは受付で訪問を断られたにもかかわらず、正当な理由なく建物内に侵入し、警備員に暴行を加えた。自分たちが今どういう立場か、わかっているのか」
「こっちだって乱暴に取り押さえられて、手ひどくやられたよ。こいつなんて、肘が逆に曲がっちまってるんだぜ」
「えっ、えっ?」
指をさされて、僕は思わず自分の肘を確認したが、もちろんそんなことはなかった。
「なぜ会長はこんなガキを」二岡はぼそりとそう言うと、椅子から立ち上がった。「ついて来い」
「ついて来いって、どこにだ」
「ついて来れば、わかる」
二岡は部屋から出て行った。師匠と俺は顔を見合わせたが、すぐにあとを追った。
部屋の外には守衛など、複数の男が囲むようにして立っていたので、逃げられそうになかった。僕らは先を歩く二岡についていく。角を曲がったところで、恰幅のよい、いかにもお偉方、という感じの初老の男性に出くわして、声をかけられた。
「オッ、こいつらですか、賊というのは。ふとどきなやつらだ。こいつらを、どうされるんですか」
「あなたは知らなくていいことです。それより、警備体制に不備があるようですね。見直しをする必要があるでしょう」
二岡は、自分の父親ほどの年齢の男に、歩きながらそう答えた。
「は、これはその。すみません」
初老の男性はカチンと来た様子だったが、その表情を隠すように頭を下げた。
僕らが通り過ぎていくうしろで、周囲にいた男が、「江藤会長、こちらへ……」と口にするのが聞こえた。
師匠は、ハッとした顔で二岡の背中を見つめる。
それから僕らは、裏口のようなところへ連れて行かれ、黒塗りの外車の前に立たされた。
「乗れ」
二岡がそう言った。
これ、乗ったらどこに連れて行かれるんだ、という、生物としてのしごくまっとうな危機感に、足が竦んでいると、あろうことか、師匠が嬉々として自分から後部座席に乗り込むではないか。しかたなく、僕も乗り込む。それを見届けてから、二岡も助手席に乗った。そして、行き先も告げられぬまま、連れてこられたのは、見たこともないような、広大な日本家屋だった。
目隠しなどはされていなかったので、そこが、ヤクモ製薬から北に行った場所にある、住宅街だということがわかった。市内ではトップクラスの、いわゆる高級住宅街だ。そんな地価の高そうな場所に、これだけの敷地を構えているというのは、とんでもない大金持ちだということがわかる。車でそのまま敷地へ入っていくとき、玄関の表札を見たが、やはりというか、『角南』という名字が確認できた。
おそらく、角南家の本家なのだろう。
僕らは大きな建物の前で車を下ろされた。
「あんたが秘書をしている会長ってのは、つまり、そういうことなんだな」
師匠が前を歩く二岡に問いかけた。彼はそれに答えず、建物のなかに入っていった。しかたなく、僕らもそれに続く。建物の奥に、大きな庭があり、庭のなかには、さらにそのまんなかに平屋建ての日本家屋があった。
「私はここまでだ」
二岡が開け放たれた縁側の前でそう言った。縁側のすぐ下には、さっき玄関で脱いだはずの靴が置かれていた。家の使用人が、先回りして届けたのか。
「あそこが、会長のお住まいってわけか。まさに奥の院って感じだな。ところでひとつだけ訊きたいんだけど」
師匠がなにげなく二岡のほうを振り向いた瞬間、ほとんどノーモーションで、右手の裏拳が突き出されていた。
それを予期していたように、二岡は左手で師匠の拳を受け止めた。ドシッ、という鈍い音がした。
「手癖が悪いな。報告のとおりだ」
師匠は驚いた顔で二岡に言う。
「やっぱあんた相当やるな。うしろから蹴ってやろうとしてたけど、ずっと隙がなかったからな。会長秘書ってのはボディーガードも兼ねてんのか?」
二岡は押し出すように師匠の腕を放すと、「行け」と言った。
「はいはい、わかったよ。おい、行こう。奥の院に」
そうして庭を越え、入った日本家屋の書斎に、深い皺のある、和装の老人の姿があったのだった。
「警察に突き出すなり、すればいいでしょう。不法な手段で建造物に侵入したんだから、覚悟はできてますよ」
師匠は挑発するように言った。
「すみませんすみません。警察だけは許してください。このとおり反省してますから」
僕は机に頭をこすりつけるようにして、謝った。なんだかわからないが、ここを乗り切れば、前科がつくようなことはまぬがれそうな気がしていたのだ。
「おまえなあ」
師匠が呆れたように言ったが、僕は頭を下げ続けた。
老人がようやく口を開く。
「ナイト・セルの本体だと名乗ったとか」
秘書の二岡と同じことを訊いてきた。しかし、師匠はそれを聞いて、「そっちも名乗れ」と言い返すことはせず、笑みを浮かべた。
「研究主任どころか、こんな大物が釣れるとは、光栄ですよ。あなたは、ヤクモ製薬を含む、角南グループ全体の実質的な持ち株会社、角南産業の会長兼、中核企業である角南建設の会長、角南盛高氏ですね」
老人は師匠の軽口にも思える物言いにも動ぜず、ゆっくりと頷いた。
「現当主である県議会議員の兄、角南総一郎氏を差し置いて、角南グループ全体を掌握する首領(ドン)。かつて、日本昭和史の影のフィクサーと呼ばれた父、角南大悟をほうふつとさせる豪腕に、政界、財界を問わず恐れられている存在」
僕は驚いて師匠を見た。僕の知らないあいだに、師匠はかなり角南家のことを調べ上げているようだった。
老人はタバコの煙をゆるゆると吐き出して、息をついた。
「お会いできて、こちらも光栄だ」
老人は小刻みに笑うように言った。
「夜の細胞の主よ」
師匠は老人を睨みつけた。
「あんたか、私のことをかぎまわってるやつは」
老人は首を振った。
「なんの。漏れ聞こえてくるだけよ」
そのとき、ドタドタと玄関のほうから足音が聞こえてきた。思わず身構えると、書斎のなかに大柄な男性が入ってきた。
「親父、なんだよ急に呼び出して。忙しいってのに」
男性は、40代後半くらいだろうか。ゴルフ焼けなのか、日焼けして精悍な顔つきをしていて、彫りの深い顔立ちをしている。目元が、目の前の老人によく似ていた。
「こいつらか、不法侵入者ってのは。とっとと警察に突き出してやれよ」
僕はその鋭い眼光に睨まれて、首をすくめた。やっぱりそうなるのか。甘い希望が断たれる音がした。
「お前を訪ねてきたそうだ」
老人が顎をしゃくる。
「俺を?」
「ヤクモ製薬の顧問、角南大輝さんですね。医療法人ヤクモ会の理事長でもあられる」
「なんだおまえは」
老人とは違って、敬意のまったくない態度で、その男、角南大輝は師匠を睨みつけた。
「用があるのは、あなたのほうじゃないんですか」
師匠は負けじと言い返す。
老人はそのやりとに、くくく、と笑って助け舟を出した。
「大輝は知りはせんよ。ナイト・セルのことなど。あれは、真悟がしていることよ」
「真悟?」
師匠が聞き返すと、老人は言った。
「大輝の息子。儂の孫よ」
「なにを言ってるんだ、親父。あの研究機関の話なのか」
「真悟という人は、ヤクモ製薬でなにか研究機関をやってるんですか」
角南大輝は苦虫を噛み潰したような顔をした。なにか触れられたくないことのようだ。
「もう帰せよこいつら。そんなこと説明する必要はない」
「地下を見られたそうだ」
角南大輝はギョッとして目をむいた。
「あそこをか。だから、とっととあんなもの埋めろって言ったんだ」
「あれはO市にはないはずの、地下鉄の路線ではないですか」
師匠が畳みかけるように言うと、角南大輝は怖い顔で凄んだ。
「おい、その辺にしておけよ」
「警察ですか。突き出せばいい。全部言ってやりますよ。あんたらが非合法の地下鉄を隠してるって」
「別に非合法じゃない。警察の幹部だって、市の、県の幹部だって知ってるさ。ただの大戦前の遺物だ」
「大戦前? 第2次世界大戦の前からあったんですか、あれは。そんなこと聞いたこともない」
「おおっぴらにする必要もないからの。それにあれはただの遺構に過ぎん。いずれ埋めてしまうだけだ」
老人が補足した。
「その遺構が、研究機関とやらと関係があるのか」
師匠の敬語が完全に飛んでいる。こうなるともう止められない。
「関係はないな」
老人はタバコの灰を落として、もう一度口元に持っていった。
「子どもというのは、不思議な力を持っていることがあるものだ。科学では説明のできない、不思議な力だ。ユリ・ゲラーを知っているかね」
「ああ」
「かの超能力者を名乗る男のパフォーマンスを、テレビで見た子どもたちのなかに、自らも力に目覚めたものがあったそうだ。スプーン曲げの少年のように、多くは子どもがそんなことをしないだろう、という心理を逆手にとったイカサマだったが、なかには本当に説明のつかない力を発揮するものもおった」
「おい、なんの話だ」
「親父」
「そんな子どもらの力を引き出し、研究すべく、設立した研究機関があるのだよ」
「ソニーの、ESP研究室みたいなものか」
師匠が老人の話に、なにか思い出したようだ。
「それが、ヤクモ製薬のなかにあるのか」
「おい、もうやめろ。親父も。あんなもの、税金対策のただの遊びだろ」
「お前は、息子が、真悟がやっていることを理解していないようだな」
老人はタバコを消すと、師匠のほうに向き直った。
「これでわかったであろう」
「ああ、だれと話すべきかってことが」
師匠と老人は目を合わせた。
「大輝、もう行ってよいぞ」
「はあ?」
老人は、文句をいいかけた息子を、ひとにらみで黙らせた。
角南大輝は僕らに不愉快そうな視線を向けながら、チッと舌打ちをしたあとで、書斎から出て行った。よほど老人のことが怖いらしい、ということが見てとれた。
そのあてつけのような足音が去ってから、老人は口を開く。
「とは言っても、儂から話せることはあまりない。真悟に任せておるからな」
「その真悟ってのは、どんなやつなんだ」
「……優秀な男だ」
老人はポツリとそう言った。
「もしかして、のっぺりした卵みたいな顔したやつじゃないか」
師匠がだれを想像しているのかわかった。だが、老人は答えなかった。かわりに別のことを言った。
「あれは、恐ろしい」
なにか後悔の念のようなものが、老人の顔に垣間見えた気がした。
「なあ、その真悟ってやつがやってる、超能力の研究をする機関があるというのはわかったけど、その研究対象のなかに、もしかして、RSPKの、反復性偶発性念力の能力を持っている子がいたんじゃないか」
師匠の声がかすかに震えている。
「……報告を受けたことはあった」
老人は慎重にそう言った。
「その子が死んだのは、知ってるか。母親にやっかいもの扱いされて、殺されたのを」
「知らぬな」
老人の言葉に、師匠の様子が変わった。僕は思わず身を引いた。
師匠の全身から、殺気が針のような鋭さで迸っている。
「あんたらが、たきつけたのか。そんな欲しくもない、不幸しか呼ばない能力を」
声の端々から、危険な感情の高まりが察せられた。髪の毛が、かすかに逆立っている。ただならない気配に、僕は師匠を止めるべきか迷った。
そのときだった。老人が窓に向かって手を振った。次の瞬間、開け放たれた障子の向こうに、シャッターのようなものが一斉に下りた。
部屋の明かりも消え、書斎は一瞬で真っ暗になった。
「わっ」
僕は驚いて立ち上がった。なにがどうしたのか、身を守るべきなのか。混乱する頭で、周囲を手探りする。
そのとき、視界の端に、キラキラと輝く光の粒子を見た。
それは師匠の頬から漏れ出ている。これまでに何度か遭遇した現象だった。
「これが、シュプライト変異体の崩壊光か」
高揚した老人の声が暗闇にこぼれた。
「死に近づいていく、破滅の光だ。だが、なんと、美しい」
「これのことを、知っているのか」
師匠が殺気を押し殺した声を出した。
「もちろんだ。菅田洋一郎(すがた よういちろう)を覚えているかね」
「菅田?」
暗闇のなかに、淡い光の粒に照らされて、師匠の顔が浮かんでいる。
「おまえに、天狗の肉を食わせた男だ。彼の、常人から大きく異なる体を研究したのは、今の超能力研究機関の前身であった機関だ。儂の作ったものだ。菅田は実に不思議な存在だった。本人の意思と関係なく、死ねない体だったからだ。自分がなにを食べたのか、理解しているのかね」
「知らねぇよ」
「あれは、恐らく、恒星間航行用の生体維持システムなのだ。有機物でできた微小な機械群。それが宿主の生命機能を保全している。摂食によってそれを体内に取り入れたものにも、その恩恵があった。自律的に新たな宿主の全身の機構を走査して、その生物としての恒常性、内部環境を維持しようとする。鹿田教授は細胞に宿るその有機的機械群を、シュプライト変異体と呼んだようだがね。そして、その変異体を含む細胞を、ナイト・セルと名づけた」
「なにをわけのわからねぇこと言ってやがる」
「残念ながら、元から好んで毒素を摂食する嗜好のあった菅田は、研究も半ばにして、早々にナイト・セルの機能の限界を迎えてしまった。彼の死に際し、役目を終えたシュプライト変異体が大気中に放出され、大量の崩壊光を発しながら消滅していったという。儂はこの目で見られなかったが、いまこうしてその再現を見ることができた」
「ボケてんのか爺さん。世迷いごとは寝てるときに言えよ」
老人は愉悦の声をあげる。不愉快な響きだった。
「その光は、おまえが、生物としての死に近づいていく証の光だ。もう長くはあるまい。これまでに得た、何度も死んでいるはずの肉体的ダメージを、ナイト・セルが支えられなくなっているのだ。特に、分娩は致命的だったな。数に限りのあるナイト・セルが、胎児と母体に分離したのだから」
分娩?
その言葉に、僕は耳を疑った。
「特に娘のほうは、出産の際にナイト・セルが体内環境の変化を無理に修復しようとしたせいなのか、逆に体質が弱く生まれてきてしまった。もうナイト・セルは機能していないのだろう」
「てめえら」
師匠が怒りを込めた声を喉の奥から絞り出した。
「私の家族に手を出したら、殺してやる」
また、師匠の頬から光がこぼれ落ちる。流れるように美しく、そして、はかない輝きだった。



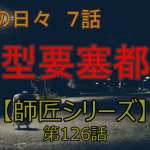
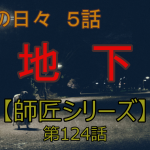
コメントを残す