くじら座
師匠に、劇団を見に行こうと誘われた。
弓使いが部屋を訪ねてきて、一晩を一緒に過ごしたことを師匠に言い出せず、もんもんとしていたころだったので、正直気まずかったが、ついていくことにした。
手にしたパンフレットを見ながら歩く師匠のあとに続いて、僕はためいきをついていた。僕がある意味師匠を裏切っている現状を、まだ自分のなかで整理できていなかったからだ。
師匠は完全に弓使いを、『敵』としてとらえている。それは犯罪者だからという単純な理由なのか、それとも、のさばらしていては、あまりに危険な人物という理由だからなのか。はっきりとはわからなかったが、いずれにしても僕とはスタンスが違っている。僕は、共通の敵を持つ仲間という認識だった。少なくとも、仲間になりうる、という思いを持っていた。あまりに楽観的な考えかも知れなかったが。
『敵』
その言葉を頭のなかで再生するとき、浮かぶ顔があった。かつての愉快な隣人の顔だ。だんだんとその特徴のない顔が、記憶のなかでさらにぼやけていく。不思議な感覚だった。
「お、ここだ」
師匠が足を止めた。繁華街から少しはずれた場所にあるビルだった。ビルの前では暖かそうなコートを着た若者たちがたむろしている。
『劇団くじら座公演』
そんな看板が出ている。ビルの壁にはさまざまな劇団のチラシが、ところせましと張り出されていた。
劇団くじら座。聞いたことがあった。白い仮面を被って演技をしている写真を、新聞の広告かなにかで見たことがある。
そしてその仮面はこの夏、小人と巨人にまつわる事件の際に、師匠と僕の前に現われ、不気味な印象だけを残して消えた人物が被っていたものと、よく似ていた。
僕はすでに想像していた。あののっぺりとした仮面の下に、のっぺりとした卵のような顔が隠れていることを。
「当日券3,000円だってよ。意外と高いな。持ってるか」
料金を読み上げる師匠の声に、我にかえった。
「え。チケットあるって言ってなかったですか。オゴリじゃないんすか」
「言ったっけそんなこと」
師匠はそう言いながら、玄関を入ったところにある受け付けで料金を払っている。
騙された。
僕は慌てて財布を取り出して、なけなしの千円札を数える。
「だれ扱いにします?」
当日券を頼むと、受付の人にそんなことを聞かれた。黄色いスタッフジャンパーを着ている人だった。劇団の人なのだろう。
あとで知ったが、こういう小劇団だと、だいたいチケットは団員の買い取りで、それを知り合いなどに頑張って売るのだそうだ。当日券の場合は、だれの紹介ということにするのかで、チケット販売のノルマ達成に影響してくるらしい。
そのときはよくわからず首をふると、「あ、いいです。どうぞ」と席のほうへ通された。
小さな箱で、客席は50くらいだろうか。入り口のあたりは地元の小さな映画館に雰囲気が似ていたが、客席の数ははるかに少ない。
1人3,000円で、かける50人とすると、1公演で15万円の売り上げということになる。見たことろ満席にはならないようだし、安い前売り券の人も多いだろうから、もっと収入は少ないだろう。劇場使用料がどのくらいするのかわからないが、差し引きの利益を劇団員の人数で割ると、時給換算では、ずいぶん安くなりそうだった。いや、そういえば入り口に物販があったな。ともかく、まあこういうのは趣味の延長で、稼ぎと考えてはいけないのかも知れない。
照明が落ちて、公演がはじまった。
部屋のベッドで少女が寝ているシーンからだった。うしろの壁に取り付けてある時計や絵、そして荷物棚などの家具類はどれも奇妙に曲がっている。
そこに母親らしき女性がやってきてドアをノックする。少女は起き上がり、曲がってしまった家具をなんとか直そうとして悪戦苦闘する。早く起きて学校に行きなさいと怒る母親。少女はドア越しに弁解しようする。
公演のタイトルは『変身』と銘打たれている。随所にフランツ・カフカの小説『変身』を思わせるシーンがあり、その名作を現代風に翻案したもののようだった。
カフカの『変身』が、ある日目覚めると大きな毒虫になってしまっていた青年の苦悩を描いているのに対し、この小劇団のものは、少女に外見的な変化はない。けれど、明らかに別の存在になってしまっていた。
そうして彼女が身につけた不思議な力で、周囲の人間が振り回されていく喜劇と悲劇とが繰り広げられていくのだが、登場人物すべてが白い仮面を被ったまま演じられていた。
正直、もっと前衛的で芸術的で、理解不能な劇を予想していたのだが、内容自体は意外とわかりやすく、面白かった。これでは、あの奇妙な仮面を被る必要がない気がする。
劇中、隣の席の師匠はずっと正面を睨みつけていた。その張り詰めた気配が伝わってきて、こちらまで妙な緊張を強いられていた。
いったいなにが気に食わないのだろう。
劇は、母親によって部屋に閉じ込められた少女が、だんだんと衰弱し、ついに死んでしまうシーンで終わった。
なんだよそれ。
救いのない話だ、と不愉快な気持ちになったとき、照明がすべて消えて、舞台は真っ暗になった。その暗闇のなかで、キラキラとかすかに輝く、植物の葉脈のようなものが浮かび上がった。いや、あれは鱗か。爬虫類や魚の、目の細かい鱗。
その淡い光が、宙を舞いながら部屋を抜け出て、舞台袖に消えていくのを、観客たちは息を潜めてじっと見ていた。
美しいシーンだった。
少女は、死んではじめて肉体という殻を破り、自らが変身すべきだったものになれた、ということなのだろうか。僕にはそういう物語のように思えた。
公演が終わり、演じていた劇団員たちが舞台に揃って挨拶をした。仮面は脱いでいた。なんだか、顔や名前をあかせない、事情を持った人たちのような印象を持ってしまっていたので、拍子抜けだった。仮面の下は、みんな普通の人たちばかりだった。
拍手のなか、師匠は腕組みをして眉間に皺を寄せている。
「終わりましたよ」
観客たちが帰り始めるなか、そう呼びかけると、師匠はようやく腰を上げた。
「どうしたんですか」
「うるせぇ」
不機嫌さを隠そうともせず、ズダズダと足音を乱暴に響かせて歩く。
どうしたんだろう。仮面のことはあっても、劇自体はさほど気になるような内容ではなかった気がする。後味の悪さはあっても、むしろなかなか良かったのではないだろうか。学芸会の劇しか間近で見たことがなかった僕には、役者たちの演技の緻密さ、リアルさがとても印象に残った。
「ありがとうございました」
出口で劇団員たちが客の見送りをしている。さっき死んだばかりの少女と、彼女を見捨てた母親が、並んでにこやかにお辞儀をしていた。
師匠はその劇団員たちのなかで、一番年かさの男に話しかけた。
「あの、どうしてみなさん、仮面を被ってたんですか」
「あ、はじめてのかた? いや僕らは、アーニー・レイスっていう新進気鋭の劇作家の演劇理論に基づいて、人間を人間たらしめる一番の武器である顔や表情を、あえて画一化させることで、観客の視点を演者の全身に広げ、舞台全体をその視野のなかに……」
「ああ、やっぱいいです」
自分から訊ねておいて、師匠はいきなり話の腰を折った。
「今日のお話はどなたが書かれたんですか」
ムッとしながらも、男は答えた。
「脚本は、座長の達樹(たつき)ですよ。オリジナルです」
「ああ、それはパンフにありました。達樹蓮(たつきれん)さんですよね。そのかたはどなたですか」
師匠は周囲を見回す真似をする。
「今日は来てないんですよ」
「え、座長なのに? 座長って、劇団の主催者ですよね。来てないんですか」
「まあ、実質うちは、演出やってる副座長の吉崎さんがしきってるから」
男はめんどくさそうに息を吐いた。
「座長はどんな人ですか」
「変わり者だよ。だって普段から、あ、まさやーん、いつも来てくれてサンキュー! 田中ちゃんも」
男は話の途中で、顔見知りらしい客たちのなかに飛び込んでいった。
「普段から、仮面を被ってるんだな」
師匠はその背中に呼びかけた。聞こえていなかったが、答えはわかっている、そんな声色だった。
客はほとんどが劇団員の知り合いばかりなのか、そこかしこで話の輪が出来て、出入り口付近からはなかなか人がいなくならなかった。
師匠はオリジナルのプリントシャツを置いてある物販コーナーを手仕舞いしている女性に、また話しかけた。
「この劇団に、曽我って人います? ソガタケヒロ」
「曽我くん? いたなあそんな子。いたけど、すぐやめちゃったよ」
「やめた、ってどうしてですか」
「さあ、いやになってバックレたんじゃないんですか。そういう人多いですから」
「そんなもんですか」
僕は師匠の口から曽我タケヒロの名前が出たことに驚いていた。夏に起きた、髪の毛にまつわる事件に関わっていた男だ。劇団に入っていたという話だったが、この劇団だったのか。
「どこに行ったかって、さあ、知らないですよ。なんかふらっと来て、すぐやめたから。うちで知ってる人もいないと思いますよ」
「そうですか。あと、座長にはどこに行ったら会えますか」
「座長ですか。それが、私もよくわかんないんですよね。稽古場にも来ないし。まあ、座長って言っても、うちの場合、オーナーみたいなもんなんで。脚本(ホン)とお金出してくれて、口は出さないっていう。あは」
どうしてもって言うなら、副座長の吉崎さんが知ってるから、と教えてくれた。その吉崎さんはなにかの打ち合わせがあるとかで、すでにこの場を離れていた。
「帰りましょうか」
ようやく人が引けてきた劇場の前で、僕は師匠に声をかけた。師匠はあいかわらず不機嫌そうな顔をしている。
「あ、次の予告です。ぜひまた来てください」
スタッフがビラをくれた。次回公演の案内のようだ。タイトルと出演者が公開されているが、公演時期などは未定になっていた。
『だれも寝てはならぬ』
僕はタイトルを読み上げた。どこかで聞いたことがあるような言葉だった。
「トゥーランドットだな」
師匠も同じビラをもらってつぶやいた。
「歌劇の名作だ」
「ああ、オペラの」
なんとかという世界3大テノールのおじさんが歌っているのを、聴いたことがあった。
「次はオペラなんですかね。歌が上手い人がいるのかな」
「さあな」
劇場をあとにして、僕らは寒々とした夜の道を歩きはじめた。
師匠は道みち、ねっせんどーるまぁ、と、うろ覚えの歌詞で、『だれも寝てはならぬ』を歌っていた。
僕は石ころを蹴って転がしながら、それを隣で聴いていた。ところどころムニャムニャとごまかしながら歌っていたが、それがかわいらしかった。
声色を変えて、女性のコーラスらしい部分を歌ったあとで、師匠が立ち止まり、僕のほうを向いた。
「いまのところ、なんて歌っているか、知ってるか」
「え、さあ」
「だれも、彼の名前を知らない。わたしたちは、必ず、殺される」
そう歌っているんだ。
そう言って、師匠はまた歩き出した。
僕はぞくりとしたものを感じて、足が一瞬動かなかった。
彼の名前。
彼の名前を、だれも知らない。
わたしたちは、殺される。
コンビニの前で立ち止まった僕の前には、影が長く伸びていた。蹴っていた石は、いつのまにかどこかに行ってしまっていた。
「あそこ見てみな」
師匠がそう言って空を指さした。
「星ですか」
「んー、暗くて見えないか」
路上には店の明かりが溢れ、夜空は白くかすんでいる。
「こっちこっち」
師匠は僕を近くの公園に誘った。小さな山を模した遊具と、ブランコが置いてある公園だった。敷地の周囲には背の高い木が並んでいて、街の喧騒から切り離された静かな空間だった。そして十分に暗い。自分の呼吸音が大きくなる。
僕らは山の遊具の上に登った。ところどころに登攀用の凹みがあったので楽に登ることができた。
「ペガサス座はわかるか。ほら、あの四角形の」
「どれですか」
「秋の大四辺形っつって、秋の星座では有名なやつだ」
師匠の指の動きを追って、なんとかそれをとらえる。
「ああ、あれですか」
「でな、四角形の左下の点から、ぐぐーっと下にいくと、明るい星があるだろ」
「んん? あれかな」
「それがくじら座のβ星、デネブカイトスだ。くじら座で一番明るい星だ。それがくじらのしっぽ。で、左のほうに胴体が続いている」
「はあ」
僕は目をこらして、くじらの巨体を夜空に追いかけた。
「なんとなくわかるような。わからないような。でも、くじら座って言えば、今日の劇団の名前ですよね」
「そうだ」
師匠は空を見上げたままで、腰を下ろした。僕も隣に腰かける。石の遊具の冷たさが、ズボン越しに尻に伝わってくる。
「あのくじら座のお腹のあたりにあるτ(タウ)星ってのが、太陽系に似た恒星系で、しかも地球からすごく近いから、よくSFなんかで人類の植民地として登場している。未来の地球人の移住先だな」
「詳しいですね」
「調べたんだ」
師匠の趣味は、時とともにコロコロと変わる。そしてすぐに飽きる。読唇術だのホーミーだのといった、その場限りの趣味に、僕はさんざん付き合わされてきた。
「私は、心臓ですよ」
ふいに師匠がそう口にした。その言葉にハッとする。
「輝きを変える心臓です」
そう言って、師匠は上着を両手で握り、胸元をあらわにするような仕草をした。
「それは」
僕は思い出していた。隣人の言葉を。その卵のような顔を。
「あの言葉が引っかかってな。どこかで聞いたことがあるような気がして。調べてみたんだ。そしたら、あったよ。あの星だ」
師匠は空を指さした。僕は満天の星のなかに目を凝らす。
「つっても、今は見えないけどな」
「見えないのかよ」
僕のツッコミにも平然として、師匠は指でくじら座の輪郭をなぞった。
「くじらの心臓の位置にある星が、珍しい長周期の脈動変光星ミラだ。見た目の明るさが、時とともに変わる性質を持っている。普段は暗い星で、肉眼じゃ見えないんだけど、極大期って呼ばれる一番明るいときには、β星のデネブカイトスに匹敵する輝きを見せるようになる。昔の人は、この、くじら座にある奇妙な性質の星のことを、ミラ・ケチ(Mira-Ceti)、『くじら座の不思議な星』って呼んだんだ」
「くじら座の、不思議な星」
僕は無意識に復唱した。
「ケチ、ケーティがラテン語のくじら座。ミラが不思議なっていう意味だな。あの空の巨大なくじらは、輝きを変える心臓を持っているんだ。」
『輝きを変える心臓です』
卵男はそう言った。これはくじら座を、そしてその心臓の星、ミラを意味していたのだろうか。
「あいつが、輝きを変える心臓だって言ったのは、まるで自分自身は、くじら座の一部であって、くじら座そのものじゃないって言っていたような気がしますね」
「だけど、心臓はコア、中枢部だ。そういう主張にも思える」
沈黙が下りた。冷たい風が吹いて、公園を囲む木々の黒々とした枝葉を揺らす。そのざわざわとした音があたりを包んでいる。
僕は心細さを覚えた。光るものはすべて空にある。僕らは暗い夜の底で、冷たい地べたに腰かけ、息を潜めている。
「あの劇団さあ」
師匠が口を開いた。
「くじら座って名前なの、たぶん座長がつけたんだぜ」
「……まあ、オーナーだって言ってたし、そうなんでしょうね」
くじら座っていう名前なのは、偶然だと思うか?
そういう言外の問いかけが、たしかにあった。僕は黙っていた。すると師匠は話題を変えた。
「今日の劇、どう思った」
「どうって、まあ良かったんじゃないですか。後味は悪かったですけど。それでも、最後は綺麗な演出で、ちょっと救われたっていうか」
「チラシに書いてあったんだけどな、今日の公演の『変身』は、2回目だってよ」
「そうですか」
僕は、師匠を包む気配が、変わったのを感じた。公演中に、怒りを込めて舞台を睨みつけていたときと、同じだ。
「去年の秋に続いて、2回目だと」
それがどういう意味かわからない僕には、師匠の怒りの根源がどこにあるのか、わからなかった。ただその怒りは、空に向けて、蒸気の柱が吹き上げているようだった。
無言で、師匠は山の遊具を滑り降りた。
僕も慌ててお尻で滑る。
歩き出した師匠は、少しして僕を振り返った。そして、着地の衝撃でずれていた黒い帽子を直しながら言った。
「近いうちに、だれも寝てはならない夜が、くるかもな」



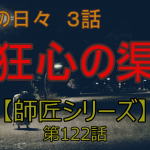
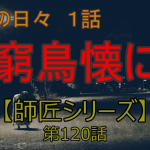
コメントを残す