冬が来る前に
「なんの用なの。1人で来るなんて、珍しいわね」
「まあ、ちょっと」
僕は、喫茶店の窓際の席で看護婦の野村さんと向かい合っていた。彼女は大学病院で看護婦長をしていて、師匠とは古くからの知人だった。その縁で僕も何度か会ったことがあった。もちろん、1人で会うのははじめてだ。
「あんまり時間はとれないわよ」
野村さんは窓の外をチラリと見た。イチョウの木の向こうに、大学病院の建物がある。
野村さんに会いに行ったとき、病院内の喫茶室に案内されそうになったのを止めて、無理に外へ誘ったのだ。師匠の主治医だった鹿田教授と会った際に、師匠と教授の会話から僕は、大学病院のなかは悪の組織の勢力範囲だ、という印象を刷り込まれていたからだ。実際にその親玉と会って、師匠の被害妄想ではなかったことを知ったばかりだった。どこの壁に耳があるか、知れたものではない。
「で、なんなの。どうせあの子のことでしょ。本人が言わないことを私からは言えないわよ」
「鹿田教授と会いました」
僕がそう言うと、野村さんは息をのんだ。
「加奈子さんの主治医だったそうですね。免疫病理学の権威だとか」
「ええ、そうよ」
野村さんはゆっくりと返事をした。
「その鹿田教授が言ってたんですよ。加奈子さんとの出会いを。看護婦の野村君が、わけのわからないことを言いながら、手を引っ張って、ひきあわせたって」
「……そうね。そうだったわね」
一瞬、懐かしそうな表情が浮かんだ。
「野村さんは、今は循環器科の看護婦長ですよね。加奈子さんと会ったときは、何科にいたんですか」
「さあ、何科だったかしら。ずいぶん昔のことだから」
彼女はコーヒーを手にとって、僕から目線を切った。
忘れるわけはない。今でも深い付き合いのある加奈子さんが、患者だったときのことなのだから。
「産婦人科ですね」
僕の言葉に、野村さんはハッとして顔を上げた。その表情が答えを語っていた。
「……違うわ」
「いえ。きっとそうです。大学の医学部の友人に頼んで調べてもらってもいいんですよ。国立大学付属病院の看護婦は公務員だから、異動情報は公表されてますよね」
野村さんはため息をついて、額に手をやった。
「あなた、あの子に似てきたわね」
その言葉に一瞬、僕のほうも動揺してしまった。
「で、どうなんですか」
「そうよ。産婦人科だったわ」
それから、しばらくのあいだ沈黙が下りた。昼下がりの喫茶店は客もまばらで、静かな店内にBGMのジャズが流れていた。野村さんはコーヒーカップを片手に、窓の外を見ていた。
物悲しいサックスのソロに入ったところで、僕は口を開いた。
「鹿田教授の専門は免疫病理学でしょう。どうして、その鹿田教授を、産婦人科の患者だった加奈子さんと会わせたんですか」
「もうやめなさい。他人のプライバシーに関わることを、言えるわけないでしょう」
「僕はもう他人じゃない」
野村さんだけではなく、自分でも思いもよらない強い言葉が出たことに、僕自身驚いていた。
「鹿田先生が、たまたま当直だったからよ」
「鹿田教授は基礎医学の人間ですよね。臨床医じゃない」
「…………」
僕は野村さんの睨むような視線に、射すくめられた。
「あなたの、思っているとおりよ。あとは本人に訊きなさい」
野村さんはそう言うと、伝票を掴んで立ち上がり、レジに向かっていった。
僕はその背中を見ながら、頭を掻いた。
どうも、師匠のようにはいかないな。
そう思って、ため息をついた。
◆
小川所長の家を訪ねたのは、野村さんに会った日の夜だった。閑静な住宅街にある、広い庭付きの立派な家だ。
「どうしたんだ、急に。なにか相談事かい」
突然の訪問だったが、僕は客間に通された。奥さんの律子さんが2人分の紅茶を置いて、微笑を浮かべると、「ごゆっくり」と言って部屋を出ていった。彼女はいつ会っても、物腰が柔らかで上品な人だった。
ドアの向こうへ消える彼女が右足を引きずっているのを、僕は横目でチラリと見た。事故だと聞いていた。
「深刻そうな顔だな。バイト代アップの件だったら、少しなら相談に乗るけど」
え、そうなの。一瞬、雀の涙の時給を思い浮かべて心が揺らいだが、今日はそういう話をしに来たのではないのだ。とはいえ、野村さんのときのようにはいかない。なにしろ相手はバイト先のオーナーなんだから。今後のことも考えないと。
庭の見える窓は開けられていて、網戸になっている。そこから風がかすかに吹いてきていた。
「少し寒いな」
小川さんは立ち上がって、窓を閉めた。
「もう秋も終わりだな」
向かいに座った小川さんは、ポツリと言った。そう、冬が来るのだ。僕はその言葉がなにか不吉な暗示を秘めているような気がして、気分が悪くなった。
「松浦が事務所に来たことを聞きましたか?」
僕は直接本題に入りづらくて、別の話を持ち出した。だが、それも気になっていたことだった。
「ああ。依頼をしたいようだ。ちょうど今日電話があったよ。いちおう加奈子には話すつもりだけど」
「ヤクザと関わりたくないようですけど」
「もちろん僕もだ。だけど、なかなかこの業界は難しくてな。情報筋ってのはどうしても、そっち方面も絡まざるをえないんだ」
小川さんは本当にいまいましげにそう言った。
「加奈子が拒否するなら、当然この話はなしだ。僕が責任をもって断るよ」
「所長、その松浦ですけど……」
「なんだ」
「前に、丸山警部によろしく、って言ってたんですよ」
「松浦が?」
小川さんは険しい顔をした。
「そのあと、西署の不破刑事に会ったときに、そのことを加奈子さんが言ったら、怒りだしたんです。それで話は終わったんですけど、なにかあるんですか、丸山警部に」
小川さんは、かつて県警の刑事だったことがあり、不破刑事とは同期の間柄だったと聞いている。律子さんの父親で、小川さんの義理の父である、タカヤ総合リサーチの高谷所長は、その県警本部の捜査第一課長だった。高谷所長が県警を退職するときに、部下だった小川さんを引き抜いたのだ。丸山警部というのは、そのとき小川さんの上司だったと加奈子さんが言っていた。そのあたりのことが、妙に気にかかっていたのだ。なにしろ、僕らは弓使いの事件で、雑貨屋が襲撃された際に、警察沙汰になり、しょっぴかれるところを、不破刑事から西署の刑事第一課長の丸山警部へ口利きをしてもらって、助かったのだ。僕は会ったことはないが、なにかと縁がある。それだけに、ひっかかりが気持ち悪かった。
「ううん」
小川さんはしばらく唸っていたが、膝に手を置くと、「しかたないな」と言った。
「君も知っておいたほうがいいかも知れない。だけど他言無用だよ。僕から聞いたというのも含めて」
「わかりました」
「警察が、民間人の情報提供者を使うことを知っているだろう」
それは聞いたことがあった。
「S(エス)でしたっけ」
「そう。民間人っていうけど、その多くはヤクザだ。そういう連中が、警察に情報を流すのは、それなりの見返りがあるからだ。彼らの生業にかかわる犯罪を見逃す代わりに、そのときどきで取締りを強化している銃器や覚醒剤なんかを出させて、警察の手柄にする。そういうことは、大なり小なり昔からあった。春に、与党の副総裁が銃撃された事件があっただろう。あれで警察庁が銃器対策にやっきになってて、今はどこの警察も、Sをつかって拳銃をかき集めてるみたいだ」
「そんなことがあるんですか」
「まあ、話半分に聞いてくれよ。僕はどっぷりつかる前に辞めた人間だから。ただの想像もあるかも知れない」
小川さんは冗談めかして笑った。
「うちの県警の暴力犯担当は、昔からSと……。というか、ヤクザと関わりが深いんだ。それ自体は珍しいことじゃないんだけど。僕のいた県警本部で、あるとき、暴力犯担当の捜査第二課が、暴力団同士の抗争で、相手を撃ち殺した犯人を捕まえてきたんだ。それを、殺人の担当の捜査第一課長だった高谷警視が、突き返したんだよ。二課が、その組に頼まれて、実行犯じゃなく、因果を含めさせた三下で手を打ったことがわかっていたからだ。身代わりだな。高谷さんはそれを認めなかったんだ。結局、一課の強引な捜査で、真犯人だった組の幹部が捕まった。これで二課の面目は丸つぶれになった。それで、もとからあつれきのあった、一課と二課の反目が決定的になったんだ。僕ら一課の人間は、どんなに睨まれようが、高谷さんについていくつもりだった。組織のなかで疎まれても、ああいう人が警察を引っ張っていくべきだと思っていた。だけど、現実は理想どおりにはいかなかった。高谷さんは、当時の刑事部長に呼びだされて、言われたんだ。『なあタカヤ。柔軟にいこうや』って。刑事部長室から飛び出してきたとき、顔が真っ白だったのをよく覚えているよ。そのやりとりはあとで聞いたんだけどね。高谷さんは刑事部長を信頼していたからね。裏切られたと思ったんだろう。それからしばらくして、高谷警視は県警を退職することになった」
「小川さんも辞めたんですよね」
「まあ、僕のことはいいよ。とにかく、うちの県警で刑事部長までが、ヤクザとのつきあいを肯定していた背景には、菱川組という存在があったんだ」
「菱川組って、あの有名な?」
「ああ。日本最大の広域指定暴力団だ。そのころは、全国に勢力を広げているところで、各地で地元の組織とバチバチにやりあっていたところだった。その菱川組がうちの県にも進出してきたんだ。元々、このあたりでは博徒系の組織が幅を利かせていたんだけど、その大きいところのいくつかがくっついて立光会(りっこうかい)という組織に一本化された。戦後10年とかの話らしいけど。とにかく、昔からこの立光会がうちの県では最大の組織だったんだ。対立する小さい組はいくつかあったけど、よくも悪くも、このあたりのアンダーグラウンドの世界は、立光会の作る秩序のなかにあったわけだ。だから、県警の暴力犯の担当は、彼らと付き合わざるをえなかった。そこへ、外から強引に菱川組が入ってきた。当然、立光会は力で対抗しようとする。県警が一番恐れたのは、二大組織の間の抗争で、民間人に被害が出ることだった。そのとき県警は立光会のほうの肩を持って、菱川組を徹底的に取り締まった。昔からの付き合いもあったし、なにより菱川組のほうは、警察の介入も無視する、すさまじい武闘派組織だったからね。第一次抗争なんていわれた時期が過ぎて、県の中心のこのO市では、ひとまず菱川組は撤退することになった。県警はホッと胸をなでおろしたけど、あとに残ったのは、さらにズブズブになった立光会との関係だった」
「その立光会っていうのは、松浦のいる石田組の上部組織ですよね」
「そうだ。石田組は直系団体だ。今の立光会の若頭の出身母体だよ。実際はまだ代替わりはしてないけど、自分の組のことは下に任せているから、石田組若頭補佐の松浦は、組では実質ナンバー2だ。立光会内部での序列も高い」
「それって、エリート中のエリートじゃないですか。ヤクザ界の」
「ああ。松浦には警察も簡単には手を出せない」
どうりで、喫茶店で松浦が突然割り込んできたとき、不破刑事が黙っていたわけだ。もっとも、松浦には、そんな肩書き以上に、なにを考えているのかわからない、底知れない不気味さがあった。
「とにかく、その立光会と県警の暴力団担当は、表向きはともあれ、蜜月にあったわけだ」
「それで松浦は丸山警部によろしくと言ったんですね。……あれ? でも丸山警部って西署の一課長ですよね。暴力団担当の不破刑事のいる二課長じゃなくて」
「そこが今の県警のデリケートな部分でね。僕や高谷さんがいたころとは、事情が変わっているんだ。実は今、菱川組がまたじわじわと侵入しつつある」
「菱川組が?」
僕はそれを聞いて思い出した。大逆事件の写真にまつわる一件の、師匠と松浦のやりとりだ。あのとき、松浦は自ら「毒」と呼ぶ写真が、石田組とも、そして角南一族とも敵対する組織に渡ることを恐れていた。それに対して師匠が言ったのだ。ジェスチャーつきで、「東の、四角いやつらか」と。それは菱川組の代紋のことらしかった。日本のヤクザの代名詞のような代紋なので、僕も気づいたが、まさか本当にそんな巨大組織が、この街に進出してきているのだろうか。
「菱川組は、第一次抗争のあと、うちの県への侵入を諦めたように見えたけど、実際は息を潜めて、周辺から少しずつ落としにかかっていたんだ。立光会とは距離を置いていたO市以外の地方の小さな組織が、ある日、急に力をつけて敵対しはじめた。立光会が対応策を練っているうちに、気がつくとその組織の代紋が菱川組の代紋に変わっている、そんなことが立て続けにあった。立光会と県警が手をこまねいているうちに、第二の県都のK市は、いまや菱川組の勢力範囲だ。武闘派集団だった第一次抗争のときとはうってかわって、絡め手から入ったんだよ」
「じゃあもう、第二次抗争状態ってことですか」
「そう。立光会が気づかないうちに、そうなっていた。O市にはまだ菱川の代紋のついた事務所は構えてないけど、フロント企業はすでに確認されている。もう本格的な抗争は避けられないように見えるね。ここに至ったからくりに、実は県警本部の捜査第一課がかかわっている」
「高谷所長が一課長をやめたあとですよね」
「ああ。県警本部の捜査第二課は昔からの慣例で、立光会とはもちつもたれつ、ズブズブの関係だ。彼らがスクラムを組んでいる限り、菱川組といえど、県都O市への侵入は容易ではない。そこで菱川組は捜査第一課のほうに目をつけた。元々対暴力団捜査に関して、一課と二課の間に軋轢があったと言っても、同じ県警内部のことだ。本来、刑事部長が高谷課長に言ったように、かねてから県警として柔軟な対応をしていたんだよ。二課だけじゃなくてね。その柔軟な刑事部長自身、捜査第一課長から昇進したんだから。推して知れるってものだ。暴力団捜査に関して、断固たる姿勢を通した高谷課長がやめたあと、菱川組はその一課に触手を伸ばしたんだ。つきあいは、最初は便利なS(エス)として。やがては、関係を断てなくなるくらいに、巧妙な糸をはりめぐらせて。二課と立光会が蜜月を謳歌しているあいだに、二課の捜査情報が、一課から漏れるような事態がひそかに生まれていたってわけだ」
僕はそれを聞いて頭がくらくらしてきた。警察とは、いうまでもなく正義の味方で、ヤクザどもを取り締まる存在だと当然のように思っていた。なのに、小川所長から聞かされる話は、その常識を壊されるようなことばかりだった。
「今じゃあ、県警本部の捜査一課と二課は冷戦状態だ。立光会と菱川組との代理戦争でね。さすがに公安からも相当睨まれてるらしいけど。銃器対策にやっきになってる警察庁から尻を叩かれている現状では、ヤクザとの関係をリセットできないんだよ。最悪、押収ノルマ達成のために、県警の予算を迂回した裏金で、首無し拳銃を大量に購入するなんていう、笑い話にもならないことになりかねないからね。県警本部の刑事部の冷戦構造は、当然所轄署にも波及している。このあたりの管轄の西署だったら、刑事第一課は菱川組のS(エス)とつながり、刑事第二課は立光会とつながっている」
「丸山警部はその西署の刑事第一課長だから……」
「そう。菱川組とつながりがあると思われる。彼は、僕の上司だったころから、つまり高谷警視の部下だったころから、密かに二課の肩を持っていて……、一課の捜査情報を、二課を通して立光会に流していた疑いがある。そんな男なんだ。それが今や菱川組の走狗だよ。本人は、自分のほうが犬を使ってやっていると、勘違いしているかも知れないけどね」
「じゃあ、松浦はそれをあげつらって言ったんですか。丸山警部によろしくって」
「脅しにかこつけた冗談だろうね。加奈子が不破とつながっているって、わかってて言ったんだろう。だけどその冗談は、いつでも本物に変わる。立光会の立場を考えればね」
「僕らは、雑貨屋の襲撃事件で、その丸山警部に助けてもらいました」
「まあ、そこは気にしなくていいよ。あれはヤクザ絡みじゃなかったからね。僕もよく知らないけど、不破はなにか丸山警部の弱みを握ってるらしい。だから無理が通ったんだろう。松浦の言葉を解釈すると、その関係も知ってるみたいだけど」
「はあ……」
僕はため息をついて、ソファーに深くもたれかかった。なんだか話を聞いているだけで疲れてしまった。
小川所長は、そんな僕の様子を見て、冗談めかしたジェスチャーで指を口にあてて言った。
「今日の話は、オフレコでね」
「はあ」
僕がぐったりしていると、律子さんが飲み物のおかわりを持ってきた。
「ずいぶん熱心にお話されてるのね」
「あ、おかまいなく。もう帰りますから」
「いえいえ、ごゆっくり」
会釈して、片足を引きずりながら部屋を出て行く律子さんの姿を見ながら、僕は想像していた。
立光会とのナアナアの関係を認めず、厳しく取り締まった高谷警視。さぞ恨みを買っていただろうことは容易に想像がつく。県警を退職し、その看板の下から出てきたとき、ヤクザからの報復の対象とならなかっただろうか。それも、もっともダメージの大きい形で。たとえば、家族を狙われて……。
僕は思い出していた。大逆事件の写真を持ち込んだ情報屋の田村が、大怪我をして朦朧としているときに、呻いていた言葉を。
『小川さんには世話になったよ。あの人は凄い探偵だ。あの人と、兄貴のコンビにはだれもかなわなかった。高谷さんのお嬢さんが、あんなことになるまでは……』
たしかそんなことを言っていた。
僕は、小川さんが高谷さんに引き抜かれて一緒に県警を退職したあと、タカヤ総合リサーチのエースとして活躍していた、という話を聞いている。本人からなので、話半分に、だったが。しかし、その小川さんがタカヤ総合リサーチをやめて、独立し、小川調査事務所を開いた経緯については聞いていない。尋ねたことはあったが、いつもはぐらかされていたような気がする。そこに、律子さんの大怪我が、なにか関係しているのだろうか。
「で、訊きたいことはこれで終わりかな」
改まった口調で小川さんにそう言われて、僕は我にかえった。頭のなかを覗かれたような気がして、そわそわしてしまう。
これで帰るわけにはいかなかった。本来の目的はこれからなのだ。それには、律子さんの体に残った障害も、無関係ではないかも知れなかった。だが、そこに直接触れることは、さすがにためらわれた。
とにかく、知りたいことだけを訊こう。
僕は深呼吸をすると、意を決して口を開いた。
「小川所長。お子さんのトーマ君ですけど」
「ん? トーマがどうかしたのか」
トーマ君とは、小川さんと律子さんのあいだの一人息子だ。ちょっと内気なところがあるけど、賢そうな子だった。
「今まで、名前の漢字を訊ねたことがなかったんですが、もしかして、冬に馬と書く、冬馬(とうま)ですか」
「そうだけど」
僕はそこでどう口にするべきか、少し迷った。人の良さそうな小川さんの顔を見ていると、なおさらだ。でも、いまさらあとにはひけない。ええい、もう言っちゃえ。
「小川さんのお姉さんって、春子さんですよね。黒谷夏雄の母親の」
「そうだよ」なにを言い出すんだろう、という怪訝な顔で小川さんは答える。「夏雄は僕の甥っ子だ。知ってるだろう?」
「小川春子が、黒谷家に嫁いで、黒谷春子になった。夫は寿満寺の住職、黒谷正月(しょうげつ)。正月に生まれたから、正月だって、本人が言ってました。その息子が夏雄。夏に生まれたから夏雄。これも聞きました。夏雄の妹のアキちゃん。これも教わりました。秋に生まれたからだって。春子と正月の間に生まれたから、そういう名前の付けかたになったわけですよね」
「……ああ」
小川さんはなにかを悟ったように、慎重に答えた。
「冬馬くんは、黒谷家の生まれですね」
「……そうだよ。養子にもらったんだ。冬馬にはまだ伝えてないけど。律子が……子どもを生めない体だったから」
僕はギクリとした。だけど、やめるわけにはいかなかった。
「アキちゃんの、弟なんですね」
「そうだ」
「ある人が言っていました。『娘のほうは、体質が弱く生まれてしまった』って。僕は最初、母親に対して、娘のほうは、という意味だと受け取りました。でもそれは違った。『息子に対して、娘のほうは』だったんだ。……加奈子さんが、寝言でなんども言っていました。私からは、名を与える、って」
僕は、師匠の趣味につきあわされて、ひたすら寝言を書きとめていた夜のことを、思い出していた。
「あれは、名前の『名』であると同時に、加奈子の『奈』だったんだ。そうして、『彼女』は完全になる。そうなる運命だったみたいに」
「…………」
小川さんは僕の目を見つめながら、黙っていた。僕も黙っていた。閉めたはずの窓から、かすかな隙間風が吹いてきて、頬を冷たくなでた。それはもう、冬の風だった。
「パパ」
ドアが開いて、男の子の顔がこちらを覗いていた。
「トーマ。どうした」
小川さんがこわばっていた顔を、笑顔に作り変えて笑いかけると、トーマはモジモジしながら、心配そうに言った。
「パパ、大丈夫?」
「大丈夫だよ。ママのところに行っていなさい」
「うん」
ドアから出て行くそのかわいらしい頭を見ながら、僕はつぶやいた。
「髪の毛は、癖っ毛で、たしかに小川家の血も引いてますね。小川さんによく似てる。……勘もいいみたいですね。なにか感じたのかも。もしかして、霊感もあるんですか」
「あのアキの弟だからね」
小川さんは、ふう、と息を大きく吐き出すと、膝を叩いた。
「もう終わりにしよう。今日みたいな日は、もう御免こうむるよ」
軽い口調だったが、有無を言わせないような、妙な迫力があった。
僕は立ち上がり、頭を下げてから部屋を出て行った。玄関を出るとき、腕組みをして見送る小川さんに訊ねた。
「どうして、答えてくれたんですか」
「松浦たちヤクザのことは、知っておいたほうがいいと思ったからだよ。君ももう、無関係ではないからね」
小川さんは、僕の問いかけを意図的に取り違えて答えた。僕もそれになにも言わなかった。
「君は加奈子の背中を追って、いつかこの世界にやってくる。そうだろう?」
同じ興信所でバイトをしながら、僕のほうはまだこの世界に足を踏み入れてもいない、そう言われていた。バカにされているわけではなく、それが事実だったのだろう。
「それは…… わかりません」
僕はそう頷いて、肌寒い空気のなかへ足を踏み出した。 冬が来る前に、ほかになにかしておくべきことが、あるだろうか。
そう思ってから、僕はこれからやってくる冬に、なんともいえない不吉な予感を抱いている自分に気づいた。
住宅街の明かりがぽつぽつと、夜の底を照らしている。川のように延びるアスファルトは黒く、冷たい。
見上げると、冬の星座が空に上ろうとしていた。



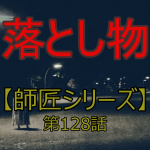
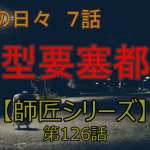
コメントを残す