写真屋
師匠から聞いた話だ。
大学2回生の秋の終わりだった。
僕は1人で、小さなマンションの前に立っていた。繁華街から少し離れたところにある、古くてみすぼらしいマンションだ。
ここには、『写真屋』と呼ばれる、天野という男が住んでいる。師匠の悪友で、普通の町なかの写真屋ではプリントしてくれないような、危ない写真を割高な料金で手がける人物だった。
師匠は、ここを興信所の仕事でも使っていたし、プライベートでも使っていた。プライベートのほうで料金を払っているのを見たことがない。いつもなにかにつけて脅し、無理やりタダで仕事をさせていた。天野のほうも弱みをもっているらしく、はじめは強気に出るが、結局言い負かされてしぶしぶ従っていた。天野はいかにも不摂生、というぽっちゃりした体型で、横で見ていると、なにかそういうSMのプレイなんじゃないか、という気がしてくる。天野のほうも、そんなぞんざいな扱いを受けているのに、師匠と会うときはいつも妙に嬉しそうなのだ。
『このブタッ』
『ブヒィッ』
という奇跡のやりとりを目の当たりにしたことがあるので、僕がそう思ってもしかたあるまい。
エレベーターが故障中だったので階段を使って、3階まで上がった。通路のなかほどにある、表札のない部屋が天野の城だ。隣近所の住人は、ここにやってくる多くの、挙動不審で、うさんくさい客たちを、どう思っているのだろうか。
部屋のチャイムを鳴らし、ドンドンとドアをノックする。
「はいはい。いるよ。そんなに叩かなくても。僕がいないことがあったかい」
ドアが少し開いて、チェーン越しに髪の毛がよじれて、額に張りついている、丸顔で眼鏡の男の顔が覗く。
「なんだ君か。今日は1人か。またお遣いか」
僕はこれまでも何度か師匠の代理で、1人でやってきたことがあった。そのたびに天野は、ガッカリしたような表情を見せるのだ。
「現像を頼みたいネガがあるそうです。預かってきました。あ、これ差し入れです」
右手で持ったコンビニの袋を、チェーンの外で振ってみせる。サンガリアのメロンソーダの缶だ。
「な、なんだ、またこれかよ。ちょっと待て」
天野はため息をつきながら、チェーンを外した。僕は、右足をドアのなかに滑り込ませると、天野の右の太ももに、左手を突き出した。
バチバチバチッ、という鋭い音がして、天野は、「アイッ」と呻き、その場に崩れ落ちた。
「アッツッツッ……」
太ももを押さえて、大きな体を折りたたんでいる。僕は自分の左手のなかの、黒い器具を見つめる。スティック型のスタンガンだ。ほとんど音と光が出るだけの、おもちゃに近いものもあるが、これは本物の護身用スタンガンだ。
ただ、それでもさほど強力なものではない。事前に自分でも試してみたが、これほどの威力はなかったはずだ。天野が想像以上に痛みに弱いのだろう。ちょっとやりすぎてしまった、という罪悪感を押さえ込み、僕はしゃがみこんで口を開く。
「天野さん、わかったと思いますが、スタンガンです。こうでもしないと口を割ってくれないことを、訊きにきました。起きられますか」
天野はううう、と呻きながら顔を上げた。
「な、な、なんだ、なんだ、君は。ひ。どうしてこんな」
「立ってください」
スティック型のスタンガンを目の前にちらつかせて、命令した。天野はぷるぷると震えながら、ゆっくりと立ち上がった。
「仕事部屋のほうへ」
「わ、わかったから、それを下げてくれ」
2人で、玄関から奥へ進む。途中、現像用の暗室につかっている部屋の前を通り過ぎるとき、酸っぱいような薬品の匂いが鼻についた。あいかわらず、この匂いには、どうも慣れない。
奥の部屋は、ところせましと物が散乱している。パソコン机の前が、彼の仕事のスペースだ。その辺に転がっているなにか重いものを使って、とっさに反撃をくらわないように、スタンガンを背中に押し付けて歩かせる。
「お、押さないでくれ。抵抗しないったら」
「座れ」
天野は愛用の椅子に腰を落とし、ふう、と大きく息を吐いた。
「お遣いだというのは、ウソか。ひ。なんでこんなことを、ひ。するんだ」
天野がしゃべるたびに、ひゅっ、と空気が漏れる音がする。
部屋は厚手のカーテンが締め切られていて、昼間なのに、時計を見ないと時間の感覚がなくなるようだった。
「師匠の……。加奈子さんの写真を持っていますね」
「は? なんだって?」
「せんず○こいてる、っていう写真ですよ」
天野はギクリとした。僕の用件がわかったようだ。
「出せ」
スタンガンの先端を、目の高さで近づける。
「ま、待ってくれ。ひ。あ、あれは、彼女がそう思い込んでるだけで……」
「出せ」
さらに近づける。次にシラを切ったら、目の前で、スパーク音を聞かせてやるつもりだった。あの音をもう一度聞けば、素直になるだろうと思っていた。そのくらい、嫌な音なのだ。だが、天野はその前に、あっさりと前言を撤回する。
「わ、わかった。言う通りにする。やめてくれ」
ゴクリと、たるんだ喉を震わせて生唾を飲み込んだ。そして、僕のほうをこわごわとチラ見しながら、机の引き出しから、鍵を取り出した。
「ど、ど、どいてくれ。ひ。そこに金庫があるんだ」
僕の後ろの壁に、それらしいものがあった。天野は洗濯物の詰まった籠をどかせて、その金庫の前にしゃがみこんだ。
「いま開ける」
ダイヤルを合わせて、鍵を入れ、捻った。ガチャリと音がする。
金庫の中から取り出したのは、大量のアルバムだった。灰色の均一な表紙に、ナンバーだけが振ってある。天野はそのなかから1冊を選び、そばにあった座卓に置いて、ページをめくりはじめる。
どのページにも、フィルムポケットに写真が数枚ずつ収められているが、どれも目を覆いたくなるような写真ばかりだった。
天野は死体マニアであることは知っていたが、これまでに見せられた写真よりも、強烈なものばかりだ。どこでこんなものを手に入れるのだろう。事故現場や設備のひどい病院で撮られたようなものもあったが、多くは戦場で撮られたものらしかった。天野はパソコン通信というものを使って、海外の好事家と交流があるようなので、トレードを繰り返して増やしていったのか。
気分が悪くなりかけたとき、ようやく天野の手が止まった。太い指をポケットに滑り込ませ、ツイ、と写真を引き抜く。
「こ、これだ」
天野は、忘れ物をしたことを教師に告げるような顔で、見下ろしている僕を見る。
その写真を見たとき、体の血液が沸騰するような感じに襲われた。思わず胸を抑える。
予想はしていた。筋金入りの死体愛好家、ネクロフィリアが、自慰行為に使っている写真なのだ。スタンガンを握る手に力が入りすぎ、光とともにバチバチと一瞬、スパーク音が室内に響いた。
「ひいっ」
天野がおびえて、頭を抱えてうずくまる。
「これはお前がやったのか」
静かにそう訊ねた。天野は「違う違う」と必死に首を頭を振る。
「事故だったんだ。ひどい事故にあったんだ。ひ。ぼ、僕は偶然通りかかっただけなんだ」
バチバチバチッ。激しい音とともに、埃が焼けるような嫌な匂いがした。今度は、自分の意思でスイッチを押したのだ。顔の先、50センチでそれを見た天野にも、それがわかっただろう。
「事故でつくような傷じゃない」
「僕は助けたんだ! つれて帰って、手当てをしたんだ。そしたら息を吹き返して、か、彼女は……」
「お前の、お友だちになったのか」
「そうだ。ひ。それからのつきあいだ。僕らは。僕は命の恩人なんだ」
「救急車を呼ばずに、部屋に連れ込んだんだな。死んだと思って」
「ちょっと待ってくれ。ひ。僕はなにもしていない。ひ。ひ」
息が荒い。目の前に突き出されたスタンガンを凝視して、ブルブルと震えている。
僕はしゃがみこんで、天野の目を見た。
「だれがやった」
「…………」
ゴクリ、という音が僕にも聞こえた。天野は何度も唾を飲み込む仕草をしている。
「知っているやつだな」
「ほ、本当に偶然通りがかったんだ。そのときは、2人とも、僕は知らなかった」
「死体を見られるかも知れないと思って、黙って見ていたのか」
「いや、僕が来たのは、もう、そ、そうなっていたあとだよ……」
語尾が小さくなって消えていく。
僕は写真を胸ポケットに入れた。
「僕がしゃべったって、言わないでくれ。彼は、そのときはその、なにかに、とりつかれてる……。ひ。みたいだった」
天野の言葉は、最後にバチバチバチ、という激しい音で途切れた。僕は、やり場のない感情を、自分にぶつけたのだ。スタンガンの衝撃が太ももから全身に、一瞬で駆け抜ける。
「ぐぅっ」
悲鳴をこらえて、頭を下げる。ふうふう、という息を吐いてから、痛みを我慢して僕は立ち上がった。
「いろいろ、すみませんでした。これで許してください」
天野は腰を抜かしたように、床にうしろ手をついて座り込み、唖然としている。
「メロンソーダ、飲んでください。じゃあ、帰ります」
言葉も出ない天野を残し、僕は『写真屋』の仕事部屋をあとにした。異臭のする暗室の前を通り、脱ぎ散らかした靴を拾う。
玄関から外に出ると、閉じたドアに、右手の拳の腹を叩きつける。
があん、という大きな音がした。遠くで、犬が吼えはじめる。
「それで、前科一犯って感じのやつかよ」
僕は憎悪を霧のように撒き散らしながら、歩き出した。




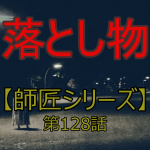
コメントを残す