2017年10月17日 00:13
大学2回生の春だった。
「幽霊がでるホテルがあるらしいぞ」
京介さんからそう誘われたとき、なんとも言えない違和感があった。
「行ってみるか」
「はい」
違和感の正体なんかより、俺には京介さんから久しぶりにお誘いがあったことが、とにかく嬉しかった。
京介さんが怖い夢をみた日から、連絡が途絶えていたのだった。ネットのオカルトフォーラムにも姿を現さなくなっていたし、しばらく会わないと不安になってくる。
このままなにも告げず、どこかへふらっと去って行ってしまうような気がして。そんな雰囲気を持っている人だったからだ。
でも、またこうして心霊スポットに誘ってくれた。嬉しくて、買ったばかりの服を着て約束の時間の30分も前に、大学前の通りで京介さんを待った。夜の8時半だった。
きっかり30分待って、合図のようにライトを点滅させながら、青いインプレッサが、目の前に停まる。
「待たせたな」
ウインドウガラスが下がり、京介さんの顔が覗く。相変わらず凛々しいが、心なしか険が取れたような柔らかさを感じた。それは、悪夢を食べられることから解き放たれた彼女に対する、自分自身の心の投影だったのかも知れない。
助手席に乗り込んで、「どこに行くんですか」と訊く。
「港のほうだ」
京介さんは南へ向かってハンドルを切った。
シートに深く腰掛けると、煙草の匂いがする。京介さんの匂いだ。
至福のときを味わっていると、あっという間に目的地についてしまった。
どんなホテルだろう。これから行っても、客室にはさすがに入れないだろうから、ロビーや廊下にその幽霊とやらが出るのだろうか?
そう思っていた俺の前に、色鮮やかな看板が現われる。
『ホテル・シーサイド』
その名前ではなく、外観が物語っていた。そこがいわゆるラブホテルであることを。
ギクリとした俺をよそに、京介さんは平然と車を駐車場に乗り入れる。
「どうした」
「あ、いや」
促されて車を降りる。建物のなかに入ると、人の気配のないフロントがあった。しかし営業中であることは、ずらりと並ぶ部屋の写真パネルでわかる。まばらに明かりがついている。
「予約しといた」
京介さんはそう言って、顔の見えないフロントの壁の向こうから、目的の部屋の鍵を受け取った。
その慣れた様子を見て、ドキドキしてしまう。
部屋に入ると、明かりが自動的に点いた。
かわいい部屋だった。ミッキーマウスによく似たぬいぐるみが、ソファに腰掛けている。その向こうには大きなベッドがあった。
「ど、どんな幽霊が出るんですか」
声が上ずっていた。自分でも恥ずかしくなる。
「ああ、ネットで聞いた噂ではな……」
京介さんはミッキーもどきをどかせて、ソファに座った。
「この部屋に泊まったカップルが、何度も見てるらしいんだ。スーツを着た男の霊を」
立ったままなのは変なので、俺もテーブルを隔てた向かいのソファに腰掛ける。ソファが2つあってよかった。さすがにこの部屋で、隣に座るのは気が引けた。
「それだけならどこにでもある話だけど、面白いのはな、その出かたなんだ」
「どんな出かたなんですか」
「カップルの片方が風呂場に入ってて、もう片方が部屋で待ってるだろ。そのとき、風呂場のほうから声がするんだ。『あれ。こんなところが開くよ』って。すると、それきり静かになってしまう。部屋で待ってるほうが、どうしたんだろう、って思っていると、急に風呂の扉が開いて、見たこともない無表情のスーツ姿の男がスーッと出てくるんだ。そしてそのまま部屋から出ていく。ドアも開けないままで、消えるように。びっくりした片方が、風呂場を覗くと、なかにだれもいない。さっきまでシャワーを浴びていたはずなのに。そして、風呂場をどんなに探しても、『開く』ところなんてないんだ。人が1人、隠れてしまうようなところは、どこにも」
ゾクリとした。確かに怖い話だ。
というか、幽霊の話だけじゃなく、それではまるで神隠しではないか。
「カップルはいきずりで、もともと相手がどこのだれかもわからない、ってオチがつくんだよ。だから人が1人いなくなっても、怖い話で済んでいる」
「そのスーツ姿の幽霊はなんなんですか」
神隠しと関連があるはずなのに、つながりがよくわからない。
「さあ。単にそのスーツの男の幽霊を見た、っていう話のほうが多かったから、ひょっとしたら、神隠しのほうはあとづけかも知れない。ただ幽霊を見たっていう話じゃ弱いからな。別の話とくっついたのかも」
さて、ちょっと見てくるか。
京介さんはそう言って、風呂場のほうへ向かった。どこも開くところがないはずなのに、『こんなところが開く』と言って人が消えたという、その風呂場に。
俺もついて行こうとすると、「デリカシーがないな」と言って押しとどめられた。
ドアの向こうに風呂場と、そしてトイレが併設されていることに思い至り、ああ、そういうことか、と頷いた。
俺も少し、もよおしてきた。しかしなんだか恥ずかしくて、家に帰るまでは我慢しようと思った。
ドアの向こうに消えた京介さんを待っているあいだ、部屋の中を見回す。ラブホテルに限らず、ホテルには幽霊の目撃談が多い。こうして落ち着いてみていると、確かに日常と違う空間だという気がする。艶かしい装飾。大きなベッド。なぜか天井に貼られている鏡。その非日常性が、怪談を生む源泉になっているのかも知れない。
そんなことを考えていると、風呂場のほうからなにか音が聞こえてくるのに気がついた。
水が流れている音。水洗トイレを流す音にしては長い。ずっと聞こえている。
シャワーだ。
それに気がついた瞬間、俺は動転して風呂場のドアに駆け寄った。
「ちょ、ちょっと、なにしてるんですか」
ドアに向かって喚く俺に、京介さんがなかから声を張り上げて言い返した。
「なんだ、シャワーは浴びないほうが好みか」
いやいや。
なにをおっしゃっているのか。
いやいやいや。
唖然として思考停止状態に陥った俺の前に、やがてガウンを着た京介さんが現われた。
「風呂場はなにもなかったぞ。そっちもなにも出なかったか」
「出ました」
「なにっ」
裸のお姉さんが出ました。
そんな冗談も、口にできなかった。
ガタガタ震えている俺を見て、京介さんはいつもの凛々しい顔を少し崩して、笑った。
◆
枕元の淡いランプシェードの光だけが、部屋を照らしている。その薄い暗闇のなかで、目を覚ました。
寝てしまっていたらしい。
京介さんが、壁に背中をつけて、煙草を吸っている。薄っすらとしたランプの明かりに、煙草の煙がゆらゆらと揺れながら、天井へのぼっていく。
暗闇のなかで、彼女はじっとそうしていた。
なにを考えているのだろう。
彼女は、自分の部屋でしか寝ることができなかった。そんな呪いにかかっていた。あるいは、そう思い込んでいたのかも知れないけれど。だから、けっして外では眠ることができなかった。俺の田舎へ旅行したときも、3日間、彼女は一睡もしていない。体力的もきついだろうが、その眠れない夜を、たった1人でどうやって過ごしていたのか、そのことを考えると、胸が締めつけられる。
あの田舎の縁側で真夜中、1人で煙草を片手に、じっと庭を見ていた。その横顔を思う。
こうして、ホテルで男が眠ってしまったあとも、たった1人で眠ることもなく、じっと朝がくるのを待っている。そんな日々を送っていた彼女のことを思う。
もうそんな日々から解き放たれたはずなのに……。
俺は我知らず、涙を流していた。
嗚咽が漏れたのだろうか。京介さんが、「起きたのか」と言った。
しばらく待ってから、俺は恥ずかしさを押し殺して「はい」と体を起こした。
それから、朝を待たずに俺たちはホテルを出た。
まだ暗い。夜明けまでには数時間あるだろう。
車で海沿いを走った。窓を開けていると、潮の香りが入り込んできて、どこか懐かしい感じがした。
「コーヒーでも飲むか」
そう言って、ぽつんと光る自動販売機の前に車を停めた。熱い缶コーヒーを握り締めながら、そのまま2人で海のほうへ歩いていった。
海水浴場からは少し離れている。幅の広い岸壁に腰掛けると、ざあざあという波の音が、眼下から聞こえてきた。
その向こうに暗い海が横たわっている。潮の香りを嗅ぎながら、じっとその向こうを見つめる。
京介さんがごそごそとジーンズのポケットを探り、煙草を取り出した。
そう言えば、禁煙はどうなったんだろう。あの怖い夢を見た日、禁煙パイポを咥えていた姿を思い出す。それとなく訊いてみると、怖い声で、「これで最後だ」と言った。
「明後日、この街を出るよ」
京介さんは煙草に火をつけながらそう言った。
そんな予感がしていた俺は、それでもショックを隠せなかった。
「嫌なことも多かったけど。いろいろ、楽しかった」
彼女を繋ぎとめていた呪縛は、もうない。これ煙から彼女は、好きなところに行って、好きなことをするのだろう。その隣にいるのは、煙草嫌いな男なのかも知れない。
ふとそう思った。
「なあ、知ってる星座はあるか」
煙草を持った右手が、空を指した。一面の星空だった。市内の中心地に暮しているとお目にかかれない綺麗な夜空が、海の上に広がっていた。
「あいつも、どんな気持ちで夜空を見ていたんだろう」
空を見上げてぽつりと言った。
「知らない星を」
そうして、京介さんは過去に体験した話をとつとつと語った。古い洋館と、星座にまつわる不思議な話だった。間崎京子という女のことを語るときの彼女は、どこか懐かしげで、そして失ったものへの悲しみのような感情を浮かべている。
怖い話でもあったけれど、幽霊は出てこなかった。
『幽霊がでるホテルがあるらしいぞ』と誘われたときに感じた違和感の正体が、おぼろげにわかった。
京介さんとした冒険や、語り合った様々なことを思い出す。不思議で、奇妙で、恐ろしい話ばかりだった。けれど、そのどこにも人間の幽霊はでてこなかった。
『なんだこのインチキ野郎は』
彼女が師匠をののしった言葉を思い出す。わけ知り顔で幽霊について語る師匠に、腹を立てたのだ。
「幽霊を見たことがないんですね」
そう口にしてみた。
京介さんは静かに笑って、煙草の煙を吐き出した。
こうして隣にいても、俺の見ている世界と、京介さんの見ている世界は、まったく違うものなのかも知れない。
息が凍える。
春の海は静かに岸壁に押し寄せては、冷たい波音を残して引いていく。
「あの星のことを知ってるか」
京介さんが空の一点を指差した。その先には、赤く輝く星があった。首を左右に振る俺に、彼女は続ける。
「なにかの本で読んだんだけど、あの星はもう存在していないらしいぞ。数百年だか、数千年だか前に、爆発しているんだって」
そう言われて見ると、赤い光が、爆発前の最後の輝きにも見えた。
「でも、その光が今こうして地球に届いている。不思議な感じがしないか? 死んで、もう存在しない星が、今私たちの会話を作っている」
京介さんは、座ったまま煙草の火を踏んだ。靴の裏が、コンクリートに擦れる音がする。
「幽霊って、そういうものじゃないのかな」
そう言って、真っ直ぐに空を見上げている。
今はもう死んだ星からの光が、何百、何千光年という長い旅のはてに、彼女の瞳のなかで静かに輝いて、そうしてもう1度死んでいった。
その横顔を見つめながら、俺は想像した。
春の海辺で、こうして並んで座っている俺たちもまた、光の粒子になって宇宙を駆けていく空想を。
はるかな未来、宇宙のかなたで、今はまだない星の、今はまだいないだれかの、その瞳のなかで、もう1度このひとときが蘇り、そして消えていく。
地球は暗い星だ。大きな望遠鏡なら見えるだろうか。そこには、去っていこうとしている彼女のかたわらで、なにもできなかった男がいるはずだ。
「尻が冷えた」
そう言って京介さんは立ち上がった。
大きく伸びをして、深く息を吐いた。そしてポケットから財布を取り出して、小銭を1枚摘んだ。じっと手のなかのそれを見つめている。
「なんですか」
「ああ」
京介さんは、うつむいたままだ。
「……友だちだったんだ」
それだけを言うと、海へ向かって、勢いよく手のなかのものを投げた。輝きもせず、それはどことも知れない波間に落ちだろう。
「帰るか」
振り返りながら、京介さんは静かに笑った。



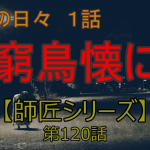

コメントを残す